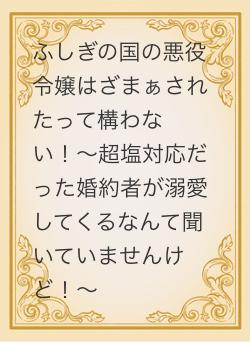貴族たちはその力を分け与えることで生計を立てていた。
より便利な魔法の爵位が高くなるのは必然だろう。
そして生活するのに便利な魔導具などを動かす雷魔法も同じで、かなり重要視されている。
(父上はこの現象はマティルダがいなくなったからだと言っていたが、同じ力を持つライボルトがいればなにも問題ないはずだ……!)
暗闇の中、バーゼルがつけた蝋燭を持って部屋に到着したローリーはホッと胸を撫で下ろした。
「これでパーティーが再開できるな!」
「…………」
「ライボルト、どうしたんだ?」
「いや……久しぶりだからうまくできるかどうか、わからなくて」
珍しく歯切れの悪い返事をするライボルトを不思議に思っていた。
しかしローリーは急かすように声を上げた。
「早くしてくれ!町の人間が城に押し寄せているんだ」
「……っ!?」
「大変だと思うが、町に行き渡る量を頼む!」
そう言うとライボルトは恐る恐る腕を上げて、目の前にある金色の球体に手を翳して力を込めた。
パッと部屋が明るくなる。
城の灯りがついたことにローリーは安堵していた。
(これで大丈夫だ……!)
より便利な魔法の爵位が高くなるのは必然だろう。
そして生活するのに便利な魔導具などを動かす雷魔法も同じで、かなり重要視されている。
(父上はこの現象はマティルダがいなくなったからだと言っていたが、同じ力を持つライボルトがいればなにも問題ないはずだ……!)
暗闇の中、バーゼルがつけた蝋燭を持って部屋に到着したローリーはホッと胸を撫で下ろした。
「これでパーティーが再開できるな!」
「…………」
「ライボルト、どうしたんだ?」
「いや……久しぶりだからうまくできるかどうか、わからなくて」
珍しく歯切れの悪い返事をするライボルトを不思議に思っていた。
しかしローリーは急かすように声を上げた。
「早くしてくれ!町の人間が城に押し寄せているんだ」
「……っ!?」
「大変だと思うが、町に行き渡る量を頼む!」
そう言うとライボルトは恐る恐る腕を上げて、目の前にある金色の球体に手を翳して力を込めた。
パッと部屋が明るくなる。
城の灯りがついたことにローリーは安堵していた。
(これで大丈夫だ……!)