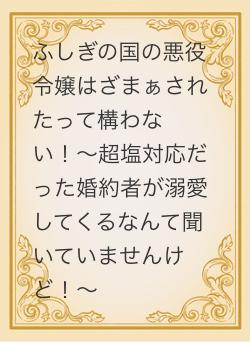シエナの体が大きく震えて、顔が歪んでいる。
ゾッとするような表情と共に、シエナが浮かべていた明かりがチカチカと点滅して消えたことで部屋が暗くなった。
「まだ部屋が暗いのか!?何故、こんなことに……!いつもならば明るくなる時間だろう?」
ローリーがそう言うと、後ろに控えていた執事が魔石を使って蝋燭に火を灯す。
ぼんやりとした灯りの中でもわかるくらい、父の顔が真っ赤になっている。
「──何を言っているッ!マティルダを追い出したのはお前だろう!?」
「……え?」
「この事態を引き起こしたのはお前だと言っているんだ!」
「な、なにを言っているのですか……?」
「それはこちらのセリフだっ!最近、マティルダがこの辺り一帯の灯りを全てつけていたんだ!毎日、城に通って皆のためにとなっ!」
寝耳に水だった。
ローリーは先程から父が何を言っているか理解できなかった。
マティルダが毎日、城に通っている理由を知ろうとしたこともなかったからだ。
しかし雷魔法を使えるのはマティルダだけではない。
「今すぐガルボルグ公爵とライボルトにマティルダの代わりをしてもらえばいいだけじゃないか!元々、そうしていたはずでしょう!?」
ゾッとするような表情と共に、シエナが浮かべていた明かりがチカチカと点滅して消えたことで部屋が暗くなった。
「まだ部屋が暗いのか!?何故、こんなことに……!いつもならば明るくなる時間だろう?」
ローリーがそう言うと、後ろに控えていた執事が魔石を使って蝋燭に火を灯す。
ぼんやりとした灯りの中でもわかるくらい、父の顔が真っ赤になっている。
「──何を言っているッ!マティルダを追い出したのはお前だろう!?」
「……え?」
「この事態を引き起こしたのはお前だと言っているんだ!」
「な、なにを言っているのですか……?」
「それはこちらのセリフだっ!最近、マティルダがこの辺り一帯の灯りを全てつけていたんだ!毎日、城に通って皆のためにとなっ!」
寝耳に水だった。
ローリーは先程から父が何を言っているか理解できなかった。
マティルダが毎日、城に通っている理由を知ろうとしたこともなかったからだ。
しかし雷魔法を使えるのはマティルダだけではない。
「今すぐガルボルグ公爵とライボルトにマティルダの代わりをしてもらえばいいだけじゃないか!元々、そうしていたはずでしょう!?」