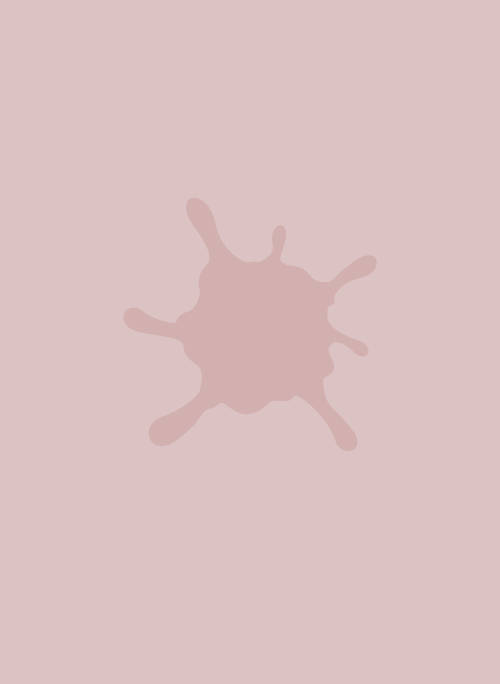…笑われたぞ、俺達。チェシャ猫に。
何笑ってんだお前。
いや、そんなことより…。
…もしかして俺達、逃げた方が良いのでは?
猫なんかに追いかけられたら、今の俺達はひとたまりもない。
さっきはネズミに追いかけられ、今度は猫に追いかけられるとは。
地獄だ。
逃げ切れるか…?姿を見られてるのに…。
そう思ったが、チェシャ猫は、お得意のにやにや顔で俺達を見つめるだけで。
どうやら、襲いかかってくる意志はなさそうだった。
「…何だよ、お前。何しに来たんだ?」
俺達を襲いに来たんじゃなかったら、何をしに来た?
もしかして、テントウムシサイズで右往左往する俺達を、野次馬しに来たのか?
「…ケケケッ」
チェシャ猫は俺の問いには答えず、小馬鹿にしたような笑い声をたてた。
…本当に、野次馬しに来たようだ。
…くっそ…。にやにやしやがって…。
これが人間だったら、絶対友達出来ないタイプだな。
にやにやとこちらを眺めるチェシャ猫を、しばし睨み返していたが。
…こんなことしてても、時間の無駄だな。
「…もう良い。あのクソ猫は放っといて…行くぞ」
「お、襲ってこないよね…?あの猫ちゃん…」
「…見てるだけだし、大丈夫だとは思うが…」
菜橋を渡ってるときに邪魔されたら、一貫の終わりだな。
今のところ、襲ってきそうな様子はないが…。
何をしでかすか、分かったもんじゃない。
じゃあ、俺が先に行こう。
そうすれば、万が一チェシャ猫が何か仕掛けてきても、俺が落っこちるだけで済む。
「俺が先に行くよ」
「…!羽久…!いや、私が先に…」
「運動音痴は後だ」
俺は強引に、先に菜橋を渡った。
…こえぇ…。
下を見たら、足が竦むな。
下は見るな。前だけを向いて歩け。
俺は、普通にイーニシュフェルト魔導学院の廊下を歩いているような気持ちになって、菜橋を渡った。
…やがて、橋の先端に辿り着いた。
…ここから先は、足場はない。
向こうに向かって、決死のダイブを試みる。
…ギリギリの距離だな。正直、絶対大丈夫だとは言えないが…。
躊躇わず、思いっきりジャンプすれば、多分届く。
でも、臆病心を起こして、躊躇ってしまったら…多分落ちる。
つまり、覚悟を決めて飛べってことだな。シンプルで分かりやすいじゃないか。
じゃ、やるべきことは一つだな。
「飛んでくるよ、シルナ」
「…気をつけて、羽久…!」
そうだな。
ここで落っこちて死んだら、お茶会には参加出来ないし。
皆とも再会出来ないし。
ここで死ぬ訳にはいかないな。
精々、全力ダイブを試みるとしようか。
何笑ってんだお前。
いや、そんなことより…。
…もしかして俺達、逃げた方が良いのでは?
猫なんかに追いかけられたら、今の俺達はひとたまりもない。
さっきはネズミに追いかけられ、今度は猫に追いかけられるとは。
地獄だ。
逃げ切れるか…?姿を見られてるのに…。
そう思ったが、チェシャ猫は、お得意のにやにや顔で俺達を見つめるだけで。
どうやら、襲いかかってくる意志はなさそうだった。
「…何だよ、お前。何しに来たんだ?」
俺達を襲いに来たんじゃなかったら、何をしに来た?
もしかして、テントウムシサイズで右往左往する俺達を、野次馬しに来たのか?
「…ケケケッ」
チェシャ猫は俺の問いには答えず、小馬鹿にしたような笑い声をたてた。
…本当に、野次馬しに来たようだ。
…くっそ…。にやにやしやがって…。
これが人間だったら、絶対友達出来ないタイプだな。
にやにやとこちらを眺めるチェシャ猫を、しばし睨み返していたが。
…こんなことしてても、時間の無駄だな。
「…もう良い。あのクソ猫は放っといて…行くぞ」
「お、襲ってこないよね…?あの猫ちゃん…」
「…見てるだけだし、大丈夫だとは思うが…」
菜橋を渡ってるときに邪魔されたら、一貫の終わりだな。
今のところ、襲ってきそうな様子はないが…。
何をしでかすか、分かったもんじゃない。
じゃあ、俺が先に行こう。
そうすれば、万が一チェシャ猫が何か仕掛けてきても、俺が落っこちるだけで済む。
「俺が先に行くよ」
「…!羽久…!いや、私が先に…」
「運動音痴は後だ」
俺は強引に、先に菜橋を渡った。
…こえぇ…。
下を見たら、足が竦むな。
下は見るな。前だけを向いて歩け。
俺は、普通にイーニシュフェルト魔導学院の廊下を歩いているような気持ちになって、菜橋を渡った。
…やがて、橋の先端に辿り着いた。
…ここから先は、足場はない。
向こうに向かって、決死のダイブを試みる。
…ギリギリの距離だな。正直、絶対大丈夫だとは言えないが…。
躊躇わず、思いっきりジャンプすれば、多分届く。
でも、臆病心を起こして、躊躇ってしまったら…多分落ちる。
つまり、覚悟を決めて飛べってことだな。シンプルで分かりやすいじゃないか。
じゃ、やるべきことは一つだな。
「飛んでくるよ、シルナ」
「…気をつけて、羽久…!」
そうだな。
ここで落っこちて死んだら、お茶会には参加出来ないし。
皆とも再会出来ないし。
ここで死ぬ訳にはいかないな。
精々、全力ダイブを試みるとしようか。
俺は、十歩ほど後ろに下がった。
助走の為だ。
少し助走して、橋の先端ギリギリまで来たら、思いっきり踏み込んでジャンプ。
食料庫に向かってダイブする。それだけ。
実に分かりやすい。
さて、手が届くと良いのだが。
ビビッてちゃ始まらない。
恐怖で足が竦む前に、さっさと飛ぼう。
「…よし」
生憎俺は、まだ死ぬ気はないんでね。
精々、生きて明日の陽の光を拝ませてもらおう。
俺は助走をつけて、先端ギリギリに来たとき、強く箸を蹴りつけた。
ふわりと身体が中に浮かんだ。
行け。届け。
時間としては、恐らく1秒くらいの出来事だったのだろうが。
俺にとっては、まるでスローモーションのように感じた。
「ふっ…ぐ…!」
精一杯伸ばした手が、食料庫の縁に届いた。
…よし…届いた。
手を滑らせないよう、俺は強く食料庫の縁を掴んだ。
そのまま、ぐいっと身体を持ち上げ、食料庫によじ登った。
…ふぅ。
かなりギリギリではあったが、何とか辿り着けたようだ。
はぁ…ネズミに追いかけられるより、命の危機を感じた。
「羽久!羽久、大丈夫!?」
食器棚から身を乗り出すようにして、シルナが大声で尋ねた。
「大丈夫だ!」
俺もまた、大声で答えた。
けど、今の俺達の大声なんて、通常サイズの人間には全然聞こえないんだろうなぁ。
誰もいないから良いけど。
「よ、良かった、羽久…。じゃあ、私も行くね!」
「いや、ちょっと待て」
後から続こうとするシルナを、俺は制止した。
「どうしたの?」
「…」
…今しがた、俺が飛んでみて分かったが。
目で見るより、結構距離があった。
俺でさえギリギリ届いたのだ。
運動音痴でビビリチキンなシルナでは、届かないかもしれない。
シルナまで飛ぶのは、危険過ぎる。
「やっぱり、お前はそっちで待っててくれ。ここは俺が…」
「やだ、行く!」
…駄々っ子かよ。
「無理をするなって言ってるんだ。お前じゃ届かない…」
「いや、絶対に行く」
「…シルナ…」
「羽久が行くところには、私も行く。それが何処かは関係ない」
…そうか。
…そうだな。
「…分かったよ」
そこまで覚悟を決めているなら、躊躇うことはないな。
シルナなら大丈夫…そう信じるしかないな。
いや、信じよう。
俺は、シルナの相棒だからな。
助走の為だ。
少し助走して、橋の先端ギリギリまで来たら、思いっきり踏み込んでジャンプ。
食料庫に向かってダイブする。それだけ。
実に分かりやすい。
さて、手が届くと良いのだが。
ビビッてちゃ始まらない。
恐怖で足が竦む前に、さっさと飛ぼう。
「…よし」
生憎俺は、まだ死ぬ気はないんでね。
精々、生きて明日の陽の光を拝ませてもらおう。
俺は助走をつけて、先端ギリギリに来たとき、強く箸を蹴りつけた。
ふわりと身体が中に浮かんだ。
行け。届け。
時間としては、恐らく1秒くらいの出来事だったのだろうが。
俺にとっては、まるでスローモーションのように感じた。
「ふっ…ぐ…!」
精一杯伸ばした手が、食料庫の縁に届いた。
…よし…届いた。
手を滑らせないよう、俺は強く食料庫の縁を掴んだ。
そのまま、ぐいっと身体を持ち上げ、食料庫によじ登った。
…ふぅ。
かなりギリギリではあったが、何とか辿り着けたようだ。
はぁ…ネズミに追いかけられるより、命の危機を感じた。
「羽久!羽久、大丈夫!?」
食器棚から身を乗り出すようにして、シルナが大声で尋ねた。
「大丈夫だ!」
俺もまた、大声で答えた。
けど、今の俺達の大声なんて、通常サイズの人間には全然聞こえないんだろうなぁ。
誰もいないから良いけど。
「よ、良かった、羽久…。じゃあ、私も行くね!」
「いや、ちょっと待て」
後から続こうとするシルナを、俺は制止した。
「どうしたの?」
「…」
…今しがた、俺が飛んでみて分かったが。
目で見るより、結構距離があった。
俺でさえギリギリ届いたのだ。
運動音痴でビビリチキンなシルナでは、届かないかもしれない。
シルナまで飛ぶのは、危険過ぎる。
「やっぱり、お前はそっちで待っててくれ。ここは俺が…」
「やだ、行く!」
…駄々っ子かよ。
「無理をするなって言ってるんだ。お前じゃ届かない…」
「いや、絶対に行く」
「…シルナ…」
「羽久が行くところには、私も行く。それが何処かは関係ない」
…そうか。
…そうだな。
「…分かったよ」
そこまで覚悟を決めているなら、躊躇うことはないな。
シルナなら大丈夫…そう信じるしかないな。
いや、信じよう。
俺は、シルナの相棒だからな。
「…よし、シルナ。じゃあ、こっちに超巨大なケーキがあると思って飛べ」
「ケーキ!?」
食いついた。
「あぁ、お前の好きなチョコケーキだ」
「チョコ…!」
「チョコクリームたっぷりで」
「クリーム…!」
「イチゴもたくさん乗ってる」
「イチゴ…!」
「そうだ。そんな魅惑のチョコケーキがここにあると思って、思いっきり飛ぶんだ」
「チョコケーキ、チョコケーキ…よし!絶対辿り着いてみせるよ!」
洗脳完了。
こんな状況で、こんなおまじないに、どれくらい効果があるのかは分からないが。
何もしないよりはマシだ。
俺達を見て、チェシャ猫は相変わらずにやにやしているが。
手を出してこないなら、あいつは放置で良い。
「…よし、いつでも良いぞ、シルナ」
俺は食料庫の縁に立って、飛んでくるシルナを待ち受けた。
いざとなったら、こちらからも手を伸ばそう。
一緒に落ちるかもしれないが、一人で落ちるよりは遥かにマシだから、別に良いや。
「チョコケーキ、チョコケーキ…。…チョコケーキ!!」
シルナはチョコケーキを連呼しながら、助走をつけて飛んだ。
シルナにしては、相当頑張ってる。
ふわりと宙を浮いたシルナの身体が、こちらに迫ってくる。
…しかし。
「…くっ…!」
…その距離は、僅かに足りない。
運動音痴のせいか。それともシルナの方が重いのか。
そんなことはどうでも良い。
俺は咄嗟に手を伸ばし、落ちるシルナの腕を掴んだ。
肩、脱臼しそうなくらい痛かったが。
今は、それどころではなかった。
「大丈夫か、シルナ!?」
「う、うぐ…お、落ちる…!」
「引っ張るから、しっかり掴まってろ!」
俺は両手でシルナの腕を掴み、シルナもまた、両手で俺の腕にしがみついた。
よし、それで良い。
あとは、俺が全力で引き上げるのみ。
さっきから、ネズミから逃げたり、テーブルクロスをつたってテーブルに登ったり。
食器にしがみついて食器棚に飛び移ったり、肩車されて鍋をよじ登ったりと。
正直、疲労困憊して、そろそろ身体が悲鳴をあげていたが。
そんな甘っちょろいこと言ってる場合じゃない。
命が懸かってるのだ。やるしかない。
明日は筋肉痛確定だな。
俺達に明日があれば、の話だが。
まずは、生きて陽の目を拝むことが最優先だ。
「ふぐっ…!重い…!お前、もっと痩せろよ…!」
「そ、そんなこと言われても…」
「こ、の…デブ学院長め…!」
悪態をつきながら、俺は全力でシルナを引っ張り上げ。
ついに、シルナを食料庫に引き上げることに成功した。
…これで、無事に二人共、食料庫に飛び移れたことになる。
安堵と疲労感のあまり、その場に崩れ落ちてしまった。
…はぁ、死ぬかと思った…。
「ケーキ!?」
食いついた。
「あぁ、お前の好きなチョコケーキだ」
「チョコ…!」
「チョコクリームたっぷりで」
「クリーム…!」
「イチゴもたくさん乗ってる」
「イチゴ…!」
「そうだ。そんな魅惑のチョコケーキがここにあると思って、思いっきり飛ぶんだ」
「チョコケーキ、チョコケーキ…よし!絶対辿り着いてみせるよ!」
洗脳完了。
こんな状況で、こんなおまじないに、どれくらい効果があるのかは分からないが。
何もしないよりはマシだ。
俺達を見て、チェシャ猫は相変わらずにやにやしているが。
手を出してこないなら、あいつは放置で良い。
「…よし、いつでも良いぞ、シルナ」
俺は食料庫の縁に立って、飛んでくるシルナを待ち受けた。
いざとなったら、こちらからも手を伸ばそう。
一緒に落ちるかもしれないが、一人で落ちるよりは遥かにマシだから、別に良いや。
「チョコケーキ、チョコケーキ…。…チョコケーキ!!」
シルナはチョコケーキを連呼しながら、助走をつけて飛んだ。
シルナにしては、相当頑張ってる。
ふわりと宙を浮いたシルナの身体が、こちらに迫ってくる。
…しかし。
「…くっ…!」
…その距離は、僅かに足りない。
運動音痴のせいか。それともシルナの方が重いのか。
そんなことはどうでも良い。
俺は咄嗟に手を伸ばし、落ちるシルナの腕を掴んだ。
肩、脱臼しそうなくらい痛かったが。
今は、それどころではなかった。
「大丈夫か、シルナ!?」
「う、うぐ…お、落ちる…!」
「引っ張るから、しっかり掴まってろ!」
俺は両手でシルナの腕を掴み、シルナもまた、両手で俺の腕にしがみついた。
よし、それで良い。
あとは、俺が全力で引き上げるのみ。
さっきから、ネズミから逃げたり、テーブルクロスをつたってテーブルに登ったり。
食器にしがみついて食器棚に飛び移ったり、肩車されて鍋をよじ登ったりと。
正直、疲労困憊して、そろそろ身体が悲鳴をあげていたが。
そんな甘っちょろいこと言ってる場合じゃない。
命が懸かってるのだ。やるしかない。
明日は筋肉痛確定だな。
俺達に明日があれば、の話だが。
まずは、生きて陽の目を拝むことが最優先だ。
「ふぐっ…!重い…!お前、もっと痩せろよ…!」
「そ、そんなこと言われても…」
「こ、の…デブ学院長め…!」
悪態をつきながら、俺は全力でシルナを引っ張り上げ。
ついに、シルナを食料庫に引き上げることに成功した。
…これで、無事に二人共、食料庫に飛び移れたことになる。
安堵と疲労感のあまり、その場に崩れ落ちてしまった。
…はぁ、死ぬかと思った…。
あまりに疲れ過ぎて、もうこのまま倒れ込んで、しばらく休みたい。
…が、そんなことをしている余裕はない。
すぐに立ち上がって、招待状を探さなくては。
「羽久、大丈夫?立てる?」
「はぁ、しんど…。…大丈夫だ。自分で立てる」
俺はよろめきながらも、自分の足で立ち上がった。
ここでへばってる暇はないぞ。
へばるなら、せめて招待状を見つけてからだ。
…すると、シルナは何を思ったか。
「…はっ!チョコケーキは!?」
あ?
「チョコクリームとイチゴたっぷりの、巨大チョコケーキ…」
…洗脳が効き過ぎている。
「あれは嘘だ。方便だ!さっさと探すぞ」
「えぇぇぇ…!チョコケーキ…!」
うるせぇ。
アホなこと言ってないで、招待状を探すぞ。
正直、俺ももう体力の限界だからな。
この食料庫になかったら、そろそろお手上げだ。
「これは…牛乳の瓶か。こっちは、ジャムの瓶…」
食料庫に保存されている食材を眺めながら、俺は招待状が紛れ込んでいないかを確認した。
バターやヨーグルトなんかもある。
乳製品勢揃いだな。
「こっちは…凄い匂い。チーズだろうな…」
このサイズじゃ、たかがチーズの匂いも相当強烈だ。
鼻が曲がりそう。
「…それにしても、羽久」
と、シルナが口を開いた。
「何だ?」
チョコケーキは、ここにはないぞ。
しかし、シルナが口にしたのは、チョコケーキのことではなかった。
「…何だかここ、寒くない?」
…シルナにそう言われて、初めて。
俺は、身体にひんやりと感じる、冷たい空気に包まれていることに気がついた。
あまりの疲労感と、さっきシルナを引っ張り上げたせいで、身体が熱くなっていたから、分からなかったが。
ここ、めちゃくちゃ寒くないか?
「もしかして…もしかしてなんだけど…ここって、もしかして冷蔵庫?」
「…そうかもしれない」
耳を澄ませたら、冷蔵庫が駆動する、ゴーッという低い音も聞こえる。
食料庫だと思ってたけど、これ冷蔵庫だったのか。
いや、でも。
「ドア開いてたじゃん。冷蔵庫なのに…」
「開けっ放しになってるみたいだよ。…ほら」
シルナの指差す方に、開けっ放しの冷蔵庫のドアがあった。
マジかよ。全然気づかなかった。
つーか、冷蔵庫を開けっ放しにするなよ。
まぁ、開けっ放しにしてくれていたお陰で、何とかここに入れたんだけど。
冷蔵庫の閉め忘れ。冬場はともかく、夏場は洒落にならんから、気をつけような。
俺との大事な約束だ。
「あー、そうと気づいたら寒っ…」
冷蔵庫の中なんだから、寒いのは当然。
冷凍庫じゃなかったのは幸いだが、冷蔵庫でも寒いことに変わりはない。
長くここにいたら、体温が下がり過ぎて危険だな。
早いところ探してしまおう。
…と、思ったそのとき。
「…ん?…シルナ、あれ」
「え?」
俺は、冷蔵庫に保管されていた、ケース入りの卵の片隅に。
青い、小さな封筒らしきものを見つけた。
…が、そんなことをしている余裕はない。
すぐに立ち上がって、招待状を探さなくては。
「羽久、大丈夫?立てる?」
「はぁ、しんど…。…大丈夫だ。自分で立てる」
俺はよろめきながらも、自分の足で立ち上がった。
ここでへばってる暇はないぞ。
へばるなら、せめて招待状を見つけてからだ。
…すると、シルナは何を思ったか。
「…はっ!チョコケーキは!?」
あ?
「チョコクリームとイチゴたっぷりの、巨大チョコケーキ…」
…洗脳が効き過ぎている。
「あれは嘘だ。方便だ!さっさと探すぞ」
「えぇぇぇ…!チョコケーキ…!」
うるせぇ。
アホなこと言ってないで、招待状を探すぞ。
正直、俺ももう体力の限界だからな。
この食料庫になかったら、そろそろお手上げだ。
「これは…牛乳の瓶か。こっちは、ジャムの瓶…」
食料庫に保存されている食材を眺めながら、俺は招待状が紛れ込んでいないかを確認した。
バターやヨーグルトなんかもある。
乳製品勢揃いだな。
「こっちは…凄い匂い。チーズだろうな…」
このサイズじゃ、たかがチーズの匂いも相当強烈だ。
鼻が曲がりそう。
「…それにしても、羽久」
と、シルナが口を開いた。
「何だ?」
チョコケーキは、ここにはないぞ。
しかし、シルナが口にしたのは、チョコケーキのことではなかった。
「…何だかここ、寒くない?」
…シルナにそう言われて、初めて。
俺は、身体にひんやりと感じる、冷たい空気に包まれていることに気がついた。
あまりの疲労感と、さっきシルナを引っ張り上げたせいで、身体が熱くなっていたから、分からなかったが。
ここ、めちゃくちゃ寒くないか?
「もしかして…もしかしてなんだけど…ここって、もしかして冷蔵庫?」
「…そうかもしれない」
耳を澄ませたら、冷蔵庫が駆動する、ゴーッという低い音も聞こえる。
食料庫だと思ってたけど、これ冷蔵庫だったのか。
いや、でも。
「ドア開いてたじゃん。冷蔵庫なのに…」
「開けっ放しになってるみたいだよ。…ほら」
シルナの指差す方に、開けっ放しの冷蔵庫のドアがあった。
マジかよ。全然気づかなかった。
つーか、冷蔵庫を開けっ放しにするなよ。
まぁ、開けっ放しにしてくれていたお陰で、何とかここに入れたんだけど。
冷蔵庫の閉め忘れ。冬場はともかく、夏場は洒落にならんから、気をつけような。
俺との大事な約束だ。
「あー、そうと気づいたら寒っ…」
冷蔵庫の中なんだから、寒いのは当然。
冷凍庫じゃなかったのは幸いだが、冷蔵庫でも寒いことに変わりはない。
長くここにいたら、体温が下がり過ぎて危険だな。
早いところ探してしまおう。
…と、思ったそのとき。
「…ん?…シルナ、あれ」
「え?」
俺は、冷蔵庫に保管されていた、ケース入りの卵の片隅に。
青い、小さな封筒らしきものを見つけた。
冷蔵庫の奥まで歩いて、卵の影から封筒を引っ張り出す。
封筒には、青い薔薇の模様が描かれていた。
「…シルナ…これって…」
もしかして…もしかするのでは?
「…!開けてみよう」
「あぁ」
俺は封筒を開け、中に入っていたものを取り出した。
封筒には、2枚のカードが入っていた。
…それは、二人分の招待状だった。
俺とシルナ、一枚ずつ。
アリスのお茶会に参加する為の招待状。
思わず、歓喜の声をあげそうになった。
…良かった。間に合った。
俺もシルナも、制限時間内に招待状を見つけたのだ。
…生きた心地しなかったなぁ…。
でも、無事に見つけることが出来たのだ。
これで、アリスのお茶会に行ける。
「はぁ…良かった…」
安堵のあまり、その場に座り込んで脱力しそうになったが。
そういうことは、冷蔵庫から出てやろう。
こんなところで座り込んだら、凍え死ぬっての。
「シルナ、冷蔵庫から出よう」
「うん…!良かったぁ…」
シルナも、この満面の笑みである。
命が助かったのだから、当然だな。
あとはこの招待状を持って、アリスのお茶会に臨むだけ。
他の皆も、同じく招待状を見つけられていれば良いのだが…。
…そう考えながら、冷蔵庫から出ようと、足を踏み出したとき。
「…ケケケッ」
悪趣味なチェシャ猫の笑い声が聞こえ。
同時に、ガン、と床に物か落ちる音がした。
「…?」
菜箸だ。
俺達が橋代わりに使った菜箸を、チェシャ猫が前脚で蹴っ飛ばして、床に落としたのだ。
…いや、もうあの橋は使わないから、別に落としても良いけど…。
あいつ、何やってんだ…?
チェシャ猫のムカつく笑い顔を見ながら、俺は首を傾げた。
何がやりたいのか知らんが、俺達はさっさとここから出…、
「?今の、何の音?」
厨房に、メイド服の女性が一人、戻ってきた。
「…やばっ…!」
「羽久、隠れて!」
俺とシルナは、すぐさまチーズの影に身を隠した。
菜箸が床に落ちた音を聞きつけて、ネズミ頭のメイドさんが戻ってきたのだ。
くそ、あのチェシャ猫、余計なことを…。
もう少しで脱出出来たのに…。
「…?菜箸…?何でこんなところに…」
メイドさんは、床に落ちた一本だけの菜箸を拾い上げた。
ごめんな、それ、俺達が無断使用した。
…更に。
「…あ、冷蔵庫開けっ放し…」
ネズミ頭のメイドさんは、ドアが開け放たれたままの冷蔵庫に気がついた。
…今気づくのか、それ。
何だか、途端に嫌な予感が…。
「全くもう…。誰が閉め忘れたのかしら…」
…そう、言いながら。
ネズミ頭のメイドさんは、冷蔵庫のドアを掴み。
…ばたん、と閉めた。
「…」
「…」
閉じられた冷蔵庫のドアの内側を、俺達はしばし、呆然と見つめていた。
「…ケケケッ」
チェシャ猫の嘲笑が、冷蔵庫の中まで聞こえてきた。
…なぁ。
…これってもしかして、俺達…超ピンチなのでは?
封筒には、青い薔薇の模様が描かれていた。
「…シルナ…これって…」
もしかして…もしかするのでは?
「…!開けてみよう」
「あぁ」
俺は封筒を開け、中に入っていたものを取り出した。
封筒には、2枚のカードが入っていた。
…それは、二人分の招待状だった。
俺とシルナ、一枚ずつ。
アリスのお茶会に参加する為の招待状。
思わず、歓喜の声をあげそうになった。
…良かった。間に合った。
俺もシルナも、制限時間内に招待状を見つけたのだ。
…生きた心地しなかったなぁ…。
でも、無事に見つけることが出来たのだ。
これで、アリスのお茶会に行ける。
「はぁ…良かった…」
安堵のあまり、その場に座り込んで脱力しそうになったが。
そういうことは、冷蔵庫から出てやろう。
こんなところで座り込んだら、凍え死ぬっての。
「シルナ、冷蔵庫から出よう」
「うん…!良かったぁ…」
シルナも、この満面の笑みである。
命が助かったのだから、当然だな。
あとはこの招待状を持って、アリスのお茶会に臨むだけ。
他の皆も、同じく招待状を見つけられていれば良いのだが…。
…そう考えながら、冷蔵庫から出ようと、足を踏み出したとき。
「…ケケケッ」
悪趣味なチェシャ猫の笑い声が聞こえ。
同時に、ガン、と床に物か落ちる音がした。
「…?」
菜箸だ。
俺達が橋代わりに使った菜箸を、チェシャ猫が前脚で蹴っ飛ばして、床に落としたのだ。
…いや、もうあの橋は使わないから、別に落としても良いけど…。
あいつ、何やってんだ…?
チェシャ猫のムカつく笑い顔を見ながら、俺は首を傾げた。
何がやりたいのか知らんが、俺達はさっさとここから出…、
「?今の、何の音?」
厨房に、メイド服の女性が一人、戻ってきた。
「…やばっ…!」
「羽久、隠れて!」
俺とシルナは、すぐさまチーズの影に身を隠した。
菜箸が床に落ちた音を聞きつけて、ネズミ頭のメイドさんが戻ってきたのだ。
くそ、あのチェシャ猫、余計なことを…。
もう少しで脱出出来たのに…。
「…?菜箸…?何でこんなところに…」
メイドさんは、床に落ちた一本だけの菜箸を拾い上げた。
ごめんな、それ、俺達が無断使用した。
…更に。
「…あ、冷蔵庫開けっ放し…」
ネズミ頭のメイドさんは、ドアが開け放たれたままの冷蔵庫に気がついた。
…今気づくのか、それ。
何だか、途端に嫌な予感が…。
「全くもう…。誰が閉め忘れたのかしら…」
…そう、言いながら。
ネズミ頭のメイドさんは、冷蔵庫のドアを掴み。
…ばたん、と閉めた。
「…」
「…」
閉じられた冷蔵庫のドアの内側を、俺達はしばし、呆然と見つめていた。
「…ケケケッ」
チェシャ猫の嘲笑が、冷蔵庫の中まで聞こえてきた。
…なぁ。
…これってもしかして、俺達…超ピンチなのでは?
冷蔵庫に、閉じ込められてしまった。
ここまで来て、こんな目に遭うか。
折角、無事に招待状を見つけたというのに。
最後の最後で、とんでもない落とし穴に突き落とされてしまった。
…とりあえず、あのチェシャ猫は絶対に許さない。
あのけばけばしい毛、毟りまくってやる。
しかし、その前にまずは、ここから出なければならなかった。
「ど、どどどどどうしよう!どうしよう!?」
シルナ、大パニック。
気持ちは分かるが、まずは落ち着こう。
落ち着ける状況ではないが、それでも落ち着こう。
狼狽えて騒ぎ立てて、良いことなんて何もない。
「落ち着け、シルナ。何とか…何か方法を考えよう」
我ながら、声が上ずってるような気がしなくもないか。
…ひとまず。
「炎魔法使おう。少しでも、体温を保てるように…」
「あ、そ、そっか…」
炎魔法を発動させ、それで暖を取ることにした。
とは言っても、今の俺達では、こんなのは気休めにしかならない。焼け石に水。
何もしないよりは多少マシ、な程度か。
…さて、これからどうしたものか。
長くは持たない。体温が下がって動けなくなる前に、早いところ脱出しなければ。
「だ、脱出…。脱出用の道具とか、設置されてないかな…?」
…業務用の冷蔵庫だったら。
万が一閉じ込められたときの為に、緊急脱出用のボタンや道具が、ドアの内側に設置されてるらしいな。
しかし。
「そんなもの、ついてたとしても…。今の俺達じゃ使えないだろ」
「あ、そっか…」
さすがに、テントウムシサイズの脱出口までは用意されてはいない。
炎魔法で暖を取り、体温が下がらないよう細心の注意を払いながら、誰かが冷蔵庫を開けてくれるのを辛抱強く待つか。
それとも…自分達で何とかするか。
…このどちらかだ。
さぁ、どちらを選ぶべきか…。
「…なんて、選択肢なんて一つしかないよな」
考えるだけ無駄、って奴だ。
ここで、誰かが冷蔵庫を開けてくれるのを待っている暇はない。
誰が、いつ開けてくれるかも分からないのに。
ましてや、今厨房の中には誰もいない。
先程菜箸を拾い、冷蔵庫のドアを閉めたネズミメイドも、既に厨房から立ち去ったようだ。
あと、冷蔵庫の外にいるのは…あのムカつくチェシャ猫くらいだが。
あいつが開けてくれるはずがない。むしろ、開けようとするのを妨害してくる恐れもある。
メイドにも、チェシャ猫にも期待は出来ない。
いつ開けてもらえるのか、そもそも開けてもらえるのかも分からない。
こうしている間にも、刻一刻とお茶会の時間が迫っている。
なら、持久戦に持ち込むのは現実的ではない。
体温が下がる前に…まだ身体が満足に動くうちに、やれることはやっておくべきだ。
情けないテントウムシサイズでも、俺達は無力ではないのだということを、あのムカつくチェシャ猫に思い知らせてやる。
そして、尻尾の毛の一束でも毟ってやる。
その為には、何としても冷蔵庫から脱出しなくては。
ここまで来て、こんな目に遭うか。
折角、無事に招待状を見つけたというのに。
最後の最後で、とんでもない落とし穴に突き落とされてしまった。
…とりあえず、あのチェシャ猫は絶対に許さない。
あのけばけばしい毛、毟りまくってやる。
しかし、その前にまずは、ここから出なければならなかった。
「ど、どどどどどうしよう!どうしよう!?」
シルナ、大パニック。
気持ちは分かるが、まずは落ち着こう。
落ち着ける状況ではないが、それでも落ち着こう。
狼狽えて騒ぎ立てて、良いことなんて何もない。
「落ち着け、シルナ。何とか…何か方法を考えよう」
我ながら、声が上ずってるような気がしなくもないか。
…ひとまず。
「炎魔法使おう。少しでも、体温を保てるように…」
「あ、そ、そっか…」
炎魔法を発動させ、それで暖を取ることにした。
とは言っても、今の俺達では、こんなのは気休めにしかならない。焼け石に水。
何もしないよりは多少マシ、な程度か。
…さて、これからどうしたものか。
長くは持たない。体温が下がって動けなくなる前に、早いところ脱出しなければ。
「だ、脱出…。脱出用の道具とか、設置されてないかな…?」
…業務用の冷蔵庫だったら。
万が一閉じ込められたときの為に、緊急脱出用のボタンや道具が、ドアの内側に設置されてるらしいな。
しかし。
「そんなもの、ついてたとしても…。今の俺達じゃ使えないだろ」
「あ、そっか…」
さすがに、テントウムシサイズの脱出口までは用意されてはいない。
炎魔法で暖を取り、体温が下がらないよう細心の注意を払いながら、誰かが冷蔵庫を開けてくれるのを辛抱強く待つか。
それとも…自分達で何とかするか。
…このどちらかだ。
さぁ、どちらを選ぶべきか…。
「…なんて、選択肢なんて一つしかないよな」
考えるだけ無駄、って奴だ。
ここで、誰かが冷蔵庫を開けてくれるのを待っている暇はない。
誰が、いつ開けてくれるかも分からないのに。
ましてや、今厨房の中には誰もいない。
先程菜箸を拾い、冷蔵庫のドアを閉めたネズミメイドも、既に厨房から立ち去ったようだ。
あと、冷蔵庫の外にいるのは…あのムカつくチェシャ猫くらいだが。
あいつが開けてくれるはずがない。むしろ、開けようとするのを妨害してくる恐れもある。
メイドにも、チェシャ猫にも期待は出来ない。
いつ開けてもらえるのか、そもそも開けてもらえるのかも分からない。
こうしている間にも、刻一刻とお茶会の時間が迫っている。
なら、持久戦に持ち込むのは現実的ではない。
体温が下がる前に…まだ身体が満足に動くうちに、やれることはやっておくべきだ。
情けないテントウムシサイズでも、俺達は無力ではないのだということを、あのムカつくチェシャ猫に思い知らせてやる。
そして、尻尾の毛の一束でも毟ってやる。
その為には、何としても冷蔵庫から脱出しなくては。
…とはいえ。
いくら俺達が、渾身の力を込めて、ドアを内側から体当りしても。
まず、びくともしないであろうことは、試すまでもない。
そんな方法で開くなら、苦労はしない。
当然だが、ぴっちりとしまったドアに、通り抜けられそうな隙間もない。
そもそも、冷蔵庫のドアが閉められたことによって、庫内灯が消えてしまい。
今、冷蔵庫の中は真っ暗だ。
これじゃあ、脱出に使えそうなものがないか、探し回ることも出来ない。
炎魔法で、かろうじて足元と、お互いの位置だけは分かっている状態。
周囲の様子が見えないと、余計に心許なくなってくるな…。
この状況で、俺達に出来ることは…。
「…魔法に頼るしかないね。こうなったら」
シルナは、冷静にそう言った。
…まぁ、そうだよな。
人の身でどうにか出来ることではないのだから、人智を超えた力でどうにかするしかない。
イーニシュフェルト魔導学院の教師を名乗るなら、魔法で事態を解決してみせろ。
…いずれにしても、他に方法はないしな。
あとは、魔法でどうやって、ここから脱出するかだが…。
普段なら、力押しでどうにかするところ。
しかし、テントウムシサイズの今の俺達は、貧弱な魔法しか使えない。
力押しには頼れないだろう。
そうなると、知恵を巡らせ、工夫を凝らしてこの場を突破…、
「…よし。ここは力押しで何とかしよう」
…とてもじゃないが、知略に優れたイーニシュフェルトの里出身で、
イーニシュフェルト魔導学院の学院長をも務める、ルーデュニア聖王国指折りの魔導師の台詞とは思えんな。
結局力押しかよ。
「時間をかけてはいられないからね。…既に寒くて震えてるし」
ご老人には辛い環境。
「気持ちは分かるが…。今の俺達が、力押しでどうにか出来るのか?」
「ただ闇雲に魔力をぶつけるだけじゃ、当然通らない…。でも、私の魔法なら…分身を大量に作って、本体の私が最大力の魔法を撃ち込んで、それを分身で反射、相乗することによって、本体が撃ち込める魔力の限界を遥かに越えて…」
…やべぇ。なんかぶつぶつ言ってる。
邪魔しない方が良さそうだ。
とにかく、この状況を何とかする為の策を講じていることは確かだ。
力押しとは言ったが、全くの無策で力押しする訳ではないようだ。
「…よし、やろう」
シルナはそう言って、杖を握り締めた。
…プランは決まったようだ。
「俺に何か出来ることは?」
「大丈夫。羽久には、もう充分助けてもらったよ。今度は私が助ける番だ」
「…シルナ…」
「絶対何とかしてみせる。…終わったら多分へばってるだろうから、肩貸してね」
悪戯っぽく、そう笑ってから。
「…よし、じゃあやろうか」
瞳に強い決意を宿し、杖を振った。
…これがテントウムシサイズじゃなかったら、さぞかし決まってただろうに。
まぁ、そこまで贅沢は言うまい。
シルナの頑張りに期待しよう。
いくら俺達が、渾身の力を込めて、ドアを内側から体当りしても。
まず、びくともしないであろうことは、試すまでもない。
そんな方法で開くなら、苦労はしない。
当然だが、ぴっちりとしまったドアに、通り抜けられそうな隙間もない。
そもそも、冷蔵庫のドアが閉められたことによって、庫内灯が消えてしまい。
今、冷蔵庫の中は真っ暗だ。
これじゃあ、脱出に使えそうなものがないか、探し回ることも出来ない。
炎魔法で、かろうじて足元と、お互いの位置だけは分かっている状態。
周囲の様子が見えないと、余計に心許なくなってくるな…。
この状況で、俺達に出来ることは…。
「…魔法に頼るしかないね。こうなったら」
シルナは、冷静にそう言った。
…まぁ、そうだよな。
人の身でどうにか出来ることではないのだから、人智を超えた力でどうにかするしかない。
イーニシュフェルト魔導学院の教師を名乗るなら、魔法で事態を解決してみせろ。
…いずれにしても、他に方法はないしな。
あとは、魔法でどうやって、ここから脱出するかだが…。
普段なら、力押しでどうにかするところ。
しかし、テントウムシサイズの今の俺達は、貧弱な魔法しか使えない。
力押しには頼れないだろう。
そうなると、知恵を巡らせ、工夫を凝らしてこの場を突破…、
「…よし。ここは力押しで何とかしよう」
…とてもじゃないが、知略に優れたイーニシュフェルトの里出身で、
イーニシュフェルト魔導学院の学院長をも務める、ルーデュニア聖王国指折りの魔導師の台詞とは思えんな。
結局力押しかよ。
「時間をかけてはいられないからね。…既に寒くて震えてるし」
ご老人には辛い環境。
「気持ちは分かるが…。今の俺達が、力押しでどうにか出来るのか?」
「ただ闇雲に魔力をぶつけるだけじゃ、当然通らない…。でも、私の魔法なら…分身を大量に作って、本体の私が最大力の魔法を撃ち込んで、それを分身で反射、相乗することによって、本体が撃ち込める魔力の限界を遥かに越えて…」
…やべぇ。なんかぶつぶつ言ってる。
邪魔しない方が良さそうだ。
とにかく、この状況を何とかする為の策を講じていることは確かだ。
力押しとは言ったが、全くの無策で力押しする訳ではないようだ。
「…よし、やろう」
シルナはそう言って、杖を握り締めた。
…プランは決まったようだ。
「俺に何か出来ることは?」
「大丈夫。羽久には、もう充分助けてもらったよ。今度は私が助ける番だ」
「…シルナ…」
「絶対何とかしてみせる。…終わったら多分へばってるだろうから、肩貸してね」
悪戯っぽく、そう笑ってから。
「…よし、じゃあやろうか」
瞳に強い決意を宿し、杖を振った。
…これがテントウムシサイズじゃなかったら、さぞかし決まってただろうに。
まぁ、そこまで贅沢は言うまい。
シルナの頑張りに期待しよう。
「rltea oge、yopc…」
シルナが杖を振ると、その周囲に、無数のシルナ分身が現れた。
ワンチャン、分身はもとのサイズだったら良いなぁと思ったのだが。
やっぱり、ミニチュアサイズの分身だった。
しかし、シルナはそんなことでは落胆しない。
「…solinesh」
今、シルナが出せる最大出力の魔法が、シルナの杖に宿った。
テントウムシサイズとは思えないほどの魔力だ。
更にこの魔力を、何倍にも「強化」して、冷蔵庫のドアに叩きつけ、風穴を開ける。
馬鹿みたいな力押しだが…出来ないことではない。
「…rirorm」
シルナの莫大な魔力が、光の速度で分身達に反射。
何倍、いや…もとの火力の何十、何百倍にも威力を増した、眩しいほどに強大な魔力の塊が。
「…っ!!」
凄まじい爆音を立てて、冷蔵庫のドアに叩きつけられた。
庫内が、がくんがくんと揺れた。
…危うく、俺まで吹き飛ばされるところだった。
チーズの影に隠れて、衝撃を受け流した。
もうもうと立ち込める煙が、ようやく晴れると。
無数のシルナ分身は消えて、本体のシルナのみになっていた。
「…シルナ…!」
「はぁ…はぁ…」
珍しく息を荒くしたシルナが、その場にがくんと膝をつきそうになった。
それを、俺はすんでのところで支えた。
「シルナ…!大丈夫か?」
「うん…だ、だいじょう、ぶ…」
…とてもじゃないが、大丈夫そうには見えないぞ。
「お前…!無茶しやがって…」
「…あはは…。久し振りに…ちょっと頑張ってみちゃった…。…けど…」
…けど?
シルナは、すっと目の前を指差した。
「『成果』は…あったみたいだよ」
「…あぁ、そうだな」
固く閉ざされていたはずの、冷蔵庫のドアに…風穴が開いていた。
精々、普通サイズの人間の、親指くらいの大きさではあるけども。
今の俺達が脱出するには、充分な大きさだった。
…ざまぁ、チェシャ猫。
ここから出たら、約束通りお前の毛を毟ってやるからな。
「…行くぞ、シルナ」
「…うん…!」
俺は招待状を二通、口に咥え。
両手でシルナを支えながら、冷蔵庫の外に飛び出した。
…その瞬間、俺達はここに転送されたときと同じ…青い光に包まれた。
シルナが杖を振ると、その周囲に、無数のシルナ分身が現れた。
ワンチャン、分身はもとのサイズだったら良いなぁと思ったのだが。
やっぱり、ミニチュアサイズの分身だった。
しかし、シルナはそんなことでは落胆しない。
「…solinesh」
今、シルナが出せる最大出力の魔法が、シルナの杖に宿った。
テントウムシサイズとは思えないほどの魔力だ。
更にこの魔力を、何倍にも「強化」して、冷蔵庫のドアに叩きつけ、風穴を開ける。
馬鹿みたいな力押しだが…出来ないことではない。
「…rirorm」
シルナの莫大な魔力が、光の速度で分身達に反射。
何倍、いや…もとの火力の何十、何百倍にも威力を増した、眩しいほどに強大な魔力の塊が。
「…っ!!」
凄まじい爆音を立てて、冷蔵庫のドアに叩きつけられた。
庫内が、がくんがくんと揺れた。
…危うく、俺まで吹き飛ばされるところだった。
チーズの影に隠れて、衝撃を受け流した。
もうもうと立ち込める煙が、ようやく晴れると。
無数のシルナ分身は消えて、本体のシルナのみになっていた。
「…シルナ…!」
「はぁ…はぁ…」
珍しく息を荒くしたシルナが、その場にがくんと膝をつきそうになった。
それを、俺はすんでのところで支えた。
「シルナ…!大丈夫か?」
「うん…だ、だいじょう、ぶ…」
…とてもじゃないが、大丈夫そうには見えないぞ。
「お前…!無茶しやがって…」
「…あはは…。久し振りに…ちょっと頑張ってみちゃった…。…けど…」
…けど?
シルナは、すっと目の前を指差した。
「『成果』は…あったみたいだよ」
「…あぁ、そうだな」
固く閉ざされていたはずの、冷蔵庫のドアに…風穴が開いていた。
精々、普通サイズの人間の、親指くらいの大きさではあるけども。
今の俺達が脱出するには、充分な大きさだった。
…ざまぁ、チェシャ猫。
ここから出たら、約束通りお前の毛を毟ってやるからな。
「…行くぞ、シルナ」
「…うん…!」
俺は招待状を二通、口に咥え。
両手でシルナを支えながら、冷蔵庫の外に飛び出した。
…その瞬間、俺達はここに転送されたときと同じ…青い光に包まれた。
―――――――…青い、光に包まれ。
私が降り立ったのは、目がちかちかしそうなカラフルな部屋だった。
…ここは?
気がつくと私は、ハンガーにかけられた、たくさんの…ドレスに囲まれた部屋にいた。
カラフルだと思ったものは、どうやらこのドレスの数々だった模様。
見たところ…衣装部屋、のようですね。
ここは、『不思議の国のアリス』が作り出した世界。
くそったれなハンプティ・ダンプティに、『不思議の国のアリス』について説明され。
アリスのお茶会とやらに参加する為、私達はそれぞれ、お茶会の招待状を探さなければならないらしい。
…非常に面倒ですね。
全く、私はこのようなことをしている暇はないというのに。
魔導教育委員会に提出する書類が、まだ書きかけのまま職員室の机の上に放置されているし。
来週授業で使う資料も、まだ完成させていない。
下らないお茶会などさっさと済ませて、学院に戻りたいですね。
アリス云々などより、明日の授業のことの方が、私にとっては遥かに大事です。
…それで、この部屋は一体何なのか。
私が引いたトランプのカードは、ハートのクイーンだった。
つまりここは、さしづめ「ハートの女王の世界」ということなのでしょう。
…非情にどうでも良いですね。
…そのとき。
衣装部屋の窓から、外の景色が見えた。
思わず、私は窓辺に歩み寄った。
…窓から見える、この世界の外の景色。
「…気色悪いですね」
さすがは不思議の国、といったところでしょうか。
青いはずの空は白く。
白い雲の代わりに、金色の懐中時計が宙に浮き。
おまけにその時計の針は、過去を刻むかのように逆回転していた。
…ふん。
こんなこけおどしで、私がびびるとでも思ったのでしょうか。
だとしたら、片腹痛いですね。
…ともあれ。
気色悪い外の景色を、悠長に眺めている暇はない。
制限時間までに、アリスのお茶会の招待状…とやらを、見つけなければならないんでしたね。
じゃあ、さっさと探すとしましょう。
まずは、この雑多な衣装部屋から。
あまりにたくさんの衣服が散乱していて、思わず全部ゴミ袋に叩き込みたくなるけれど。
残念ながら、掃除をしている暇はない。
一枚一枚ドレスを退かして、早速招待状を探し始めた…。
…そのとき。
「…ケケケッ」
「…」
非常に不愉快な笑い声が聞こえて、私は振り返った。
私が降り立ったのは、目がちかちかしそうなカラフルな部屋だった。
…ここは?
気がつくと私は、ハンガーにかけられた、たくさんの…ドレスに囲まれた部屋にいた。
カラフルだと思ったものは、どうやらこのドレスの数々だった模様。
見たところ…衣装部屋、のようですね。
ここは、『不思議の国のアリス』が作り出した世界。
くそったれなハンプティ・ダンプティに、『不思議の国のアリス』について説明され。
アリスのお茶会とやらに参加する為、私達はそれぞれ、お茶会の招待状を探さなければならないらしい。
…非常に面倒ですね。
全く、私はこのようなことをしている暇はないというのに。
魔導教育委員会に提出する書類が、まだ書きかけのまま職員室の机の上に放置されているし。
来週授業で使う資料も、まだ完成させていない。
下らないお茶会などさっさと済ませて、学院に戻りたいですね。
アリス云々などより、明日の授業のことの方が、私にとっては遥かに大事です。
…それで、この部屋は一体何なのか。
私が引いたトランプのカードは、ハートのクイーンだった。
つまりここは、さしづめ「ハートの女王の世界」ということなのでしょう。
…非情にどうでも良いですね。
…そのとき。
衣装部屋の窓から、外の景色が見えた。
思わず、私は窓辺に歩み寄った。
…窓から見える、この世界の外の景色。
「…気色悪いですね」
さすがは不思議の国、といったところでしょうか。
青いはずの空は白く。
白い雲の代わりに、金色の懐中時計が宙に浮き。
おまけにその時計の針は、過去を刻むかのように逆回転していた。
…ふん。
こんなこけおどしで、私がびびるとでも思ったのでしょうか。
だとしたら、片腹痛いですね。
…ともあれ。
気色悪い外の景色を、悠長に眺めている暇はない。
制限時間までに、アリスのお茶会の招待状…とやらを、見つけなければならないんでしたね。
じゃあ、さっさと探すとしましょう。
まずは、この雑多な衣装部屋から。
あまりにたくさんの衣服が散乱していて、思わず全部ゴミ袋に叩き込みたくなるけれど。
残念ながら、掃除をしている暇はない。
一枚一枚ドレスを退かして、早速招待状を探し始めた…。
…そのとき。
「…ケケケッ」
「…」
非常に不愉快な笑い声が聞こえて、私は振り返った。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…