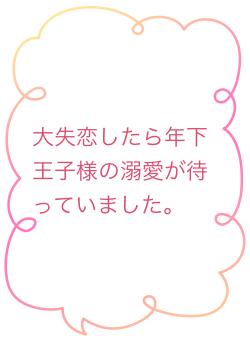「漣っ、顔っ!かお近いっ!!」
両の腕で蓮の胸をグイグイ押すも、無駄な抵抗みたいだった。
漣はわたしの髪に触れ、頬に触れ、額にキスを落とし…、
そして、唇に触れるだけのキスを。
「…れんっ、」
「これ以上はしないから」
「え、」
「ふっ、して欲しい?」
「ちが…っ!」
「みあのこと傷付けないことが結婚の絶対条件だし、そうじゃなくても俺自身の意思としてもみあのこと傷付けたくない。みあは俺にとって自分の命よりも大切な唯一の女の子だからな」
わたしの頭を優しく撫でながら、漣は自身にブレーキをかけるように言葉を紡ぐ。
そんな漣の気持ちに少しでも近付きたくて、
「ありがとう。待ってて。漣の気持ちにすぐ追い付くから」
言えば、
「みあ、俺のみあへの愛の深さ、舐めてない?」
もの凄く不本意な顔をされてしまった。
「…プッ、舐めてるかも」
「まあ、一生かかっても追いつけまいよ」
クスクス笑いながら何回もキスを重ねて、微笑みあって、ふたりで眠りに落ちた。