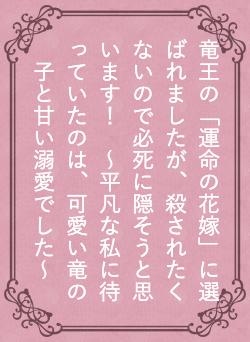「…………っ!」
牢屋から連れ出された彼女は、たった一晩で今にも倒れそうなほど弱りきっていた。顔は青ざめ、頬には涙の痕が痛々しいほど残っていた。
大きな瞳はただ虚ろで、何も見ていない。処刑が行われる聖女の崖に到着してようやく、俺の存在に気がついたようだ。一瞬目を見開き驚いた顔をしていたが、これから行われることを理解し、そっと目を伏せた。
その健気な姿に、胸がえぐられるような痛みが走る。
(あと少し、あと少しで君を助けてあげられる!)
細心の注意を払って、王女を欺かなくては。少しの違和感でも感じさせたら、彼女を突き落とす役目を他の者に譲るだろう。いや王女本人が、やるつもりかもしれない。
そうなったら全てが台無しだ。王女が剣を持つ腕をわざと前に動かし彼女を傷つけようとも、気付かないふりをしてやり過ごした。
「……悪く思わないでくれ」
これから俺がすることは、君を助ける行為だ。だからどうかこのまま動かないでほしい。俺に身を任せて、一緒に崖から飛び降りてくれ。