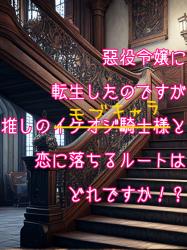「大丈夫ですか!?」
先生の声。大きすぎる物音に、ハッとした。
次の瞬間、私の中には『絶望』の文字が浮かんだ。
「……ごめんなさい」
声が震えた。泣きたくなった。手からこぼれた書道具一式が、目の前に散らばっている。
その下で、『個展の準備』と言っていた大きな紙に、墨の跡がついている。顔を伏せれば、倒れた私の下では、紙がしわくちゃに折り曲がっていた。
「ほんっとうにごめんなさい! 私……、なんてことを……」
おっちょこちょいにも程がある。ダメだ、バカだ、何をやっているんだろう。
もう、本当に、私のバカ、バカ、バカ――。
涙をこらえて息を吐き出すと、溜息みたいになってしまった。それで、余計に申し訳なくなった。
「宍戸さん、立てますか?」
先生は私の前に回り、手を差し出していた。
「え? あ、……はい。あの、本当にごめんなさい……」
先生に差し出された手を取り、立ち上がる。罪悪感でいっぱいで、先生の顔を見られない。
「大丈夫ですよ。文字は書き直せばいいだけです。それに、悪いのは私の方です。こんなものを広げたまま、お客様をここに上げて。……お怪我は、ありませんか?」
ろくに確認もせず、こくりとうなずいた。足元に広がる書道具としわくちゃになった紙は、先生の優しい言葉によって私を余計に罪悪感に苛ませる。
「では、失礼しますね」
先生はそう言うと、私の手を離した。すると次の瞬間、身体がふわりと浮いた。
「え……っ!?」
驚き顔を上げると、目の前に先生のアップが迫る。どうやら私は、先生に横抱きにされているらしい。
「すみません、また滑って宍戸さんが怪我をしてしまったら申し訳ないですし、それに硯が割れて破片が飛び散っているといけないので」
先生はそう言いながら、私を優しくリビングのソファに下ろしてくれた。
「座っていてください。温かいお茶を淹れてきます」
先生はキッチンへ去っていく。
私は座ったまま、今度はヘマをしまいと固まっていた。
リビングのテーブルの上に、古い古文書のようなものや、古い本が広げてあったのだ。
――これ、とても高価なもののような気がする。これは絶対に汚せない!
茶を淹れて戻ってきた先生は、テーブルの上にそれらが広がっていることに気が付き、慌てて隅の方に重ねた。
「すみません、散らかっていて。あまり人を家に呼ばないもので、片付けができていないんですよ」
先生は恥ずかしそうに笑って、それから私の前にお茶を出す。しかし、それを手にしてしまっては、古い貴重な資料のようなそれにこぼしてしまいそうで怖い。
動けずにいると、先生は向かいに座り文字通り首をかしげた。
「宍戸さん、先程のことなら気にしないでくださいね? 本当に、大丈夫ですから」
先生は笑った。無理やり笑ってもらっているような気がして、申し訳なくて、お茶に手を伸ばした。
「熱っ……!」
湯呑に触れた手を、慌てて引っ込めた。
それがいけなかった。
「あ……」
だから思ったのに。
どうして私は、こんなにも落ち着きがないのだろう。
見事に湯呑を倒してしまった。その古い資料ような紙に、お茶が少し染みてしまった。
先生の声。大きすぎる物音に、ハッとした。
次の瞬間、私の中には『絶望』の文字が浮かんだ。
「……ごめんなさい」
声が震えた。泣きたくなった。手からこぼれた書道具一式が、目の前に散らばっている。
その下で、『個展の準備』と言っていた大きな紙に、墨の跡がついている。顔を伏せれば、倒れた私の下では、紙がしわくちゃに折り曲がっていた。
「ほんっとうにごめんなさい! 私……、なんてことを……」
おっちょこちょいにも程がある。ダメだ、バカだ、何をやっているんだろう。
もう、本当に、私のバカ、バカ、バカ――。
涙をこらえて息を吐き出すと、溜息みたいになってしまった。それで、余計に申し訳なくなった。
「宍戸さん、立てますか?」
先生は私の前に回り、手を差し出していた。
「え? あ、……はい。あの、本当にごめんなさい……」
先生に差し出された手を取り、立ち上がる。罪悪感でいっぱいで、先生の顔を見られない。
「大丈夫ですよ。文字は書き直せばいいだけです。それに、悪いのは私の方です。こんなものを広げたまま、お客様をここに上げて。……お怪我は、ありませんか?」
ろくに確認もせず、こくりとうなずいた。足元に広がる書道具としわくちゃになった紙は、先生の優しい言葉によって私を余計に罪悪感に苛ませる。
「では、失礼しますね」
先生はそう言うと、私の手を離した。すると次の瞬間、身体がふわりと浮いた。
「え……っ!?」
驚き顔を上げると、目の前に先生のアップが迫る。どうやら私は、先生に横抱きにされているらしい。
「すみません、また滑って宍戸さんが怪我をしてしまったら申し訳ないですし、それに硯が割れて破片が飛び散っているといけないので」
先生はそう言いながら、私を優しくリビングのソファに下ろしてくれた。
「座っていてください。温かいお茶を淹れてきます」
先生はキッチンへ去っていく。
私は座ったまま、今度はヘマをしまいと固まっていた。
リビングのテーブルの上に、古い古文書のようなものや、古い本が広げてあったのだ。
――これ、とても高価なもののような気がする。これは絶対に汚せない!
茶を淹れて戻ってきた先生は、テーブルの上にそれらが広がっていることに気が付き、慌てて隅の方に重ねた。
「すみません、散らかっていて。あまり人を家に呼ばないもので、片付けができていないんですよ」
先生は恥ずかしそうに笑って、それから私の前にお茶を出す。しかし、それを手にしてしまっては、古い貴重な資料のようなそれにこぼしてしまいそうで怖い。
動けずにいると、先生は向かいに座り文字通り首をかしげた。
「宍戸さん、先程のことなら気にしないでくださいね? 本当に、大丈夫ですから」
先生は笑った。無理やり笑ってもらっているような気がして、申し訳なくて、お茶に手を伸ばした。
「熱っ……!」
湯呑に触れた手を、慌てて引っ込めた。
それがいけなかった。
「あ……」
だから思ったのに。
どうして私は、こんなにも落ち着きがないのだろう。
見事に湯呑を倒してしまった。その古い資料ような紙に、お茶が少し染みてしまった。