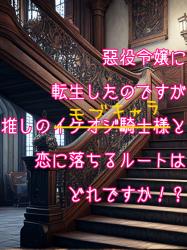「メディアに出てみようって思えたのも、杏凪さんのおかげです。自分は自分、それでいいんだって、言ってくれたから」
「先生……」
優しい手の温もりと、紡がれる夢みたいな言葉に、心が震えた。
目頭がジンとして、気付いたら涙が頬を伝っていた。
「だから、杏凪さんに気持ちを伝えるなら、文字を書いて伝えようと思いました。一緒に読み解いた恋文のように、伝えたいと思いました」
「でも、あの書き方はズルいです。……私、最初あの恋文の現代語訳だと思って――」
顔を上げると、先生がはっと目を見開く。それから、柔らかな親指の腹で、優しく頬をなぞり、溢れた涙を拭ってくれた。
「仕方ないじゃないですか。あの恋文を記した彼女の気持ちと、私の気持ちが同じだったんですから」
「本当、ズルい……」
先生はふふっと笑った。
「私はズルい男です。ズルい男は、嫌ですか?」
――だから、その聞き方がズルい。
「嫌なわけ、ないじゃないですか……」
先生の目を見つめた。
眼鏡の奥の彼の瞳に、私がだけが映っている。
その事実がどうしようもなく嬉しくて、泣いているのに頬が緩んでくる。
「可愛いですね」
その言葉に、急に顔全体が熱くなる。
すると、先生の目が、口元が、優しく細められていく。
「……もう!」
思わず視線をそらせば、ふふっと笑い声が聞こえた。
「すみません、杏凪さん、ひとつだけ……」
「何でしょう……?」
「『先生』っていうの、やめてもらえませんか? 何だか、いけないことをしている気がしてしまって」
ハッとした。
デジャブだ、と思ったが、あれは夢の中の話だ。
先生は知らない。顔をそむけていてよかった。
それなのに。
「こっちを向いて、名前を呼んでくれませんか?」
顎に指を置かれ、クイッと先生の方を向かされた。ニコニコと微笑む先生の圧に、「言えません」とは言えなくなる。
「えっと……佳之、さん」
その瞬間、唇に柔らかな感覚を覚えた。
口づけだと気付いたのは、彼の唇が離れていってからだった。
「好きです、杏凪さん」
彼はそう言うと、もう一度私の唇に優しい口づけを落とす。
――私も、好きです。
思いを込めて、私も彼の唇に自分のそれを押し付ける。
幸せが胸に流れ込んできて、いつものマイナス思考が入り込む余地もない。
プラスな未来を想像しながら、ほのかに墨の香りを感じる彼の部屋で、私は彼のキスに酔いしれた。
〈完〉
「先生……」
優しい手の温もりと、紡がれる夢みたいな言葉に、心が震えた。
目頭がジンとして、気付いたら涙が頬を伝っていた。
「だから、杏凪さんに気持ちを伝えるなら、文字を書いて伝えようと思いました。一緒に読み解いた恋文のように、伝えたいと思いました」
「でも、あの書き方はズルいです。……私、最初あの恋文の現代語訳だと思って――」
顔を上げると、先生がはっと目を見開く。それから、柔らかな親指の腹で、優しく頬をなぞり、溢れた涙を拭ってくれた。
「仕方ないじゃないですか。あの恋文を記した彼女の気持ちと、私の気持ちが同じだったんですから」
「本当、ズルい……」
先生はふふっと笑った。
「私はズルい男です。ズルい男は、嫌ですか?」
――だから、その聞き方がズルい。
「嫌なわけ、ないじゃないですか……」
先生の目を見つめた。
眼鏡の奥の彼の瞳に、私がだけが映っている。
その事実がどうしようもなく嬉しくて、泣いているのに頬が緩んでくる。
「可愛いですね」
その言葉に、急に顔全体が熱くなる。
すると、先生の目が、口元が、優しく細められていく。
「……もう!」
思わず視線をそらせば、ふふっと笑い声が聞こえた。
「すみません、杏凪さん、ひとつだけ……」
「何でしょう……?」
「『先生』っていうの、やめてもらえませんか? 何だか、いけないことをしている気がしてしまって」
ハッとした。
デジャブだ、と思ったが、あれは夢の中の話だ。
先生は知らない。顔をそむけていてよかった。
それなのに。
「こっちを向いて、名前を呼んでくれませんか?」
顎に指を置かれ、クイッと先生の方を向かされた。ニコニコと微笑む先生の圧に、「言えません」とは言えなくなる。
「えっと……佳之、さん」
その瞬間、唇に柔らかな感覚を覚えた。
口づけだと気付いたのは、彼の唇が離れていってからだった。
「好きです、杏凪さん」
彼はそう言うと、もう一度私の唇に優しい口づけを落とす。
――私も、好きです。
思いを込めて、私も彼の唇に自分のそれを押し付ける。
幸せが胸に流れ込んできて、いつものマイナス思考が入り込む余地もない。
プラスな未来を想像しながら、ほのかに墨の香りを感じる彼の部屋で、私は彼のキスに酔いしれた。
〈完〉