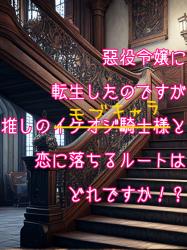「では、次はここです。『あなた』『苦しい』と、彼女の筆跡を分析して読みましたが、どうです?」
それから1時間ほど。先生はお手上げだというように私を見上げて、口をとがらせる。
「苦しい時もあなたを見ていると頑張れる、というような文かと思ったのですが、『頑張る』に値するような文字が見つからず、――」
「――彼女は、きっと苦しかったんですよ」
「え?」
「思いが募りすぎて、苦しかった。思いを伝えられず、内にとどめておくのが辛かった。だけど、同じくらい気持ちを伝えるのも辛い。怖い。だったら、見てるだけでもいい。……そんな気持ちだったんじゃないかな、と」
顔を上げると、先生は顎に手を当て考え込んでいた。
「恋は苦しい、ですか」
私はこくりとうなずいた。
「好きになってしまったら、その気持ちってどうしようもなく溢れてきちゃうものじゃないですか。止められない。私はこんなに好きなのに、あなたは私をそういうふうには見ていない。だから、苦しい。そんな気持ちを、綴ったんじゃないですか……?」
先生は私の方を向いた。
隣同士で座ったソファ、至近距離で目が合う。ドキリと胸が鳴る。
じっと見つめられ、思わずパッと目を逸らしてしまった。
頬が熱い。先生はこんなこと、きっと思っていないだろうけれど。
「すみません……」
先生は小声で呟いた。
「宍戸さんの言葉が興味深くて、つい。本当、子供っぽくて……お恥ずかしい」
「い、いえ! そういうのじゃ、ないですか、ら……」
じゃあどういうのだ、と自分に問うけれど、胸に抱いた淡い気持ちに名前をつけるのも違う気がして、私の語尾は濁る。
「それに、こういうの……趣味っていうんですか? いいなって思うから……私は、その……趣味とか、なくて、だから……」
何を取り繕って喋っているのだろう。私の方が、本当恥ずかしい。
先生はふふっと笑った。
「ありがとうございます」
先生の方をちらりと見た。優しい笑みが浮かんでいて、なぜか無性に安心した。
「宍戸さんは、おもしろいですね」
それから1時間ほど。先生はお手上げだというように私を見上げて、口をとがらせる。
「苦しい時もあなたを見ていると頑張れる、というような文かと思ったのですが、『頑張る』に値するような文字が見つからず、――」
「――彼女は、きっと苦しかったんですよ」
「え?」
「思いが募りすぎて、苦しかった。思いを伝えられず、内にとどめておくのが辛かった。だけど、同じくらい気持ちを伝えるのも辛い。怖い。だったら、見てるだけでもいい。……そんな気持ちだったんじゃないかな、と」
顔を上げると、先生は顎に手を当て考え込んでいた。
「恋は苦しい、ですか」
私はこくりとうなずいた。
「好きになってしまったら、その気持ちってどうしようもなく溢れてきちゃうものじゃないですか。止められない。私はこんなに好きなのに、あなたは私をそういうふうには見ていない。だから、苦しい。そんな気持ちを、綴ったんじゃないですか……?」
先生は私の方を向いた。
隣同士で座ったソファ、至近距離で目が合う。ドキリと胸が鳴る。
じっと見つめられ、思わずパッと目を逸らしてしまった。
頬が熱い。先生はこんなこと、きっと思っていないだろうけれど。
「すみません……」
先生は小声で呟いた。
「宍戸さんの言葉が興味深くて、つい。本当、子供っぽくて……お恥ずかしい」
「い、いえ! そういうのじゃ、ないですか、ら……」
じゃあどういうのだ、と自分に問うけれど、胸に抱いた淡い気持ちに名前をつけるのも違う気がして、私の語尾は濁る。
「それに、こういうの……趣味っていうんですか? いいなって思うから……私は、その……趣味とか、なくて、だから……」
何を取り繕って喋っているのだろう。私の方が、本当恥ずかしい。
先生はふふっと笑った。
「ありがとうございます」
先生の方をちらりと見た。優しい笑みが浮かんでいて、なぜか無性に安心した。
「宍戸さんは、おもしろいですね」