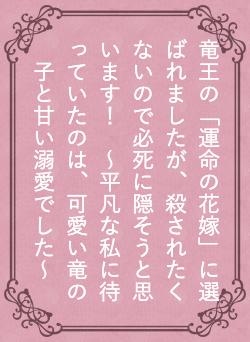「ニセモノのあなたより、私の方がグレッグ様を幸せにできるわ」
先日そう言った彼女が、婚約者のグレッグの胸に顔をうずめている。信じられない気持ちで見ていると、グレッグの腕が彼女の背中にまわろうとした。彼女は私の方を見て、ニヤリと笑っている。
その瞬間、私は弾かれたように2人に背を向け走り出した。曇っていた空は暗い雨雲に変わり、私の頬を雨粒が濡らしていく。
(いつから……? だってこの前の夜会も、その次の日もいつもどおりだったのに)
2人がいつからこんな関係になっていたのかわからない。私は原因を探るように、ほんの数日前の日々を思い出し始めていた。
「まあ! 今夜もレイラ様とグレッグ様の美しさは際立っているわ」
「ドレスもマダムロゼのものよ。センスが良いわ」
「グレッグ様は騎士団で鍛えてるだけあって、凛々しくていらっしゃるわね」
「本当にお2人は完璧ですわ」
今夜の夜会も私達が顔を出したとたん、噂話が耳に入ってくる。美しい宮廷音楽に色とりどりのドレス。令嬢なら心ときめかせて過ごすはずなのに、私はさっきから上の空だ。今日は蒸すわね。早く家に帰りたい。そんな私の気持ちなどおかまいなしに、私達2人と話そうとやってくる人の列は絶えない。
「レイラ、次はハワード侯爵夫人だ。さっき教えた本の題名を覚えているか?」
「……?」
「乙女の誓いだ。夫人お抱えの作家が書いている作品だから、話題に出すように」
「わかりましたわ」
(乙女の誓い、乙女の誓い、乙女の…… よし! 覚えたわ!)
私はいつもの様にグレッグから指示を受け、笑顔でハワード夫人を待ち受ける。
「レイラ! お久しぶりね! 最近見なかったけど、どうしていたの?」
「……少し体調を崩しておりまして、ようやく元気を取り戻したところです」
「まあ! お若いのに」
「ええ、でも療養中も今話題の……乙女の誓いという本に慰められましたわ」
「まあ! あなたも読んでいるの? あれ、実は私の――」
ふう、うまくいったわ。思い出せなくて少し妙な間があいたけど、これで大丈夫! あとはグレッグがうまくやってくれるから、隣で微笑んでいればいい。案の定グレッグは私から会話を引きつぎ、ハワード夫人と楽しそうに話し始めた。
「ハワード夫人、僕もレイラにすすめられて、乙女の誓いを読ませていただきました」
「まあ! あなたまで? 男性は読まないどころか、馬鹿にする方もいらっしゃるのに! 嬉しいわ」
「ええ、とても素敵な本で、夢中で読みましたよ。特にヒロインのシャーロットが婚約者に捨てられた後、健気に孤児院で働くところに心を打たれました。またシャーロットが襲われた時。121ページですね。現れた騎士団長のマルクのセリフですが――」
「え? え? そ、そんなに?」
ちょっとグレッグ! 感想を一気にまくしたてるから、ハワード夫人引いているじゃない。彼の腕にぎゅっと力をこめると、その意味に気づいたグレッグは、とろけるような甘い微笑みで振り返った。
「――とレイラが熱心に語ってくれました。ね、レイラ」
「ええ、そうね」
2人揃ってにっこりとハワード夫人に向かって微笑むと、感激した夫人は「読書会を開くから、ぜひ来てほしい」と言って、上機嫌で去っていった。
「グレッグったら興奮しすぎよ。そんなにあの……乙女のなんたらが好きなの?」
「題名忘れるの早いぞ。あの本は最近の少女小説の中でも最高傑作に近い。俺は昨夜も2回読んでから寝た」
「まあ……早く寝ればよろしいのに」
「寝るのが好きな君からしたらそうだろうな。体調を崩していたのではなく、ただお茶会が面倒で寝てただけだと知ったら、みんな驚くだろう」
「寝ること以上に楽しいことはありません」
私達が2人になるとすぐに顔を近づけ話すものだから、まわりからは「愛し合っているのね」「本当に素敵」という声が再び聞こえてきた。
(ふう、今日もなんとか、完璧な令嬢としてごまかせたわ)
そう、私レイラ・クライトン伯爵令嬢は、社交界で完璧な令嬢だと思われている。でも本当の私は無趣味で、少女小説はもちろんドレスや舞踏会にも興味がない。令嬢の嗜みである刺繍もグレッグが作ってくれる。社交も彼が指示してくれないとわからない、完璧とはほど遠い「ニセモノ令嬢」だ。
反対に婚約者のグレッグ・ラウザー伯爵令息は、女性が好むものは全て好きらしい。少女小説を愛読し自分で作ったケーキを食べ、大切に育てたハーブティーを飲む。趣味はもちろん刺繍。最近は真面目に頑張っているけど、本当は騎士団の仕事も嫌がっていた。
それでも鍛えられたたくましい体でタキシードを着こなす姿は、私が隣にいるのにも関わらず令嬢達の視線を一身に惹きつけている。