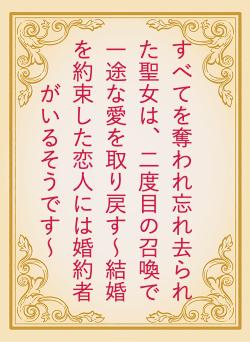「だが、その頃には父親より、俺のほうが強くなっていた。すぐに父は退位し、俺が竜王となったのだが、周囲の感心事は竜王の卵を誰が宿すかになっていく。それが俺にはつらかった」
「それは、結婚が嫌だとかではなく……」
「ああ、俺は二十年、自分の膨大な力をコントロールできず、部屋に一人きりで過ごしていた。あんな生活を自分の子どもにさせたい親などいないだろう?」
今の竜王様は、小さな子どもの竜だ。しかしその姿がよけいに、ひとりぼっちで泣き叫んでいた頃の姿に重なり、気づいた時には私は竜王様をぎゅっと抱きしめていた。
「リコ……」
「次に竜王様のような力のある子が生まれても、私の血でなんとかできます! 話だってできます! だからもう淋しい子は生まれません!」
私の瞳からボロボロとあふれる涙が、竜王様の頭にあたって弾ける。もう、私が竜王様のお妃だって言ってしまおう。私なら安心させられるって、伝えたい。