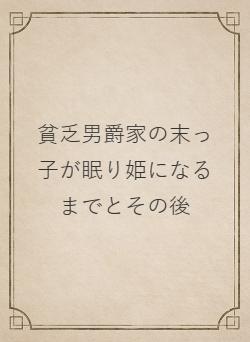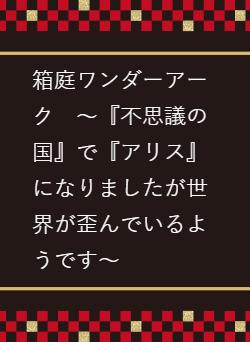「聖女アーテル……いや、アーテル・シュニッツァー! 私は、お前との婚約を破棄する!」
「ありがとうございます! ……って、え?」
完全に人払いがされた王の執務室で、我が国シェーンヴァイトの若き王、クロード・ヴィル・ベルカランテが告げた婚約破棄に、反射で礼を述べてから、私は目を瞬いた。
「あの、申し訳ありません、クロード様。先ほど、聞き違いでなければ『婚約を破棄する』と……?」
「ああ、言った。間違いなく言ったぞ」
「それは、つまり、――つまり、そういうこと……?」
「つまり、そういうことだ」
力強くクロードが頷く。『婚約破棄』という事実がじわじわと心に浸透してきて、私は思わず――快哉をあげた。
「やったー!」
とってつけていた敬語もふっとんだけれど、クロードはそれを咎めることもなくにこにこと満面の笑みでこちらを見ている。
「ああ、やったね」
「なんでそんなに落ちついてるの! 私たちの悲願が、十年越しの夢が叶ったのよ!?」
「俺は一人で達成感を噛みしめた後だから」
「なんでそのときに呼んでくれなかったの!」
「真夜中に君を呼びつけるわけにもいかなかったから」
よそ行き、もとい『王様』の顔を剥がしたクロードの言葉に、それもそうねと納得する。
でも同じ熱量で喜べないことがちょっと悔しくて、さみしい。
「君が何を考えているかは手に取るようにわかるけど、こればっかりはどうしようもない。そもそもの気質も違うし」
「まあ……クロードが私みたいに『やったー!』って諸手を挙げて喜ぶのも何か違うわよね」
「でも君と喜びを分かち合いたいのも本音だよ。というわけで、ささやかだけど祝宴の用意をしておいた」
「わかってるじゃない!」
部屋に入ったときから気になっていたワゴンの正体はそれらしい。
クロード自らテーブルにセッティングしてくれて、祝宴の用意は調った。
「それじゃあ、俺たちの洋々たる前途を祝福して」
「私たちの悲願の成就を祝って」
『乾杯!』
かちん、とグラスを重ねる。
用意されていたのは果実酒だ。ワインがまだあまり舌に馴染まない私に合わせてくれたのだろうことが察せられて、相変わらず隙がないわね、と思う。
「事前に言ってくれれば、私も秘蔵のお酒持ってきたのに。願掛けしてたお酒があったのよ?」
「知ってるよ。でも驚かせたくて。君の秘蔵のお酒は、またの機会にね」
「変なところ遊び心があるんだから……」
「俺も浮かれてるんだよ。許して?」
「許すけど!」
おいしいお酒と、おいしい食事の前に、怒りは持続しない。そもそも本気で怒っているわけでもないし。
「それで……政治と教会の分離が叶ったのね?」
「うん。父の説得が成ったからね。議会はねじ伏せた後だし、これでもう、教会と政治は完全に分離できた。……一応だけどね」
「それでもすごいわ! そりゃあ、完全に影響を無くすことはまだ無理としても、仕組みとしてがっちり絡んでたのを分離できたのは大きいわよ」
「君のおかげだよ。本当にありがとう」
「私はただ、私怨で腐った教会をぶち壊しただけだし……」
「それができるだけの力と頭がある君が、筆頭聖女として立ってくれてなかったらそもそも分離は無理だったよ。ありがとう」
「こちらこそありがとう。これで心置きなく聖女をやめられるわ」
「君の夢だったもんね。……実家に帰るのかい?」
少しだけ、気遣うような視線を向けられて、私は苦笑する。この王様は、出会ったときからずっと、ずっと優しい。
「ううん。もう家族から引き離されて十五年よ? 私なんて行き遅れのお荷物にしかならないもの。実家に顔は出すけれど……」
「教会の『洗脳』は解けたんだろう? 家族だって君と過ごしたいのではない?」
「解けたっていっても、長年続いた思考の方向性の癖はどうにもできないってわかったから……。言ったでしょ? 『洗脳』時に思考のしっかりしていた両親の方が、影響から逃れにくかったって」
「それは聞いたけど……」
私は五歳の時に、『聖女』として見出された。そうしてその時に、家族共々教会に『洗脳』を受けている。『聖女』として見出されるのは誉れ、教会に尽くすのが幸い、どんなに愛しい子どもでも差し出すのが当然、そんなふうに。
幸い、私は『洗脳』を施す者よりも潜在能力が高かった。『聖女』として能力を開花させるにつれて『洗脳』を自力で解けるようになったけれど、家族は違う。他人の『洗脳』を解けるようになってから、こっそりと実家に訪れて『洗脳』を解いたけれど……『洗脳』時にまだ小さかった弟はともかく、両親への『洗脳』は、もう深く思考にしみついてしまっていて、術を解いただけではだめだった。それからも、折りを見ては実家を訪れて、『洗脳』の影響の完全な除去を試していたけれど……。
「君はあんなに、実家に帰りたがっていたのに」
「いつの頃の話よ、もう」
「でも、君の弟は、王族付きの騎士になってまで、君の傍にいようとしてるのに」
「それねぇ、不思議なのよね……」
弟は、『洗脳』の影響から逃れてから、「姉ちゃんをひとりにはしない!」と言って王都まで来て、でも『聖女教』に近寄らせるのは危なすぎたから、クロードに任せたのだ。そうしたらいつの間にか、騎士見習いになって、騎士になっていた。
もう図体はかわいくないけれど、かわいい弟だ。かわいい弟だけど、そこまでしてもらえるほどの関係だったかというと謎だ。
「そこで不思議がっちゃうのが君だよね。……でも、心苦しいな。婚約破棄して君と俺とのつながりがなくなると、弟くんの努力が無に帰してしまうから」
「姉離れするいい機会じゃないかしら?」
「俺は騎士をやめて君のところに行くのに賭けるね」
「あなたが言うと冗談に聞こえないからやめて!?」
「冗談じゃないからね」
そう言って笑うクロードも、結構な苦労をしてきた人だ。
どれだけ金を積めるかで、教会からの聖女派遣が決まっていた頃。それによって、病弱だった異母妹を亡くしたクロードは、密かに教会への不信感を抱いていた。
けれどもうその頃は王家と教会――ひいては政治と教会がずぶずぶだったので、賛同者を得るにもうまく立ち回らないと、『思想』か『存在』そのものかが消されかねなかった。
けれど、父である王は特に教会からの『洗脳』を深く受けていたから、味方を探すのも一苦労で――そんな中、『洗脳』の影響下から逃れ得た聖女(つまり私)と出会ったのだ。教会と王家とのつながりを強くするための婚約者、という立場で。
『洗脳』なんてもので、幸せな家族の元での暮らしを奪い取った教会に一泡吹かせてやりたい私と、政治をほしいままにしつつある教会をどうにか王家から引き剥がしたい、そして異母妹のような不幸な例を無くしたいクロード。
こう比べると私の方が私怨丸出しすぎて恥ずかしいけれど、まあそれは資質と教育の差ということで。
ともあれ、手を組んだ私たちは、いろんな人の『洗脳』を密かに解きつつ、教会内部を掌握する私と、『洗脳』が薄い人や解けた人々を味方につけて、理想とする政治のあり方へと近づけていくクロード、という感じで役割分担をし、雌伏の時を過ごしていたわけだけど――。
「それにしても……まさか君が先に動くとは思わなかったから、あの時はびっくりしたよ」
「だって、勘づかれちゃって万事休すだったんだもの。こうなったら力業でぶち壊すしかないと思って……」
「それで本当にぶち壊せちゃうから、君は希代の聖女なんだよね」
「聖女としての力だけは強いみたいだから」
「聖女の力だけで人はついてこないよ。君の人柄もあるよ、絶対」
真っ正面からそんなことを言ってくるクロードに、ちょっと気恥ずかしい気持ちになるものの、そう言ってもらえるのは嬉しい。
「人柄って言ったら、それこそクロードの方がすごいじゃない。たくさんの人に慕われてるし、頭もいいし、話術もすごいし、それに……」
「待って待って、そこまでにして。君に褒められるとなんだか恥ずかしいよ」
「さっきの私の気持ちを思い知った?」
「わかった、わかったから」
そんな会話をして、目を見合わせて、くすくすと笑い合う。
穏やかな時間だ。こんな時間を過ごせる日が本当に来るなんて、家族から引き離されて絶望したあの日には思いもしなかった。
「それで、聖女やめて、実家には戻らないで、どこに行くつもり?」
「それなのよね。聖女はやめるけど、この力を本当に必要としている場所ってやっぱりあると思うから、旅でもしようかと思って」
「諸国漫遊の旅?」
「まあ、そんな感じかしら。聖女として他国に派遣されたときもあったけど、もう全然楽しくもなんともなかったし、肩の力を抜いて気楽に、この力を活かしていこうかなって」
「いいと思うよ。でも、他国に行くなら、聖女時代に『洗脳』を解いたりして関わった人たちも君に会いたいだろうから、会ってあげるといいんじゃないかな」
「聖女のときに会った人なんて、王侯貴族ばっかりじゃない。聖女じゃなくなった私はただの行き遅れの平民なんだから、会えるはずないわよ」
「……これが、知らぬは本人ばかりなり、か」
「え?」
「ううん、なんでもない。君って本当に、自分の価値に無頓着だよね」
「何の話?」
「君の自己評価の話」
「?」
「ま、そのうちわかるよ」
意味深な、何か含みのある笑みが気にならなくはなかったけれど、こういうときのクロードが詳しく説明してくれないのは経験則でわかっている。
とりあえず用意された食事とお酒を楽しみつつ、私は気になっていたことを聞く。
「そういうクロードは、これからどうするの?」
「どうするって……普通に王としてこの国を治めるけど?」
「そうじゃなくて、お妃様の話」
「婚約破棄が成ったばっかりなのに、もう次の話?」
クロードが目を丸くするけれど、私は知っているのだ。
「メアリ・フォルテ嬢」
「……!」
「王子時代、私の欠席した夜会で、虐められてるメアリ嬢を助けたことがきっかけで交流が続いてるって聞いてるわ。もちろん、『婚約者のいる身分』として逸脱しない程度に――別に、逸脱してくれて構わなかったのよ?」
「それは君に不誠実過ぎるだろう」
「かったいわね。まあ、そういうあなただから、メアリ嬢も惹かれたんでしょうけど」
「なっ……」
「いや、想い合ってることくらいわかるから。聖女の情報網舐めちゃだめよ」
「君の耳には入ってるだろうなとは思ってたけど、その……想い合ってるとかは……」
「ない、なんて言ったらメアリ嬢泣いちゃうわよ。いや、聞いた人となりだと、涙を堪えて身を引く感じかしら。ちゃんと捕まえときなさいよ」
「……了解」
降参、というようにクロードが両手をあげる。
私は満足して、グラスに残っていたお酒を一気にあおった。
「あー、おいしい! 人の恋の話をつまみに呑むお酒はおいしい!」
「飲み過ぎないようにね。君、そんなにお酒強くないんだから」
「それを見越して弱めのお酒を用意してくれてるでしょ? 本当、隙がないわよね」
「こんなところに隙を作ってどうするの。ほら、注いであげる」
おいしそうな音を立てて、グラスにお酒が注がれる。
それをちびちびとやりながら、私はちょっとクダを巻いた。
「私も恋愛とかしてみたかったな~。まあそれどころじゃなかったけど」
「それどころじゃなかったのに恋愛しててごめん……」
「そういう意味じゃなくて! わかってるのよ、私に魅力がないだけの話だって」
「いや、それはない。俺にとって君が恋愛対象にならなかっただけで、君は魅力的な人だよ」
「そういうのしらふで言わない! ……いや、しらふじゃなかったわ、あなたも呑んでるわね、ちゃんと」
「そう、ちゃんと呑んでるからこんなことも言える。……俺にとって君は、同志で、盟友で、そして何より――救いの聖女だったから」
「……え」
「天が遣わしてくれた救いの聖女だと、本気で思ってたんだよ。だから恋愛って感じにならなかったっていうか」
「えええ」
そんなの、そんなの聞いてない。今まで一度も。
そう言うと、そりゃあね、とクロードは頷いた。お酒のせいか、目元がちょっと赤くなっている。
「君は出会ったときから心強い味方で、今この時代に俺が君に会えたのは、天の采配だと思った。でもそんなこと言ったら、君、俺の正気を疑ったでしょう」
当たり前だ。違う方向の『洗脳』を受けたのかと思ったに違いない。今このとき、すべてが終わって祝杯を挙げる段階だから、一応受け止められているけれども。
「恋とか愛とか……そういうものにはならなかったけど、君のことはすごく頼りにしているし、頼りにされたいし、何より幸せでいてほしい、そういう気持ちはあるよ。……もし、遠く離れても、ずっと会えなくても、いつだって、君の幸せを祈ってる」
「よ、酔ってるでしょう、クロード」
「そうかな? そうかも。いつもはこれしきの量じゃ酔わないけど、何せ、宿願が叶った祝いの席だからね」
「そ、そうね」
「だから、君、結婚相手を見つけたら絶対俺に会わせてね。君にふさわしいか見定めるからね」
「過激派? 過激派なの? お父さんなの?」
「うん、君の過激派。お父さんよりはお兄ちゃんの気持ちかなぁ。生半なやつに大事な妹はやらんぞー! って」
「……確実に酔ってるわね、クロード」
「お兄ちゃん」
「はい?」
「お兄ちゃんって呼んでよ」
「…………」
……確かに、ちょっと年上の婚約者を、『兄がいたらこんな感じだったのかしら』と思って見たことがないとは言わないけど。
そして、異母妹を亡くしたクロードが、異母妹と歳の近かった私を重ねて見ていた時期があったのもなんとなく察していたけれど。
いい歳した女が、一国の王を、『お兄ちゃん』呼びは、いろんな意味で痛い。
「無理!」
「そんなこと言わずに」
「無理なものは無理!」
「『兄様』呼びでもいいよ?」
「いや私そんなガラじゃないでしょ!?」
「じゃあ『兄さん』で」
「なかなか諦めないわね、この酔っ払い!」
――そんな、ちょっと賑やかで穏やかな夜を越えても。
盟友兼『自称兄』となったクロードとの関係は続き続けていくのだけど――そして私の気楽なはずの旅は、なんだか思ったのと違う方向に転がったりもするのだけど、それを語るのは、また次の機会に。