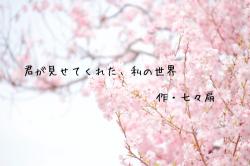「大丈夫ですよ。」
「え……?」
「若の手にかかってる男は、元々処分が下る組の人間ですので。
藤の姫に対して…うちの若姐に対して、あのような態度を取っていたんですから当然です。」
「え、あ…でも…。」
「気にしなくていいのよ、芽来ちゃん。
会合なんてこんなもんなんだから。」
「…姐さん、若姐さん。
おふたりはこちらでお待ちください。
今お茶をお淹れ致しましょう。」
「大丈夫よ、あとは私がやるわ。
藤くんのところに戻ってあげて。」
「承知。…失礼致します。」
案内された部屋の中で。
千歳さんは、紅茶を淹れてくれた。
その時に、まだ自分の手が震えてる事に気がついて…さっきの事が思い出される。
「びっくりしたわよね。…怖かった…?」
「……あの時と、同じでした。
わたしが…藤雅の目の前から、消えた時と…。」
「そう…。
あの子、芽来ちゃんの事になると周りが見えなくなっちゃうのね…。
ごめんね、ろくな息子じゃなくて…。」
「ち、違うんです。
藤雅には本当に、良くしてもらってるんです。
ご飯も作ってくれて、いつも優しくしてくれて…。
わたしのわがままも、嫌な顔しないで聞いてくれて…それで…。」
だから、そんな事言わないで。
藤雅のこと…悪く言わないで。
「え……?」
「若の手にかかってる男は、元々処分が下る組の人間ですので。
藤の姫に対して…うちの若姐に対して、あのような態度を取っていたんですから当然です。」
「え、あ…でも…。」
「気にしなくていいのよ、芽来ちゃん。
会合なんてこんなもんなんだから。」
「…姐さん、若姐さん。
おふたりはこちらでお待ちください。
今お茶をお淹れ致しましょう。」
「大丈夫よ、あとは私がやるわ。
藤くんのところに戻ってあげて。」
「承知。…失礼致します。」
案内された部屋の中で。
千歳さんは、紅茶を淹れてくれた。
その時に、まだ自分の手が震えてる事に気がついて…さっきの事が思い出される。
「びっくりしたわよね。…怖かった…?」
「……あの時と、同じでした。
わたしが…藤雅の目の前から、消えた時と…。」
「そう…。
あの子、芽来ちゃんの事になると周りが見えなくなっちゃうのね…。
ごめんね、ろくな息子じゃなくて…。」
「ち、違うんです。
藤雅には本当に、良くしてもらってるんです。
ご飯も作ってくれて、いつも優しくしてくれて…。
わたしのわがままも、嫌な顔しないで聞いてくれて…それで…。」
だから、そんな事言わないで。
藤雅のこと…悪く言わないで。