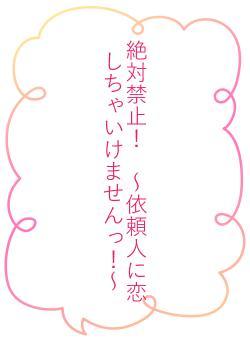「……そんなの、俺が一番おまえのことを知ってるからに決まってるだろ。だって俺、三年後におまえの夫になるんだろ?」
俺が唯菜の耳元でそう囁くと、唯菜が俺の背中のところをきゅっと握りしめ、こくこくと何度もうなずく。
そして――唐突に突き飛ばされた。おい。
「ちょっと! 警報鳴らして減点なんかされたら、トップに追いつけなくなっちゃうでしょ!?」
涙を拭うと、腕組みして唯菜が睨みつけてくる。
はいはい。そーいうヤツだよな。
「あーもう悪かったって。もうしないから安心しろ」
俺は両手をあげて降参した。
ってか、マジでなにやってんだよ、俺。
俺が、ほんとに自分からやったのか? ありえねえ。
だけど、腕の中には唯菜の感触がしっかりと残っていて。
――思っていたよりもずっと華奢な体つきだったな。
だけど、なんだかフワフワして、抱き心地がよくて、ずっと抱きしめていたいような……。
って、だからなに考えてんだよ、俺!
「んで? 将来の夫に、なにがあったのかちゃんと話す気になった?」
必死に平静を装って唯菜から離れた場所にあぐらをかいて座り直すと、唯菜もその場にすとんと腰を下ろした。
「……うん」
俺が唯菜の耳元でそう囁くと、唯菜が俺の背中のところをきゅっと握りしめ、こくこくと何度もうなずく。
そして――唐突に突き飛ばされた。おい。
「ちょっと! 警報鳴らして減点なんかされたら、トップに追いつけなくなっちゃうでしょ!?」
涙を拭うと、腕組みして唯菜が睨みつけてくる。
はいはい。そーいうヤツだよな。
「あーもう悪かったって。もうしないから安心しろ」
俺は両手をあげて降参した。
ってか、マジでなにやってんだよ、俺。
俺が、ほんとに自分からやったのか? ありえねえ。
だけど、腕の中には唯菜の感触がしっかりと残っていて。
――思っていたよりもずっと華奢な体つきだったな。
だけど、なんだかフワフワして、抱き心地がよくて、ずっと抱きしめていたいような……。
って、だからなに考えてんだよ、俺!
「んで? 将来の夫に、なにがあったのかちゃんと話す気になった?」
必死に平静を装って唯菜から離れた場所にあぐらをかいて座り直すと、唯菜もその場にすとんと腰を下ろした。
「……うん」