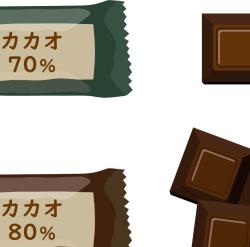私は影山さんを部屋に招き入れ、一枚しかない座布団を敷いた小さなテーブルの前に座ってもらった。
ここでも影山さんは物珍しそうに、キョロキョロと部屋の中を眺めていた。
六畳一間の質素な部屋に、影山さんの目を楽しませるものなど何も無かった。
「あんまりジロジロ見ないでください。恥ずかしいです。」
「いや・・・女の子の部屋ってカンジだな。なんだかいい匂いがするしインテリアも色々可愛く工夫してる。カーテンやクッションも手作り?」
「はい。部屋は和室だけど、なんとなくカントリーっぽくしたくて。これでもインテリア雑誌を見て研究したんです。それが案外楽しくて。・・・でも影山さんは女の子の部屋なんて見慣れてるんじゃないんですか?影山さん、優しいから女性にモテそう。」
「俺なんてモテないよ。金持ってないし。女の子ってプレゼントの一つも買えない男となんて付き合ってもくれないじゃん。・・・田山さんはブランド物のバッグや洋服に興味はないの?」
「興味がないって言ったら嘘になるけど・・・それよりもっと欲しいものがあるんです。」
プラダのバッグ、エルメスの靴、グッチの腕時計、ティファニーのアクセサリー、ヴィトンの財布・・・どれも私には不必要なものだ。
「じゃあ何が欲しいの?」
影山さんが私を見て首をかしげた。
「恥ずかしいから教えません。・・・それより私の宝物、見て下さい。」
私は箪笥の上に飾ってある、サボテンの鉢を、テーブルの上に置いた。
「サボテン?」
「そう。このサボテンは青王丸っていう名前なんです。ちょっとの間しか咲かないけど黄色くて可愛い花が咲くんです。私、このサボテンみたいになりたいんです。どんな環境でも生きていけるように強くなりたい。」
「・・・伊織ちゃんはもう十分強いよ。」
「あれ?私、影山さんに名前教えましたっけ?」
私が不思議そうな顔をすると、影山さんが照れくさそうに笑った。
「あの店のスタッフに君のフルネームを聞いたんだ。君のことがもっと知りたくて。」
私は赤くなった顔を隠すように影山さんから目を逸らし、立ち上がった。
ここで恋のフラグが立ってしまうことは、避けなければならない。
「あの。夕ご飯食べて行ってください。簡単なものしか作れないけど。」
「ああ。じゃ遠慮なくご馳走になろうかな。そして今夜ストーカー男が現れたら俺が捕まえる。」
「え?」
「だから伊織ちゃん、今夜は俺をこの家に泊めてくれる?」
私は昨日買っておいた食材を使って肉じゃがと味噌汁、そしてサバの味噌煮を作った。
私がキッチンに立って料理をしている間、影山さんは再びパソコンを取り出してなにやら作業を始めた。
パソコンを真剣にみつめ、文章を打ち込んでいる。
きっと劇を見た人の心を温かくするような、素敵な脚本を書いているに違いない。
忙しいはずなのに、私なんかの為に動いてくれている影山さんの親切には、感謝の念しかなかった。
出来上がった料理をテーブルに乗せて夕食の準備をし始めると、影山さんはまたもや素早くパソコンを仕舞った。
「本当にお仕事、大丈夫ですか?」
「うん。大丈夫。気にしないで。」
「・・・ならいいけど。」
「お。美味そう!俺、手料理に飢えてるんだよね。」
私の作った料理を見て影山さんは大袈裟にそう言って喜んだ。
「では食べましょうか。」
二人でいただきますと声を合わせて、料理を食べ始めた。
テレビを点けると、お笑い芸人にドッキリを仕掛けるバラエティ番組が映し出された。
巨大な落し穴に突き落とされた太った芸人が、顔じゅう白い粉だらけになりながら大きなリアクションでのたうち回っている。
「あはははっ」
「すっげーな!」
二人して大きな声で笑い合う。
ふいに影山さんが私の手元をみつめた。
「どうしたんですか?」
「いや、伊織ちゃんの箸の使い方、綺麗だなって思って。」
「そんなことないですよ。」
私は影山さんの食べたサバの味噌煮が乗った皿を指さした。
「それを言うなら私の方です。影山さんのお魚の食べ方、とても綺麗。」
「そう?俺は単に食い意地が張ってるだけなんだけどね。」
「ふふっ。そうなんですか?」
「伊織ちゃんの好きな料理ってなに?俺はね、カレーライスとハンバーグ。」
「影山さんの舌って意外とお子様ですね。私は~エビフライとオムライスかな。」
「伊織ちゃんだって人の事言えないだろ?どれもお子様ランチの皿に乗ってる食い物ばかりじゃん。」
「あ!ホントだ!」
それから私と影山さんは、好きなラーメンの味の当てっこをした。
私は味噌味が好きだけど、影山さんは醤油味が好きだった。
誰かと一緒に家で夕食を食べるなんて、何年振りだろう。
誰かの為に食事を作るなんて、初めてのことかもしれない。
それくらい私はずっと冷たい氷のような箱の中で暮らしてきたことに、いま気付いた。
思わず私の口から嗚咽がこぼれ、そんな自分自身に戸惑っていた。
突然泣き出した私に、影山さんは目を見開いて驚いた。
「伊織ちゃん?どうしたの?」
「うっうっ・・・」
「・・・辛かったよな。伊織ちゃんはたったひとりで、今日までよく頑張ったよ。」
影山さんはそう言って私の頭を撫でた。
「ストーカーは俺がなんとかするから、そんなに心配すんな。大丈夫だから。」
「違うの・・・誰かと一緒に食事するのがこんなに楽しいってこと、久々に思い出して・・・。」
「・・・・・・。」
「ウチは一人親だからママは仕事で忙しくて、子供の頃からいつもひとりで食事をすることが多かった。家の中はいつもガランとしていて、空気も冷たくて。ひとり暮らしをした今もそれは変わらなくて。だからこうして影山さんと食事してるのが嬉しくて・・・。」
「伊織ちゃん・・・。」
影山さんは励ますように、私の顔をみて微笑んだ。
「俺も家ではいつもひとりだったよ。俺達似た者同士だね。」
それがどういう意味なのか、その時の私にはわからなかった。
ここでも影山さんは物珍しそうに、キョロキョロと部屋の中を眺めていた。
六畳一間の質素な部屋に、影山さんの目を楽しませるものなど何も無かった。
「あんまりジロジロ見ないでください。恥ずかしいです。」
「いや・・・女の子の部屋ってカンジだな。なんだかいい匂いがするしインテリアも色々可愛く工夫してる。カーテンやクッションも手作り?」
「はい。部屋は和室だけど、なんとなくカントリーっぽくしたくて。これでもインテリア雑誌を見て研究したんです。それが案外楽しくて。・・・でも影山さんは女の子の部屋なんて見慣れてるんじゃないんですか?影山さん、優しいから女性にモテそう。」
「俺なんてモテないよ。金持ってないし。女の子ってプレゼントの一つも買えない男となんて付き合ってもくれないじゃん。・・・田山さんはブランド物のバッグや洋服に興味はないの?」
「興味がないって言ったら嘘になるけど・・・それよりもっと欲しいものがあるんです。」
プラダのバッグ、エルメスの靴、グッチの腕時計、ティファニーのアクセサリー、ヴィトンの財布・・・どれも私には不必要なものだ。
「じゃあ何が欲しいの?」
影山さんが私を見て首をかしげた。
「恥ずかしいから教えません。・・・それより私の宝物、見て下さい。」
私は箪笥の上に飾ってある、サボテンの鉢を、テーブルの上に置いた。
「サボテン?」
「そう。このサボテンは青王丸っていう名前なんです。ちょっとの間しか咲かないけど黄色くて可愛い花が咲くんです。私、このサボテンみたいになりたいんです。どんな環境でも生きていけるように強くなりたい。」
「・・・伊織ちゃんはもう十分強いよ。」
「あれ?私、影山さんに名前教えましたっけ?」
私が不思議そうな顔をすると、影山さんが照れくさそうに笑った。
「あの店のスタッフに君のフルネームを聞いたんだ。君のことがもっと知りたくて。」
私は赤くなった顔を隠すように影山さんから目を逸らし、立ち上がった。
ここで恋のフラグが立ってしまうことは、避けなければならない。
「あの。夕ご飯食べて行ってください。簡単なものしか作れないけど。」
「ああ。じゃ遠慮なくご馳走になろうかな。そして今夜ストーカー男が現れたら俺が捕まえる。」
「え?」
「だから伊織ちゃん、今夜は俺をこの家に泊めてくれる?」
私は昨日買っておいた食材を使って肉じゃがと味噌汁、そしてサバの味噌煮を作った。
私がキッチンに立って料理をしている間、影山さんは再びパソコンを取り出してなにやら作業を始めた。
パソコンを真剣にみつめ、文章を打ち込んでいる。
きっと劇を見た人の心を温かくするような、素敵な脚本を書いているに違いない。
忙しいはずなのに、私なんかの為に動いてくれている影山さんの親切には、感謝の念しかなかった。
出来上がった料理をテーブルに乗せて夕食の準備をし始めると、影山さんはまたもや素早くパソコンを仕舞った。
「本当にお仕事、大丈夫ですか?」
「うん。大丈夫。気にしないで。」
「・・・ならいいけど。」
「お。美味そう!俺、手料理に飢えてるんだよね。」
私の作った料理を見て影山さんは大袈裟にそう言って喜んだ。
「では食べましょうか。」
二人でいただきますと声を合わせて、料理を食べ始めた。
テレビを点けると、お笑い芸人にドッキリを仕掛けるバラエティ番組が映し出された。
巨大な落し穴に突き落とされた太った芸人が、顔じゅう白い粉だらけになりながら大きなリアクションでのたうち回っている。
「あはははっ」
「すっげーな!」
二人して大きな声で笑い合う。
ふいに影山さんが私の手元をみつめた。
「どうしたんですか?」
「いや、伊織ちゃんの箸の使い方、綺麗だなって思って。」
「そんなことないですよ。」
私は影山さんの食べたサバの味噌煮が乗った皿を指さした。
「それを言うなら私の方です。影山さんのお魚の食べ方、とても綺麗。」
「そう?俺は単に食い意地が張ってるだけなんだけどね。」
「ふふっ。そうなんですか?」
「伊織ちゃんの好きな料理ってなに?俺はね、カレーライスとハンバーグ。」
「影山さんの舌って意外とお子様ですね。私は~エビフライとオムライスかな。」
「伊織ちゃんだって人の事言えないだろ?どれもお子様ランチの皿に乗ってる食い物ばかりじゃん。」
「あ!ホントだ!」
それから私と影山さんは、好きなラーメンの味の当てっこをした。
私は味噌味が好きだけど、影山さんは醤油味が好きだった。
誰かと一緒に家で夕食を食べるなんて、何年振りだろう。
誰かの為に食事を作るなんて、初めてのことかもしれない。
それくらい私はずっと冷たい氷のような箱の中で暮らしてきたことに、いま気付いた。
思わず私の口から嗚咽がこぼれ、そんな自分自身に戸惑っていた。
突然泣き出した私に、影山さんは目を見開いて驚いた。
「伊織ちゃん?どうしたの?」
「うっうっ・・・」
「・・・辛かったよな。伊織ちゃんはたったひとりで、今日までよく頑張ったよ。」
影山さんはそう言って私の頭を撫でた。
「ストーカーは俺がなんとかするから、そんなに心配すんな。大丈夫だから。」
「違うの・・・誰かと一緒に食事するのがこんなに楽しいってこと、久々に思い出して・・・。」
「・・・・・・。」
「ウチは一人親だからママは仕事で忙しくて、子供の頃からいつもひとりで食事をすることが多かった。家の中はいつもガランとしていて、空気も冷たくて。ひとり暮らしをした今もそれは変わらなくて。だからこうして影山さんと食事してるのが嬉しくて・・・。」
「伊織ちゃん・・・。」
影山さんは励ますように、私の顔をみて微笑んだ。
「俺も家ではいつもひとりだったよ。俺達似た者同士だね。」
それがどういう意味なのか、その時の私にはわからなかった。