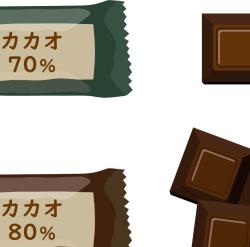私が東京へ戻り再び凌と暮らし始めてから、また新しい冬を迎えようとしていた。
凌は影山エステートの専務として精力的に仕事をこなしていた。
そして「リリー」のセラピストとして復帰した私を、古田さんや美紀ちゃん、他のスタッフも喜んで迎え入れてくれた。
凌は私がスナック「ゆり」で働いていた時のことを詳しく聞きたがった。
「お客様にお酒を作ってお出ししたり、話を聞いたりしていただけだよ。」
「ふーん。で?」
「たまにお客様と歌ったり・・・。」
「歌?一緒に?」
「うん。それも仕事だから。」
レミオロメンの『粉雪』が泣いて歌えなくなってしまったことは、恥ずかしいので黙っていた。
「ふーん。なんかムカつく。」
自分から尋ねたくせに、私のスナックでの仕事内容を聞くにつれて、凌はどんどんご機嫌ななめになっていった。
そして少し拗ねた声で私に言った。
「りおちゃん。俺にも水割り作ってよ。」
「かしこまりました。影山さん。」
私は肩をすくめると、グラスに氷を入れ、ウイスキーをソーダで割ってハイボールを作り、ソファに座る不機嫌そうな顔の凌に手渡した。
「りおちゃん、俺の隣に座って。」
「はいはい。」
私が凌の隣に座ると、凌は私の肩に手を回した。
「影山さん。ここはお触り禁止ですよ?」
ゆりさんの真似をして、私は凌の手の甲を軽く叩いて窘めた。
「やだ。これからは俺だけの、りおちゃんでいて。」
凌はハイボールをぐいっと一息で飲むと、甘えるように私の肩に頭を預けた。
「ね。客にこんなこともされた?」
「されるわけないよ。・・・凌は特別。」
私は凌の頭を抱きかかえると、ウイスキーの味がするその唇に自分の唇を押し当てた。
それからは、凌はたまに私のことを「りおちゃん」と呼ぶようになった。
凌が私をそう呼ぶときは、決まって私に甘えたいときなのだった。
凌は元々自動車の免許を持っていたらしく、私が戻って来てからすぐに「フィアット500」というイタリア製のコンパクトでレトロな空色の車を購入した。
そして休日にはふたりでその車に乗って、凌の実家がある鎌倉のアジサイを見に行ったり、湘南の海を眺めたり、ラーメンやソフトクリームの食べ歩きをして楽しんだ。
凌はたまに高級なフランス料理をフルコースでご馳走してくれた。
けれど、私はふたりで食べるなら吉野家の牛丼でも充分だった。
凌の運転は速すぎず遅すぎず、安心して乗っていられるので、私はその穏やかな揺れに身体を委ね、ついつい助手席で眠ってしまい、凌に「伊織、口を開けたまま寝てたぞ。」とからかわれた。
ある日の休日に、いつものように凌の車に乗って、郊外をドライブした。
「伊織、ちょっと寄りたい所があるんだけど、いい?」
凌にそう聞かれ、私は頷いた。
「いいよ。どこへ行くの?」
私が尋ねると、凌は何も言わずただ意味深な笑みを私に返した。
凌は閑静な住宅街に建つ、ある一軒家の脇に車を停めた。
私達は車から出ると、その一軒家の前に立った。
その家は北欧テイストでナチュラルな外観の建物だった。
紺色の三角屋根に一階部分はベージュ色、2階部分はパステルブルーの壁の色で、玄関のドアも同じくパステルブルーで揃えた優しい印象の可愛い家だ。
「素敵な家だね。」
「ああ。この家、影山エステートで扱っている物件なんだ。ちょっと覗いてみない?」
「え?中へ入れるの?」
「もちろん。俺の担当の物件だからね。」
私は鍵を開ける凌の後ろについて、玄関で靴を脱ぎ、家の中へ入った。
家の中は新築なのか、壁も床も天井も真新しかった。
新鮮な樹木の香りがした。
リビングはダイニングテーブルやソファを置いても、十分余白があるくらい広かった。
「伊織。もしここに住むならどんな家具を置きたい?」
凌の問いかけに私はうーんと頭を悩ませた。
「こんな広い家に住んだことがないからぴんとこないけど・・・焦げ茶色のレトロなダイニングテーブルを置いて、ネイビーブルーのソファを置くの。フランス刺繍のクッションを抱いて、そこで凌とネトフリの洋画を観たいなあ。」
「そっか。他の部屋も見てみようか。」
「うん!」
私達は2階へと続く階段を上り、手前の部屋の扉を開けた。
そこにはサンプル用のシンプルなベッドが置いてあった。
「ここは寝室だな。」
「わあ。広いね。」
私は窓際に近寄り、美しい庭が見える外の景色を眺めた。
空から粉雪がはらはらと降りはじめていた。
「寝室はどんな風にしたい?」
「そうね。真っ白な寝室って憧れる。カーテンのレースもベッドも枕も全部真っ白なの。まるで雪の中で眠っているようじゃない?」
「俺はダブルベッドならどんな部屋でもいい。毎日伊織と抱き合って眠りたい。」
「もう。凌ったら。今はインテリアの話をしてるんでしょ?」
私が帰ってから凌と私は、凌のベッドでずっと一緒に眠るようになった。
凌は私がいなくなってしまった時のことがまだトラウマらしく、朝目が覚めると私の身体が実体を伴っているかを確かめるように、きつく私を抱きしめる。
その瞬間は、私も凌がそばにいることを実感できて、幸福感で胸がいっぱいになる。
目が覚めて、目の前に凌の少し眠たげで安らかな顔がある日常が、何よりも嬉しかった。
2階には寝室の他にも部屋が3つもあった。
「客室も作れるんだ。こんな素敵な家に住める人は幸せだね。」
私がそう言うと、凌はにっこりと笑った。
「伊織、俺達がここに住まない?」
「え?」
私はぽかんと凌の顔をみつめた。
「この家を伊織が自由に飾ったらいいよ。そういうの好きだろ?」
「・・・こんなすごい家・・・高いんじゃない?」
「俺を誰だと思ってるの?せっかく不動産の仕事をしているんだ。これくらいの役得があってもよくない?」
「本当に?・・・嬉しい!」
私は素直に喜び、凌の胸に抱きついた。
「でも私、凌さえいればどんな家だっていいんだよ?」
「伊織は欲がないなあ。君はこれからもっともっと俺と一緒に幸せになるんだ。」
「すごく嬉しいけど、どんなに素敵な家に住んでも、凌がいなかったらただの大きな箱だよ?それだけは忘れないでね。」
私は凌の目を見て、正直な想いを伝えた。
「わかってる。俺が帰る場所はいつだって伊織のいるところだ。伊織こそそれを忘れないで。」
凌が私のおでこに自分のおでこを押しあてた。
「うん。絶対に忘れない。」
「・・・伊織に渡したい物があるんだ。」
凌はジャケットの内ポケットから、ビロードの四角い箱を取り出した。
「今からすごくベタなことしていい?」
凌はそう言うと立膝を付き、その四角い箱をパカッと開けて私に差し出した。
「田山伊織さん。俺と結婚してください。一生俺のそばで笑っていてください。君なしの人生はもう考えられません。お願いします。」
凌の真剣な眼差しが私の視線とぶつかった。
私はその箱の中で輝く指輪をみつめ、涙が溢れた。
凌と会えなかった辛い一年間を思い出し、こんな幸せな瞬間が訪れるなんて信じられない気持ちでいっぱいになった。
「凌・・・ありがとう。私だってもう凌のいない人生なんて生きていけないよ。これからもずっとずっと凌が好きです。」
私は心を込めて、そう凌に告げた。
「・・・よかったぁ。緊張した。」
ホッと安心したような飾らない表情の凌を見て、ああ私はこの人の全てが好きだなあと改めて思った。
「コユキもこの家、気に入るかな?」
「気に入るよ、きっと。そうだ!そろそろコユキにもお友達を作ってあげない?」
私がそう提案すると凌も頷いた。
「そうだな。今度、ペットショップへ行ってみようか。」
「うん。」
「ゆくゆくは・・・子供の事も考えような。」
「・・・でも私、いいお母さんになれるかな。」
私にはママの血が流れている。
そんな私の不安を吹き飛ばすように、凌が私の手を握った。
「いいお母さんになんてなろうとしなくていいよ。ただ愛してあげよう。俺達が欲しかったものをあげればいいんだ。」
「・・・うん!そうだね。きっとゆりさんも喜んでくれる。」
私達の元へ来てくれる未来の子供に、私がして欲しかった全てを与えてあげよう、そう思った。
これから私と凌の前には悲しいことや困難なことも訪れるだろう。
それでもふたりでならきっと乗り越えられる。
孤独だった私と凌を引き合わせてくれた、粉雪舞う白い世界は、いつまでも私達を見守ってくれるに違いない・・・。
fin
凌は影山エステートの専務として精力的に仕事をこなしていた。
そして「リリー」のセラピストとして復帰した私を、古田さんや美紀ちゃん、他のスタッフも喜んで迎え入れてくれた。
凌は私がスナック「ゆり」で働いていた時のことを詳しく聞きたがった。
「お客様にお酒を作ってお出ししたり、話を聞いたりしていただけだよ。」
「ふーん。で?」
「たまにお客様と歌ったり・・・。」
「歌?一緒に?」
「うん。それも仕事だから。」
レミオロメンの『粉雪』が泣いて歌えなくなってしまったことは、恥ずかしいので黙っていた。
「ふーん。なんかムカつく。」
自分から尋ねたくせに、私のスナックでの仕事内容を聞くにつれて、凌はどんどんご機嫌ななめになっていった。
そして少し拗ねた声で私に言った。
「りおちゃん。俺にも水割り作ってよ。」
「かしこまりました。影山さん。」
私は肩をすくめると、グラスに氷を入れ、ウイスキーをソーダで割ってハイボールを作り、ソファに座る不機嫌そうな顔の凌に手渡した。
「りおちゃん、俺の隣に座って。」
「はいはい。」
私が凌の隣に座ると、凌は私の肩に手を回した。
「影山さん。ここはお触り禁止ですよ?」
ゆりさんの真似をして、私は凌の手の甲を軽く叩いて窘めた。
「やだ。これからは俺だけの、りおちゃんでいて。」
凌はハイボールをぐいっと一息で飲むと、甘えるように私の肩に頭を預けた。
「ね。客にこんなこともされた?」
「されるわけないよ。・・・凌は特別。」
私は凌の頭を抱きかかえると、ウイスキーの味がするその唇に自分の唇を押し当てた。
それからは、凌はたまに私のことを「りおちゃん」と呼ぶようになった。
凌が私をそう呼ぶときは、決まって私に甘えたいときなのだった。
凌は元々自動車の免許を持っていたらしく、私が戻って来てからすぐに「フィアット500」というイタリア製のコンパクトでレトロな空色の車を購入した。
そして休日にはふたりでその車に乗って、凌の実家がある鎌倉のアジサイを見に行ったり、湘南の海を眺めたり、ラーメンやソフトクリームの食べ歩きをして楽しんだ。
凌はたまに高級なフランス料理をフルコースでご馳走してくれた。
けれど、私はふたりで食べるなら吉野家の牛丼でも充分だった。
凌の運転は速すぎず遅すぎず、安心して乗っていられるので、私はその穏やかな揺れに身体を委ね、ついつい助手席で眠ってしまい、凌に「伊織、口を開けたまま寝てたぞ。」とからかわれた。
ある日の休日に、いつものように凌の車に乗って、郊外をドライブした。
「伊織、ちょっと寄りたい所があるんだけど、いい?」
凌にそう聞かれ、私は頷いた。
「いいよ。どこへ行くの?」
私が尋ねると、凌は何も言わずただ意味深な笑みを私に返した。
凌は閑静な住宅街に建つ、ある一軒家の脇に車を停めた。
私達は車から出ると、その一軒家の前に立った。
その家は北欧テイストでナチュラルな外観の建物だった。
紺色の三角屋根に一階部分はベージュ色、2階部分はパステルブルーの壁の色で、玄関のドアも同じくパステルブルーで揃えた優しい印象の可愛い家だ。
「素敵な家だね。」
「ああ。この家、影山エステートで扱っている物件なんだ。ちょっと覗いてみない?」
「え?中へ入れるの?」
「もちろん。俺の担当の物件だからね。」
私は鍵を開ける凌の後ろについて、玄関で靴を脱ぎ、家の中へ入った。
家の中は新築なのか、壁も床も天井も真新しかった。
新鮮な樹木の香りがした。
リビングはダイニングテーブルやソファを置いても、十分余白があるくらい広かった。
「伊織。もしここに住むならどんな家具を置きたい?」
凌の問いかけに私はうーんと頭を悩ませた。
「こんな広い家に住んだことがないからぴんとこないけど・・・焦げ茶色のレトロなダイニングテーブルを置いて、ネイビーブルーのソファを置くの。フランス刺繍のクッションを抱いて、そこで凌とネトフリの洋画を観たいなあ。」
「そっか。他の部屋も見てみようか。」
「うん!」
私達は2階へと続く階段を上り、手前の部屋の扉を開けた。
そこにはサンプル用のシンプルなベッドが置いてあった。
「ここは寝室だな。」
「わあ。広いね。」
私は窓際に近寄り、美しい庭が見える外の景色を眺めた。
空から粉雪がはらはらと降りはじめていた。
「寝室はどんな風にしたい?」
「そうね。真っ白な寝室って憧れる。カーテンのレースもベッドも枕も全部真っ白なの。まるで雪の中で眠っているようじゃない?」
「俺はダブルベッドならどんな部屋でもいい。毎日伊織と抱き合って眠りたい。」
「もう。凌ったら。今はインテリアの話をしてるんでしょ?」
私が帰ってから凌と私は、凌のベッドでずっと一緒に眠るようになった。
凌は私がいなくなってしまった時のことがまだトラウマらしく、朝目が覚めると私の身体が実体を伴っているかを確かめるように、きつく私を抱きしめる。
その瞬間は、私も凌がそばにいることを実感できて、幸福感で胸がいっぱいになる。
目が覚めて、目の前に凌の少し眠たげで安らかな顔がある日常が、何よりも嬉しかった。
2階には寝室の他にも部屋が3つもあった。
「客室も作れるんだ。こんな素敵な家に住める人は幸せだね。」
私がそう言うと、凌はにっこりと笑った。
「伊織、俺達がここに住まない?」
「え?」
私はぽかんと凌の顔をみつめた。
「この家を伊織が自由に飾ったらいいよ。そういうの好きだろ?」
「・・・こんなすごい家・・・高いんじゃない?」
「俺を誰だと思ってるの?せっかく不動産の仕事をしているんだ。これくらいの役得があってもよくない?」
「本当に?・・・嬉しい!」
私は素直に喜び、凌の胸に抱きついた。
「でも私、凌さえいればどんな家だっていいんだよ?」
「伊織は欲がないなあ。君はこれからもっともっと俺と一緒に幸せになるんだ。」
「すごく嬉しいけど、どんなに素敵な家に住んでも、凌がいなかったらただの大きな箱だよ?それだけは忘れないでね。」
私は凌の目を見て、正直な想いを伝えた。
「わかってる。俺が帰る場所はいつだって伊織のいるところだ。伊織こそそれを忘れないで。」
凌が私のおでこに自分のおでこを押しあてた。
「うん。絶対に忘れない。」
「・・・伊織に渡したい物があるんだ。」
凌はジャケットの内ポケットから、ビロードの四角い箱を取り出した。
「今からすごくベタなことしていい?」
凌はそう言うと立膝を付き、その四角い箱をパカッと開けて私に差し出した。
「田山伊織さん。俺と結婚してください。一生俺のそばで笑っていてください。君なしの人生はもう考えられません。お願いします。」
凌の真剣な眼差しが私の視線とぶつかった。
私はその箱の中で輝く指輪をみつめ、涙が溢れた。
凌と会えなかった辛い一年間を思い出し、こんな幸せな瞬間が訪れるなんて信じられない気持ちでいっぱいになった。
「凌・・・ありがとう。私だってもう凌のいない人生なんて生きていけないよ。これからもずっとずっと凌が好きです。」
私は心を込めて、そう凌に告げた。
「・・・よかったぁ。緊張した。」
ホッと安心したような飾らない表情の凌を見て、ああ私はこの人の全てが好きだなあと改めて思った。
「コユキもこの家、気に入るかな?」
「気に入るよ、きっと。そうだ!そろそろコユキにもお友達を作ってあげない?」
私がそう提案すると凌も頷いた。
「そうだな。今度、ペットショップへ行ってみようか。」
「うん。」
「ゆくゆくは・・・子供の事も考えような。」
「・・・でも私、いいお母さんになれるかな。」
私にはママの血が流れている。
そんな私の不安を吹き飛ばすように、凌が私の手を握った。
「いいお母さんになんてなろうとしなくていいよ。ただ愛してあげよう。俺達が欲しかったものをあげればいいんだ。」
「・・・うん!そうだね。きっとゆりさんも喜んでくれる。」
私達の元へ来てくれる未来の子供に、私がして欲しかった全てを与えてあげよう、そう思った。
これから私と凌の前には悲しいことや困難なことも訪れるだろう。
それでもふたりでならきっと乗り越えられる。
孤独だった私と凌を引き合わせてくれた、粉雪舞う白い世界は、いつまでも私達を見守ってくれるに違いない・・・。
fin