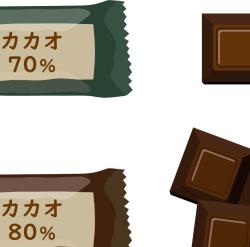私は退院してからすぐに今まで通り、スナック「ゆり」で働き始めていた。
ぼおっと休んでいるより、仕事をしている方が気が紛れた。
私はゆりさんに頼まれて、お客様にだす料理の材料を買いに店の外へ出た。
急いで買い物を終え、店へと帰る道を早足で歩いた。
冷えるな、と思っていたら、曇天の空からは粉雪が舞っていた。
粉雪は天使の落とし物。
私の心も真っ白に染まっていくようだった。
凌と初めて出会ったあの寒い冬の朝を思い出していた。
私は凌から貰ったマフラーを巻いた首をすくめ、肩にバックをかけて、傘をさした。
ふと気づくと、店の前に傘をさした誰かが、私の方を向いて立っていた。
私の傘の中から、よく磨かれた黒い革靴を履いた足元が見えた。
その人は、仕立ての良いチャコールグレーのスーツを着ていた。
傘を上げて、背の高いその人の顔を見た。
そこには凌が佇んでいた。
私は息を飲んだ。
また夢をみているのかと思った。
恐る恐る名前を呼んでみた。
「・・・・・・凌?」
凌は怒っているような、今にも泣き出しそうな顔をしていた。
瞳が充血し、潤んでいる。
頬がこけ、少し痩せたようだった。
凌は私をじっとみつめ、震えた声を発した。
「伊織・・・生きてた。」
私の鼓膜に心地よく響く、懐かしい凌の声だった。
凌は傘を放り投げ、私を抱きしめた。
私も傘を投げ捨て、凌の背中に手を回した。
「伊織・・・ごめん・・・遅くなってごめん。出張でずっと会社に戻れなくて、手紙を受け取ったのは今日の朝だった。」
「本当に凌だよね?まぼろしじゃないよね?」
「ああ。本物だよ。ほら、触れるだろ?」
「凌・・・会いたかったよ・・・すごくすごく会いたかった。」
「俺も会いたかった。」
私と凌はそのまましばらく、お互いを固く抱きしめ合った。
凌の身体は温かくて、私の凍っていた今日までの悲しみを溶かしてくれた。
言葉にならない想いで、胸が張り裂けそうだった。
「伊織がいなくなったこの1年間、俺の毎日は地獄だった。君を忘れようと無我夢中で仕事して、君を忘れる為に酒を浴びるほど飲んで、酔って、気絶するように寝て、また君の夢を見て泣いた。」
「凌・・・・・・。」
「君を恨んで憎んで、でも恋しくて、どうしても忘れられなくて。」
絞り出すような凌の言葉に、私の胸は苦しくなった。
「ある日、コユキがこう喋ったんだ。『リョウ、スキダヨ、ダイスキダヨ』って。それは伊織から俺への本当のメッセージだと思った。それを支えに俺は今日まで生きてきたんだ。」
私はさらに凌を強く抱きしめた。
これからは私が凌の全てを温めてあげたい、そう思った。
「凌を悲しませてごめん。苦しませてごめんね。」
「俺の方こそ、伊織をまたひとりぼっちにさせてごめん。もう二度と俺から離れないで。」
「うん。ずっと凌のそばにいる。」
もう凌のいない世界なんて生きていけない。
この1年間の日々の中で、私はそのことを嫌というほど思い知った。
これからは誰に何を言われても、凌だけをみつめて生きていく。
私と凌の肩に粉雪が降り積もっていった。
二人でスナック「ゆり」の店内に入り、ゆりさんに凌を紹介した。
ゆりさんは泣きながら、熱いお茶を入れてくれた。
私達はカウンターに座ってお茶を飲んだ。
「俺と伊織が再び出会えたのはゆりさんのお陰です。本当にどうもありがとうございました。」
凌がゆりさんに向かい、頭を下げた。
「私のことなんてどうでもいいからさ。でも本当に良かった。私は生きてきてこんなに嬉しいことはないよ。」
それだけ言うと、ゆりさんは店の奥へ引っ込んでしまった。
「凌・・・ママからは何もされなかった?」
私はそれだけが心配だった。
「うん。・・・伊織のお母さんは、亡くなったよ。」
「え・・・?」
「俺は伊織のことを何か知っているんじゃないかと、まず君の母親の居場所をつきとめた。簡単だったよ。深沢良一郎に聞いたんだ。」
深沢良一郎。ママの借金の相手。
「君の母親は君の居場所など知らないの一点張りだった。俺は強引に自分の名刺を渡して、なにか伊織のことが判ったら、すぐに連絡して欲しいと頼み込んだ。そして半年前、君の母親が交通事故で死んだと、俺の名刺を見た警察官が連絡してきたんだ。酒と薬の飲み過ぎで身体がフラフラな状態だったらしい。」
すでにママを捨てた私に、ママの死を悼む資格などない。
けれど結局私とママは、実の親子なのに何一つ通じ合えなかった。
そのことが哀しかった。
凌はお茶を一口飲むと、私を優しくみつめた。
「伊織・・・俺を守ってくれてありがとう。」
「ううん。私が凌に相談しなかったのが悪かったの。」
凌は私の頭にポンと手を置いた。
「いいさ。いま、伊織とこうしてまた出会えたことで、苦しかった1年間の全てが吹っ飛んだから。・・・伊織はどんな1年を過ごしていたの?」
「私も凌のことを一時も忘れたことはなかったよ。凌と会いたい、ただそればかりを考えてた。私も凌の夢を見ては泣いてた。」
「俺達、離れていても同じ気持ちでいたんだな。」
「うん。」
「これからは俺になんでも話して。辛いことも悲しいことも困っていることも嬉しいことも全部。約束だよ。」
「うん。約束。」
私と凌は小指を絡めると、微笑みあった。
1ヶ月後、私は凌と一緒に、東京へ戻ることを決めた。
ゆりさんの事だけが気がかりだったけれど、ゆりさんはあっけらかんと私の背中を押してくれた。
「私も大鶴さんと結婚するかもしれないし、丁度良かったわ。」
「ゆりさん。今まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。」
「こちらこそ。りおに会えて嬉しかった。ううん。過去形はナシ。また遊びにおいで。元気でね。うんと幸せになるんだよ。」
「はい!またすぐに会いに来ます。ゆりさんも元気でいてください。大鶴さんと仲良くね。」
私は来た時と同じスポーツバッグを持って、凌と宇都宮駅へ向かった。
東京行きの東北新幹線の座席に、凌と並んで座った。
ひとりで心細く新幹線に乗った一年前の夜を思い出し、凌が隣にいることがまだ信じられなかった。
「凌のスーツ姿、恰好いいね。見惚れちゃうよ。」
身体にピッタリあった三つ揃えのスーツに紺とグレーのストライプのネクタイで決めている仕事モードの凌が眩しかった。
「ありがと。でも仕事に必要だから着てるだけ。伊織こそ・・・綺麗になった。うん。色っぽくなった。」
薄化粧をしている私の顔を見て凌が目を細めたので、私は耳まで真っ赤になった。
凌の横顔をじっとみつめる私の視線に気づいた凌が、優しく微笑んだ。
「そんなにみつめられると、なんか照れるな。」
「だって・・・また夢だったら、今度こそ私、死んじゃうと思って。」
「それは俺の台詞。・・・事故の後遺症はどう?まだどこか痛む?」
「ううん。大丈夫。」
「もし伊織が死んでたら、天国まで追いかけていこうと思ってた。」
「それは駄目!」
「じゃあ、俺の為に、伊織も二度と危ないことしないで。」
「わかった。絶対しない。」
凌の真剣な瞳に、私は大きく頷いた。
東京駅へ着くと大勢の人波が目に飛び込んできた。
その光景を見て、東京へ帰って来たんだ、という実感か沸いた。
家までの道のりを凌と手を繋いで歩いた。
私は凌と住んでいた部屋の扉を開けて、その空気を深く吸い込んだ。
懐かしさで胸がいっぱいになった。
テーブルの上のコユキが、ケージの中で私を不思議そうに見ていた。
「コユキ。忘れちゃった?伊織だよ。」
私がそう話しかけると、コユキが思い出したように喋り出した。
「イオリ アイシテル」
「おかえり。伊織。」
「ただいま。凌。」
凌は私を抱き上げると、ベッドの上にそっと横たわらせた。
私と凌は深い口づけを交わし、お互いの肌の温かさを確かめながら、激しく求め合った。
ぼおっと休んでいるより、仕事をしている方が気が紛れた。
私はゆりさんに頼まれて、お客様にだす料理の材料を買いに店の外へ出た。
急いで買い物を終え、店へと帰る道を早足で歩いた。
冷えるな、と思っていたら、曇天の空からは粉雪が舞っていた。
粉雪は天使の落とし物。
私の心も真っ白に染まっていくようだった。
凌と初めて出会ったあの寒い冬の朝を思い出していた。
私は凌から貰ったマフラーを巻いた首をすくめ、肩にバックをかけて、傘をさした。
ふと気づくと、店の前に傘をさした誰かが、私の方を向いて立っていた。
私の傘の中から、よく磨かれた黒い革靴を履いた足元が見えた。
その人は、仕立ての良いチャコールグレーのスーツを着ていた。
傘を上げて、背の高いその人の顔を見た。
そこには凌が佇んでいた。
私は息を飲んだ。
また夢をみているのかと思った。
恐る恐る名前を呼んでみた。
「・・・・・・凌?」
凌は怒っているような、今にも泣き出しそうな顔をしていた。
瞳が充血し、潤んでいる。
頬がこけ、少し痩せたようだった。
凌は私をじっとみつめ、震えた声を発した。
「伊織・・・生きてた。」
私の鼓膜に心地よく響く、懐かしい凌の声だった。
凌は傘を放り投げ、私を抱きしめた。
私も傘を投げ捨て、凌の背中に手を回した。
「伊織・・・ごめん・・・遅くなってごめん。出張でずっと会社に戻れなくて、手紙を受け取ったのは今日の朝だった。」
「本当に凌だよね?まぼろしじゃないよね?」
「ああ。本物だよ。ほら、触れるだろ?」
「凌・・・会いたかったよ・・・すごくすごく会いたかった。」
「俺も会いたかった。」
私と凌はそのまましばらく、お互いを固く抱きしめ合った。
凌の身体は温かくて、私の凍っていた今日までの悲しみを溶かしてくれた。
言葉にならない想いで、胸が張り裂けそうだった。
「伊織がいなくなったこの1年間、俺の毎日は地獄だった。君を忘れようと無我夢中で仕事して、君を忘れる為に酒を浴びるほど飲んで、酔って、気絶するように寝て、また君の夢を見て泣いた。」
「凌・・・・・・。」
「君を恨んで憎んで、でも恋しくて、どうしても忘れられなくて。」
絞り出すような凌の言葉に、私の胸は苦しくなった。
「ある日、コユキがこう喋ったんだ。『リョウ、スキダヨ、ダイスキダヨ』って。それは伊織から俺への本当のメッセージだと思った。それを支えに俺は今日まで生きてきたんだ。」
私はさらに凌を強く抱きしめた。
これからは私が凌の全てを温めてあげたい、そう思った。
「凌を悲しませてごめん。苦しませてごめんね。」
「俺の方こそ、伊織をまたひとりぼっちにさせてごめん。もう二度と俺から離れないで。」
「うん。ずっと凌のそばにいる。」
もう凌のいない世界なんて生きていけない。
この1年間の日々の中で、私はそのことを嫌というほど思い知った。
これからは誰に何を言われても、凌だけをみつめて生きていく。
私と凌の肩に粉雪が降り積もっていった。
二人でスナック「ゆり」の店内に入り、ゆりさんに凌を紹介した。
ゆりさんは泣きながら、熱いお茶を入れてくれた。
私達はカウンターに座ってお茶を飲んだ。
「俺と伊織が再び出会えたのはゆりさんのお陰です。本当にどうもありがとうございました。」
凌がゆりさんに向かい、頭を下げた。
「私のことなんてどうでもいいからさ。でも本当に良かった。私は生きてきてこんなに嬉しいことはないよ。」
それだけ言うと、ゆりさんは店の奥へ引っ込んでしまった。
「凌・・・ママからは何もされなかった?」
私はそれだけが心配だった。
「うん。・・・伊織のお母さんは、亡くなったよ。」
「え・・・?」
「俺は伊織のことを何か知っているんじゃないかと、まず君の母親の居場所をつきとめた。簡単だったよ。深沢良一郎に聞いたんだ。」
深沢良一郎。ママの借金の相手。
「君の母親は君の居場所など知らないの一点張りだった。俺は強引に自分の名刺を渡して、なにか伊織のことが判ったら、すぐに連絡して欲しいと頼み込んだ。そして半年前、君の母親が交通事故で死んだと、俺の名刺を見た警察官が連絡してきたんだ。酒と薬の飲み過ぎで身体がフラフラな状態だったらしい。」
すでにママを捨てた私に、ママの死を悼む資格などない。
けれど結局私とママは、実の親子なのに何一つ通じ合えなかった。
そのことが哀しかった。
凌はお茶を一口飲むと、私を優しくみつめた。
「伊織・・・俺を守ってくれてありがとう。」
「ううん。私が凌に相談しなかったのが悪かったの。」
凌は私の頭にポンと手を置いた。
「いいさ。いま、伊織とこうしてまた出会えたことで、苦しかった1年間の全てが吹っ飛んだから。・・・伊織はどんな1年を過ごしていたの?」
「私も凌のことを一時も忘れたことはなかったよ。凌と会いたい、ただそればかりを考えてた。私も凌の夢を見ては泣いてた。」
「俺達、離れていても同じ気持ちでいたんだな。」
「うん。」
「これからは俺になんでも話して。辛いことも悲しいことも困っていることも嬉しいことも全部。約束だよ。」
「うん。約束。」
私と凌は小指を絡めると、微笑みあった。
1ヶ月後、私は凌と一緒に、東京へ戻ることを決めた。
ゆりさんの事だけが気がかりだったけれど、ゆりさんはあっけらかんと私の背中を押してくれた。
「私も大鶴さんと結婚するかもしれないし、丁度良かったわ。」
「ゆりさん。今まで本当にお世話になりました。ありがとうございました。」
「こちらこそ。りおに会えて嬉しかった。ううん。過去形はナシ。また遊びにおいで。元気でね。うんと幸せになるんだよ。」
「はい!またすぐに会いに来ます。ゆりさんも元気でいてください。大鶴さんと仲良くね。」
私は来た時と同じスポーツバッグを持って、凌と宇都宮駅へ向かった。
東京行きの東北新幹線の座席に、凌と並んで座った。
ひとりで心細く新幹線に乗った一年前の夜を思い出し、凌が隣にいることがまだ信じられなかった。
「凌のスーツ姿、恰好いいね。見惚れちゃうよ。」
身体にピッタリあった三つ揃えのスーツに紺とグレーのストライプのネクタイで決めている仕事モードの凌が眩しかった。
「ありがと。でも仕事に必要だから着てるだけ。伊織こそ・・・綺麗になった。うん。色っぽくなった。」
薄化粧をしている私の顔を見て凌が目を細めたので、私は耳まで真っ赤になった。
凌の横顔をじっとみつめる私の視線に気づいた凌が、優しく微笑んだ。
「そんなにみつめられると、なんか照れるな。」
「だって・・・また夢だったら、今度こそ私、死んじゃうと思って。」
「それは俺の台詞。・・・事故の後遺症はどう?まだどこか痛む?」
「ううん。大丈夫。」
「もし伊織が死んでたら、天国まで追いかけていこうと思ってた。」
「それは駄目!」
「じゃあ、俺の為に、伊織も二度と危ないことしないで。」
「わかった。絶対しない。」
凌の真剣な瞳に、私は大きく頷いた。
東京駅へ着くと大勢の人波が目に飛び込んできた。
その光景を見て、東京へ帰って来たんだ、という実感か沸いた。
家までの道のりを凌と手を繋いで歩いた。
私は凌と住んでいた部屋の扉を開けて、その空気を深く吸い込んだ。
懐かしさで胸がいっぱいになった。
テーブルの上のコユキが、ケージの中で私を不思議そうに見ていた。
「コユキ。忘れちゃった?伊織だよ。」
私がそう話しかけると、コユキが思い出したように喋り出した。
「イオリ アイシテル」
「おかえり。伊織。」
「ただいま。凌。」
凌は私を抱き上げると、ベッドの上にそっと横たわらせた。
私と凌は深い口づけを交わし、お互いの肌の温かさを確かめながら、激しく求め合った。