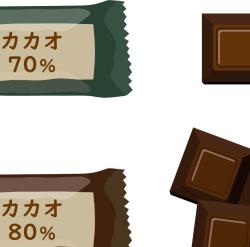次の日、私はMRI検査という脳のレントゲンを撮った。
病院の食事を食べ、あとは何をするでもなく、ただぼんやりと過ごした。
本を読みたかったけれど、まだ脳を疲れさせることはやめなさいと看護師さんに注意された。
私は窓の外の木の枝に止まる鳥を、所在なく見ていた。
鳥を見て、コユキを思い出した。
コユキ、元気にしてるかな。
窓を開けていると、カーテンが風に揺れて、外の木々の緑がさわさわと音を鳴らし気持ち良かった。
午後になるとゆりさんが来て、着替えや細かい雑貨を持ってきてくれた。
「具合はどう?」
「特に変わりはないです。たまにズキンと頭が響くくらいで。」
私の身体は順調に回復していった。
入院して7日目には病院の庭を散歩できるようになった。
8日目の診察で、医者はMRI検査の結果写真を私が見えるようにパソコン画面に写しながら、私の脳の状態を説明した。
「検査の結果を見ると、特に脳に目立った損傷は見られませんでした。脳の出血もありません。アナタは幸運ですね。助かった命を大事に生きて下さい。」
「はい。ありがとうございました。」
私は医者に一礼をして診察室を出た。
私にはゆりさんという心強い味方がいるし、仕事もある。
ここ宇都宮の街で、過去を振り返らず、毎日を積み重ねていけば、新しい未来が自ずと開けていくに違いない。
これからも頑張って生きていこう、気持ちも新たにそう決意した。
その後、吐き気もなく、頭痛もおさまってきた。
頭を打ち付けた後遺症による体へのダメージはおそらく大丈夫だと判断され、10日目の朝、私は退院した。
ゆりさんが迎えにきてくれて、一緒に店までの道を歩いた。
ゆりさんは家に着くと、私を自分の部屋へ呼んだ。
ふたりきりで話したいことがある、ということだった。
ゆりさんの部屋は和風な家具に囲まれ、落ち着きのある装飾が施されていた。
特にゆりさんは蝶の柄が好きみたいで、壁には美しい蝶のタペストリーが飾られていた。
茶箪笥に飾られた招き猫が私とゆりさんを眺めていた。
ゆりさんはほとんど私を自分の部屋に入れない。
話をするときはいつも私の部屋だった。
よっぽど大切な話なのだろうか?
もしかしたら、店を辞めてもらいたいなどと言われるのだろうか?
でもここを追い出されたら、私は行く当てなどない。
その時は次の仕事が決まるまでなんでもやるから、しばらくの間だけでも私を雇って欲しいと頼み込もう、と思った。
ゆりさんは私にジャスミン茶を出してくれた。
そして自分も一口飲んだ。
ゆりさんがとても言いづらそうにしていたので、私から口火を切った。
「もしかして私の今後のことですか?」
「・・・・・・。」
ゆりさんはまだ言い淀んでいた。
「もし私の存在がご迷惑なら、次の仕事を探します。だからもう少しだけここにいさせて下さい。」
私はそう言って必死に頭を下げた。
するとゆりさんは怒ったように言った。
「なに言ってんの!りおはもう私の家族みたいなものなんだ。頼まれたって手放す気はないよ。アンタはそんな心配しないでいいんだよ。」
「じゃあ、なんですか。話って・・・。」
「実はりお、アンタに謝らなければならないことがある。」
ゆりさんは短く息を吸うと、話し始めた。
「アンタが事故にあって死ぬかもしれないって状況になって、私はアンタの大事な人にそれを伝えなければならないって思ったんだ。だからりおの荷物を見させてもらった。だってアンタを見送るのが私ひとりじゃ可哀想すぎると思ったんだ。」
「・・・・・・。」
「そうしたらりおのバッグのポケットの中から手紙を見つけた。りお、アンタが影山凌って男に宛てて書いた手紙だよ。」
「凌への手紙・・・」
私が東京を発つ前に、凌へ書いた手紙。
渡そうとして渡せなかった、凌への想いが綴られた手紙。
「アンタの手紙を読ませてもらった。不覚にも、私は泣いたよ。」
「・・・・・・。」
「りおにとって影山凌は大切な大切な男だと思った。影山凌だってきっと、アンタの事を・・・。だから私は影山凌に連絡を取ろうとした。」
「連絡・・・?どうやって?」
私の鼓動が早くなった。
「影山凌という名前をネットで検索してみた。そしたらひとつだけ引っかかったサイトがあった。影山エステートという会社のホームページさ。影山凌はその会社のホームページ内で専務として紹介されていた。私はダメ元でその会社の代表番号に電話をかけてみた。影山凌さんに取り次いでもらいたいってね。でもやっぱり取り次いでもらえなかった。そりゃそうだよね。相手は大きな会社の専務さんだ。どこの馬の骨ともわからない人間が取り次いでもらえるわけがない。」
「そうだったんですね・・・。」
私は頷いた。
凌はあれから影山エステートで出世をしたのだ。
ママは約束を守って、凌を強請るような真似をしなかったのだ。
そのことに私は心からホッとしていた。
「でもどうしても諦めきれなくて、せめてりおが・・・伊織が死んでしまうまえに、伊織が抱えていた想いを影山凌にどうしても知っておいて欲しくて、それで会社の住所に影山凌宛で伊織が書いた手紙と伊織が今死ぬかもしれないという現状、そしてスナック「ゆり」の住所が書かれた名刺を入れた封書を送ったんだ。」
「・・・・・・。」
「りお、私はアンタが大切にとっておいた手紙を勝手に送ってしまった。もしかしたらあの封書は影山凌の元へ届く前に捨てられてしまうかもしれないのに。本当に申し訳ないことをした。なんて言って詫びたらいいか私にはわからない。」
ゆりさんは涙声でそう言って私に頭を下げた。
「ゆりさん。頭を上げて下さい。」
私は静かにそうつぶやいた。
「私はなにも怒ったりしません。だってゆりさんは私の為にしてくれたんでしょ?」
「りお・・・。」
「ゆりさん。その手紙を凌に出したのはいつですか?」
「・・・アンタがまだ昏睡状態だった時だから、2週間前くらいかな。」
「2週間も経ってなんの音沙汰もないということは、きっと手紙が届かなかったか、届いたとしても、もう凌にとってはなんの意味もない手紙だったってことです。」
「・・・・・・。」
「私は凌のことを知るのが怖くて、ネットで検索するなんてことすら思いつかなかった。だから凌が会社で頑張ってるのを知れて本当に嬉しい。凌が同じ空の下のどこかで元気に暮らしていることがわかっただけで、それだけで私は満足なんです。」
私のきっぱりとした言葉を聞いたゆりさんは、私の為に子供のように大きな声で泣いてくれた。
私の為に泣いてくれる人がいる・・・その事実だけで私は充分幸せだった。
病院の食事を食べ、あとは何をするでもなく、ただぼんやりと過ごした。
本を読みたかったけれど、まだ脳を疲れさせることはやめなさいと看護師さんに注意された。
私は窓の外の木の枝に止まる鳥を、所在なく見ていた。
鳥を見て、コユキを思い出した。
コユキ、元気にしてるかな。
窓を開けていると、カーテンが風に揺れて、外の木々の緑がさわさわと音を鳴らし気持ち良かった。
午後になるとゆりさんが来て、着替えや細かい雑貨を持ってきてくれた。
「具合はどう?」
「特に変わりはないです。たまにズキンと頭が響くくらいで。」
私の身体は順調に回復していった。
入院して7日目には病院の庭を散歩できるようになった。
8日目の診察で、医者はMRI検査の結果写真を私が見えるようにパソコン画面に写しながら、私の脳の状態を説明した。
「検査の結果を見ると、特に脳に目立った損傷は見られませんでした。脳の出血もありません。アナタは幸運ですね。助かった命を大事に生きて下さい。」
「はい。ありがとうございました。」
私は医者に一礼をして診察室を出た。
私にはゆりさんという心強い味方がいるし、仕事もある。
ここ宇都宮の街で、過去を振り返らず、毎日を積み重ねていけば、新しい未来が自ずと開けていくに違いない。
これからも頑張って生きていこう、気持ちも新たにそう決意した。
その後、吐き気もなく、頭痛もおさまってきた。
頭を打ち付けた後遺症による体へのダメージはおそらく大丈夫だと判断され、10日目の朝、私は退院した。
ゆりさんが迎えにきてくれて、一緒に店までの道を歩いた。
ゆりさんは家に着くと、私を自分の部屋へ呼んだ。
ふたりきりで話したいことがある、ということだった。
ゆりさんの部屋は和風な家具に囲まれ、落ち着きのある装飾が施されていた。
特にゆりさんは蝶の柄が好きみたいで、壁には美しい蝶のタペストリーが飾られていた。
茶箪笥に飾られた招き猫が私とゆりさんを眺めていた。
ゆりさんはほとんど私を自分の部屋に入れない。
話をするときはいつも私の部屋だった。
よっぽど大切な話なのだろうか?
もしかしたら、店を辞めてもらいたいなどと言われるのだろうか?
でもここを追い出されたら、私は行く当てなどない。
その時は次の仕事が決まるまでなんでもやるから、しばらくの間だけでも私を雇って欲しいと頼み込もう、と思った。
ゆりさんは私にジャスミン茶を出してくれた。
そして自分も一口飲んだ。
ゆりさんがとても言いづらそうにしていたので、私から口火を切った。
「もしかして私の今後のことですか?」
「・・・・・・。」
ゆりさんはまだ言い淀んでいた。
「もし私の存在がご迷惑なら、次の仕事を探します。だからもう少しだけここにいさせて下さい。」
私はそう言って必死に頭を下げた。
するとゆりさんは怒ったように言った。
「なに言ってんの!りおはもう私の家族みたいなものなんだ。頼まれたって手放す気はないよ。アンタはそんな心配しないでいいんだよ。」
「じゃあ、なんですか。話って・・・。」
「実はりお、アンタに謝らなければならないことがある。」
ゆりさんは短く息を吸うと、話し始めた。
「アンタが事故にあって死ぬかもしれないって状況になって、私はアンタの大事な人にそれを伝えなければならないって思ったんだ。だからりおの荷物を見させてもらった。だってアンタを見送るのが私ひとりじゃ可哀想すぎると思ったんだ。」
「・・・・・・。」
「そうしたらりおのバッグのポケットの中から手紙を見つけた。りお、アンタが影山凌って男に宛てて書いた手紙だよ。」
「凌への手紙・・・」
私が東京を発つ前に、凌へ書いた手紙。
渡そうとして渡せなかった、凌への想いが綴られた手紙。
「アンタの手紙を読ませてもらった。不覚にも、私は泣いたよ。」
「・・・・・・。」
「りおにとって影山凌は大切な大切な男だと思った。影山凌だってきっと、アンタの事を・・・。だから私は影山凌に連絡を取ろうとした。」
「連絡・・・?どうやって?」
私の鼓動が早くなった。
「影山凌という名前をネットで検索してみた。そしたらひとつだけ引っかかったサイトがあった。影山エステートという会社のホームページさ。影山凌はその会社のホームページ内で専務として紹介されていた。私はダメ元でその会社の代表番号に電話をかけてみた。影山凌さんに取り次いでもらいたいってね。でもやっぱり取り次いでもらえなかった。そりゃそうだよね。相手は大きな会社の専務さんだ。どこの馬の骨ともわからない人間が取り次いでもらえるわけがない。」
「そうだったんですね・・・。」
私は頷いた。
凌はあれから影山エステートで出世をしたのだ。
ママは約束を守って、凌を強請るような真似をしなかったのだ。
そのことに私は心からホッとしていた。
「でもどうしても諦めきれなくて、せめてりおが・・・伊織が死んでしまうまえに、伊織が抱えていた想いを影山凌にどうしても知っておいて欲しくて、それで会社の住所に影山凌宛で伊織が書いた手紙と伊織が今死ぬかもしれないという現状、そしてスナック「ゆり」の住所が書かれた名刺を入れた封書を送ったんだ。」
「・・・・・・。」
「りお、私はアンタが大切にとっておいた手紙を勝手に送ってしまった。もしかしたらあの封書は影山凌の元へ届く前に捨てられてしまうかもしれないのに。本当に申し訳ないことをした。なんて言って詫びたらいいか私にはわからない。」
ゆりさんは涙声でそう言って私に頭を下げた。
「ゆりさん。頭を上げて下さい。」
私は静かにそうつぶやいた。
「私はなにも怒ったりしません。だってゆりさんは私の為にしてくれたんでしょ?」
「りお・・・。」
「ゆりさん。その手紙を凌に出したのはいつですか?」
「・・・アンタがまだ昏睡状態だった時だから、2週間前くらいかな。」
「2週間も経ってなんの音沙汰もないということは、きっと手紙が届かなかったか、届いたとしても、もう凌にとってはなんの意味もない手紙だったってことです。」
「・・・・・・。」
「私は凌のことを知るのが怖くて、ネットで検索するなんてことすら思いつかなかった。だから凌が会社で頑張ってるのを知れて本当に嬉しい。凌が同じ空の下のどこかで元気に暮らしていることがわかっただけで、それだけで私は満足なんです。」
私のきっぱりとした言葉を聞いたゆりさんは、私の為に子供のように大きな声で泣いてくれた。
私の為に泣いてくれる人がいる・・・その事実だけで私は充分幸せだった。