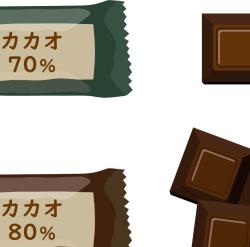気が付くと、私は真っ白な部屋のベッドに仰向けで横たわっていた。
ゆっくりと目を開くも、蛍光灯の光が眩しくて何も見えない。
しばらくするとやはり白くて高い天井が目に映った。
そのままぼんやりしていると、誰かが私の手を握りしめた。
「りお!」
今度こそしっかりと目を開いて横を向くと、ゆりさんが私を見ながら目に涙を浮かべていた。
「ゆり・・・さん?」
「よかった!目を覚ましてくれて、本当によかったよ!今、看護師さんを呼ぶから待っててね。」
ゆりさんは枕元にあったナースコールのボタンを押して、私が目を覚ましたことを看護師に告げた。
「ここはどこですか?」
私がそう聞くと、ゆりさんは目を吊り上げて、早口で言った。
「病院に決まってるだろ!りお、アンタ覚えてないの?」
「何をですか?」
「アンタは車道を飛び出して車に轢かれたんだよ!先に車道を飛び出した女の子をかばってさ。まったく無茶なことする子だよ。人を助けたって、自分が死んじまったんじゃ元も子もないだろうが!」
「そうなんですか・・・。」
たしかに私のいる場所は病院の部屋のようだった。
部屋の中は壁も天井も真っ白で、余計なものは何ひとつ置かれていない。
かすかに消毒液の匂いがする。
そしてさっきから腕が痛いと思っていたら、左の肘関節に点滴の針が刺さっていた。
私は事故のことを思い出しハッとした。
赤いリュックの小さな後ろ姿が脳裏に浮かんだ。
「あの女の子は無事でしたか?!」
「ああ。無事だったよ。かすり傷ひとつないって。」
「良かった・・・。」
廊下から人の足音が聞こえてきて、看護師と白衣を着た医者と思われる男性が部屋に入ってきた。
医者は私の顔を見て、穏やかに微笑んだ。
「気分はどうですか?気持ち悪いとか痛みはありませんか?」
「頭がズキズキと痛みます。」
さきほどから等間隔で襲ってくる頭痛に、私は眉をひそめた。
「アナタは丸二日ほど、昏睡状態だったのですよ。でも意識が戻ったならもう大丈夫でしょう。奇跡的に身体の怪我は左足の打撲以外、ほとんどありませんでした。あとは脳の損傷ですが、こちらも様子を見ていきましょう。」
「はい。」
それだけ言うと、医者は忙しそうに、さっさと病室から去っていった。
「じゃあ、丁度点滴が切れそうだから、処置しちゃいましょうね。」
眼鏡をかけた中年の看護師さんが親し気にそう言うと、私の点滴を手早く取り替えた。
看護師さんが部屋を出て行くと、ゆりさんが再び私の手を握りしめた。
「本当によかった。もう死んじゃうかと思ったよ。アンタ、私に葬式を出させるとこだったんだよ?まったく勘弁してよね。」
そんな冗談が飛び出すほど、ゆりさんは私が目を覚ましたことで安心したようだった。
「ほんとにすみませんでした。」
「じゃあ、私は店があるから一旦帰るよ。また明日見舞いにくるからね。欲しいものがあったら言ってね。それとその椅子の上にある紙袋の中に、下着とかタオルとか入ってるから使って。」
「ありがとうございます。」
ゆりさんは私の手を離すと、ひとつ大きく頷いて、病室を出ていった。
ひとりになり、私はただぽかんと虚空をみつめた。
私、まだ生きてるんだ。
生死を彷徨う間、私は夢をみていた。
私と凌は粉雪舞う白い世界で、手を繋いで歩いていた。
ふたりきりで、笑い合いながら、どこまでもどこまでも歩いていた。
嬉しくて楽しくて、胸の奥が切なくて、凌の横顔をずっと見ていたい、そう思った。
幸せに満ち溢れた奇跡のような夢だった。
夢から覚めて、またひとりぼっちの自分に気づき、凌が恋しくて目尻から涙が頬を伝い、無性に悲しくなった。
夢を見ながらそのまま死んでしまえればよかったのに・・・。
心にぽっかりと穴が開いたまま、私はまたこの世に戻って来たのだった。
私はさきほどまで私に付き添っていてくれた、ゆりさんの涙を思い出した。
・・・やっぱり死ななくて良かった。
ゆりさんを悲しませたまま逝かなくて良かった。
私はそう思いながら横たわると、頭から布団をかぶった。
ゆっくりと目を開くも、蛍光灯の光が眩しくて何も見えない。
しばらくするとやはり白くて高い天井が目に映った。
そのままぼんやりしていると、誰かが私の手を握りしめた。
「りお!」
今度こそしっかりと目を開いて横を向くと、ゆりさんが私を見ながら目に涙を浮かべていた。
「ゆり・・・さん?」
「よかった!目を覚ましてくれて、本当によかったよ!今、看護師さんを呼ぶから待っててね。」
ゆりさんは枕元にあったナースコールのボタンを押して、私が目を覚ましたことを看護師に告げた。
「ここはどこですか?」
私がそう聞くと、ゆりさんは目を吊り上げて、早口で言った。
「病院に決まってるだろ!りお、アンタ覚えてないの?」
「何をですか?」
「アンタは車道を飛び出して車に轢かれたんだよ!先に車道を飛び出した女の子をかばってさ。まったく無茶なことする子だよ。人を助けたって、自分が死んじまったんじゃ元も子もないだろうが!」
「そうなんですか・・・。」
たしかに私のいる場所は病院の部屋のようだった。
部屋の中は壁も天井も真っ白で、余計なものは何ひとつ置かれていない。
かすかに消毒液の匂いがする。
そしてさっきから腕が痛いと思っていたら、左の肘関節に点滴の針が刺さっていた。
私は事故のことを思い出しハッとした。
赤いリュックの小さな後ろ姿が脳裏に浮かんだ。
「あの女の子は無事でしたか?!」
「ああ。無事だったよ。かすり傷ひとつないって。」
「良かった・・・。」
廊下から人の足音が聞こえてきて、看護師と白衣を着た医者と思われる男性が部屋に入ってきた。
医者は私の顔を見て、穏やかに微笑んだ。
「気分はどうですか?気持ち悪いとか痛みはありませんか?」
「頭がズキズキと痛みます。」
さきほどから等間隔で襲ってくる頭痛に、私は眉をひそめた。
「アナタは丸二日ほど、昏睡状態だったのですよ。でも意識が戻ったならもう大丈夫でしょう。奇跡的に身体の怪我は左足の打撲以外、ほとんどありませんでした。あとは脳の損傷ですが、こちらも様子を見ていきましょう。」
「はい。」
それだけ言うと、医者は忙しそうに、さっさと病室から去っていった。
「じゃあ、丁度点滴が切れそうだから、処置しちゃいましょうね。」
眼鏡をかけた中年の看護師さんが親し気にそう言うと、私の点滴を手早く取り替えた。
看護師さんが部屋を出て行くと、ゆりさんが再び私の手を握りしめた。
「本当によかった。もう死んじゃうかと思ったよ。アンタ、私に葬式を出させるとこだったんだよ?まったく勘弁してよね。」
そんな冗談が飛び出すほど、ゆりさんは私が目を覚ましたことで安心したようだった。
「ほんとにすみませんでした。」
「じゃあ、私は店があるから一旦帰るよ。また明日見舞いにくるからね。欲しいものがあったら言ってね。それとその椅子の上にある紙袋の中に、下着とかタオルとか入ってるから使って。」
「ありがとうございます。」
ゆりさんは私の手を離すと、ひとつ大きく頷いて、病室を出ていった。
ひとりになり、私はただぽかんと虚空をみつめた。
私、まだ生きてるんだ。
生死を彷徨う間、私は夢をみていた。
私と凌は粉雪舞う白い世界で、手を繋いで歩いていた。
ふたりきりで、笑い合いながら、どこまでもどこまでも歩いていた。
嬉しくて楽しくて、胸の奥が切なくて、凌の横顔をずっと見ていたい、そう思った。
幸せに満ち溢れた奇跡のような夢だった。
夢から覚めて、またひとりぼっちの自分に気づき、凌が恋しくて目尻から涙が頬を伝い、無性に悲しくなった。
夢を見ながらそのまま死んでしまえればよかったのに・・・。
心にぽっかりと穴が開いたまま、私はまたこの世に戻って来たのだった。
私はさきほどまで私に付き添っていてくれた、ゆりさんの涙を思い出した。
・・・やっぱり死ななくて良かった。
ゆりさんを悲しませたまま逝かなくて良かった。
私はそう思いながら横たわると、頭から布団をかぶった。