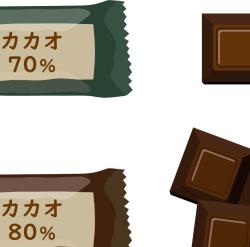初夏のある日。
凌が知り合いの人から小鳥を貰って帰ってきた。
「ヒナを沢山産んじゃったんだって。もう無理矢理押し付けられたようなもんだよ。俺、鳥なんか飼ったことないし、困ったなぁ。」
その小鳥は綺麗な空色の身体に頭部は白く黒いぶちが入った、つぶらな丸い瞳を持つセキセイインコだった。
「わあ。可愛い!」
私がそのセキセイインコの頭を触ろうとすると、怯えて部屋の片隅へ飛んでいってしまった。
「あっ。」
「ほれ。」
凌が人差し指を差し出すと、セキセイインコはぴょんとその指に乗った。
「ずるい。もう凌に懐いてる。」
「俺、昔から何故か動物には好かれるんだよね。」
「じゃあ、困ることなんて何もないよ。私達でこのインコ、可愛いがって育てよう!」
私達は早速近くのホームセンター内にあるペットショップへ行った。
あらかじめネットで調べておいた、インコを飼育するのに必要なものをピックアップしたメモを見ながら、買い物を進めていった。
インコを入れておくケージは白くて四角い、少し大きめなものを選んだ。
穀物で出来たエサ、水浴び用容器、ケージにつけてインコが遊ぶカラフルなブランコも購入した。
私はインコについてもっと知りたいと思い、「手のりの小鳥の楽しみ方」という本も買った。
セキセイインコは好奇心いっぱいで遊び好き、とその本には書かれてあった。
カゴの中のブランコに乗ってみたり、パソコンの上を歩き回ったりする。
ブランコに乗ると、小さな鈴の音がちりんと鳴った。
「インコの名前なににしよっか?」
私と凌は私達の元へ来てくれたインコにぴったりな名前を付けるのに、頭を悩ませた。
「コユキにしない?」
私の提案に凌が首を傾げた。
「コユキ?」
「凌と初めて出会った時、粉雪が降っていたでしょ?でもコナユキって言いにくいからコユキ。」
「うん。いいね。じゃあ今からお前はコユキだぞ。ほら、こっちこい。」
いつものように凌が人差し指を出すと、コユキはちょこんと凌の指に止まった。
そして「ピュロロピュロロ」と鳴いた。
コユキが家に来てから、凌のいない長い夜も淋しくなくなった。
いや、淋しくないと言えば嘘になるけれど、ひとりでいるときよりも淋しさは和らいだ。
もしかして凌は私のためにコユキを家に連れてきたのかもしれない、そう思った。
コユキが来て一週間後、コユキを動物病院へ連れていった。
コユキの健康診断をするためだ。
初めて行く、白い壁が真新しく、綺麗で清潔な動物病院には、猫の先客がいた。
猫はコユキをのそりと見て、にゃあと鳴いた。
コユキは猫の鳴き声に、少し怯えているようだった。
小鳥の中には、病院の診察を怖がる子がいると本に書かれてあったので、コユキの反応が心配だった。
少し待つと、名前を呼ばれ診察室に入り、診察台にコユキを入れたキャリーケースを載せた。
「こんにちは。はいはい、ちょっといい子にしててね~。」
眉毛の太い若い男の獣医さんは手慣れた手つきでコユキをキャリーケースから出すと、右手で保定した。
そしてコユキの体を丁寧に触診し、透明な箱に入れて、キッチンで使うはかりのようなものでコユキの体重を測った。
フンの状態も確認し、爪も切ってもらった。
特に異常なしということでホッと安心した。
私のたどたどしい仕草から察したのか、獣医さんが私に尋ねた。
「鳥を飼うのは初めて?」
「はい。」
「愛情をかければ動物は必ず答えてくれるからね。可愛がってあげてね。」
「はい。わかりました。」
会計を済ませ、レシートを見ると名前の欄に「田山コユキちゃん」とボールペンで書かれてあった。
家族が増えたようで、嬉しくて思わず微笑んだ。
私が家にいるときは、なるべくコユキをケージの外へ出してあげた。
なるべくなら広い空間で自由に過ごして欲しかった。
コユキは部屋の色んな場所へ飛びまわって遊んだ。
そして少しすると、私の手の甲へ止まり、羽根を休めた。
コユキがオスなのかメスなのか、最初はわからなかった。
けれど「ピュロロピュロロ」という鳴き声はオスからメスへのラブコールなのだと知った。
だからコユキは私達の間でオス、ということになった。
甘えん坊のコユキは、少し部屋を飛び回ると、人間にべったりとくっつくのが好きだった。
そしてコユキは私より凌によく懐いていた。
凌がいないときは、私の膝でくつろぐ。
けれど凌がいるときは、私には目もくれず、一目散に凌の元へ飛んでいく。
そして「チッチッチ」と嬉しそうに鳴く。
どうやらコユキは私をライバル視しているようだった。
インコはおしゃべりが得意な鳥だ。
私はコユキにおしゃべりトレーニングを始めた。
まずはことあるごとに名前を呼び掛けるようにした。
「コユキ。おいで。」
はっきりと名前を呼び掛けることで、コユキも自分が呼ばれていることを理解しているようだった。
そして朝晩の挨拶も忘れないように語りかけた。
「おはよう。コユキ。」
「おやすみ。コユキ。」
コユキは私の話す言葉をすぐに覚えた。
「オハヨウ。コユキ。」
「オヤスミ。コユキ。」
私は凌に伝わるように、こう語りかけてみた。
「おはよう。凌。」
「おやすみ。凌。」
コユキはこれもすぐ覚えた。
「オハヨウ。リョウ。」
「オヤスミ。リョウ。」
私はためらいがちにコユキにこう語りかけた。
「凌。好きだよ。大好きだよ。」
そう言葉にした途端、私は急に恥ずかしくなった。
「あ、今のナシ!コユキ、覚えなくていいからね!」
コユキは何も言わなかった。
凌が知り合いの人から小鳥を貰って帰ってきた。
「ヒナを沢山産んじゃったんだって。もう無理矢理押し付けられたようなもんだよ。俺、鳥なんか飼ったことないし、困ったなぁ。」
その小鳥は綺麗な空色の身体に頭部は白く黒いぶちが入った、つぶらな丸い瞳を持つセキセイインコだった。
「わあ。可愛い!」
私がそのセキセイインコの頭を触ろうとすると、怯えて部屋の片隅へ飛んでいってしまった。
「あっ。」
「ほれ。」
凌が人差し指を差し出すと、セキセイインコはぴょんとその指に乗った。
「ずるい。もう凌に懐いてる。」
「俺、昔から何故か動物には好かれるんだよね。」
「じゃあ、困ることなんて何もないよ。私達でこのインコ、可愛いがって育てよう!」
私達は早速近くのホームセンター内にあるペットショップへ行った。
あらかじめネットで調べておいた、インコを飼育するのに必要なものをピックアップしたメモを見ながら、買い物を進めていった。
インコを入れておくケージは白くて四角い、少し大きめなものを選んだ。
穀物で出来たエサ、水浴び用容器、ケージにつけてインコが遊ぶカラフルなブランコも購入した。
私はインコについてもっと知りたいと思い、「手のりの小鳥の楽しみ方」という本も買った。
セキセイインコは好奇心いっぱいで遊び好き、とその本には書かれてあった。
カゴの中のブランコに乗ってみたり、パソコンの上を歩き回ったりする。
ブランコに乗ると、小さな鈴の音がちりんと鳴った。
「インコの名前なににしよっか?」
私と凌は私達の元へ来てくれたインコにぴったりな名前を付けるのに、頭を悩ませた。
「コユキにしない?」
私の提案に凌が首を傾げた。
「コユキ?」
「凌と初めて出会った時、粉雪が降っていたでしょ?でもコナユキって言いにくいからコユキ。」
「うん。いいね。じゃあ今からお前はコユキだぞ。ほら、こっちこい。」
いつものように凌が人差し指を出すと、コユキはちょこんと凌の指に止まった。
そして「ピュロロピュロロ」と鳴いた。
コユキが家に来てから、凌のいない長い夜も淋しくなくなった。
いや、淋しくないと言えば嘘になるけれど、ひとりでいるときよりも淋しさは和らいだ。
もしかして凌は私のためにコユキを家に連れてきたのかもしれない、そう思った。
コユキが来て一週間後、コユキを動物病院へ連れていった。
コユキの健康診断をするためだ。
初めて行く、白い壁が真新しく、綺麗で清潔な動物病院には、猫の先客がいた。
猫はコユキをのそりと見て、にゃあと鳴いた。
コユキは猫の鳴き声に、少し怯えているようだった。
小鳥の中には、病院の診察を怖がる子がいると本に書かれてあったので、コユキの反応が心配だった。
少し待つと、名前を呼ばれ診察室に入り、診察台にコユキを入れたキャリーケースを載せた。
「こんにちは。はいはい、ちょっといい子にしててね~。」
眉毛の太い若い男の獣医さんは手慣れた手つきでコユキをキャリーケースから出すと、右手で保定した。
そしてコユキの体を丁寧に触診し、透明な箱に入れて、キッチンで使うはかりのようなものでコユキの体重を測った。
フンの状態も確認し、爪も切ってもらった。
特に異常なしということでホッと安心した。
私のたどたどしい仕草から察したのか、獣医さんが私に尋ねた。
「鳥を飼うのは初めて?」
「はい。」
「愛情をかければ動物は必ず答えてくれるからね。可愛がってあげてね。」
「はい。わかりました。」
会計を済ませ、レシートを見ると名前の欄に「田山コユキちゃん」とボールペンで書かれてあった。
家族が増えたようで、嬉しくて思わず微笑んだ。
私が家にいるときは、なるべくコユキをケージの外へ出してあげた。
なるべくなら広い空間で自由に過ごして欲しかった。
コユキは部屋の色んな場所へ飛びまわって遊んだ。
そして少しすると、私の手の甲へ止まり、羽根を休めた。
コユキがオスなのかメスなのか、最初はわからなかった。
けれど「ピュロロピュロロ」という鳴き声はオスからメスへのラブコールなのだと知った。
だからコユキは私達の間でオス、ということになった。
甘えん坊のコユキは、少し部屋を飛び回ると、人間にべったりとくっつくのが好きだった。
そしてコユキは私より凌によく懐いていた。
凌がいないときは、私の膝でくつろぐ。
けれど凌がいるときは、私には目もくれず、一目散に凌の元へ飛んでいく。
そして「チッチッチ」と嬉しそうに鳴く。
どうやらコユキは私をライバル視しているようだった。
インコはおしゃべりが得意な鳥だ。
私はコユキにおしゃべりトレーニングを始めた。
まずはことあるごとに名前を呼び掛けるようにした。
「コユキ。おいで。」
はっきりと名前を呼び掛けることで、コユキも自分が呼ばれていることを理解しているようだった。
そして朝晩の挨拶も忘れないように語りかけた。
「おはよう。コユキ。」
「おやすみ。コユキ。」
コユキは私の話す言葉をすぐに覚えた。
「オハヨウ。コユキ。」
「オヤスミ。コユキ。」
私は凌に伝わるように、こう語りかけてみた。
「おはよう。凌。」
「おやすみ。凌。」
コユキはこれもすぐ覚えた。
「オハヨウ。リョウ。」
「オヤスミ。リョウ。」
私はためらいがちにコユキにこう語りかけた。
「凌。好きだよ。大好きだよ。」
そう言葉にした途端、私は急に恥ずかしくなった。
「あ、今のナシ!コユキ、覚えなくていいからね!」
コユキは何も言わなかった。