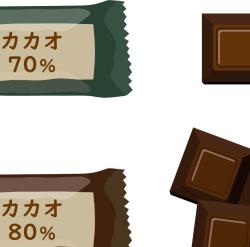私と古田さんと美紀ちゃんは着替えをし店を出ると、降り出した雨をよけながら、隣のビルの地下にあるサイゼリヤに入った。
窓際の4人掛けテーブル席にそれぞれ座った。
「あ~お腹すいたね。何食べようか?」
「サイゼと言ったらやっぱりミラノ風ドリア一択でしょ。」
古田さんと美紀ちゃんが明るく言った。
私は食欲などまったくなかったけれど、何も食べないわけにもいかないので、たらこスパゲティを注文した。
それからドリンクバーで好きな飲み物を取りにいった。
古田さんはホットコーヒー、美紀ちゃんはオレンジジュース、私はアイスミルクティーを持って席についた。
しばらくするとそれぞれが頼んだ料理が届いた。
私達は今日担当したお客様の話や、施術の反省点など当たり障りないことを話しながら、食事を始めた。
しかし何を話していても、頭の片隅には里香先輩のことが離れなかった。
それは古田さんも美紀ちゃんも同じだったらしく、二人の会話もどこか上滑りしていた。
食事が終わると、私達の会話に静かな間が空いた。
最初に口を開いたのは美紀ちゃんだった。
「里香先輩のこと・・・ショックだね。」
美紀ちゃんの言葉に私も古田さんも、お互いの目を見ながら同じ思いを共有した。
「まだ信じられない・・・どうして?なんで里香先輩は死を選んだんだろう・・・」
私はそうつぶやいて顔を両手で覆い、俯いた。
「ほんとにね。」
「里香先輩は店の要だったのに。」
「まさか、こんなことになるなんてね。」
「・・・え?」
私は古田さんの言葉に、ハッと顔を上げた。
まさか、こんなことになるなんて・・・って言った?
「古田さんは・・・里香先輩が亡くなった理由を何か知ってるんですか?」
私の縋るような言葉に、古田さんと美紀ちゃんは目配せした。
どうやら美紀ちゃんも何かを知っているようだった。
「そっか・・・伊織ちゃんは知らなかったか。」
「伊織ちゃん、スタッフの人間関係、あまり興味ないもんね。」
どういうこと?
里香先輩は「リリー」で、他のスタッフとなにか問題でもあったの?
私の無言の問いかけに答える様に、古田さんが話し始めた。
「先月までスタッフだった吉住君、覚えてるでしょ?」
「はい。」
吉住大地さんは、「リリー」で働く以前にも別の店舗で働いていた経験がある、若いけれど腕のいいベテランセラピストだった。
アイドルのような甘い顔をした、凌とは違うタイプのイケメンで、女性客からの指名も多かった。
次期店長候補とも噂されていたのに、先月どういうわけか突然店を辞めてしまったのだ。
「吉住さん、急に店を辞めてしまいましたよね。」
「辞めたんじゃないわ。辞めさせられたのよ。店長の一存で。」
「そうだったんですか?」
私はその事実を初めて知り、驚いた。
「どうしてですか?」
「素行が悪かったからね。吉住君。」
「素行が悪い?」
「吉住君は女性にだらしなかったの。店の中でも外でも入れ食い状態だったらしいわ。」
「知らなかった・・・。」
私にとっての吉住さんは、施術のやり方を丁寧に教えてくれて頼りになる先輩だった。
「で、吉住君を追いかけるように辞めちゃった紗英ちゃんって女の子いたでしょ?実は吉住君と紗英ちゃんはデキてたんだよね。何人ものスタッフが、2人が腕を組んで歩いているところを目撃してるからそれは間違いない事実。」
「歌舞伎町のホテル街で見掛けたっていう人もいたよね。」
美紀ちゃんは投げやりにそう言うと、ストローでオレンジジュースを啜った。
紗英ちゃんは美紀ちゃんより歳が一つ下で、韓国風メイクが特徴の甘え上手な女の子だった。
雑用をさぼるのが上手くて、そのくせ店の男性スタッフにはことあるごとに「飲みに連れて行ってくださいよ~」とねだるのが口癖だったと記憶している。
でもその吉住さんと紗英ちゃんが里香先輩とどう関係してくるのだろうか?
「実はその前から、吉住君と里香ちゃんはセフレだったんだよね。」
古田さんは苦いものを吐き出すように言った
「セフレ・・・?」
「でも里香ちゃんは真剣だったみたい。実は私、少しだけ相談されてたんだ。里香ちゃんに。」
古田さんは唇を震わせ、泣きそうな顔になった。
「いつも会う時は向こうから突然呼び出さる。会うのはホテルかお互いの家だけ。外でのデートもなし。友人にも紹介してもらえない・・・って悩んでた。典型的な男がセフレを扱う態度だよ。だからそんな男、もう関わるの止めなって何度も忠告したんだ。・・・でも里香ちゃんは諦めきれなかったみたい。それでもいいって苦しそうに笑ってた。」
「里香先輩はどうして吉住さんみたいなヤリチンを本気で好きになっちゃったんだろ。そりゃ吉住さんは仕事出来るしイケメンだけど、何人もの女の子と同時進行で関係持ってさ。最低だよ。」
「うん。紗英ちゃんや里香ちゃん以外でも、吉住君の毒牙にかかった女性スタッフは少なくないって聞いてる。酷い男だよ。」
「でも紗英ちゃんも吉住さんのことは、別に本気じゃなかったんでしょ?それなのに里香先輩にマウントとるように吉住さんとの仲を見せびらかして。紗英ちゃんもどうかしてるよ。」
「・・・まあ、そんないきさつで堪忍袋の緒が切れた店長が、吉住君と紗英ちゃんをクビにしたってわけ。そんな二人はのうのうと生きて、捨てられた里香ちゃんがふたりの関係を苦にして死んじゃうなんて・・・里香ちゃんは本当に大馬鹿だよ。」
私はただ黙って古田さんと美紀ちゃんの話に耳を傾けていた。
私の知らないところで、そんなドロドロとした恋愛模様が繰り広げられていたことに、大きなショックを受けていた。
里香先輩には私に見せる強くて優しい顔とは別の一面があったのだ。
里香先輩の悲しみに、どうして私は気づいてあげられなかったのだろう。
あんなに近くで一緒に仕事をしていたのに。
自分の鈍感さが情けなかった。
「愛ってさ」
古田さんがコーヒーカップに口をつけたあと、ぽつりと語りだした。
「諸刃の剣なんだよね。上手くいってる時は何をしていても楽しいし世界は薔薇色。だけど失った時、失いそうな時、その愛が本物であればあるほど、どこまでも暗い底へと堕ちて行く。その闇が精神を蝕み命を奪うなんてことは、そんなに珍しいことじゃないんだよ。むしろ本人にとってはその愛を失うくらいなら死んでしまうほうが楽だってこともあるんだよ。」
「だったら私は本気の恋なんてしたくない。そんな辛い思いするなんてまっぴらゴメン。」
美紀ちゃんがそう言ってオレンジジュースを飲み干した。
私達は窓の外に降る雨を静かに眺めた。
それは里香先輩の涙に思えた。
窓際の4人掛けテーブル席にそれぞれ座った。
「あ~お腹すいたね。何食べようか?」
「サイゼと言ったらやっぱりミラノ風ドリア一択でしょ。」
古田さんと美紀ちゃんが明るく言った。
私は食欲などまったくなかったけれど、何も食べないわけにもいかないので、たらこスパゲティを注文した。
それからドリンクバーで好きな飲み物を取りにいった。
古田さんはホットコーヒー、美紀ちゃんはオレンジジュース、私はアイスミルクティーを持って席についた。
しばらくするとそれぞれが頼んだ料理が届いた。
私達は今日担当したお客様の話や、施術の反省点など当たり障りないことを話しながら、食事を始めた。
しかし何を話していても、頭の片隅には里香先輩のことが離れなかった。
それは古田さんも美紀ちゃんも同じだったらしく、二人の会話もどこか上滑りしていた。
食事が終わると、私達の会話に静かな間が空いた。
最初に口を開いたのは美紀ちゃんだった。
「里香先輩のこと・・・ショックだね。」
美紀ちゃんの言葉に私も古田さんも、お互いの目を見ながら同じ思いを共有した。
「まだ信じられない・・・どうして?なんで里香先輩は死を選んだんだろう・・・」
私はそうつぶやいて顔を両手で覆い、俯いた。
「ほんとにね。」
「里香先輩は店の要だったのに。」
「まさか、こんなことになるなんてね。」
「・・・え?」
私は古田さんの言葉に、ハッと顔を上げた。
まさか、こんなことになるなんて・・・って言った?
「古田さんは・・・里香先輩が亡くなった理由を何か知ってるんですか?」
私の縋るような言葉に、古田さんと美紀ちゃんは目配せした。
どうやら美紀ちゃんも何かを知っているようだった。
「そっか・・・伊織ちゃんは知らなかったか。」
「伊織ちゃん、スタッフの人間関係、あまり興味ないもんね。」
どういうこと?
里香先輩は「リリー」で、他のスタッフとなにか問題でもあったの?
私の無言の問いかけに答える様に、古田さんが話し始めた。
「先月までスタッフだった吉住君、覚えてるでしょ?」
「はい。」
吉住大地さんは、「リリー」で働く以前にも別の店舗で働いていた経験がある、若いけれど腕のいいベテランセラピストだった。
アイドルのような甘い顔をした、凌とは違うタイプのイケメンで、女性客からの指名も多かった。
次期店長候補とも噂されていたのに、先月どういうわけか突然店を辞めてしまったのだ。
「吉住さん、急に店を辞めてしまいましたよね。」
「辞めたんじゃないわ。辞めさせられたのよ。店長の一存で。」
「そうだったんですか?」
私はその事実を初めて知り、驚いた。
「どうしてですか?」
「素行が悪かったからね。吉住君。」
「素行が悪い?」
「吉住君は女性にだらしなかったの。店の中でも外でも入れ食い状態だったらしいわ。」
「知らなかった・・・。」
私にとっての吉住さんは、施術のやり方を丁寧に教えてくれて頼りになる先輩だった。
「で、吉住君を追いかけるように辞めちゃった紗英ちゃんって女の子いたでしょ?実は吉住君と紗英ちゃんはデキてたんだよね。何人ものスタッフが、2人が腕を組んで歩いているところを目撃してるからそれは間違いない事実。」
「歌舞伎町のホテル街で見掛けたっていう人もいたよね。」
美紀ちゃんは投げやりにそう言うと、ストローでオレンジジュースを啜った。
紗英ちゃんは美紀ちゃんより歳が一つ下で、韓国風メイクが特徴の甘え上手な女の子だった。
雑用をさぼるのが上手くて、そのくせ店の男性スタッフにはことあるごとに「飲みに連れて行ってくださいよ~」とねだるのが口癖だったと記憶している。
でもその吉住さんと紗英ちゃんが里香先輩とどう関係してくるのだろうか?
「実はその前から、吉住君と里香ちゃんはセフレだったんだよね。」
古田さんは苦いものを吐き出すように言った
「セフレ・・・?」
「でも里香ちゃんは真剣だったみたい。実は私、少しだけ相談されてたんだ。里香ちゃんに。」
古田さんは唇を震わせ、泣きそうな顔になった。
「いつも会う時は向こうから突然呼び出さる。会うのはホテルかお互いの家だけ。外でのデートもなし。友人にも紹介してもらえない・・・って悩んでた。典型的な男がセフレを扱う態度だよ。だからそんな男、もう関わるの止めなって何度も忠告したんだ。・・・でも里香ちゃんは諦めきれなかったみたい。それでもいいって苦しそうに笑ってた。」
「里香先輩はどうして吉住さんみたいなヤリチンを本気で好きになっちゃったんだろ。そりゃ吉住さんは仕事出来るしイケメンだけど、何人もの女の子と同時進行で関係持ってさ。最低だよ。」
「うん。紗英ちゃんや里香ちゃん以外でも、吉住君の毒牙にかかった女性スタッフは少なくないって聞いてる。酷い男だよ。」
「でも紗英ちゃんも吉住さんのことは、別に本気じゃなかったんでしょ?それなのに里香先輩にマウントとるように吉住さんとの仲を見せびらかして。紗英ちゃんもどうかしてるよ。」
「・・・まあ、そんないきさつで堪忍袋の緒が切れた店長が、吉住君と紗英ちゃんをクビにしたってわけ。そんな二人はのうのうと生きて、捨てられた里香ちゃんがふたりの関係を苦にして死んじゃうなんて・・・里香ちゃんは本当に大馬鹿だよ。」
私はただ黙って古田さんと美紀ちゃんの話に耳を傾けていた。
私の知らないところで、そんなドロドロとした恋愛模様が繰り広げられていたことに、大きなショックを受けていた。
里香先輩には私に見せる強くて優しい顔とは別の一面があったのだ。
里香先輩の悲しみに、どうして私は気づいてあげられなかったのだろう。
あんなに近くで一緒に仕事をしていたのに。
自分の鈍感さが情けなかった。
「愛ってさ」
古田さんがコーヒーカップに口をつけたあと、ぽつりと語りだした。
「諸刃の剣なんだよね。上手くいってる時は何をしていても楽しいし世界は薔薇色。だけど失った時、失いそうな時、その愛が本物であればあるほど、どこまでも暗い底へと堕ちて行く。その闇が精神を蝕み命を奪うなんてことは、そんなに珍しいことじゃないんだよ。むしろ本人にとってはその愛を失うくらいなら死んでしまうほうが楽だってこともあるんだよ。」
「だったら私は本気の恋なんてしたくない。そんな辛い思いするなんてまっぴらゴメン。」
美紀ちゃんがそう言ってオレンジジュースを飲み干した。
私達は窓の外に降る雨を静かに眺めた。
それは里香先輩の涙に思えた。