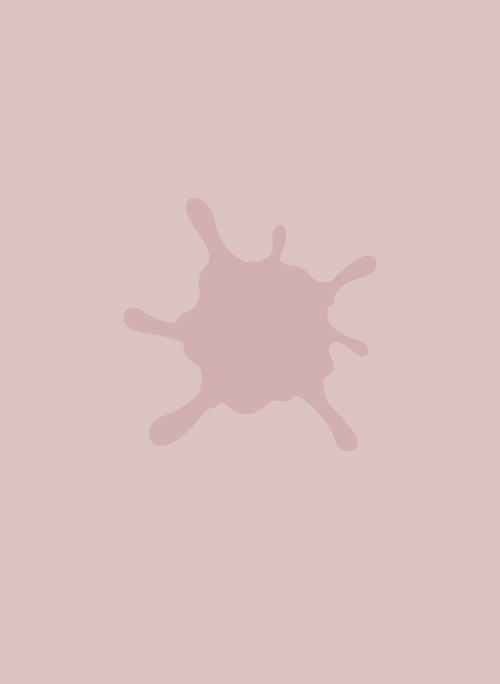その後、夏フェス最終日のメインイベント。
『frontier』以下、ゲストアーティストとのコラボライブが始まった。
語るべきことは多くない。
いつも通り素晴らしかった、とだけ言っておこう。
いや…今回はいつも以上か?
なんと言っても今回は、『frontier』の単独ライブではない。
あの『ポテサラーズ』を始め、他にも豪華アーティストとの合同ライブだからな。
ライブはずっと盛り上がっていたが、特に『ポテサラーズ』が『frontier』の曲を歌ったときは、大歓声、拍手喝采だった。
そして、それ以上に盛り上がったのは。
『frontier』が、『ポテサラーズ』の曲を歌ったとき。
いやはや、天地が割れそうなほどの大歓声でしたよ。
「もう『frontier』は、『ポテサラーズ』を超えてるかもね」
と、アイズが認めるほどだ。
「俺もそう思いますよ。…本人達は認めないでしょうけどね」
『ポテサラーズ』も良いけど、『frontier』は今や、それ以上のアーティストだと思う。
身内贔屓かもしれないが。
まぁ、俺のマネジメントのお陰ですね。
そして。
「普通に歌ってるな…。全然緊張してるように見えない」
舞台に立つルトリアさんを見て、ルルシーが呟いた。
ね?言ったでしょう?
ルトリアさんなら大丈夫だって。
「きっと今頃彼は、誰よりも舞台を楽しんでると思いますよ」
自分が楽しくないと、人を楽しませることなんて出来ないからな。
それがルトリアさんの、一番の強みだと思う。
…そして。
そんなルトリアさんの努力の甲斐あって。
夏フェス最終日を飾る屋外ライブは、大成功、大盛況で終わった。
『frontier』以下、ゲストアーティストとのコラボライブが始まった。
語るべきことは多くない。
いつも通り素晴らしかった、とだけ言っておこう。
いや…今回はいつも以上か?
なんと言っても今回は、『frontier』の単独ライブではない。
あの『ポテサラーズ』を始め、他にも豪華アーティストとの合同ライブだからな。
ライブはずっと盛り上がっていたが、特に『ポテサラーズ』が『frontier』の曲を歌ったときは、大歓声、拍手喝采だった。
そして、それ以上に盛り上がったのは。
『frontier』が、『ポテサラーズ』の曲を歌ったとき。
いやはや、天地が割れそうなほどの大歓声でしたよ。
「もう『frontier』は、『ポテサラーズ』を超えてるかもね」
と、アイズが認めるほどだ。
「俺もそう思いますよ。…本人達は認めないでしょうけどね」
『ポテサラーズ』も良いけど、『frontier』は今や、それ以上のアーティストだと思う。
身内贔屓かもしれないが。
まぁ、俺のマネジメントのお陰ですね。
そして。
「普通に歌ってるな…。全然緊張してるように見えない」
舞台に立つルトリアさんを見て、ルルシーが呟いた。
ね?言ったでしょう?
ルトリアさんなら大丈夫だって。
「きっと今頃彼は、誰よりも舞台を楽しんでると思いますよ」
自分が楽しくないと、人を楽しませることなんて出来ないからな。
それがルトリアさんの、一番の強みだと思う。
…そして。
そんなルトリアさんの努力の甲斐あって。
夏フェス最終日を飾る屋外ライブは、大成功、大盛況で終わった。
「いやはや、楽しかったですね〜」
「あぁ。さすが『frontier』だな」
「どうでした?セカイさん」
「凄く面白かった!また連れてきてね、ルーチェス君」
「今日も可愛かったなぁ、ベーシュちゃん…」
「アリューシャ、疲れた?眠い?」
「んにゃ〜…。…zzz…」
「…お前ら…」
上から。
俺、ルルシー、ルーチェス、ルーチェス嫁、シュノさん、アイズ、アリューシャ、ルルシーの順である。
皆、思い思い楽しんでくれたようで何より。
ライブで騒ぎ疲れたらしいアリューシャは、既に寝落ちしてしまったので。
「よいしょっと…」
アイズが背中にアリューシャをおんぶして、運んであげていた。
「その馬鹿、会場に置いて帰れ」
ルルシーったら、過激なんだから。
…さて、それはそうと。
「ルリシヤ、後でオムライスとチュロスとフラッペ、届けさせますね」
「あぁ、頼む」
「シュノさんも。アクスタ、明日まで待ってもらって良いですか?」
「うん、急がなくて良いよ。ありがとう」
…それから、これは皆に。
「皆さんに後日、プレゼントをお渡ししますね」
「プレゼント…?何だ?」
何だと思う?
聞いて驚け、ですよ。
「今日のライブに参加した、全アーティストの直筆サイン入り色紙です」
「えっ…!」
これには、ルルシーもびっくり。
「本来は、会場でCDを購入した人限定で、抽選100名に送られる超レアアイテムなんですが…」
「お前、まさかそれもスポンサー権限で…」
「…てへっ」
そういうことです、ルルシー。
「てへっじゃないんだよ。てへっじゃ。そんな不正を…」
「抽選100名に配られるのは事実ですよ。ただ、予備に10枚くらい多めに用意しておいたので」
俺達がもらうのは、その予備分だ。
会場でCDを買った、幸運な100人のもとにも、ちゃんと届けられますよ。
「凄い…!ありがとう、ルレイア。大事にするよ」
シュノさん、大喜び。
いえいえ、とんでもない。
今日は皆さんが来てくれたお陰で、俺も楽しかったですからね。
ちょっとしたお土産みたいなものだ。
「全く…。権力の濫用だ…」
まぁ、ルルシーはぶつぶつ言ってましたけど。
別にこれくらい、可愛いものじゃないですか…と。
言おうとした、そのとき。
何処からか視線を感じて、俺は振り向いた。
「…?」
…誰もいなかった。
何だ、今の…。誰か…。
「…ルレイア?どうした?」
ふと立ち止まった俺を、ルルシーが呼んだ。
「あ、いえ…何でもないです」
そう言って、俺は視線を感じた方向に背中を向けた。
…何事もないとは思うが。
あまり、気にし過ぎてもな。
何より、今日くらいは…余計なことに煩わることなく、楽しく一日を終えたかった。
「あぁ。さすが『frontier』だな」
「どうでした?セカイさん」
「凄く面白かった!また連れてきてね、ルーチェス君」
「今日も可愛かったなぁ、ベーシュちゃん…」
「アリューシャ、疲れた?眠い?」
「んにゃ〜…。…zzz…」
「…お前ら…」
上から。
俺、ルルシー、ルーチェス、ルーチェス嫁、シュノさん、アイズ、アリューシャ、ルルシーの順である。
皆、思い思い楽しんでくれたようで何より。
ライブで騒ぎ疲れたらしいアリューシャは、既に寝落ちしてしまったので。
「よいしょっと…」
アイズが背中にアリューシャをおんぶして、運んであげていた。
「その馬鹿、会場に置いて帰れ」
ルルシーったら、過激なんだから。
…さて、それはそうと。
「ルリシヤ、後でオムライスとチュロスとフラッペ、届けさせますね」
「あぁ、頼む」
「シュノさんも。アクスタ、明日まで待ってもらって良いですか?」
「うん、急がなくて良いよ。ありがとう」
…それから、これは皆に。
「皆さんに後日、プレゼントをお渡ししますね」
「プレゼント…?何だ?」
何だと思う?
聞いて驚け、ですよ。
「今日のライブに参加した、全アーティストの直筆サイン入り色紙です」
「えっ…!」
これには、ルルシーもびっくり。
「本来は、会場でCDを購入した人限定で、抽選100名に送られる超レアアイテムなんですが…」
「お前、まさかそれもスポンサー権限で…」
「…てへっ」
そういうことです、ルルシー。
「てへっじゃないんだよ。てへっじゃ。そんな不正を…」
「抽選100名に配られるのは事実ですよ。ただ、予備に10枚くらい多めに用意しておいたので」
俺達がもらうのは、その予備分だ。
会場でCDを買った、幸運な100人のもとにも、ちゃんと届けられますよ。
「凄い…!ありがとう、ルレイア。大事にするよ」
シュノさん、大喜び。
いえいえ、とんでもない。
今日は皆さんが来てくれたお陰で、俺も楽しかったですからね。
ちょっとしたお土産みたいなものだ。
「全く…。権力の濫用だ…」
まぁ、ルルシーはぶつぶつ言ってましたけど。
別にこれくらい、可愛いものじゃないですか…と。
言おうとした、そのとき。
何処からか視線を感じて、俺は振り向いた。
「…?」
…誰もいなかった。
何だ、今の…。誰か…。
「…ルレイア?どうした?」
ふと立ち止まった俺を、ルルシーが呼んだ。
「あ、いえ…何でもないです」
そう言って、俺は視線を感じた方向に背中を向けた。
…何事もないとは思うが。
あまり、気にし過ぎてもな。
何より、今日くらいは…余計なことに煩わることなく、楽しく一日を終えたかった。
――――――…『青薔薇連合会』に立ち入り調査を行ってからというもの。
私達帝国自警団は、絶えず『青薔薇連合会』の動きを見張っていた。
何か怪しい動きがないものかと。
しかし、これまで私達は…『青薔薇連合会』を検挙するに足る証拠を、何も掴めずにいた。
…不甲斐ないばかりである。
私がルティス帝国に帰ってきたからには、『青薔薇連合会』にこれ以上、好き勝手なことはさせない。
そう誓ったはずなのに…。
現状私は、二の足を踏んでいる状態だった。
各方面から『青薔薇連合会』について…そして、ルレイア・ティシェリーについて調べているのだが…。
あの狡猾な男、噂だけはごまんとあるのだが…確かな証拠は何も残していない。
…厄介だな。
でも、例え噂だけだったとしても、それは大事な情報だ。
その噂を辿って、『青薔薇連合会』の…ルレイア・ティシェリーの実態を掴む。
焦る必要はない。いずれは必ず、『青薔薇連合会』を止めてみせる。
帝国騎士団と『青薔薇連合会』の癒着を暴き、人質になっているベルガモット王家の皇太子を解放するのだ。
それが、帝国自警団のリーダーである私の使命だ。
…そして、この日。
帝国自警団に、また一つ有益な情報がもたらされた。
…と、いうのも。
「…帝都で開かれた屋外イベントに、ルレイア・ティシェリーが参加してる?」
「あぁ。非番の団員が偶然、このイベントに参加して…。そこでルレイアを見つけたらしい」
「…そんな偶然が…」
ルレイア・ティシェリーは神出鬼没。何処に現れるか分からないのに。
偶然、非番の団員が見つけたとは…。
これはお手柄だね。
「でも、それは本当にルレイアなの?確かな情報?」
話しかけて確認した訳じゃないんだよね?
遠目から見ただけなら、ただ似ているだけの別人という可能性も…。
「見間違えるはずがないよ。ブロテも見ただろう?…あんな男は、ルティス帝国に二人といないよ」
と、報告に来たセルニアが言った。
…そうだったね。
忘れようと思っても、忘れられるはずがない。
「それに、証拠として…写真を撮ってきたって」
「写真?」
「遠くから、スマホで拡大して撮った写真。一枚しかないけど…」
「見せて」
そう言うと思ったとばかりに、セルニアはすぐに、クリアファイルに入っていた写真を見せてくれた。
若干ぼやけた写真だったが、そこに写っている顔は…間違いなかった。
「…ルレイア・ティシェリー…」
疑う余地もなく、私達が追っている人物その人であった。
私達帝国自警団は、絶えず『青薔薇連合会』の動きを見張っていた。
何か怪しい動きがないものかと。
しかし、これまで私達は…『青薔薇連合会』を検挙するに足る証拠を、何も掴めずにいた。
…不甲斐ないばかりである。
私がルティス帝国に帰ってきたからには、『青薔薇連合会』にこれ以上、好き勝手なことはさせない。
そう誓ったはずなのに…。
現状私は、二の足を踏んでいる状態だった。
各方面から『青薔薇連合会』について…そして、ルレイア・ティシェリーについて調べているのだが…。
あの狡猾な男、噂だけはごまんとあるのだが…確かな証拠は何も残していない。
…厄介だな。
でも、例え噂だけだったとしても、それは大事な情報だ。
その噂を辿って、『青薔薇連合会』の…ルレイア・ティシェリーの実態を掴む。
焦る必要はない。いずれは必ず、『青薔薇連合会』を止めてみせる。
帝国騎士団と『青薔薇連合会』の癒着を暴き、人質になっているベルガモット王家の皇太子を解放するのだ。
それが、帝国自警団のリーダーである私の使命だ。
…そして、この日。
帝国自警団に、また一つ有益な情報がもたらされた。
…と、いうのも。
「…帝都で開かれた屋外イベントに、ルレイア・ティシェリーが参加してる?」
「あぁ。非番の団員が偶然、このイベントに参加して…。そこでルレイアを見つけたらしい」
「…そんな偶然が…」
ルレイア・ティシェリーは神出鬼没。何処に現れるか分からないのに。
偶然、非番の団員が見つけたとは…。
これはお手柄だね。
「でも、それは本当にルレイアなの?確かな情報?」
話しかけて確認した訳じゃないんだよね?
遠目から見ただけなら、ただ似ているだけの別人という可能性も…。
「見間違えるはずがないよ。ブロテも見ただろう?…あんな男は、ルティス帝国に二人といないよ」
と、報告に来たセルニアが言った。
…そうだったね。
忘れようと思っても、忘れられるはずがない。
「それに、証拠として…写真を撮ってきたって」
「写真?」
「遠くから、スマホで拡大して撮った写真。一枚しかないけど…」
「見せて」
そう言うと思ったとばかりに、セルニアはすぐに、クリアファイルに入っていた写真を見せてくれた。
若干ぼやけた写真だったが、そこに写っている顔は…間違いなかった。
「…ルレイア・ティシェリー…」
疑う余地もなく、私達が追っている人物その人であった。
…こんなところに、ルレイア・ティシェリーが現れるとは。
それに…この周りに写ってる人達。
「『青薔薇連合会』の幹部仲間だね」
「あぁ、そのようだ」
ルレイア・ティシェリーの隣に写っているこの男、見覚えがある。
立ち入り調査に行ったときも、ルレイアの隣にいた人だ。
名前は確か…ルルシーだったか?
それに、立ち入り調査に行ったとき、私達を出迎えた男も一緒だ。
他にも何人か、ルレイアの周りに一緒に写っていた。
これらは誰だろう…。ルレイアのお付きの人だろうか?
部下を何人も引き連れて歩くなんて、随分なご身分じゃない。
それより…この写真。
「ここでイベントがあったって言ったよね?何のイベント…?」
あのルレイア・ティシェリーが、部下を引き連れてわざわざ足を運ぶほどなのだ。
きっと、ただの催事では…。
「聞いたところによると、『frontier』っていうアーティストのイベントらしい」
セルニアは、困ったような顔でそう答えた。
…『frontier』?アーティスト?
「…聞いたことがあるような、ないような…。セルニア、知ってる?」
「さぁ…。僕も、ほとんど…。確か、動画サイトで有名なアイドルらしいね」
「…」
…そんなアイドルのイベントに、何故ルレイアが?
分からない…まさかそのアーティストのファンだとでも言うのだろうか?
マフィアの幹部が、まさか巷で噂のアイドルに夢中になるなんて…とても信じられない。
「きっと、何か魂胆があるに違いないよ」
あのルレイアともあろう男が、純粋にイベントを楽しみに来たはずがない。
何かを企んでいるのだ。無辜の人々を苦しめる何かを。
「僕もそう思って、少し調べてみたんだ。この…『frontier』っていうアーティストのこと」
と、セルニア。
「何か分かったの?」
「うん。どうやら『frontier』っていうアーティストが所属している事務所の親玉が、『青薔薇連合会』らしいね」
…やっぱり、そういうことなんだ。
つまりこのアーティストは、『青薔薇連合会』の息が…ルレイア・ティシェリーの息がかかっているんだ。
ルレイアがこの会場にいたのも、それが理由か。
「始めから、このアーティストは『青薔薇連合会』が作らせたものなのか…。それとも、元々いたアーティストに、『青薔薇連合会』が声をかけたのか…」
「…『青薔薇連合会』が作らせたんだと思うよ、私は」
そして、金に物を言わせ、権力に物を言わせ。
あらゆる汚い手口を使って、『frontier』というアーティストを有名人に仕立て上げたのだ。
『frontier』の人々は、ルレイア・ティシェリーの金儲けの為に使われているのだ。
可哀想に…。
あの男は、どれほど罪のない人々を苦しめたら気が済むのか…。
…やはり、何としてもルレイアだけは逮捕しなくては。
これ以上、罪のない人々を苦しめることがないように。
「…それだけじゃないんだよ、ブロテ」
「…え?」
セルニアは、酷く深刻な顔で私を見つめていた。
それだけじゃない、って…。
ルレイア・ティシェリーが『frontier』というアーティストを従わせて、金儲けをしている。
それ以上に問題なことが、他にあると?
それに…この周りに写ってる人達。
「『青薔薇連合会』の幹部仲間だね」
「あぁ、そのようだ」
ルレイア・ティシェリーの隣に写っているこの男、見覚えがある。
立ち入り調査に行ったときも、ルレイアの隣にいた人だ。
名前は確か…ルルシーだったか?
それに、立ち入り調査に行ったとき、私達を出迎えた男も一緒だ。
他にも何人か、ルレイアの周りに一緒に写っていた。
これらは誰だろう…。ルレイアのお付きの人だろうか?
部下を何人も引き連れて歩くなんて、随分なご身分じゃない。
それより…この写真。
「ここでイベントがあったって言ったよね?何のイベント…?」
あのルレイア・ティシェリーが、部下を引き連れてわざわざ足を運ぶほどなのだ。
きっと、ただの催事では…。
「聞いたところによると、『frontier』っていうアーティストのイベントらしい」
セルニアは、困ったような顔でそう答えた。
…『frontier』?アーティスト?
「…聞いたことがあるような、ないような…。セルニア、知ってる?」
「さぁ…。僕も、ほとんど…。確か、動画サイトで有名なアイドルらしいね」
「…」
…そんなアイドルのイベントに、何故ルレイアが?
分からない…まさかそのアーティストのファンだとでも言うのだろうか?
マフィアの幹部が、まさか巷で噂のアイドルに夢中になるなんて…とても信じられない。
「きっと、何か魂胆があるに違いないよ」
あのルレイアともあろう男が、純粋にイベントを楽しみに来たはずがない。
何かを企んでいるのだ。無辜の人々を苦しめる何かを。
「僕もそう思って、少し調べてみたんだ。この…『frontier』っていうアーティストのこと」
と、セルニア。
「何か分かったの?」
「うん。どうやら『frontier』っていうアーティストが所属している事務所の親玉が、『青薔薇連合会』らしいね」
…やっぱり、そういうことなんだ。
つまりこのアーティストは、『青薔薇連合会』の息が…ルレイア・ティシェリーの息がかかっているんだ。
ルレイアがこの会場にいたのも、それが理由か。
「始めから、このアーティストは『青薔薇連合会』が作らせたものなのか…。それとも、元々いたアーティストに、『青薔薇連合会』が声をかけたのか…」
「…『青薔薇連合会』が作らせたんだと思うよ、私は」
そして、金に物を言わせ、権力に物を言わせ。
あらゆる汚い手口を使って、『frontier』というアーティストを有名人に仕立て上げたのだ。
『frontier』の人々は、ルレイア・ティシェリーの金儲けの為に使われているのだ。
可哀想に…。
あの男は、どれほど罪のない人々を苦しめたら気が済むのか…。
…やはり、何としてもルレイアだけは逮捕しなくては。
これ以上、罪のない人々を苦しめることがないように。
「…それだけじゃないんだよ、ブロテ」
「…え?」
セルニアは、酷く深刻な顔で私を見つめていた。
それだけじゃない、って…。
ルレイア・ティシェリーが『frontier』というアーティストを従わせて、金儲けをしている。
それ以上に問題なことが、他にあると?
「どういうこと?セルニア…」
「ここに写ってる写真の人物を、帝国騎士団と共有しているデータベースと照らし合わせて、該当する人物を調べてみたんだ」
そこまでしてくれたんだ。
さすがセルニア、仕事が早い。
「それで?誰なの?」
「この写真に写ってる人物の中で、身元が分かったのは二人だけだった」
「二人…?ルレイアと、もう一人は誰?」
「いや、ルレイアは含まずに二人だ。正確に言えば、ルレイアもまだ身元が割れた訳じゃない。彼らは闇の戸籍を持ってるから」
あ、そうか…。
『青薔薇連合会』は、裏社会に所属する非合法組織。
まともな戸籍を持たず、闇から流れてきた、あるいは不法に購入した戸籍を使っている者も多い。
そういう者は、当然ながら帝国騎士団が管理する戸籍リストに載っていない。
ルレイアもその一人だっけ…。
お陰で私達は、ルレイア・ティシェリーが何処で生まれ、何処から来た、どのような身分の出自なのか、未だに分かってないのだ。
何処かに親兄弟はいるはずだが、それが何処なのか分からない。
ルティス帝国の生まれだとは思うのだが…。それだってあくまで推測だし。
…いや、今はそれよりも。
身元が判明した二人、というのが誰なのかを確認しよう。
「一人は、普通にルティス帝国市民権を持つ一般人の女性だった」
…一般人の女性?
何だか拍子抜けしてしまった。
何で一般人の女性が、『青薔薇連合会』の幹部達と一緒にいるの…?
「どれ?どの人?」
私は写真を覗き込んだ。
「この人だよ」
セルニアが、写真に写っている一人の女性を指差した。
この人が…。
顔はぼやけていて、どんな表情をしているのかよく見えない。
一体どういう関係で、『青薔薇連合会』なんかと一緒に…。
「名前は、セカイ・アンブローシア。帝都に住む一般女性。職業は主婦」
「『青薔薇連合会』との関係は?」
「元々は帝都の歓楽街で、長い間水商売をしていたみたいなんだけど…」
成程、夜の仕事をしている人だったんだね。
じゃあもしかして、『青薔薇連合会』との繫がりはそこで…。
「…どうもその人、亡くなった母親が相当借金を残していたらしくてね。その借金が、まるまる彼女に押し付けられたらしい」
「借金…?その借金って…。まさか…」
私は、一つの可能性に思い至った。
まさか。『青薔薇連合会』はそんな汚いことを。
しかし、セルニアのこの表情を見るに。
私の推測が当たっていることは、明白だった。
「うん。借金をした相手は、『青薔薇連合会』の下部組織の一つ。恐らく…この女性は『青薔薇連合会』への借金のカタに、こうして従わされてるんだと思う」
「…!」
やはり…やはり、そうなのか。
ルレイア・ティシェリー…なんという卑劣なことを。
借金を背負わされ、身動きの取れない一般女性を脅し、無理矢理言うことを聞かせ。
こうして自分の傍に侍らせて、奴隷のように扱っているなんて。
私は、写真に写っているセカイ・アンブローシアさんの顔を見た。
ぼやけていて、表情は分からない。
でもきっと…酷く悲しい顔をしているに違いない。
借金に縛り付けられ、望んでもいない相手に無理矢理従わされて…。
今すぐに写真の中に飛び込んで、彼女を救ってあげたい衝動にさえ駆られた。
それが出来たら、どんなに良かったか…。
「…気の毒に…。何とかして救ってあげられたら…」
「…確かにその人も気の毒だけど、その人の隣に写っている人も」
「え?」
…そういえば。
写真の中で、身元が分かったのは二人だって言ってたね。
セカイさんと、それからもう一人は…。
「セカイ・アンブローシアさんの隣に写っている人、その人の身元が分かった」
相変わらず堅い表情で、セルニアが言った。
「ここに写ってる写真の人物を、帝国騎士団と共有しているデータベースと照らし合わせて、該当する人物を調べてみたんだ」
そこまでしてくれたんだ。
さすがセルニア、仕事が早い。
「それで?誰なの?」
「この写真に写ってる人物の中で、身元が分かったのは二人だけだった」
「二人…?ルレイアと、もう一人は誰?」
「いや、ルレイアは含まずに二人だ。正確に言えば、ルレイアもまだ身元が割れた訳じゃない。彼らは闇の戸籍を持ってるから」
あ、そうか…。
『青薔薇連合会』は、裏社会に所属する非合法組織。
まともな戸籍を持たず、闇から流れてきた、あるいは不法に購入した戸籍を使っている者も多い。
そういう者は、当然ながら帝国騎士団が管理する戸籍リストに載っていない。
ルレイアもその一人だっけ…。
お陰で私達は、ルレイア・ティシェリーが何処で生まれ、何処から来た、どのような身分の出自なのか、未だに分かってないのだ。
何処かに親兄弟はいるはずだが、それが何処なのか分からない。
ルティス帝国の生まれだとは思うのだが…。それだってあくまで推測だし。
…いや、今はそれよりも。
身元が判明した二人、というのが誰なのかを確認しよう。
「一人は、普通にルティス帝国市民権を持つ一般人の女性だった」
…一般人の女性?
何だか拍子抜けしてしまった。
何で一般人の女性が、『青薔薇連合会』の幹部達と一緒にいるの…?
「どれ?どの人?」
私は写真を覗き込んだ。
「この人だよ」
セルニアが、写真に写っている一人の女性を指差した。
この人が…。
顔はぼやけていて、どんな表情をしているのかよく見えない。
一体どういう関係で、『青薔薇連合会』なんかと一緒に…。
「名前は、セカイ・アンブローシア。帝都に住む一般女性。職業は主婦」
「『青薔薇連合会』との関係は?」
「元々は帝都の歓楽街で、長い間水商売をしていたみたいなんだけど…」
成程、夜の仕事をしている人だったんだね。
じゃあもしかして、『青薔薇連合会』との繫がりはそこで…。
「…どうもその人、亡くなった母親が相当借金を残していたらしくてね。その借金が、まるまる彼女に押し付けられたらしい」
「借金…?その借金って…。まさか…」
私は、一つの可能性に思い至った。
まさか。『青薔薇連合会』はそんな汚いことを。
しかし、セルニアのこの表情を見るに。
私の推測が当たっていることは、明白だった。
「うん。借金をした相手は、『青薔薇連合会』の下部組織の一つ。恐らく…この女性は『青薔薇連合会』への借金のカタに、こうして従わされてるんだと思う」
「…!」
やはり…やはり、そうなのか。
ルレイア・ティシェリー…なんという卑劣なことを。
借金を背負わされ、身動きの取れない一般女性を脅し、無理矢理言うことを聞かせ。
こうして自分の傍に侍らせて、奴隷のように扱っているなんて。
私は、写真に写っているセカイ・アンブローシアさんの顔を見た。
ぼやけていて、表情は分からない。
でもきっと…酷く悲しい顔をしているに違いない。
借金に縛り付けられ、望んでもいない相手に無理矢理従わされて…。
今すぐに写真の中に飛び込んで、彼女を救ってあげたい衝動にさえ駆られた。
それが出来たら、どんなに良かったか…。
「…気の毒に…。何とかして救ってあげられたら…」
「…確かにその人も気の毒だけど、その人の隣に写っている人も」
「え?」
…そういえば。
写真の中で、身元が分かったのは二人だって言ってたね。
セカイさんと、それからもう一人は…。
「セカイ・アンブローシアさんの隣に写っている人、その人の身元が分かった」
相変わらず堅い表情で、セルニアが言った。
『青薔薇連合会』への多額の借金のカタに、無理矢理従わされている一般女性。
それだけでも、あまりに気の毒だというのに。
隣に写っているこの男性は、それ以上だというのか?
「この人?この男の人?」
「そうだよ」
私が写真の中を指差すと、セルニアは頷いた。
…こちらも、ぼやけていて表情は読めないが。
どうやら、かなり若い男性だということは分かる。
こんな若い人が、どうして『青薔薇連合会』なんかと…。
…すると。
「…その人なんだよ、ブロテ」
「え…?」
その人、って…?
「『青薔薇連合会』に脅されて、人質にされているベルガモット王家の皇太子」
セルニアがそう言ったとき、私は頭を殴られたようなショックを受けた。
…そんな、まさか。
「ローゼリア様とアルティシア様の弟君らしい。名前はルーチェス殿下と言って…」
「この人が…!あ、いや…この御方が、ベルガモット王家の皇太子…!?」
「あぁ。一般に顔は知られていないから…でも、データベースには載っていた。僕も驚いたよ…」
…この御方が、『青薔薇連合会』に人質に取られた皇太子。
ルーチェス殿下。
「なんと…お労しい。こんなところに連れてこられて…」
あの男。ルレイア・ティシェリーは、どれほど卑劣なのだ。
人質に取ったルーチェス殿下を、小間使いのように自分に従わせ、好き勝手に連れ回すなんて。
命を脅かされているルーチェス殿下には、逆らうという選択肢が取れない。
こうして、ルレイア・ティシェリーに奴隷のように従うしかない。
本来なら、ベルガモット王家の王位を継ぐべき方が…このような憐れな姿に。
王家の威信と権威を何だと思っているのだ。あの卑劣な男は…!
牢獄に閉じ込めている訳じゃないのだから、まだマシだとでも言うつもりか?
…それなら、この写真に写っている人は…。
「…戸籍が見つからなかっただけで、他にもルレイアの周りに写っている人は皆、ルレイアに弱みを握られて、従わせられているんだろうね」
「…僕もそう思う」
このルルシーという人も、他にルレイアの周りに写っている人も。
何らかの理由でルレイアに弱みを握られ、無理矢理言うことを聞かされている。
それで自分は、王様のように侍従を従え、左団扇で満足していると。
本当に…何処まで卑劣なんだ、この男は。
無辜の人々を…そして、ベルガモット王家の皇太子殿下を、まるで自分の奴隷のように…。
「…許せない。私…この人を許せないよ」
「同感だ。絶対に許しちゃいけない…」
「詳しいことを、もっとよく調べよう。二の足を踏んではいられない」
悠長にしている暇はない。今すぐにでも動いて、少しでもたくさん情報を集める。
そして、こうしてルレイアのもとで苦しんでいる人を…少しでも早く、地獄から救ってあげなくては。
それだけでも、あまりに気の毒だというのに。
隣に写っているこの男性は、それ以上だというのか?
「この人?この男の人?」
「そうだよ」
私が写真の中を指差すと、セルニアは頷いた。
…こちらも、ぼやけていて表情は読めないが。
どうやら、かなり若い男性だということは分かる。
こんな若い人が、どうして『青薔薇連合会』なんかと…。
…すると。
「…その人なんだよ、ブロテ」
「え…?」
その人、って…?
「『青薔薇連合会』に脅されて、人質にされているベルガモット王家の皇太子」
セルニアがそう言ったとき、私は頭を殴られたようなショックを受けた。
…そんな、まさか。
「ローゼリア様とアルティシア様の弟君らしい。名前はルーチェス殿下と言って…」
「この人が…!あ、いや…この御方が、ベルガモット王家の皇太子…!?」
「あぁ。一般に顔は知られていないから…でも、データベースには載っていた。僕も驚いたよ…」
…この御方が、『青薔薇連合会』に人質に取られた皇太子。
ルーチェス殿下。
「なんと…お労しい。こんなところに連れてこられて…」
あの男。ルレイア・ティシェリーは、どれほど卑劣なのだ。
人質に取ったルーチェス殿下を、小間使いのように自分に従わせ、好き勝手に連れ回すなんて。
命を脅かされているルーチェス殿下には、逆らうという選択肢が取れない。
こうして、ルレイア・ティシェリーに奴隷のように従うしかない。
本来なら、ベルガモット王家の王位を継ぐべき方が…このような憐れな姿に。
王家の威信と権威を何だと思っているのだ。あの卑劣な男は…!
牢獄に閉じ込めている訳じゃないのだから、まだマシだとでも言うつもりか?
…それなら、この写真に写っている人は…。
「…戸籍が見つからなかっただけで、他にもルレイアの周りに写っている人は皆、ルレイアに弱みを握られて、従わせられているんだろうね」
「…僕もそう思う」
このルルシーという人も、他にルレイアの周りに写っている人も。
何らかの理由でルレイアに弱みを握られ、無理矢理言うことを聞かされている。
それで自分は、王様のように侍従を従え、左団扇で満足していると。
本当に…何処まで卑劣なんだ、この男は。
無辜の人々を…そして、ベルガモット王家の皇太子殿下を、まるで自分の奴隷のように…。
「…許せない。私…この人を許せないよ」
「同感だ。絶対に許しちゃいけない…」
「詳しいことを、もっとよく調べよう。二の足を踏んではいられない」
悠長にしている暇はない。今すぐにでも動いて、少しでもたくさん情報を集める。
そして、こうしてルレイアのもとで苦しんでいる人を…少しでも早く、地獄から救ってあげなくては。
―――――…どっかのアホが、とんでもない誤解と勘違いの沼に、ずぶずぶと足を踏み入れているその頃。
そんなことは、全く意に介さない俺達は。
「…どうです?ルリシヤ。進捗状況は?」
「あぁ。任せてくれ、もう少しだ」
「楽しみですね〜」
…『frontier』の夏フェスを終わった、その翌週。
今日も今日とて、当たり前のようにルレイアとルリシヤは、俺の執務室にやって来て、楽しくお喋り。
…してるだけなら、まぁ可愛いもんだ。いつものことだからな。
しかし、今日はいつもとは違った。
何故なら。
今日はこの二人、実験用ゴーグルをつけて、何やら怪しい実験をやっていた。
「…」
…なぁ。
…別に良いよ。お前らが何の実験をしようと。
危険がないなら、俺は口を出すつもりはない。
…でもな、これだけは言わせてもらうぞ。
俺の部屋でやるな。よそでやれ、と。
そんなことは、全く意に介さない俺達は。
「…どうです?ルリシヤ。進捗状況は?」
「あぁ。任せてくれ、もう少しだ」
「楽しみですね〜」
…『frontier』の夏フェスを終わった、その翌週。
今日も今日とて、当たり前のようにルレイアとルリシヤは、俺の執務室にやって来て、楽しくお喋り。
…してるだけなら、まぁ可愛いもんだ。いつものことだからな。
しかし、今日はいつもとは違った。
何故なら。
今日はこの二人、実験用ゴーグルをつけて、何やら怪しい実験をやっていた。
「…」
…なぁ。
…別に良いよ。お前らが何の実験をしようと。
危険がないなら、俺は口を出すつもりはない。
…でもな、これだけは言わせてもらうぞ。
俺の部屋でやるな。よそでやれ、と。
こいつら、俺の執務室を何だと思ってるんだ?
いつでも遊びに来て良い、公園みたいなものだと思ってるだろ。
公園感覚で訪ねてくるだけならともかく、そこで謎の実験を始めるんじゃない。
挙げ句、こいつら俺に無断で実験を始めたからな。
せめて家主の許可を取ってからにしろ。
これが本当に公園だとしても、勝手に実験をしたら怒られるぞ。
…しかも、顕微鏡を覗くとか、標本箱を眺めるとか、そんな可愛らしい実験ならまだしも。
「ルレイア先輩、そこの粉末ドラゴンズ・ブレスを取ってくれるか」
「はい、これですね」
「あぁ。これをビーカーに入れて、先程のハバネロペーストと…」
見てみろ。聞くにおぞましい実験をしてやがる。
ドラゴン?何だ?その無駄に格好良い材料は。
ちらりとルリシヤの手元を見ると、マグマのような赤い液体が入ったビーカーがあった。
なんか目がチリチリするんだが。気のせいか?
絶対近寄らない方が良い。本能で分かる。
何でそんな危険な実験を、俺の部屋でやるのか。
俺の部屋は実験室じゃないんだぞ。
すぐに出て行け!と叫びたいところだが…あまりにも奴らが危険な実験をしているせいで、声もかけづらい。
何で俺の部屋なのに、俺が遠慮しなければならないのか。
理不尽極まりない。
何を、何の為に作ってるんだか…。
まぁ、大体予想はつく。
あの実験材料を見るに、恐らくまた…ルリシヤの激辛カラーボールの改良版なんだろう。
あのシリーズ、もういい加減にした方が良いと思うんだが。ルリシヤはまだ満足していないらしいな。
…しかし、気になるのはルレイアだ。
ルリシヤが、あの悪趣味な自作カラーボールシリーズを開発するのはいつものことだが。
今回は何故か、そんなルリシヤの隣にルレイアがいる。
普段、ルレイアがルリシヤの実験に付き合うことはないはずだが…。
今日はまた、どういう風の吹き回しだ?
「ドラゴンズ・ブレスカラーボールの方はこれで良いとして…。他のブツは?」
他のブツ…?
ドラゴンズ・ブレスの時点で相当ヤバそうなんだが、他にもあるのか?
「色々考えてあるぞ。やはり母国の素材の方が馴染みがあるだろうと思って、調べてみたんだ」
「匠の気遣いですね!」
「ありがとう。ルレイア先輩に褒められると照れるな」
…何言ってんだ?お前らは。
匠の気遣い…?
「そういう訳で、こっちがシェルドニア王国で最も辛いと言われる、シェルドニアジゴクトウガラシだ」
シェルドニアジゴクトウガラシ…?
「こっちが、シェルドニア王国で最も酸っぱいと言われる、シェルドニアジゴクレモン。こっちがシェルドニア王国で最も甘い、シェルドニアジゴクザラメだ」
…そんな種類が…?
シェルドニア王国の名産物って…俺もそんなに詳しくないけどさ。
本当、突飛な食べ物が多いよな。
ルティス帝国の食文化に慣れていたら、カルチャーショックが半端じゃない。
…で、ルリシヤとルレイアは、そのシェルドニア王国の謎の特産物で、何をたくらん、
「これでカラーボールを作って、ルシードにぶん投げてやりましょうね!」
「ちょっと待て。何考えてんだお前」
これ以上、黙って静観しておけなかった。
ルレイアの相棒兼、お目付け役として。
今のは聞き捨てならなかったぞ、おい。
いつでも遊びに来て良い、公園みたいなものだと思ってるだろ。
公園感覚で訪ねてくるだけならともかく、そこで謎の実験を始めるんじゃない。
挙げ句、こいつら俺に無断で実験を始めたからな。
せめて家主の許可を取ってからにしろ。
これが本当に公園だとしても、勝手に実験をしたら怒られるぞ。
…しかも、顕微鏡を覗くとか、標本箱を眺めるとか、そんな可愛らしい実験ならまだしも。
「ルレイア先輩、そこの粉末ドラゴンズ・ブレスを取ってくれるか」
「はい、これですね」
「あぁ。これをビーカーに入れて、先程のハバネロペーストと…」
見てみろ。聞くにおぞましい実験をしてやがる。
ドラゴン?何だ?その無駄に格好良い材料は。
ちらりとルリシヤの手元を見ると、マグマのような赤い液体が入ったビーカーがあった。
なんか目がチリチリするんだが。気のせいか?
絶対近寄らない方が良い。本能で分かる。
何でそんな危険な実験を、俺の部屋でやるのか。
俺の部屋は実験室じゃないんだぞ。
すぐに出て行け!と叫びたいところだが…あまりにも奴らが危険な実験をしているせいで、声もかけづらい。
何で俺の部屋なのに、俺が遠慮しなければならないのか。
理不尽極まりない。
何を、何の為に作ってるんだか…。
まぁ、大体予想はつく。
あの実験材料を見るに、恐らくまた…ルリシヤの激辛カラーボールの改良版なんだろう。
あのシリーズ、もういい加減にした方が良いと思うんだが。ルリシヤはまだ満足していないらしいな。
…しかし、気になるのはルレイアだ。
ルリシヤが、あの悪趣味な自作カラーボールシリーズを開発するのはいつものことだが。
今回は何故か、そんなルリシヤの隣にルレイアがいる。
普段、ルレイアがルリシヤの実験に付き合うことはないはずだが…。
今日はまた、どういう風の吹き回しだ?
「ドラゴンズ・ブレスカラーボールの方はこれで良いとして…。他のブツは?」
他のブツ…?
ドラゴンズ・ブレスの時点で相当ヤバそうなんだが、他にもあるのか?
「色々考えてあるぞ。やはり母国の素材の方が馴染みがあるだろうと思って、調べてみたんだ」
「匠の気遣いですね!」
「ありがとう。ルレイア先輩に褒められると照れるな」
…何言ってんだ?お前らは。
匠の気遣い…?
「そういう訳で、こっちがシェルドニア王国で最も辛いと言われる、シェルドニアジゴクトウガラシだ」
シェルドニアジゴクトウガラシ…?
「こっちが、シェルドニア王国で最も酸っぱいと言われる、シェルドニアジゴクレモン。こっちがシェルドニア王国で最も甘い、シェルドニアジゴクザラメだ」
…そんな種類が…?
シェルドニア王国の名産物って…俺もそんなに詳しくないけどさ。
本当、突飛な食べ物が多いよな。
ルティス帝国の食文化に慣れていたら、カルチャーショックが半端じゃない。
…で、ルリシヤとルレイアは、そのシェルドニア王国の謎の特産物で、何をたくらん、
「これでカラーボールを作って、ルシードにぶん投げてやりましょうね!」
「ちょっと待て。何考えてんだお前」
これ以上、黙って静観しておけなかった。
ルレイアの相棒兼、お目付け役として。
今のは聞き捨てならなかったぞ、おい。
「…?どうしたんですか、ルルシー」
どうしたんですかじゃない。
お前がどうしたんだよ。
ちょっと色々聞き捨てならないから、1から説明してもらおうか。
「何やろうとしてんだ?お前らは。ちょっと目を離したら…」
絶対ろくなことじゃないに決まってる。
椅子から立ち上がって、ルレイアに近づこうとしたら。
「あ、ルルシーゴーグル無しで近づいたら、」
「うっ…」
「あー…。言わんこっちゃない」
ドラゴンズ・ブレスの凄まじい威力に、ゴーグルをつけていなかった俺は、後ろにひっくり返りそうになった。
目が燃える。
「大丈夫ですか?ルルシー」
「迂闊に近寄ると、痛い目を見るぞ。ルルシー先輩。これはかの名高きドラゴンズ・ブレスだからな」
そんな危険物を、俺の部屋に持ち込むんじゃねぇ。
ルレイアが、俺に真っ黒のレース付きハンカチを差し出してくれたので。
有り難くそれを借りて、両目を押さえた。
はぁ…危ないところだった…。
…。
…って、一息ついてる場合じゃない。
「お前ら、何を企んでるんだ?」
「はい?」
とぼけたって無駄だぞ。
さっき聞いたからな、俺。
お前今、聞き捨てならないことを言ってただろう。
「お前ら、さっきから俺の部屋で何をやってるんだ」
「嫌がらせカラーボールを作ってます」
潔いな。やっぱり嫌がらせ目的なのか。
まぁ、それ以外に用途なんてないわな…。
「何か駄目でした?」
「…駄目ではない」
勘違いしないで欲しいが、俺は別に、カラーボールを作ってることに文句を言っている訳ではない。
別に良い。嫌がらせカラーボールを作る行為自体は。
馬鹿馬鹿しいように見えて、意外と有事には役に立つと知ってるからな。
これまで何度も、ルリシヤのお手製カラーボールに助けられてきた。
だから、カラーボールを作る行為そのものは別に良い。
問題は、その開発を俺の部屋でやるなってことと…。
「…誰にぶつけるって?」
「はい?」
「それを誰に投げつけるって?」
「ルシードです」
大問題。
聞き捨てならない大問題だ。
覚えているだろうか、ルシード・キルシュテンという人物を。
彼はシェルドニア王国の女王、縦ロールおばさんこと、アシミム・ヘールシュミットの腹心である。
ルレイアに言わせれば、アシミムの腰巾着…らしいが。
あれでかなりの実力者であり、アシミムにとっては頼りになるボディーガードだろう。
シェルドニア王国で一悶着あった相手だが、何故その人物に、激辛カラーボールをぶん投げるという事態になるんだ。
「何でそんなことをするんだ?」
「え?だってムカつくじゃないですか」
「…」
…そんな適当な理由で。
ルシードはドラゴンズ・ブレスやら、シェルドニアジゴク何たらいう素材で作った、嫌がらせカラーボールを投げられるのか。
たまったもんじゃないな。気の毒に。
どうしたんですかじゃない。
お前がどうしたんだよ。
ちょっと色々聞き捨てならないから、1から説明してもらおうか。
「何やろうとしてんだ?お前らは。ちょっと目を離したら…」
絶対ろくなことじゃないに決まってる。
椅子から立ち上がって、ルレイアに近づこうとしたら。
「あ、ルルシーゴーグル無しで近づいたら、」
「うっ…」
「あー…。言わんこっちゃない」
ドラゴンズ・ブレスの凄まじい威力に、ゴーグルをつけていなかった俺は、後ろにひっくり返りそうになった。
目が燃える。
「大丈夫ですか?ルルシー」
「迂闊に近寄ると、痛い目を見るぞ。ルルシー先輩。これはかの名高きドラゴンズ・ブレスだからな」
そんな危険物を、俺の部屋に持ち込むんじゃねぇ。
ルレイアが、俺に真っ黒のレース付きハンカチを差し出してくれたので。
有り難くそれを借りて、両目を押さえた。
はぁ…危ないところだった…。
…。
…って、一息ついてる場合じゃない。
「お前ら、何を企んでるんだ?」
「はい?」
とぼけたって無駄だぞ。
さっき聞いたからな、俺。
お前今、聞き捨てならないことを言ってただろう。
「お前ら、さっきから俺の部屋で何をやってるんだ」
「嫌がらせカラーボールを作ってます」
潔いな。やっぱり嫌がらせ目的なのか。
まぁ、それ以外に用途なんてないわな…。
「何か駄目でした?」
「…駄目ではない」
勘違いしないで欲しいが、俺は別に、カラーボールを作ってることに文句を言っている訳ではない。
別に良い。嫌がらせカラーボールを作る行為自体は。
馬鹿馬鹿しいように見えて、意外と有事には役に立つと知ってるからな。
これまで何度も、ルリシヤのお手製カラーボールに助けられてきた。
だから、カラーボールを作る行為そのものは別に良い。
問題は、その開発を俺の部屋でやるなってことと…。
「…誰にぶつけるって?」
「はい?」
「それを誰に投げつけるって?」
「ルシードです」
大問題。
聞き捨てならない大問題だ。
覚えているだろうか、ルシード・キルシュテンという人物を。
彼はシェルドニア王国の女王、縦ロールおばさんこと、アシミム・ヘールシュミットの腹心である。
ルレイアに言わせれば、アシミムの腰巾着…らしいが。
あれでかなりの実力者であり、アシミムにとっては頼りになるボディーガードだろう。
シェルドニア王国で一悶着あった相手だが、何故その人物に、激辛カラーボールをぶん投げるという事態になるんだ。
「何でそんなことをするんだ?」
「え?だってムカつくじゃないですか」
「…」
…そんな適当な理由で。
ルシードはドラゴンズ・ブレスやら、シェルドニアジゴク何たらいう素材で作った、嫌がらせカラーボールを投げられるのか。
たまったもんじゃないな。気の毒に。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…