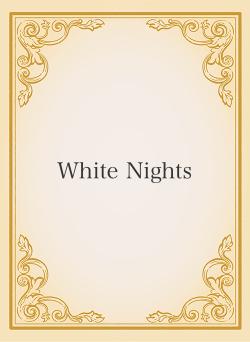「やっと」
やっとだ。
棗はそう、何度も何度も呟いて。
「やっと、こうして目を見られる」
「うぇ、」
「もう逃げないよな」
「、なちゅ、め」
「ん。よかったよかった。」
「ふぁなして」
「はいはい。仕方ないなあ」
───棗は優しかった。想像していたよりずっと。
ずっと優しくて。
だから、大いに戸惑った。
柄にもなく怯えていたから。今まで。
熱の籠もった両手が、ゆっくりと私を解放する。
「…許してくれるの」
「…うん」
「私、あんなに酷いことしたのに」
「うん。」
「怒ってないの、?」
「…案外、気にしてくれてたんだ。お前も」
呟く棗はどこか寂しそうで。
───俺等もな、と優しく付け足す。
「怖かったよ。ずっと」
お前に逢うまで。顔を見るまで。
「ずっと。お前に拒絶されることに怯えてた」
「…、」
あの日の棗を思い出す。
私を抱きしめた腕の温もり。
私に向けられた真っすぐな喜び。
その奥で揺れていた、たしかな迷いの色。
ちゃんと見ていた。私も。
怯えていたのは、彼等も同じだった。
…何か、バカみたい。