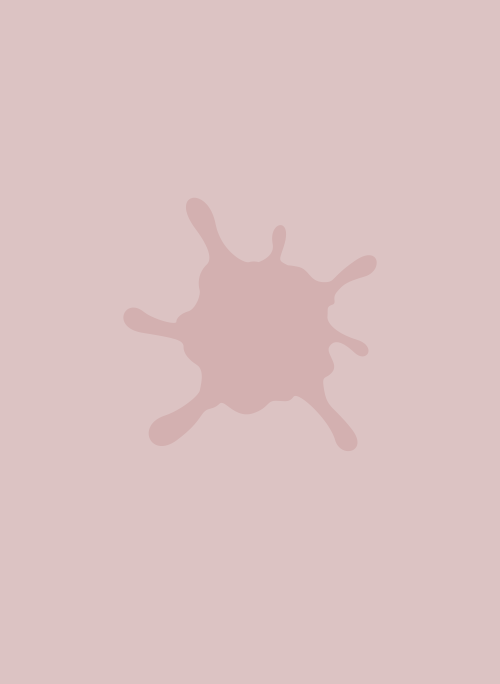…そもそも。
私だけ差し入れもらって、私だけ温かいもの食べるという、この状況。
これもなかなかに気まずいよ。
真菜達に悪気がないのは分かってるけど…。でもやっぱり気まずい。
ど、どうしよう?
え…えーと…あ、そうだ。
「結月君、折角お昼なんだし、ちょっと抜けてきたらどう?」
と、私は提案した。
我ながら良い提案。
「お昼ご飯買っておいでよ。ここは私が見てるから」
そうだよ。それが良い。
そうすれば、結月君も少しは文化祭を楽しめるし、お昼ご飯も買ってこられ、
「いえ、僕は結構です」
…何で?
会心の提案のつもりだったのに、呆気なく却下された。
「ど、どうして?だって、お昼ご飯…」
「お弁当持ってきてるので」
君はこんな日でも、お弁当作りをやめないんだね。
偉過ぎる。
文化祭の日くらい、お弁当以外のもの食べたい、とは思わないのかな…?
そりゃまぁ、結月君は料理が上手だから。
そこらの素人が屋台で作る食べ物よりも、自分で作った方が美味しいのかもしれない。
それでも、だよ。
周りにこんな、屋台がたくさん出てるのに。
その中でやっぱり自作のお弁当を食べようと思う、その精神は何なんだ。
…プライド?
何にせよ、私には理解不能。
「じ、じゃあ…ちょっと分けてあげるね。一緒に食べよ」
私は、さっき真菜達が持ってきてくれた差し入れの袋を掲げて、結月君にそう言った。
とにかく、一人で温かいものを、結月君の前で食べるのはあまりに気まずかった。
しかし。
「大丈夫ですよ。それは星ちゃんさんがもらったものですから、どうぞ遠慮なく食べてください」
にこりと、笑顔で。
結月君は丁寧に辞退した。
…それが出来たら良いんだけどね。
そんな気まずいことが平気で出来るほど、私は図太くないんだよ…。
…でも。
ここまできっぱりと拒否されたら、他にどう勧めたら良いのか分からなかった。
私だけ差し入れもらって、私だけ温かいもの食べるという、この状況。
これもなかなかに気まずいよ。
真菜達に悪気がないのは分かってるけど…。でもやっぱり気まずい。
ど、どうしよう?
え…えーと…あ、そうだ。
「結月君、折角お昼なんだし、ちょっと抜けてきたらどう?」
と、私は提案した。
我ながら良い提案。
「お昼ご飯買っておいでよ。ここは私が見てるから」
そうだよ。それが良い。
そうすれば、結月君も少しは文化祭を楽しめるし、お昼ご飯も買ってこられ、
「いえ、僕は結構です」
…何で?
会心の提案のつもりだったのに、呆気なく却下された。
「ど、どうして?だって、お昼ご飯…」
「お弁当持ってきてるので」
君はこんな日でも、お弁当作りをやめないんだね。
偉過ぎる。
文化祭の日くらい、お弁当以外のもの食べたい、とは思わないのかな…?
そりゃまぁ、結月君は料理が上手だから。
そこらの素人が屋台で作る食べ物よりも、自分で作った方が美味しいのかもしれない。
それでも、だよ。
周りにこんな、屋台がたくさん出てるのに。
その中でやっぱり自作のお弁当を食べようと思う、その精神は何なんだ。
…プライド?
何にせよ、私には理解不能。
「じ、じゃあ…ちょっと分けてあげるね。一緒に食べよ」
私は、さっき真菜達が持ってきてくれた差し入れの袋を掲げて、結月君にそう言った。
とにかく、一人で温かいものを、結月君の前で食べるのはあまりに気まずかった。
しかし。
「大丈夫ですよ。それは星ちゃんさんがもらったものですから、どうぞ遠慮なく食べてください」
にこりと、笑顔で。
結月君は丁寧に辞退した。
…それが出来たら良いんだけどね。
そんな気まずいことが平気で出来るほど、私は図太くないんだよ…。
…でも。
ここまできっぱりと拒否されたら、他にどう勧めたら良いのか分からなかった。
結果。
私は一人で、差し入れのお好み焼きや、フランクフルトや、フライドポテトを食べ。
その向かい側で、結月君はいつも通り。
自分で作ってきたというお弁当を、もぐもぐ食べていた。
言っておくけど、私だって凄く気まずかったんだからね。
でも、他にどうしたら良かったのよ。
折角の差し入れのはずが、ほとんど味を感じない。
更に、訪問者は真菜と海咲だけではなく。
「よっ、星野、いる?」
「あ、隆盛…」
ステージ設営担当の隆盛が、空き教室に顔を出した。
どうして、ここに隆盛が。
と、思ったら。
隆盛は、片手にプラスチックのカップにストローを刺したドリンクを持っていた。
ま、まさか。
「ささやかな差し入れ。まぁ、これ飲んで英気を養えよ」
やっぱりまた差し入れだった。
嬉しいし、有り難いのだけど。
「あ、ありがとう…」
チラッと、結月君の方を見る。
結月君は我関せずといった風に、黙々とお弁当を食べていた。
私ばっかり差し入れをもらって、物凄く気まずい。
「お前の好きなラズベリーのドリンクだよ」
「あー、うん。ありがと」
鮮やかな赤色が綺麗で、見た目にも映えるドリンクだ。
とても嬉しい。
嬉しい、そして気まずい。
でも、私がこれほど気まずい思いをしているのに、誰もそれに気づかない。
「どう?こっちは。忙しい?」
隆盛は、何事もなかったように聞いた。
「結構忙しいよ。でも…結月君が凄い頑張ってくれるから、めちゃくちゃ助けられてる」
お世辞ではなく、これは事実だ。
私一人だったら、今頃半分も進んでない。
「ふーん、そっか。俺はフリーだからさ、何か買ってきて欲しいものあったらEINLくれよ。遠慮なくパシリにしてくれ」
「う、うん。ありがと」
これほど頼もしい言葉はない。のに。
今ばかりは、不必要な有り難さだった。
「じゃ、頑張ってな」
「うん。隆盛もね…」
「って言われても、俺はもうほとんどやることないんだけどな」
隆盛は苦笑いでそう言って、空き教室を出ていった。
…差し入れに、ドリンクが一つ増え。
更に、私の気まずさも一段階レベルアップ。
何度も言うように、真菜や隆盛達に悪気がないのは分かってる。
でも、やっぱり気まずかった。
私は一人で、差し入れのお好み焼きや、フランクフルトや、フライドポテトを食べ。
その向かい側で、結月君はいつも通り。
自分で作ってきたというお弁当を、もぐもぐ食べていた。
言っておくけど、私だって凄く気まずかったんだからね。
でも、他にどうしたら良かったのよ。
折角の差し入れのはずが、ほとんど味を感じない。
更に、訪問者は真菜と海咲だけではなく。
「よっ、星野、いる?」
「あ、隆盛…」
ステージ設営担当の隆盛が、空き教室に顔を出した。
どうして、ここに隆盛が。
と、思ったら。
隆盛は、片手にプラスチックのカップにストローを刺したドリンクを持っていた。
ま、まさか。
「ささやかな差し入れ。まぁ、これ飲んで英気を養えよ」
やっぱりまた差し入れだった。
嬉しいし、有り難いのだけど。
「あ、ありがとう…」
チラッと、結月君の方を見る。
結月君は我関せずといった風に、黙々とお弁当を食べていた。
私ばっかり差し入れをもらって、物凄く気まずい。
「お前の好きなラズベリーのドリンクだよ」
「あー、うん。ありがと」
鮮やかな赤色が綺麗で、見た目にも映えるドリンクだ。
とても嬉しい。
嬉しい、そして気まずい。
でも、私がこれほど気まずい思いをしているのに、誰もそれに気づかない。
「どう?こっちは。忙しい?」
隆盛は、何事もなかったように聞いた。
「結構忙しいよ。でも…結月君が凄い頑張ってくれるから、めちゃくちゃ助けられてる」
お世辞ではなく、これは事実だ。
私一人だったら、今頃半分も進んでない。
「ふーん、そっか。俺はフリーだからさ、何か買ってきて欲しいものあったらEINLくれよ。遠慮なくパシリにしてくれ」
「う、うん。ありがと」
これほど頼もしい言葉はない。のに。
今ばかりは、不必要な有り難さだった。
「じゃ、頑張ってな」
「うん。隆盛もね…」
「って言われても、俺はもうほとんどやることないんだけどな」
隆盛は苦笑いでそう言って、空き教室を出ていった。
…差し入れに、ドリンクが一つ増え。
更に、私の気まずさも一段階レベルアップ。
何度も言うように、真菜や隆盛達に悪気がないのは分かってる。
でも、やっぱり気まずかった。
おまけに。
差し入れを食べながら、会話に困って、無駄に長く沈黙が続いて。
ヤバい、もうこの沈黙に耐えられない…と、思っていると。
「…お友達、たくさんいて良いですね」
という、結月君の不意の一撃が飛んできた。
うぐっ。
そ、それって嫌味?
「そんなに差し入れ持ってきてもらえて…」
「う…うん…。…その、ごめん…」
「あ、いえ。嫌味のつもりじゃないんですよ」
いや、嫌味にしか聞こえなかったんだよ。
「改めて、星ちゃんさんがクラスの人気者なんだな、って実感しました」
「に、人気者なんて…」
「本当に残念でしたね。踊る方のグループになってたら、今日は楽しかったでしょうに」
…。
…台詞だけ聞けば、嫌味以外の何物でもないのだけど。
結月君の顔が本当に残念そうで、本当に惜しく思ってるのが分かって。
嫌味ではなく、本心なんだと分かる。
…君は純粋過ぎるよ。
「…結月君も、外行って…調査抜けておいでよ」
私は、再度そう言った。
同じアンケート係なのに、私だけ文化祭を楽しんでるなんて…そんなのフェアじゃない。
しかし。
「いえ、結構です」
「屋台とか、嫌いなの?」
ここまで拒むということは、そもそも屋台巡りに興味がないのかと思ったのだ。
そんなジャンクフードは食わん!っていう主義とか?
結月君自身が、とっても料理上手だもんね。
ジャンクフードなんて食べられない、と思うのも無理もな、
「あぁいえ、そうじゃなく。僕、お金持ってきてないので」
え。
「…忘れたの?なら、そう言ってくれれば良いのに。貸してあげるよ」
財布を忘れるなんて、結月君も結構抜けてるところがあっ、
「学校に財布は持ってこないんです。お金を持ってきて、トラブルになったら嫌ですから」
なんてことだ。
結月君は、財布を持ってくるのを忘れた訳じゃない。
元々、普段から財布を持ってくる主義じゃなかったのだ。
そんな人、いる?
お金も持たずに、よく普通に生活出来るね。
でも、学食で食べるときとか、自販機で飲み物欲しいときとかどうするんだろう…?
「不便じゃないの…?購買で何か買うときとか…」
「…?いえ、別に…。不意な買い物が必要なときなんて滅多にありませんし…。必要なときには、必要なだけ持ってきてますけど」
今日は必要なときじゃないの?文化祭だよ?
「でも、自販機で飲み物欲しいときとか」
「水筒にお茶入れて持ってきてるんで、学校で飲み物を買う必要はないんです」
エコだな君は。
何処にでも水筒持っていくんだ?
真夏でも飲み物を持たずに外出して、出先でいちいちドリンクを買っている私が、とてつもなく怠惰な浪費家に思えてきた。
それが普通だと思ってた。
真菜や海咲達だってそうだし。
二人が水筒を持って遊びに来てるのなんて、見たことがない。
私達が大雑把過ぎるのか、結月君がマメなのか…。
…多分後者だ。
差し入れを食べながら、会話に困って、無駄に長く沈黙が続いて。
ヤバい、もうこの沈黙に耐えられない…と、思っていると。
「…お友達、たくさんいて良いですね」
という、結月君の不意の一撃が飛んできた。
うぐっ。
そ、それって嫌味?
「そんなに差し入れ持ってきてもらえて…」
「う…うん…。…その、ごめん…」
「あ、いえ。嫌味のつもりじゃないんですよ」
いや、嫌味にしか聞こえなかったんだよ。
「改めて、星ちゃんさんがクラスの人気者なんだな、って実感しました」
「に、人気者なんて…」
「本当に残念でしたね。踊る方のグループになってたら、今日は楽しかったでしょうに」
…。
…台詞だけ聞けば、嫌味以外の何物でもないのだけど。
結月君の顔が本当に残念そうで、本当に惜しく思ってるのが分かって。
嫌味ではなく、本心なんだと分かる。
…君は純粋過ぎるよ。
「…結月君も、外行って…調査抜けておいでよ」
私は、再度そう言った。
同じアンケート係なのに、私だけ文化祭を楽しんでるなんて…そんなのフェアじゃない。
しかし。
「いえ、結構です」
「屋台とか、嫌いなの?」
ここまで拒むということは、そもそも屋台巡りに興味がないのかと思ったのだ。
そんなジャンクフードは食わん!っていう主義とか?
結月君自身が、とっても料理上手だもんね。
ジャンクフードなんて食べられない、と思うのも無理もな、
「あぁいえ、そうじゃなく。僕、お金持ってきてないので」
え。
「…忘れたの?なら、そう言ってくれれば良いのに。貸してあげるよ」
財布を忘れるなんて、結月君も結構抜けてるところがあっ、
「学校に財布は持ってこないんです。お金を持ってきて、トラブルになったら嫌ですから」
なんてことだ。
結月君は、財布を持ってくるのを忘れた訳じゃない。
元々、普段から財布を持ってくる主義じゃなかったのだ。
そんな人、いる?
お金も持たずに、よく普通に生活出来るね。
でも、学食で食べるときとか、自販機で飲み物欲しいときとかどうするんだろう…?
「不便じゃないの…?購買で何か買うときとか…」
「…?いえ、別に…。不意な買い物が必要なときなんて滅多にありませんし…。必要なときには、必要なだけ持ってきてますけど」
今日は必要なときじゃないの?文化祭だよ?
「でも、自販機で飲み物欲しいときとか」
「水筒にお茶入れて持ってきてるんで、学校で飲み物を買う必要はないんです」
エコだな君は。
何処にでも水筒持っていくんだ?
真夏でも飲み物を持たずに外出して、出先でいちいちドリンクを買っている私が、とてつもなく怠惰な浪費家に思えてきた。
それが普通だと思ってた。
真菜や海咲達だってそうだし。
二人が水筒を持って遊びに来てるのなんて、見たことがない。
私達が大雑把過ぎるのか、結月君がマメなのか…。
…多分後者だ。
結局、結月君はテコでも動かないとばかりに、空き教室を出ていくことはなかったので。
気まずいまま、昼食が終わった。
折角のお好み焼きとラズベリージュースだったのに、全然味を感じなかったよ。
そして、午後からも午前と同じ作業の繰り返し。
本番前になったら、お客さんにアンケート用紙を配り。
本番が終わったら、そのアンケート用紙を回収ボックスに集める。
集め終わったら、それを持って空き教室に移動(今度は間違えなかったよ)。
あとはひたすら、アンケート結果を集計するだけ。
物静かな結月君と、時折一言二言、言葉を交わしながら。
ゆっくりのんびりと時間が過ぎていく。
言うまい言うまいと思っていたけど。
不意に、口をついて出ていた。
「…嫌じゃない?毎年…こんな裏方仕事するの」
と、聞いてから。
私はしまった、不味いことを聞いたと思った。
そんなの愚問というものだろう。
「あ、いや、ごめ…」
謝ろうと思ったけど、結月君は気を悪くした様子はなく。
2、3秒ほど、ピタリと静止して。
そして、何事もなかったように作業を続けた。
「別に何とも思いませんよ。僕はむしろ、踊ったり歌ったり、客を呼び込んだり…そういう人前に立つ仕事の方が苦手ですから」
あ、うん…。
それは…そうなのかもしれないけど。
「星ちゃんさんが思ってるほど、僕はアンケート係を苦痛だとは思ってませんから」
「…」
…そうなの?本当に?
私が過剰に反応し過ぎ…?
「表舞台に立って、華やかな仕事をするのも楽しいのかもしれませんけど。僕は生来、縁の下の力持ちタイプなので」
縁の下の力持ち…か。
結月君は、本当にそれだよね。
知らなかった。
私は、ほぼ毎年…結月君が言うところの、「表舞台で華やかな仕事」をするタイプで。
文化祭と言えばこれだ!とばかりに、楽しんできて。
今年初めて裏方仕事を任されて、つまんないつまんないと思ってたけど。
いたんだよね、毎年。
こうして、私がつまらないと思ってる裏方仕事を黙々とこなしてくれている人が。
そういう人がいるから、私はこれまで、楽しく華やかな役ばかりやってこれたのだ。
…そういう人達がいることを、私は知りもしなかった。
知ろうともしなかった。
自分の無知が恥ずかしい。
「…結月君は、偉いね」
「まさか。僕は、自分の役割を果たしてるだけですよ」
それが偉いんだよ。
「今年は私も…縁の下の力持ち、になれたのかな?」
結月君に比べたら、私の力なんて、足を引っ張ってるくらいが関の山だろうに。
「えぇ、ちゃんとなれてますよ」
結月君は、笑顔でそう言ってくれるから。
君は本当に…優しい人だよ。
気まずいまま、昼食が終わった。
折角のお好み焼きとラズベリージュースだったのに、全然味を感じなかったよ。
そして、午後からも午前と同じ作業の繰り返し。
本番前になったら、お客さんにアンケート用紙を配り。
本番が終わったら、そのアンケート用紙を回収ボックスに集める。
集め終わったら、それを持って空き教室に移動(今度は間違えなかったよ)。
あとはひたすら、アンケート結果を集計するだけ。
物静かな結月君と、時折一言二言、言葉を交わしながら。
ゆっくりのんびりと時間が過ぎていく。
言うまい言うまいと思っていたけど。
不意に、口をついて出ていた。
「…嫌じゃない?毎年…こんな裏方仕事するの」
と、聞いてから。
私はしまった、不味いことを聞いたと思った。
そんなの愚問というものだろう。
「あ、いや、ごめ…」
謝ろうと思ったけど、結月君は気を悪くした様子はなく。
2、3秒ほど、ピタリと静止して。
そして、何事もなかったように作業を続けた。
「別に何とも思いませんよ。僕はむしろ、踊ったり歌ったり、客を呼び込んだり…そういう人前に立つ仕事の方が苦手ですから」
あ、うん…。
それは…そうなのかもしれないけど。
「星ちゃんさんが思ってるほど、僕はアンケート係を苦痛だとは思ってませんから」
「…」
…そうなの?本当に?
私が過剰に反応し過ぎ…?
「表舞台に立って、華やかな仕事をするのも楽しいのかもしれませんけど。僕は生来、縁の下の力持ちタイプなので」
縁の下の力持ち…か。
結月君は、本当にそれだよね。
知らなかった。
私は、ほぼ毎年…結月君が言うところの、「表舞台で華やかな仕事」をするタイプで。
文化祭と言えばこれだ!とばかりに、楽しんできて。
今年初めて裏方仕事を任されて、つまんないつまんないと思ってたけど。
いたんだよね、毎年。
こうして、私がつまらないと思ってる裏方仕事を黙々とこなしてくれている人が。
そういう人がいるから、私はこれまで、楽しく華やかな役ばかりやってこれたのだ。
…そういう人達がいることを、私は知りもしなかった。
知ろうともしなかった。
自分の無知が恥ずかしい。
「…結月君は、偉いね」
「まさか。僕は、自分の役割を果たしてるだけですよ」
それが偉いんだよ。
「今年は私も…縁の下の力持ち、になれたのかな?」
結月君に比べたら、私の力なんて、足を引っ張ってるくらいが関の山だろうに。
「えぇ、ちゃんとなれてますよ」
結月君は、笑顔でそう言ってくれるから。
君は本当に…優しい人だよ。
そんな結月君に比べて、私と来たら。
「星ちゃーん、迎えに来たよ〜」
まだ集計作業の真っ最中なのに。
本番を終えた真菜と海咲が、私を連れ出す為に迎えに来た。
あぁ…今大変なところなのに。
計4回のステージ発表が終わり、いよいよ最終的な集計を出そうとしていたところ。
ここからが一番大変だ、ってときに。
普段なら、こんなタイミングに誰かが迎えに来てくれたら。
「やった、助け舟!」とか思ってたんだろうけど。
私にとって助け舟でも、結月君にとっては泥舟じゃん。
ただでさえ人手が足りてないのに、こんな重要なタイミングで私が抜けちゃって。
そりゃ私なんて、結月君に比べたら、大した戦力にはなってないのかもしれないけど。
私だけ逃げ出すみたいで、凄く感じ悪いよね。
「あ、真菜…。もうちょっと待って。今忙しいところで…」
と、私は言いかけたけれど。
「えぇ?だって、今すぐ行かなきゃ軽音部のライブ終わっちゃうよ?」
「そうそう。もうラストスパートなんだからさ。急がないと」
事情を知らない真菜と海咲は、何の悪意もなくそう言って私を急かす。
去年までの私だったら、何も考えず、二人についていったんだろうな。
でも今年は、私も結月君みたいに。
ちゃんと自分の役目をきちんと果たして…。
…しかし。
「大丈夫ですよ、ここは」
結月君は相変わらずそう言う。
「行ってきてください」
「でも…ここからが大変なのに」
「大丈夫です。のんびりやってますから。星ちゃんさんも、のんびりしてきてください」
…のんびりやるなんて、嘘ばっかり。
結月君のことだから、少しもペースをゆるめることなく、テキパキやっちゃうんでしょ。
やっぱり手伝う、と言いたかったが。
「ほらほら、三珠クンもこう言ってるんだしさぁ」
海咲が、そう言って私を立たせた。
更に、真菜も。
「アンケートの集計なんて、後でも出来るじゃない。軽音部のライブは今だけだよ?見逃したら後悔するって」
…それは、そうだけど。
でも、私には軽音部のライブよりも、優先すべきことが…。
「行ってらっしゃい。楽しんできてくださいね」
何の屈託もなく、結月君は微笑んだ。
…今の結月君の心情は如何ほどか。
私には推し量ることも出来ない。
「…うん、じゃあ…ここ、お願いね、結月君」
こんなに気を遣ってもらって、それ以外何が言えただろう。
「星ちゃーん、迎えに来たよ〜」
まだ集計作業の真っ最中なのに。
本番を終えた真菜と海咲が、私を連れ出す為に迎えに来た。
あぁ…今大変なところなのに。
計4回のステージ発表が終わり、いよいよ最終的な集計を出そうとしていたところ。
ここからが一番大変だ、ってときに。
普段なら、こんなタイミングに誰かが迎えに来てくれたら。
「やった、助け舟!」とか思ってたんだろうけど。
私にとって助け舟でも、結月君にとっては泥舟じゃん。
ただでさえ人手が足りてないのに、こんな重要なタイミングで私が抜けちゃって。
そりゃ私なんて、結月君に比べたら、大した戦力にはなってないのかもしれないけど。
私だけ逃げ出すみたいで、凄く感じ悪いよね。
「あ、真菜…。もうちょっと待って。今忙しいところで…」
と、私は言いかけたけれど。
「えぇ?だって、今すぐ行かなきゃ軽音部のライブ終わっちゃうよ?」
「そうそう。もうラストスパートなんだからさ。急がないと」
事情を知らない真菜と海咲は、何の悪意もなくそう言って私を急かす。
去年までの私だったら、何も考えず、二人についていったんだろうな。
でも今年は、私も結月君みたいに。
ちゃんと自分の役目をきちんと果たして…。
…しかし。
「大丈夫ですよ、ここは」
結月君は相変わらずそう言う。
「行ってきてください」
「でも…ここからが大変なのに」
「大丈夫です。のんびりやってますから。星ちゃんさんも、のんびりしてきてください」
…のんびりやるなんて、嘘ばっかり。
結月君のことだから、少しもペースをゆるめることなく、テキパキやっちゃうんでしょ。
やっぱり手伝う、と言いたかったが。
「ほらほら、三珠クンもこう言ってるんだしさぁ」
海咲が、そう言って私を立たせた。
更に、真菜も。
「アンケートの集計なんて、後でも出来るじゃない。軽音部のライブは今だけだよ?見逃したら後悔するって」
…それは、そうだけど。
でも、私には軽音部のライブよりも、優先すべきことが…。
「行ってらっしゃい。楽しんできてくださいね」
何の屈託もなく、結月君は微笑んだ。
…今の結月君の心情は如何ほどか。
私には推し量ることも出来ない。
「…うん、じゃあ…ここ、お願いね、結月君」
こんなに気を遣ってもらって、それ以外何が言えただろう。
その後私は、真菜と海咲に連れられて、宣言通り軽音部のライブを観に行った。
それだけじゃなくて、真菜達に勧められるままに。
お化け屋敷とか脱出ゲームとか、やたら時間のかかるアトラクションに参加し。
かと思えば、行列の出来てるフレンチトーストの屋台に並んで、たっぷり時間をかけてフレンチトーストを買いに行ったり。
何だか、わざとゆっくりしてるんじゃないかとさえ思った。
正直、私は内心焦っていた。
早く戻らないと。
今頃結月君、一人で作業してるんだから。
「じゃあ、次は…あ、そうだ。Aクラスの喫茶店にでも入らない?」
と、真菜が提案した。
喫茶店なんて。
入ったら、絶対ぺちゃくちゃお喋りに夢中で、無駄に時間を潰すじゃない。
「私、そろそろ戻るわ」
私はすかさずそう言った。
このままズルズル流されて、喫茶店にまで入っちゃったら。
本当に、戻る頃には作業が終わっちゃってる。
それなのに。
「え?何で?」
と、真菜と海咲は首を傾げた。
何でって…。
二人はもう、今日やるべきことは終わったから、好きなだけ遊んでて良いかもしれないけど…。
私は…私と結月君の仕事は、まだ終わってないんだよ。
むしろ、今が一番大変なときなの。
「結月君手伝わなきゃ。だから戻る」
「えぇ、良いじゃん別に」
何が良いのよ。
「そうそう、三珠クンがやってくれるって言ってるんだからさぁ、任せておきなよ」
「…そんな訳にはいかないわよ」
ただでさえアンケート用紙を作る段階から、ほぼ結月君に任せっぱなしなのに。
集計作業くらいは、ちゃんと付き合わなきゃ。
それだって、こうして私だけサボってるんだし。
さすがにこれ以上は無理。
「私、戻るわ」
「ふーん…」
「真面目だねー、星ちゃん…」
二人は意外そうな顔で私を見ていた。
私が真面目とは。面白い冗談だ。
私が真面目なら、その真面目な仕事を、当たり前のようにこなしている結月君はどうなるのよ。
結月君が真面目なんじゃない。
これまでの私が、ずっと怠惰だったのよ。
…空き教室に戻る途中。
「…あっ」
私は一つ気がついて、悪いと思いながら、ほんの少し寄り道をした。
それだけじゃなくて、真菜達に勧められるままに。
お化け屋敷とか脱出ゲームとか、やたら時間のかかるアトラクションに参加し。
かと思えば、行列の出来てるフレンチトーストの屋台に並んで、たっぷり時間をかけてフレンチトーストを買いに行ったり。
何だか、わざとゆっくりしてるんじゃないかとさえ思った。
正直、私は内心焦っていた。
早く戻らないと。
今頃結月君、一人で作業してるんだから。
「じゃあ、次は…あ、そうだ。Aクラスの喫茶店にでも入らない?」
と、真菜が提案した。
喫茶店なんて。
入ったら、絶対ぺちゃくちゃお喋りに夢中で、無駄に時間を潰すじゃない。
「私、そろそろ戻るわ」
私はすかさずそう言った。
このままズルズル流されて、喫茶店にまで入っちゃったら。
本当に、戻る頃には作業が終わっちゃってる。
それなのに。
「え?何で?」
と、真菜と海咲は首を傾げた。
何でって…。
二人はもう、今日やるべきことは終わったから、好きなだけ遊んでて良いかもしれないけど…。
私は…私と結月君の仕事は、まだ終わってないんだよ。
むしろ、今が一番大変なときなの。
「結月君手伝わなきゃ。だから戻る」
「えぇ、良いじゃん別に」
何が良いのよ。
「そうそう、三珠クンがやってくれるって言ってるんだからさぁ、任せておきなよ」
「…そんな訳にはいかないわよ」
ただでさえアンケート用紙を作る段階から、ほぼ結月君に任せっぱなしなのに。
集計作業くらいは、ちゃんと付き合わなきゃ。
それだって、こうして私だけサボってるんだし。
さすがにこれ以上は無理。
「私、戻るわ」
「ふーん…」
「真面目だねー、星ちゃん…」
二人は意外そうな顔で私を見ていた。
私が真面目とは。面白い冗談だ。
私が真面目なら、その真面目な仕事を、当たり前のようにこなしている結月君はどうなるのよ。
結月君が真面目なんじゃない。
これまでの私が、ずっと怠惰だったのよ。
…空き教室に戻る途中。
「…あっ」
私は一つ気がついて、悪いと思いながら、ほんの少し寄り道をした。
「結月君!お待たせ」
私は、駆け足で空き教室まで戻った。
すると。
「あ、お帰りなさい…」
テーブルの上を見て、私はあっ、と思った。
アンケート用紙が並んでいたテーブルは、すっかり片付けられ。
大きな表の紙一枚だけが残っていた。
ま、まさか。
「も、もう終わっちゃった…?」
「はい。今しがた終わったので…後片付けをしていたところです」
…あぁ…終わっちゃってた…。
私がグズグズしてる間に…。
私は、ガックリと肩を落とした。
何やってるのよ。
結局、結月君一人に任せたようなものじゃない。
手伝うどころか、結局私だけ逃げることになって。
申し訳無さでいっぱいだ。
「ごめん…。出来るだけ早く戻るつもりだったんだけど…」
「あ、そんなこと気にしてたんですか?」
気にするよ。当たり前じゃない。
「大丈夫ですよ。なんか勢いでささっと済ませちゃいました」
そうね。
私がいなくても、結月君はささっと終わらせちゃえるんだろうけど。
少しでもそれを手伝えなかった私は、いてもいなくても変わらない無能ってこと。
はぁ…。
「気にしないでください。外…楽しかったです?ライブ観に行ったんですよね」
「うん…」
「良かったですね。見逃さずに済んで。やっぱり年に一回のことですから、見逃したら損ですよ」
その、年に一回のことを。
君は毎年、こんな風に過ごしてるんでしょ?
それを知ったからには、結月君を放り出して文化祭を楽しめる訳がない。
あぁ、やっぱり、無理にでも早く帰ってくるべきだった…。
今更後悔しても、後の祭り。
せめて少しでもフォローに回るしかない。
「…結月君、これ」
「はい?」
「カステラ買ってきたの。鈴カステラ。一緒に食べよ」
こんなものを買う為に、さっき少しだけ寄り道してたんだ。
今思えば、そんな寄り道をせず、急いで戻ってきていれば。
せめて後片付けだけでも手伝えたかもしれないのに。
でも、今更そんなこと言ったって仕方ない。
それに、こうせずにはいられなかった。
今日一日、いや…準備期間も含めて。
私なんかより、ずっと真面目に働いてくれた結月君に。
少しでも労いが必要だと思ったから。
「ほら、頭使ってるでしょ?糖分は必要だよ」
「え、いや、でも…。僕お金持ってないですから」
何それ。
私がお金請求すると思ったの?それはちょっと失礼でしょ。
「奢りに決まってるじゃない。さ、食べよ」
「でも、それは星ちゃんさんが買ってきたものなんですから、僕は遠慮、」
「しなくて良いの。私、今回ずっと結月君に助けられっぱなしだったんだから。せめてこんな形でも…何かお礼させて」
鈴カステラくらいじゃ、とてもお礼にならないけどね。
でも、何もないよりマシ。
「そんな、お礼なんて必要ないですよ。僕は自分の役目を果たしただけですから。僕に気を遣わ、むぐっ」
「はいはい、お疲れ様でしたー」
私は、あれこれ言って固辞しようとする結月君の口に鈴カステラを押し込んだ。
こうなったら、強行突破だ。
嫌だって言っても食べてもらうからね。
私は、駆け足で空き教室まで戻った。
すると。
「あ、お帰りなさい…」
テーブルの上を見て、私はあっ、と思った。
アンケート用紙が並んでいたテーブルは、すっかり片付けられ。
大きな表の紙一枚だけが残っていた。
ま、まさか。
「も、もう終わっちゃった…?」
「はい。今しがた終わったので…後片付けをしていたところです」
…あぁ…終わっちゃってた…。
私がグズグズしてる間に…。
私は、ガックリと肩を落とした。
何やってるのよ。
結局、結月君一人に任せたようなものじゃない。
手伝うどころか、結局私だけ逃げることになって。
申し訳無さでいっぱいだ。
「ごめん…。出来るだけ早く戻るつもりだったんだけど…」
「あ、そんなこと気にしてたんですか?」
気にするよ。当たり前じゃない。
「大丈夫ですよ。なんか勢いでささっと済ませちゃいました」
そうね。
私がいなくても、結月君はささっと終わらせちゃえるんだろうけど。
少しでもそれを手伝えなかった私は、いてもいなくても変わらない無能ってこと。
はぁ…。
「気にしないでください。外…楽しかったです?ライブ観に行ったんですよね」
「うん…」
「良かったですね。見逃さずに済んで。やっぱり年に一回のことですから、見逃したら損ですよ」
その、年に一回のことを。
君は毎年、こんな風に過ごしてるんでしょ?
それを知ったからには、結月君を放り出して文化祭を楽しめる訳がない。
あぁ、やっぱり、無理にでも早く帰ってくるべきだった…。
今更後悔しても、後の祭り。
せめて少しでもフォローに回るしかない。
「…結月君、これ」
「はい?」
「カステラ買ってきたの。鈴カステラ。一緒に食べよ」
こんなものを買う為に、さっき少しだけ寄り道してたんだ。
今思えば、そんな寄り道をせず、急いで戻ってきていれば。
せめて後片付けだけでも手伝えたかもしれないのに。
でも、今更そんなこと言ったって仕方ない。
それに、こうせずにはいられなかった。
今日一日、いや…準備期間も含めて。
私なんかより、ずっと真面目に働いてくれた結月君に。
少しでも労いが必要だと思ったから。
「ほら、頭使ってるでしょ?糖分は必要だよ」
「え、いや、でも…。僕お金持ってないですから」
何それ。
私がお金請求すると思ったの?それはちょっと失礼でしょ。
「奢りに決まってるじゃない。さ、食べよ」
「でも、それは星ちゃんさんが買ってきたものなんですから、僕は遠慮、」
「しなくて良いの。私、今回ずっと結月君に助けられっぱなしだったんだから。せめてこんな形でも…何かお礼させて」
鈴カステラくらいじゃ、とてもお礼にならないけどね。
でも、何もないよりマシ。
「そんな、お礼なんて必要ないですよ。僕は自分の役目を果たしただけですから。僕に気を遣わ、むぐっ」
「はいはい、お疲れ様でしたー」
私は、あれこれ言って固辞しようとする結月君の口に鈴カステラを押し込んだ。
こうなったら、強行突破だ。
嫌だって言っても食べてもらうからね。
「もぐ…もぐ」
「どう?美味しい?」
「ごくん…。…はい、久し振りに食べました。鈴カステラ…」
それは良かった。
「じゃあどんどん食べて。もう閉店間際だからって、たくさん入れてもらったのよ」
私はテーブルの上に、鈴カステラの袋を広げた。
幸い、もうやるべきことは終わってるんだし。
結月君が終わらせてくれたからね。
こうして鈴カステラ食べてたって、誰にも文句は言われない。
「いや、ですけど…」
まだ断ろうとしてる。
意固地。
「これ全部私に食べさせて、私を太らせるつもり?」
「え」
「そうは行かないからね。ちゃんと結月君も手伝って、はい」
私は、なおも強行突破とばかりに。
結月君の口に鈴カステラを押し込んだ。
自分から食べないなら、こうして無理矢理食べてもらうから。
「むぐ、た、食べる…自分で食べますから」
「食べる?自分で食べるの?」
「食べます…だから、無理矢理押し込まないでください」
「うん、宜しい」
じゃ、自分で食べてね。
少なくとも半分は結月君のノルマだから。
ノルマ達成出来なかったら、また口に押し込む。
結月君が押しに弱いタイプで良かった。
今だけはそう思う。
「…あの、えぇと…ありがとうございます、星ちゃんさん…」
「何それ。お礼を言うべきはこっちでしょ?」
ほぼ全部、結月君に仕事任せちゃってるんだから。
鈴カステラ一袋くらいじゃ、全然お礼にはならないわ。
「…」
一つ二つと、鈴カステラを摘んで。
「…今日は、星ちゃんさんと一緒の係で良かったです」
と、結月君は呟いた。
うん?
「どうしたの?いきなり…」
「いえ…。ふとそう思っただけです」
何それ。
「そんなに、鈴カステラ美味しかった?」
「いや、鈴カステラは抜きにして…」
「…?」
「…何でもないです」
どうしたのよ。
何でもないことないでしょ。
そっか。私と一緒で良かった…か。
私なんて、ちっとも戦力になってないはずなんだけどなぁ。
でも、そう思ってくれて良かった。
ちょっとだけ罪悪感が薄れた。
「私も、結月君と一緒で良かったと思ってるよ」
今だけは本心からそう思えた。
あんなに嫌だったはずなのにね。不思議だ。
「どう?美味しい?」
「ごくん…。…はい、久し振りに食べました。鈴カステラ…」
それは良かった。
「じゃあどんどん食べて。もう閉店間際だからって、たくさん入れてもらったのよ」
私はテーブルの上に、鈴カステラの袋を広げた。
幸い、もうやるべきことは終わってるんだし。
結月君が終わらせてくれたからね。
こうして鈴カステラ食べてたって、誰にも文句は言われない。
「いや、ですけど…」
まだ断ろうとしてる。
意固地。
「これ全部私に食べさせて、私を太らせるつもり?」
「え」
「そうは行かないからね。ちゃんと結月君も手伝って、はい」
私は、なおも強行突破とばかりに。
結月君の口に鈴カステラを押し込んだ。
自分から食べないなら、こうして無理矢理食べてもらうから。
「むぐ、た、食べる…自分で食べますから」
「食べる?自分で食べるの?」
「食べます…だから、無理矢理押し込まないでください」
「うん、宜しい」
じゃ、自分で食べてね。
少なくとも半分は結月君のノルマだから。
ノルマ達成出来なかったら、また口に押し込む。
結月君が押しに弱いタイプで良かった。
今だけはそう思う。
「…あの、えぇと…ありがとうございます、星ちゃんさん…」
「何それ。お礼を言うべきはこっちでしょ?」
ほぼ全部、結月君に仕事任せちゃってるんだから。
鈴カステラ一袋くらいじゃ、全然お礼にはならないわ。
「…」
一つ二つと、鈴カステラを摘んで。
「…今日は、星ちゃんさんと一緒の係で良かったです」
と、結月君は呟いた。
うん?
「どうしたの?いきなり…」
「いえ…。ふとそう思っただけです」
何それ。
「そんなに、鈴カステラ美味しかった?」
「いや、鈴カステラは抜きにして…」
「…?」
「…何でもないです」
どうしたのよ。
何でもないことないでしょ。
そっか。私と一緒で良かった…か。
私なんて、ちっとも戦力になってないはずなんだけどなぁ。
でも、そう思ってくれて良かった。
ちょっとだけ罪悪感が薄れた。
「私も、結月君と一緒で良かったと思ってるよ」
今だけは本心からそう思えた。
あんなに嫌だったはずなのにね。不思議だ。
こうして。
様々な意味で実りの多かった、高校一年生の文化祭が終わった。
…ちなみに、残った鈴カステラは結月君に押し付けた。
めちゃくちゃ固辞していたけど、鞄に無理矢理突っ込んだら、さすがの結月君も降参だった。
そう、それで宜しい。
様々な意味で実りの多かった、高校一年生の文化祭が終わった。
…ちなみに、残った鈴カステラは結月君に押し付けた。
めちゃくちゃ固辞していたけど、鞄に無理矢理突っ込んだら、さすがの結月君も降参だった。
そう、それで宜しい。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…