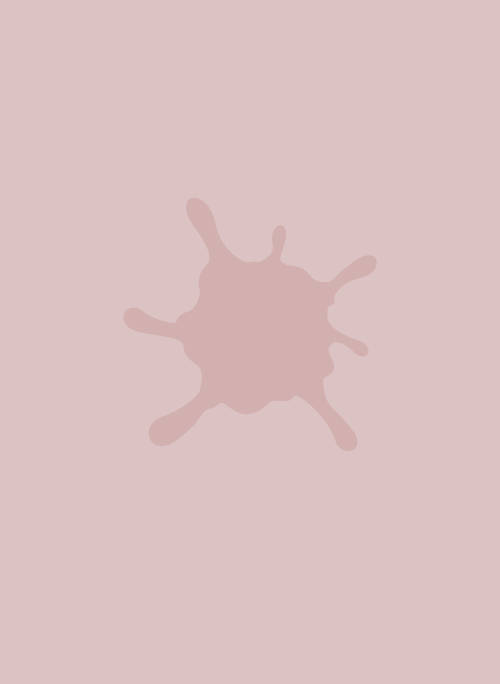湯野っちと、皆と話さなきゃ。分かってもらわなくちゃ。
そう思いながら、学校に来て。
でもやっぱり、湯野っち達を目の前にすると気が引けてしまった。
いくら私が一人で何を言っても、多勢に無勢のように思えてしまって。
しばらく悶々として、そして意を決した私は。
自分の席から立ち上がり、湯野っち達のところに行こう…とした。
すると。
「お、来た来た」
湯野っちは、教室の扉を見ながらそう言った。
え?来たって、誰が?
思わず振り向くと。
「エレベーターが使えるようになって、随分便利になりましたね」
「本当にね…。瑠璃華さんと琥珀さんに、頭が上がらないよ」
などという会話をしながら。
丁度、緋村君と久露花さんが、一緒に登校してきたところだった。
あ。あの二人…。
湯野っちはおもむろに、そんな緋村君達に近寄った。
…?
「ねぇ、緋村。ちょっと話したいことがあるんだけど」
湯野っちはにやにやとしながら、緋村君にそう言った。
「は、話したいこと?」
「果たし合いですか?」
久露花さん、何言ってるの?
しかしそれより、その後湯野っちの言った言葉に、私は驚愕した。
「実はさ、私、前から緋村のこと好きだったんだ。私と付き合ってくれない?」
「…は?」
と、緋村君は首を傾げていたけど。
私も「は?」だった。
湯野っち、あんた…何言って。
「…」
「…」
「…?」
緋村君はポカンとして、湯野っちはにやにやしていて、そして久露花さんは首を傾げていた。
聞き耳を立てていた他のクラスメイトは、皆興味津々といった風に盗み見ていた。
これって、もしかして。
昨日言ってた、あの罰ゲーム…。
そう気づいて、私はカッと頭に血が上った。
が。
「湯野さんは、奏さんに好意を抱いてらっしゃるんですか?それは良かったです。友情の芽生えですね」
久露花さんが、あまりにズレた解釈をしてしまった為。
思わず、その場にずっこけそうになった。
多分、周りで聞いていたクラスメイトもそうだったと思う。
そう思いながら、学校に来て。
でもやっぱり、湯野っち達を目の前にすると気が引けてしまった。
いくら私が一人で何を言っても、多勢に無勢のように思えてしまって。
しばらく悶々として、そして意を決した私は。
自分の席から立ち上がり、湯野っち達のところに行こう…とした。
すると。
「お、来た来た」
湯野っちは、教室の扉を見ながらそう言った。
え?来たって、誰が?
思わず振り向くと。
「エレベーターが使えるようになって、随分便利になりましたね」
「本当にね…。瑠璃華さんと琥珀さんに、頭が上がらないよ」
などという会話をしながら。
丁度、緋村君と久露花さんが、一緒に登校してきたところだった。
あ。あの二人…。
湯野っちはおもむろに、そんな緋村君達に近寄った。
…?
「ねぇ、緋村。ちょっと話したいことがあるんだけど」
湯野っちはにやにやとしながら、緋村君にそう言った。
「は、話したいこと?」
「果たし合いですか?」
久露花さん、何言ってるの?
しかしそれより、その後湯野っちの言った言葉に、私は驚愕した。
「実はさ、私、前から緋村のこと好きだったんだ。私と付き合ってくれない?」
「…は?」
と、緋村君は首を傾げていたけど。
私も「は?」だった。
湯野っち、あんた…何言って。
「…」
「…」
「…?」
緋村君はポカンとして、湯野っちはにやにやしていて、そして久露花さんは首を傾げていた。
聞き耳を立てていた他のクラスメイトは、皆興味津々といった風に盗み見ていた。
これって、もしかして。
昨日言ってた、あの罰ゲーム…。
そう気づいて、私はカッと頭に血が上った。
が。
「湯野さんは、奏さんに好意を抱いてらっしゃるんですか?それは良かったです。友情の芽生えですね」
久露花さんが、あまりにズレた解釈をしてしまった為。
思わず、その場にずっこけそうになった。
多分、周りで聞いていたクラスメイトもそうだったと思う。
「いや、あの、瑠璃華さん。多分そういうことじゃ…」
「付き合うって、何処に付き合うのですか?深海魚水族館でしたら、是非私もご一緒したいですね」
「いや…。それは多分、瑠璃華さんだけなんじゃないかな…?」
何?深海魚水族館って。
い、いや。そんなことより。
「…何かの冗談?罰ゲームか何か?」
緋村君は、湯野っちに向かってそう尋ねた。
すると湯野っちは、にやにやしながら頷いた。
「そ。分かってるじゃん」
「あぁ、やっぱり…」
「何?ちょっと期待しちゃった?」
「いや、別に…」
戸惑った顔の緋村君。それを見て、にやにやと笑う湯野っちと、その取り巻き。
私はもう我慢が出来なかった。
「ちょっと、湯野っち…!どういうこと?」
起きてしまったものは、どうしようも出来なかったが。
それでも、割って入らずにはいられなかった。
「あ、星ちゃんおはよ」
おはよ、じゃないでしょ。
「どういうこと?何で罰ゲーム…」
「あぁ。実は昨日星ちゃんが帰った後、別のカラオケルーム行って、採点バトルやり直したんだよね」
湯野っちは全く悪びれずに、それどころか笑顔でそう言った。
何ですって?
「そしたら、言い出しっぺの私が負けちゃってさぁ。正々堂々、潔く罰ゲームを受けることにしたの」
「…!」
「ね?幽霊君はちゃんと身の程を弁えてるんだから、大丈夫だって言ったじゃん。こんなの大したことじゃないのに、星ちゃんったら大袈裟なんだから」
私は湯野っちに詰め寄ったまま、言葉を失った。
…話せば分かってくれるとか、それどころじゃなかった。
「さっきの緋村の顔!超ウケるよね」
「本当。罰ゲームお疲れ〜」
「私危なかったわ。あと一点低かったら、私が罰ゲームだったんだもん」
湯野っちも、その取り巻きも、楽しそうに笑うばかり。
その、一方で。
湯野っち達が「楽しい罰ゲーム」に笑っている一方で。
「…??どういうことですか?深海魚水族館で友好を深めるのでは?」
「深めないよ…」
事情が掴めていないらしく、相変わらず首を傾げている久露花さんと。
疲れたような、何かを悟ったような、困ったような…色々な感情を感じさせる顔の緋村君がいた。
…どうしてこれを見て、笑っていられるの。
…そして。
「…っ!」
思わず悲鳴が出そうになった。
振り向くと、そこには結月君がいて。
彼は無言で、全てを見ていた。
「付き合うって、何処に付き合うのですか?深海魚水族館でしたら、是非私もご一緒したいですね」
「いや…。それは多分、瑠璃華さんだけなんじゃないかな…?」
何?深海魚水族館って。
い、いや。そんなことより。
「…何かの冗談?罰ゲームか何か?」
緋村君は、湯野っちに向かってそう尋ねた。
すると湯野っちは、にやにやしながら頷いた。
「そ。分かってるじゃん」
「あぁ、やっぱり…」
「何?ちょっと期待しちゃった?」
「いや、別に…」
戸惑った顔の緋村君。それを見て、にやにやと笑う湯野っちと、その取り巻き。
私はもう我慢が出来なかった。
「ちょっと、湯野っち…!どういうこと?」
起きてしまったものは、どうしようも出来なかったが。
それでも、割って入らずにはいられなかった。
「あ、星ちゃんおはよ」
おはよ、じゃないでしょ。
「どういうこと?何で罰ゲーム…」
「あぁ。実は昨日星ちゃんが帰った後、別のカラオケルーム行って、採点バトルやり直したんだよね」
湯野っちは全く悪びれずに、それどころか笑顔でそう言った。
何ですって?
「そしたら、言い出しっぺの私が負けちゃってさぁ。正々堂々、潔く罰ゲームを受けることにしたの」
「…!」
「ね?幽霊君はちゃんと身の程を弁えてるんだから、大丈夫だって言ったじゃん。こんなの大したことじゃないのに、星ちゃんったら大袈裟なんだから」
私は湯野っちに詰め寄ったまま、言葉を失った。
…話せば分かってくれるとか、それどころじゃなかった。
「さっきの緋村の顔!超ウケるよね」
「本当。罰ゲームお疲れ〜」
「私危なかったわ。あと一点低かったら、私が罰ゲームだったんだもん」
湯野っちも、その取り巻きも、楽しそうに笑うばかり。
その、一方で。
湯野っち達が「楽しい罰ゲーム」に笑っている一方で。
「…??どういうことですか?深海魚水族館で友好を深めるのでは?」
「深めないよ…」
事情が掴めていないらしく、相変わらず首を傾げている久露花さんと。
疲れたような、何かを悟ったような、困ったような…色々な感情を感じさせる顔の緋村君がいた。
…どうしてこれを見て、笑っていられるの。
…そして。
「…っ!」
思わず悲鳴が出そうになった。
振り向くと、そこには結月君がいて。
彼は無言で、全てを見ていた。
「ゆ…結月君…」
目の前で起きたことについて、何と言ったら良いのか分からなくて。
私は視線を彷徨わせながら、彼に言うべき言葉を探した。
「ご、ごめ…」
「…随分と、趣味の良い友達をお持ちですね」
思わず謝ってしまいそうになった私に、結月君は冷たくそう言った。
心臓が跳ね上がった。
「嫌だったら、そう言ってくださいね」
「…え…?」
嫌だったらって、何が…。
結月君は、険しい顔で私を見つめていた。
その視線が痛くて、私は顔が上げられなかった。
「別に別れても良いんですよ。…どうやら僕は、あなたに相応しい人物ではないようなので」
「…!」
…どうして。
それは誤解なのよ。この罰ゲームは、私が提案した訳じゃなくて。
私は止めようとしたけど、でも湯野っち達が勝手に。
そう思ったけど…。…しかし。
結月君にとっては、そういうことをする友達を持つを私も、同類のように見えるのだ。
当たり前だ。
私だって、かつては加害者の側に立っていたんだから。
「…」
結月君は、もうそれ以上は何も言わなかった。
彼が何か言う前に。私が、何かを言う前に。
タイミングを図ったかのように、始業を告げるチャイムが鳴ったからだ。
…結局その日、私は一言も結月君と口を利かなかった。
彼と言葉を交わすのが、怖かったからだ。
目の前で起きたことについて、何と言ったら良いのか分からなくて。
私は視線を彷徨わせながら、彼に言うべき言葉を探した。
「ご、ごめ…」
「…随分と、趣味の良い友達をお持ちですね」
思わず謝ってしまいそうになった私に、結月君は冷たくそう言った。
心臓が跳ね上がった。
「嫌だったら、そう言ってくださいね」
「…え…?」
嫌だったらって、何が…。
結月君は、険しい顔で私を見つめていた。
その視線が痛くて、私は顔が上げられなかった。
「別に別れても良いんですよ。…どうやら僕は、あなたに相応しい人物ではないようなので」
「…!」
…どうして。
それは誤解なのよ。この罰ゲームは、私が提案した訳じゃなくて。
私は止めようとしたけど、でも湯野っち達が勝手に。
そう思ったけど…。…しかし。
結月君にとっては、そういうことをする友達を持つを私も、同類のように見えるのだ。
当たり前だ。
私だって、かつては加害者の側に立っていたんだから。
「…」
結月君は、もうそれ以上は何も言わなかった。
彼が何か言う前に。私が、何かを言う前に。
タイミングを図ったかのように、始業を告げるチャイムが鳴ったからだ。
…結局その日、私は一言も結月君と口を利かなかった。
彼と言葉を交わすのが、怖かったからだ。
…つくづく、とんでもないことをしてくれた。
言うまでもないが、湯野っち達のことだ。
同じクラスになれて、あんなに喜んでたのに。
今となっては、別々のクラスになれば良かったと思っているくらいだ。
それでも湯野っち達は、全く気にすることなく。
今頃は、自分が今日罰ゲームを行ったことさえ忘れてるんだろうな。
でも緋村君はきっと、いや…絶対、忘れてないはずだ。
気を悪くしただろう。嫌な気持ちになっただろう。
傷ついただろうな。
久露花さんも、今朝は罰ゲームの意味が分かってなかったみたいだけど。
彼女も今頃は、罰ゲームの意味に気づいて、そして憤慨しているはずだ。
それなのに、二人を傷つけた張本人の湯野っちは、もう今日のことなんて忘れて、今頃楽しそうに笑ってるんだよ。
信じられないけど、これが事実なのだ。
私だって少し前までは、それが普通だったのだ。
あんな光景を見せられて、結月君はどう思っただろう。
あんなことをする人達と、私が友達だって知って、どんな気持ちだったろう。
自宅に帰ってから、私は半泣きでスマホを握り締めていた。
結月君に電話しようか、メールしようかと、そもそも連絡するべきなのかと、さっきからずっと葛藤している。
結月君の方から連絡してくれれば良いけど、彼の性格からして、それは多分ない。
…朝、結月君に言われた言葉が、ずっと頭の中をぐるぐるしてる。
別れても良いって、何よ。
相応しくないって、何よ。どういう意味よ。
何でそんなこと言うの。
お前も湯野っち達と同類なんだろう、って?
少し前までは、確かに同類だったかもしれないけど。
今は違うんだよ。今は…あんな酷い罰ゲームをして、平気な顔をしていられる人間じゃない。
私は反対したんだよ。やめようって言った。
でも、やめてくれなかったんだよ。
私のいないところで、湯野っち達が勝手に決めちゃったんだよ…。
私の前で相談していたなら、絶対に止めてた。絶対にあんなことはさせなかったのに…。
「何で相応しくないなんて言うのよ…。馬鹿…」
私は滲み出る涙を拭った。
こんなつまんない、馬鹿なことで。
私達の関係は、それで終わりだって言うの?
言うまでもないが、湯野っち達のことだ。
同じクラスになれて、あんなに喜んでたのに。
今となっては、別々のクラスになれば良かったと思っているくらいだ。
それでも湯野っち達は、全く気にすることなく。
今頃は、自分が今日罰ゲームを行ったことさえ忘れてるんだろうな。
でも緋村君はきっと、いや…絶対、忘れてないはずだ。
気を悪くしただろう。嫌な気持ちになっただろう。
傷ついただろうな。
久露花さんも、今朝は罰ゲームの意味が分かってなかったみたいだけど。
彼女も今頃は、罰ゲームの意味に気づいて、そして憤慨しているはずだ。
それなのに、二人を傷つけた張本人の湯野っちは、もう今日のことなんて忘れて、今頃楽しそうに笑ってるんだよ。
信じられないけど、これが事実なのだ。
私だって少し前までは、それが普通だったのだ。
あんな光景を見せられて、結月君はどう思っただろう。
あんなことをする人達と、私が友達だって知って、どんな気持ちだったろう。
自宅に帰ってから、私は半泣きでスマホを握り締めていた。
結月君に電話しようか、メールしようかと、そもそも連絡するべきなのかと、さっきからずっと葛藤している。
結月君の方から連絡してくれれば良いけど、彼の性格からして、それは多分ない。
…朝、結月君に言われた言葉が、ずっと頭の中をぐるぐるしてる。
別れても良いって、何よ。
相応しくないって、何よ。どういう意味よ。
何でそんなこと言うの。
お前も湯野っち達と同類なんだろう、って?
少し前までは、確かに同類だったかもしれないけど。
今は違うんだよ。今は…あんな酷い罰ゲームをして、平気な顔をしていられる人間じゃない。
私は反対したんだよ。やめようって言った。
でも、やめてくれなかったんだよ。
私のいないところで、湯野っち達が勝手に決めちゃったんだよ…。
私の前で相談していたなら、絶対に止めてた。絶対にあんなことはさせなかったのに…。
「何で相応しくないなんて言うのよ…。馬鹿…」
私は滲み出る涙を拭った。
こんなつまんない、馬鹿なことで。
私達の関係は、それで終わりだって言うの?
結局その日、私は結月君に連絡を取ることは出来なかった。
それどころじゃない。
翌日になっても、翌々日になっても、私は結月君に話しかけることも出来なかった。
結月君は終始、何だかずっと怒ってるみたいな険しい顔をしていて。
私の話なんて聞きたくもない、と言わんばかりの態度だった。
そして、私自身、結月君と話し合わなければと思う反面。
結月君と話をするのが怖かった。
「あれから色々考えたけど、やっぱり別れましょう」と言われるかもしれないと思うと、怖くて。
言いかねないじゃない。結月君のあの様子じゃ。
別れ話を切り出されるのが怖くて、私は結月君に話しかけられなかった。
結月君もまた、私に話しかけてこなかった。
その間も湯野っち達は、すっかり何事もなかったように平常運転。
正直、「なんてことをしてくれたんだ」と詰め寄りたい気分だった。
でも、そんなこと湯野っち達には関係ない。
あんな人達を親友だと思っていた自分を、つくづく馬鹿だと思った。
あの人達のせいで、結月君を失うことになるかと思うと、あまりに情けなくて。
誰を責めたら良いのやら、これからどうしたら良いのやら分からない。
ただ、このままではいけないことは確かだった。
それどころじゃない。
翌日になっても、翌々日になっても、私は結月君に話しかけることも出来なかった。
結月君は終始、何だかずっと怒ってるみたいな険しい顔をしていて。
私の話なんて聞きたくもない、と言わんばかりの態度だった。
そして、私自身、結月君と話し合わなければと思う反面。
結月君と話をするのが怖かった。
「あれから色々考えたけど、やっぱり別れましょう」と言われるかもしれないと思うと、怖くて。
言いかねないじゃない。結月君のあの様子じゃ。
別れ話を切り出されるのが怖くて、私は結月君に話しかけられなかった。
結月君もまた、私に話しかけてこなかった。
その間も湯野っち達は、すっかり何事もなかったように平常運転。
正直、「なんてことをしてくれたんだ」と詰め寄りたい気分だった。
でも、そんなこと湯野っち達には関係ない。
あんな人達を親友だと思っていた自分を、つくづく馬鹿だと思った。
あの人達のせいで、結月君を失うことになるかと思うと、あまりに情けなくて。
誰を責めたら良いのやら、これからどうしたら良いのやら分からない。
ただ、このままではいけないことは確かだった。
――――――…一方、その頃。
「…ちょっとお願いがあるんですけど、良いですか」
「…どうした?」
「僕を屋根からぶん投げてください」
「…さすがに死ぬんじゃないか…?」
そうですか。
でも今は、死ぬかもしれないと分かっていても、屋根から飛び降りたい気分だった。
それくらい、自分のことを激しく嫌悪していた。
控えめに言って、僕は最低である。
「…ちょっとお願いがあるんですけど、良いですか」
「…どうした?」
「僕を屋根からぶん投げてください」
「…さすがに死ぬんじゃないか…?」
そうですか。
でも今は、死ぬかもしれないと分かっていても、屋根から飛び降りたい気分だった。
それくらい、自分のことを激しく嫌悪していた。
控えめに言って、僕は最低である。
「一体どうしたんだ…。今日は…?」
「性格が悪いにも程がある…。お願いです、加賀宮さん。僕のこの、ねじ曲がった性根を叩き直してください」
「…誰かに言われたのか?性格が悪いと…」
誰にも言われてない。自分でそう思ってるだけ。
でも、多分唯華さんは思ってるんじゃないか。
「何コイツ。性格悪っ」って。
きっとそう。そうに違いない。
ここ数日、僕のことを避けているのもそのせいなのだろう。
性格のひねくれた僕に、ほとほと愛想を尽かした可能性が大。
そうされても仕方がないと思うほどには、自分の性格が悪い自覚がある。
「だって、ひねくれてるでしょ?僕」
「…自分で自分をひねくれていると言えるほど自覚があるなら、大したことないんじゃないか?」
本当にひねくれてる奴は、自分がひねくれてる自覚もないだろうって?
そうかもしれないけど。でもそうじゃない。
そうじゃないんですよ。
「それから、お前は…ひねくれてるんじゃなくて、ただ素直になれないだけだと思うが…」
それをひねくれてるって言うんでしょうよ。
「忘れたい…。言ってしまった失言を、なかったことにしたい…」
そんな魔法の道具はないものか。
我ながら、あれは酷い八つ当たりだった。
思い出しても、自分の愚かさに自分を殴りたくなる。
今からでも遅くないから、自分を殴ろうか?
いや、いっそ屋根から放り投げて欲しいんですよね。
全てを忘れられそうな気がする。
何であんなことを言ってしまったのか。
かつて自分がされた罰ゲームと同じことを、別のクラスメイトが目の前でされてて。
それを見て、頭に血が上ったのは確かだ。
馬鹿共が、また懲りずに馬鹿なことをしてると思った。
そしてその馬鹿共は、唯華さんが「同じクラスになれた」と喜んでいた、唯華さんの親友だった。
それでつい。八つ当たり的に。唯華さんを罵倒してしまった。
何であんなこと言ってしまったのか。
別に、彼女が罰ゲームをやった訳じゃないだろ。
ついでに言うと唯華さんは、あの湯野さんとかいう馬鹿なクラスメイトを、止めようとしていたのだ。
馬鹿なことするな、って。
それなのに、どうして僕は唯華さんにあんな、つっけんどんな態度を取ってしまったのか。
もう、完全に八つ当たり。
涙が出てきそうなくらい、自業自得である。
「性格が悪いにも程がある…。お願いです、加賀宮さん。僕のこの、ねじ曲がった性根を叩き直してください」
「…誰かに言われたのか?性格が悪いと…」
誰にも言われてない。自分でそう思ってるだけ。
でも、多分唯華さんは思ってるんじゃないか。
「何コイツ。性格悪っ」って。
きっとそう。そうに違いない。
ここ数日、僕のことを避けているのもそのせいなのだろう。
性格のひねくれた僕に、ほとほと愛想を尽かした可能性が大。
そうされても仕方がないと思うほどには、自分の性格が悪い自覚がある。
「だって、ひねくれてるでしょ?僕」
「…自分で自分をひねくれていると言えるほど自覚があるなら、大したことないんじゃないか?」
本当にひねくれてる奴は、自分がひねくれてる自覚もないだろうって?
そうかもしれないけど。でもそうじゃない。
そうじゃないんですよ。
「それから、お前は…ひねくれてるんじゃなくて、ただ素直になれないだけだと思うが…」
それをひねくれてるって言うんでしょうよ。
「忘れたい…。言ってしまった失言を、なかったことにしたい…」
そんな魔法の道具はないものか。
我ながら、あれは酷い八つ当たりだった。
思い出しても、自分の愚かさに自分を殴りたくなる。
今からでも遅くないから、自分を殴ろうか?
いや、いっそ屋根から放り投げて欲しいんですよね。
全てを忘れられそうな気がする。
何であんなことを言ってしまったのか。
かつて自分がされた罰ゲームと同じことを、別のクラスメイトが目の前でされてて。
それを見て、頭に血が上ったのは確かだ。
馬鹿共が、また懲りずに馬鹿なことをしてると思った。
そしてその馬鹿共は、唯華さんが「同じクラスになれた」と喜んでいた、唯華さんの親友だった。
それでつい。八つ当たり的に。唯華さんを罵倒してしまった。
何であんなこと言ってしまったのか。
別に、彼女が罰ゲームをやった訳じゃないだろ。
ついでに言うと唯華さんは、あの湯野さんとかいう馬鹿なクラスメイトを、止めようとしていたのだ。
馬鹿なことするな、って。
それなのに、どうして僕は唯華さんにあんな、つっけんどんな態度を取ってしまったのか。
もう、完全に八つ当たり。
涙が出てきそうなくらい、自業自得である。
かくなる上は。
「師匠ってあれ…。ちょっと聞きたいんですけど」
「何だ?」
「真面目に答えてくださいね。夫婦喧嘩したときって、いつもどうやって解決してます?」
「そ…!そう聞かれても…」
僕はずっと片親育ちで、両親が夫婦喧嘩をする光景を見たことがない。
正確には、僕と唯華さんは夫婦ではないが。
交際関係にある男女が、一般的にどのようにして仲直りをするのか聞きたい。
どうすれば良いんですか。
「こっちは真剣なんです、至って真剣なんですよ。良い歳してもじもじしてないで、ちゃんと教えてください」
「え、いや。そ、そう言われても…。…何も思いつかない」
はい?
「そもそもうちは、お互い離れて暮らしてるから…喧嘩をする機会がない」
「…成程」
賢いですね、お宅。
喧嘩したときどうするかじゃなくて、そもそも喧嘩をしないという選択を取るとは。
確かに、それは正しいのかもしれない。
交通事故に遭ったらどうするか、について考えるよりも。
そんな時間があったら、そもそも交通事故に遭わない為にどうするか、について考えた方が余程建設的というものだ。
しかしどんなに対策していても、細心の注意を払っていたとしても。
事故というものは、どうしても起きてしまうもので。
そんなとき、どうしたら良いのか知りたい。
「別居してるとはいえ…たまには喧嘩くらいしてくださいよ」
「そ、そう言われても…」
「それだけ長く生きてて…夫婦喧嘩もしたことがないとは…。…はぁ…」
「…何故か、物凄く理不尽な理由で怒られてる気がする…」
それは気のせいです。
「別に難しく考えなくても…。悪いことをしてしまったと思ってるなら、謝れば良いんじゃないか?」
ド正論。
悪いことをしたなら謝りましょう。幼稚園児でも分かる大原則。
その通り過ぎて、言い返す言葉が見つからない。
「謝って…許してくれるものなんでしょうか」
「…世の中の大抵のことは、謝れば許されると思うが」
「謝っても許されないことが、世の中にはあるんですよ」
「…そんなに悪いことをしたのか?」
「…」
したんですよ。多分。
八つ当たりという、この上なく自分勝手な理由で唯華さんを傷つけてしまった。
最低ですよ。
「師匠ってあれ…。ちょっと聞きたいんですけど」
「何だ?」
「真面目に答えてくださいね。夫婦喧嘩したときって、いつもどうやって解決してます?」
「そ…!そう聞かれても…」
僕はずっと片親育ちで、両親が夫婦喧嘩をする光景を見たことがない。
正確には、僕と唯華さんは夫婦ではないが。
交際関係にある男女が、一般的にどのようにして仲直りをするのか聞きたい。
どうすれば良いんですか。
「こっちは真剣なんです、至って真剣なんですよ。良い歳してもじもじしてないで、ちゃんと教えてください」
「え、いや。そ、そう言われても…。…何も思いつかない」
はい?
「そもそもうちは、お互い離れて暮らしてるから…喧嘩をする機会がない」
「…成程」
賢いですね、お宅。
喧嘩したときどうするかじゃなくて、そもそも喧嘩をしないという選択を取るとは。
確かに、それは正しいのかもしれない。
交通事故に遭ったらどうするか、について考えるよりも。
そんな時間があったら、そもそも交通事故に遭わない為にどうするか、について考えた方が余程建設的というものだ。
しかしどんなに対策していても、細心の注意を払っていたとしても。
事故というものは、どうしても起きてしまうもので。
そんなとき、どうしたら良いのか知りたい。
「別居してるとはいえ…たまには喧嘩くらいしてくださいよ」
「そ、そう言われても…」
「それだけ長く生きてて…夫婦喧嘩もしたことがないとは…。…はぁ…」
「…何故か、物凄く理不尽な理由で怒られてる気がする…」
それは気のせいです。
「別に難しく考えなくても…。悪いことをしてしまったと思ってるなら、謝れば良いんじゃないか?」
ド正論。
悪いことをしたなら謝りましょう。幼稚園児でも分かる大原則。
その通り過ぎて、言い返す言葉が見つからない。
「謝って…許してくれるものなんでしょうか」
「…世の中の大抵のことは、謝れば許されると思うが」
「謝っても許されないことが、世の中にはあるんですよ」
「…そんなに悪いことをしたのか?」
「…」
したんですよ。多分。
八つ当たりという、この上なく自分勝手な理由で唯華さんを傷つけてしまった。
最低ですよ。
「何をしたのか知らないが…。…お前は日頃の行いが良いから、たまの失敗くらいは、謝れば許してもらえるんじゃないのか?」
優しい言葉をどうもありがとうございます。
僕って日頃の行い良いんですか?
「…それでも、許してもらえなかったら?」
「それは…。…まぁ、そういうことも、たまにはあるかもしれない」
ですよね。
僕もそう思います。
「でも、許してもらえる努力をした上で許されないのと、ハナから何もせずに許されないのとでは、前者の方がまだマシなんじゃないか?」
…またしても、ド正論。
胸に突き刺さりますよ。それはもうグサグサと。
「そうか…。うん、そうですよね…」
結局のところ、誠心誠意対応するしかない、ってことですね。
そりゃそうだ。
許してもらえるにしても、許してもらえないにしても。
ともかく謝らないことには、僕だって気が済まない。
「分かりましたよ…。…頑張ってみます」
「そうか」
「それでもし、許してもらえなかったら…そのときは今度こそ、屋根から放り投げてください」
「いや、そ…。それはやめた方が良いんじゃないか…?」
そうですね。僕も、屋根から放り投げられるような事態にはならないことを祈ってますよ。
それってつまり、唯華さんとの破局を意味する訳ですから。
こちらから「別れても良いんですよ」とか言っときながら、本当に「じゃあ別れる」と言われるのが怖いなんて。
つくづく、馬鹿なことを言ってしまったものだ。
自分の愚かさを恥じる前に、やるべきことがある。
全く、我ながら何をしているのだか。
去年までなら、唯華さんみたいな人と付き合うなんて、絶対有り得なかっただろうに。
僕にとっては、一生手が届かないほど遠くにいる人だった。
住んでいる世界が違う。両者の間には、越えられない壁がある。
お互いに、一生分かり合うことは出来ない。
罰ゲームで他人と付き合おうとする、そんな人を好きになるなんて絶対に有り得ない。
…そう思っていたのに。
何故か今となっては、そんな人を失うことを心から恐れている。
変わってしまったものだ。…僕も。
唯華さんと過ごした日々が、僕を変えてしまった。
その変化が、良いものなのか、悪いものなのかは分からない。
それでも今、ここに。
彼女を失いたくないと、心の底から願っている自分がいるのだ。
優しい言葉をどうもありがとうございます。
僕って日頃の行い良いんですか?
「…それでも、許してもらえなかったら?」
「それは…。…まぁ、そういうことも、たまにはあるかもしれない」
ですよね。
僕もそう思います。
「でも、許してもらえる努力をした上で許されないのと、ハナから何もせずに許されないのとでは、前者の方がまだマシなんじゃないか?」
…またしても、ド正論。
胸に突き刺さりますよ。それはもうグサグサと。
「そうか…。うん、そうですよね…」
結局のところ、誠心誠意対応するしかない、ってことですね。
そりゃそうだ。
許してもらえるにしても、許してもらえないにしても。
ともかく謝らないことには、僕だって気が済まない。
「分かりましたよ…。…頑張ってみます」
「そうか」
「それでもし、許してもらえなかったら…そのときは今度こそ、屋根から放り投げてください」
「いや、そ…。それはやめた方が良いんじゃないか…?」
そうですね。僕も、屋根から放り投げられるような事態にはならないことを祈ってますよ。
それってつまり、唯華さんとの破局を意味する訳ですから。
こちらから「別れても良いんですよ」とか言っときながら、本当に「じゃあ別れる」と言われるのが怖いなんて。
つくづく、馬鹿なことを言ってしまったものだ。
自分の愚かさを恥じる前に、やるべきことがある。
全く、我ながら何をしているのだか。
去年までなら、唯華さんみたいな人と付き合うなんて、絶対有り得なかっただろうに。
僕にとっては、一生手が届かないほど遠くにいる人だった。
住んでいる世界が違う。両者の間には、越えられない壁がある。
お互いに、一生分かり合うことは出来ない。
罰ゲームで他人と付き合おうとする、そんな人を好きになるなんて絶対に有り得ない。
…そう思っていたのに。
何故か今となっては、そんな人を失うことを心から恐れている。
変わってしまったものだ。…僕も。
唯華さんと過ごした日々が、僕を変えてしまった。
その変化が、良いものなのか、悪いものなのかは分からない。
それでも今、ここに。
彼女を失いたくないと、心の底から願っている自分がいるのだ。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…