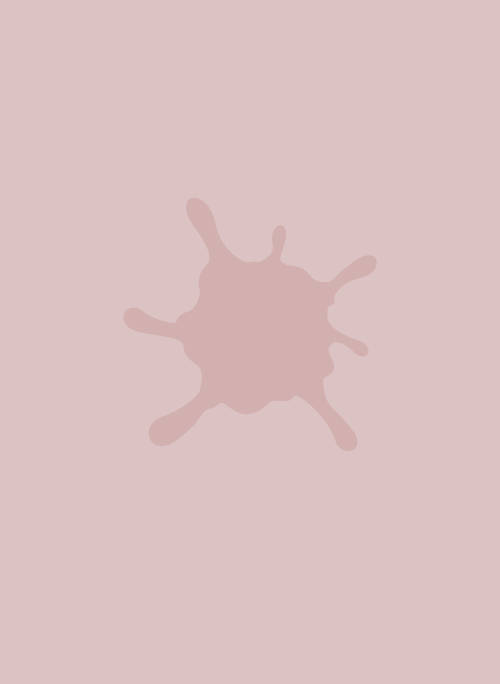「おかしいよ。おかしいよ、こんな風に思うなんて。私だって分かんないよ…!」
星野さんはそう言った。
僕も同じ気持ちだった。
何でこんな風に思うのか、僕も分からない。
「罰ゲームで付き合うって聞かされたときは、絶対嫌だって思ってたのに。有り得ないって思ってたのに。それなのに…それなのに、君が底無しに優しいんだもん」
…そんな、ことは。
そんなつもりは…。
「地味で根暗で、私と話が合うことなんてないはずだったのに。いつの間にか、君といる時間がどんどん早くなって」
僕も同じだ。
あなたと話が合うなんて、絶対有り得なかった。
「一緒にいればいるほど、意外な姿が増えていって。何でかめちゃくちゃ料理上手だしさ、お裁縫も上手いしさ。貧乏だって聞いて、デートに行く場所も限られてて、つまんないはずだったのにさ…」
僕もそのつもりだった。
僕と一緒に過ごす時間なんて、あなたにとってつまらないもの以外の何物でもないと。
僕にとっても、つまらない時間だと思っていたのに。
「お母さんの話ばっかするから、マザコンかよって思ってたら…。身体の弱いお母さんを献身的に支えてあげててさ…。どれだけ親孝行なのよ?」
「…」
「君のお母さんだって、会ってみたら凄く優しい人でさ…。嫌いになる要素、一個もないじゃない。どうやって嫌いになれば良いのよ?君と過ごす時間が、苦痛じゃなくなって、むしろ心地良くなっていって…」
…僕も同じだ。
騙されていたんだから。ずっと騙されてたんだから。
あなたと過ごす時間は、苦痛でしかないはずだったのに。
そんな時間が、全然苦痛に感じなくなって…。
「罰ゲームのはずだったのに、何でか凄く満たされてたの。結月君なんて、好きになるところ一つもないと思ってたのに、今はその全部が…好きで堪らないんだよ」
「…」
「訳分かんないよ、自分でも。だけど…どうしようもないの。こんな身勝手な私の気持ちに、結月君が応えてくれるはずないって分かってるのに…」
そう言って。
星野さんは、ぐちゃぐちゃの顔を両手で覆った。
…そう、ですか。
そう思ってたんですか。そんな風に。
…僕もなんです。
僕も…あなたと過ごす時間が、最初に出会った頃よりずっと、心地良くなっていって…。
…だからこそ。
「…あなたに裏切られて、本当に悲しかった…」
あなたが、勇気を出して自分の思いを告げたんだから。
今度は、僕が本音を語る番だ。
星野さんはそう言った。
僕も同じ気持ちだった。
何でこんな風に思うのか、僕も分からない。
「罰ゲームで付き合うって聞かされたときは、絶対嫌だって思ってたのに。有り得ないって思ってたのに。それなのに…それなのに、君が底無しに優しいんだもん」
…そんな、ことは。
そんなつもりは…。
「地味で根暗で、私と話が合うことなんてないはずだったのに。いつの間にか、君といる時間がどんどん早くなって」
僕も同じだ。
あなたと話が合うなんて、絶対有り得なかった。
「一緒にいればいるほど、意外な姿が増えていって。何でかめちゃくちゃ料理上手だしさ、お裁縫も上手いしさ。貧乏だって聞いて、デートに行く場所も限られてて、つまんないはずだったのにさ…」
僕もそのつもりだった。
僕と一緒に過ごす時間なんて、あなたにとってつまらないもの以外の何物でもないと。
僕にとっても、つまらない時間だと思っていたのに。
「お母さんの話ばっかするから、マザコンかよって思ってたら…。身体の弱いお母さんを献身的に支えてあげててさ…。どれだけ親孝行なのよ?」
「…」
「君のお母さんだって、会ってみたら凄く優しい人でさ…。嫌いになる要素、一個もないじゃない。どうやって嫌いになれば良いのよ?君と過ごす時間が、苦痛じゃなくなって、むしろ心地良くなっていって…」
…僕も同じだ。
騙されていたんだから。ずっと騙されてたんだから。
あなたと過ごす時間は、苦痛でしかないはずだったのに。
そんな時間が、全然苦痛に感じなくなって…。
「罰ゲームのはずだったのに、何でか凄く満たされてたの。結月君なんて、好きになるところ一つもないと思ってたのに、今はその全部が…好きで堪らないんだよ」
「…」
「訳分かんないよ、自分でも。だけど…どうしようもないの。こんな身勝手な私の気持ちに、結月君が応えてくれるはずないって分かってるのに…」
そう言って。
星野さんは、ぐちゃぐちゃの顔を両手で覆った。
…そう、ですか。
そう思ってたんですか。そんな風に。
…僕もなんです。
僕も…あなたと過ごす時間が、最初に出会った頃よりずっと、心地良くなっていって…。
…だからこそ。
「…あなたに裏切られて、本当に悲しかった…」
あなたが、勇気を出して自分の思いを告げたんだから。
今度は、僕が本音を語る番だ。
「あなたが告白してきたのは罰ゲームなんだって、最初から分かってた…」
あのときに、断っていれば良かった。
下らないプライドに負けて、素知らぬ顔で告白を受けてしまった。
でも、思えばあのときから。
僕は、信じたいと思っていたのだ。
「だからあなたの笑顔も、言葉も、全部偽物なんだって…分かってた…」
どれだけ僕に笑顔を見せてくれても。
どんな言葉をかけてくれてと。
それは偽物で、ただ罰ゲームの一環なのだと、頭の中では理解していたのに。
万が一、億に一つでも。
それは紛れもない、星野さんの本音なんじゃないかと期待していた。
「それでも、本気で言ってくれてるんじゃないかと…。本気で、こんな僕のことを…好きでいてくれるんじゃないかって、ほんの少しでも…。自分が誰かに好かれてるんだって、そんな希望に浸りたくて…」
我ながら幼稚で、儚い望み。
何でそんな、自分に都合の良い願いを抱いてしまったのか。
それが過ちだった。
「だから、裏切られて悲しかった。やっぱり罰ゲームでしかなかったんだと分かって…。あなたを散々罵ることで、腹いせをして…八つ当たりして…」
泣かせるようなことをたくさん言って、下らない自尊心を守ろうとして。
本当は、あんなことを言うつもりなんてなかった。
罰ゲームで付き合っていたことを知られていたのだと、赤恥をかかせてやるだけのつもりだった。
でも、それ以上に傷つけることをたくさん、たくさん言ってしまった。
復讐でもするかのように。
そう、あれは確かに復讐だった。
僕は心の何処かで、あなたのことを信じていたのに。
その期待を裏切った星野さんへ、復讐するつもりだった。
だから、言った後あんなに後悔した。
星野さんの泣き顔が、いつまでも頭から離れない。
あんなに傷つけるつもりはなかった。
どれほど恨んでいても。騙されていたことを憎らしく思っていても。
それでも僕は、あなたを信じていたかった。
師匠の言った通りだった。
期待してた。心の何処かで信じていた。
だから裏切られて、悲しくて…悔しくて。
それで八つ当たりしてしまった。
そんなことしても…虚しいだけだって分かってたのに。
「…傷つけてしまって、ごめんなさい」
自分に非なんて、一切ないと思っていた。
だけど、僕は自然と謝罪の言葉を口にしていた。
そうしてやっと、脳裏に焼き付いて離れなかった星野さんの泣き顔が。
まるで憑き物が取れたかのように、霧散してなくなった。
あぁ、僕はずっと、このことを謝りたかったんだと。
今になってようやく分かった。
…もっと、素直になれば良かった。
裏切られて悲しかったと、悔しかったのだと言えば良かった。
言ったら負けだと思って…そんな弱さを見せたら負けだと思って、言えなかった。
それこそが、僕の弱さだったのだ。
あのときに、断っていれば良かった。
下らないプライドに負けて、素知らぬ顔で告白を受けてしまった。
でも、思えばあのときから。
僕は、信じたいと思っていたのだ。
「だからあなたの笑顔も、言葉も、全部偽物なんだって…分かってた…」
どれだけ僕に笑顔を見せてくれても。
どんな言葉をかけてくれてと。
それは偽物で、ただ罰ゲームの一環なのだと、頭の中では理解していたのに。
万が一、億に一つでも。
それは紛れもない、星野さんの本音なんじゃないかと期待していた。
「それでも、本気で言ってくれてるんじゃないかと…。本気で、こんな僕のことを…好きでいてくれるんじゃないかって、ほんの少しでも…。自分が誰かに好かれてるんだって、そんな希望に浸りたくて…」
我ながら幼稚で、儚い望み。
何でそんな、自分に都合の良い願いを抱いてしまったのか。
それが過ちだった。
「だから、裏切られて悲しかった。やっぱり罰ゲームでしかなかったんだと分かって…。あなたを散々罵ることで、腹いせをして…八つ当たりして…」
泣かせるようなことをたくさん言って、下らない自尊心を守ろうとして。
本当は、あんなことを言うつもりなんてなかった。
罰ゲームで付き合っていたことを知られていたのだと、赤恥をかかせてやるだけのつもりだった。
でも、それ以上に傷つけることをたくさん、たくさん言ってしまった。
復讐でもするかのように。
そう、あれは確かに復讐だった。
僕は心の何処かで、あなたのことを信じていたのに。
その期待を裏切った星野さんへ、復讐するつもりだった。
だから、言った後あんなに後悔した。
星野さんの泣き顔が、いつまでも頭から離れない。
あんなに傷つけるつもりはなかった。
どれほど恨んでいても。騙されていたことを憎らしく思っていても。
それでも僕は、あなたを信じていたかった。
師匠の言った通りだった。
期待してた。心の何処かで信じていた。
だから裏切られて、悲しくて…悔しくて。
それで八つ当たりしてしまった。
そんなことしても…虚しいだけだって分かってたのに。
「…傷つけてしまって、ごめんなさい」
自分に非なんて、一切ないと思っていた。
だけど、僕は自然と謝罪の言葉を口にしていた。
そうしてやっと、脳裏に焼き付いて離れなかった星野さんの泣き顔が。
まるで憑き物が取れたかのように、霧散してなくなった。
あぁ、僕はずっと、このことを謝りたかったんだと。
今になってようやく分かった。
…もっと、素直になれば良かった。
裏切られて悲しかったと、悔しかったのだと言えば良かった。
言ったら負けだと思って…そんな弱さを見せたら負けだと思って、言えなかった。
それこそが、僕の弱さだったのだ。
「…結月君は…悪くないよ」
「そうかもしれませんね。でも…謝りたかったんです」
あなたに、涙を流させてしまったことを。
ずっと後悔していた。無意識に。
そして、その上で。
「謝らなきゃいけないのは、私の方だよ…結月君を、たくさん傷つけてしまった…」
「…そうですね。でも…僕は、あなたを許します」
「…え?」
…結局、師匠の言った通りになってしまった。
全くあの人と来たら、鈍いんだか、鋭いんだか…。
「許し以外に…あなたに与えられるものは何もないから。だから、僕はあなたを許します」
「そんな…。許してくれるの…?こんなに…馬鹿な私を…」
「えぇ。…許します」
そうと決めたら、心が楽になった。
意地を張っていたのが馬鹿みたいだ。
「あなたがちゃんと反省しているのなら…それで良いです」
「結月君…。君って人は、何でこんなときまで…私に優しくするのかなぁ…」
さて、何でででしょう。
「…まだ僕はあなたのこと、信じたいと思ってるからでしょうかね?」
「…そんな風に思ってくれるの?まだ?」
…信じたい、とは少し違うな。
信じているからだ。
例え罰ゲームの関係だったのだとしても。
きっかけなんて、どうでも良い。
一緒に過ごしたこの三ヶ月の日々は、決して偽りではなかった。
僕は、そう信じているから。
「…もう一度、信じても良いですか」
「…結月君…」
「信じさせてくれますか。…今度こそ…僕達の思いは、偽物ではないのだと」
「…うん」
星野さんは、微笑んでいるのか、泣いているのか。
顔をくちゃくちゃにして、何度も頷いた。
「君がもう一度…チャンスをくれるなら。私は絶対、君を裏切らない。もう二度と…間違えたりしないよ」
…そうですか。
あなたがそう言うなら。それなら、僕も。
「そうかもしれませんね。でも…謝りたかったんです」
あなたに、涙を流させてしまったことを。
ずっと後悔していた。無意識に。
そして、その上で。
「謝らなきゃいけないのは、私の方だよ…結月君を、たくさん傷つけてしまった…」
「…そうですね。でも…僕は、あなたを許します」
「…え?」
…結局、師匠の言った通りになってしまった。
全くあの人と来たら、鈍いんだか、鋭いんだか…。
「許し以外に…あなたに与えられるものは何もないから。だから、僕はあなたを許します」
「そんな…。許してくれるの…?こんなに…馬鹿な私を…」
「えぇ。…許します」
そうと決めたら、心が楽になった。
意地を張っていたのが馬鹿みたいだ。
「あなたがちゃんと反省しているのなら…それで良いです」
「結月君…。君って人は、何でこんなときまで…私に優しくするのかなぁ…」
さて、何でででしょう。
「…まだ僕はあなたのこと、信じたいと思ってるからでしょうかね?」
「…そんな風に思ってくれるの?まだ?」
…信じたい、とは少し違うな。
信じているからだ。
例え罰ゲームの関係だったのだとしても。
きっかけなんて、どうでも良い。
一緒に過ごしたこの三ヶ月の日々は、決して偽りではなかった。
僕は、そう信じているから。
「…もう一度、信じても良いですか」
「…結月君…」
「信じさせてくれますか。…今度こそ…僕達の思いは、偽物ではないのだと」
「…うん」
星野さんは、微笑んでいるのか、泣いているのか。
顔をくちゃくちゃにして、何度も頷いた。
「君がもう一度…チャンスをくれるなら。私は絶対、君を裏切らない。もう二度と…間違えたりしないよ」
…そうですか。
あなたがそう言うなら。それなら、僕も。
僕ももう一度あなたを信じます。
今度は、残酷な復讐心からではなく。
ただ心の底から、あなたの気持ちと、自分の気持ちを信じたいと思っているから。
――――――…こうして。
結月君に、再び微笑みかけてもらった瞬間に。
私は、この一ヶ月の間抱え続けてきた心の重荷を、ようやく降ろすことが出来た。
…もっと早くに、こうしておけば良かった。
こんなに楽になるなんて、思ってもみなかった。
これで、明日から私は。
やっと、自分に素直に生きることが出来る。
結月君に、再び微笑みかけてもらった瞬間に。
私は、この一ヶ月の間抱え続けてきた心の重荷を、ようやく降ろすことが出来た。
…もっと早くに、こうしておけば良かった。
こんなに楽になるなんて、思ってもみなかった。
これで、明日から私は。
やっと、自分に素直に生きることが出来る。
「…ふふっ」
その日の夜。
私は、久し振りに…くよくよもめそめそもせずに。
むしろ晴れ晴れとした気持ちで、ベッドに寝そべっていた。
夕食のとき、両親に「何か良いことでもあったの?」と聞かれるくらいには。
私は酷く浮かれていた。
そりゃ、浮かれもするだろう。
何と言っても、私は、ようやく。
本当の意味で、自分の彼氏が出来たんだもん。
昨日の私にそんなこと言っても、絶対信じなかっただろうなぁ。
三ヶ月前の自分に言ったら、もっと信じなかったと思う。
自分に彼氏がいて、しかもその相手は、クラスで最も有り得ないだろうという人物なのだから。
でも、これは全部現実なのだ。紛れもない現実。
そして私は今、この現実に深く満足している。
我ながら正気か、とツッコミを入れたくなるけど。
正気で、しかも現実なのよ。
…わくわくすると思わない?これからの毎日を思うと。
なーにをニヤけてんだか。現金な奴。
…完全に、許されたなんて思ってないよ。
結月君が許してくれたのは、それは彼が優しいから。
普通は、どんなに謝ったって許してもらえるなんて有り得ない。
十字架が消えた訳じゃない。
本当の償いは、これから始まるのだ。
これからの毎日で、私は結月君を傷つけた償いをするんだ。
もう二度と、私は決して。
彼を傷つけるような真似はしないと、心に固く誓った。
…それにしても、と私は思った。
私はこれまで、三ヶ月の間、結月君と付き合っていた訳だけど。
この三ヶ月間は、ずっと罰ゲームのつもりで付き合っていたから。
私は、結月君のことを知ろうとか、もっと交友を深めようとか、そういう努力は全然してこなかったんだよね。
…これって、結構問題なのでは?
少なくとも、私達は一応今日から、交際をしている彼氏彼女の関係になる訳だから…。
もっと、お互いのことをよく知り合わないと駄目だよね。
…そんな、恋人同士として当たり前の努力さえしてこなかった私達って。
でも、これからリカバリー出来る。
まずはその第一歩として…。
「…よし」
慣れないことを、始めてみることにした。
その日の夜。
私は、久し振りに…くよくよもめそめそもせずに。
むしろ晴れ晴れとした気持ちで、ベッドに寝そべっていた。
夕食のとき、両親に「何か良いことでもあったの?」と聞かれるくらいには。
私は酷く浮かれていた。
そりゃ、浮かれもするだろう。
何と言っても、私は、ようやく。
本当の意味で、自分の彼氏が出来たんだもん。
昨日の私にそんなこと言っても、絶対信じなかっただろうなぁ。
三ヶ月前の自分に言ったら、もっと信じなかったと思う。
自分に彼氏がいて、しかもその相手は、クラスで最も有り得ないだろうという人物なのだから。
でも、これは全部現実なのだ。紛れもない現実。
そして私は今、この現実に深く満足している。
我ながら正気か、とツッコミを入れたくなるけど。
正気で、しかも現実なのよ。
…わくわくすると思わない?これからの毎日を思うと。
なーにをニヤけてんだか。現金な奴。
…完全に、許されたなんて思ってないよ。
結月君が許してくれたのは、それは彼が優しいから。
普通は、どんなに謝ったって許してもらえるなんて有り得ない。
十字架が消えた訳じゃない。
本当の償いは、これから始まるのだ。
これからの毎日で、私は結月君を傷つけた償いをするんだ。
もう二度と、私は決して。
彼を傷つけるような真似はしないと、心に固く誓った。
…それにしても、と私は思った。
私はこれまで、三ヶ月の間、結月君と付き合っていた訳だけど。
この三ヶ月間は、ずっと罰ゲームのつもりで付き合っていたから。
私は、結月君のことを知ろうとか、もっと交友を深めようとか、そういう努力は全然してこなかったんだよね。
…これって、結構問題なのでは?
少なくとも、私達は一応今日から、交際をしている彼氏彼女の関係になる訳だから…。
もっと、お互いのことをよく知り合わないと駄目だよね。
…そんな、恋人同士として当たり前の努力さえしてこなかった私達って。
でも、これからリカバリー出来る。
まずはその第一歩として…。
「…よし」
慣れないことを、始めてみることにした。
…翌日。
の、昼休み。
「星ちゃん。学食行こー」
と、いつも通り真菜と海咲が声をかけてきたけど。
残念ながら、今日はそのお誘いには乗れない。
「ごめん。今日、私お弁当なんだ。教室で食べるから」
「え?珍しいね、星ちゃんがお弁当なんて」
いつもは学食か購買だもんね。
でも、今日は違うのだ。
新しいことに挑戦してみようと思ったから。
「うん、ちょっとね」
「ふーん…。じゃあ、二人だけで行ってくるわ」
「行ってらっしゃい」
私は、学食に向かう二人を見送り。
そして、学生カバンの中から、お弁当の巾着袋を取り出した。
…よし。
じゃ、私は。
「…結月君っ」
僅かな勇気を出して、私は結月君に声をかけた。
「は、はい?」
驚いたような顔で返事をする結月君。
それが、自分の彼女に声をかけられたときの反応か。
そんなにびっくりしなくても良いものを。
「お昼、一緒に食べよ」
「え…?」
「結月君、お弁当なんでしょ?」
「そうですが…。星野さんは、いつも学食では…?」
いつもは、そうなんだけどね。
でも今日はちょっと、趣向を変えてみたって言うか。
新しいことに挑戦してみたんだよ。
結月君を見習ってね。
「今日はお弁当にしてみたんだ。一緒に食べよう。…嫌?」
「あ、いえ…。嫌じゃないですよ。どうぞ…」
「じゃ、遠慮なく…。ここ、座るね」
私は、自分の椅子を持ってきて。
結月君の机の前に置いて、向かい合うようにして座った。
こうして学校で、昼休みに二人でお弁当を食べるなんて。
初めての体験だね。
…って言うか…。
結月君とやることなすこと、全部、お互いにとって初めてのような気がするよ。
まぁ、それも悪くないじゃない。
どんな経験でも。
君と一緒に積み重ねていけば、いつかきっと、この日を振り返ったとき。
「あぁ、こんなこともあったなぁ」って思い出して笑えるよ。
の、昼休み。
「星ちゃん。学食行こー」
と、いつも通り真菜と海咲が声をかけてきたけど。
残念ながら、今日はそのお誘いには乗れない。
「ごめん。今日、私お弁当なんだ。教室で食べるから」
「え?珍しいね、星ちゃんがお弁当なんて」
いつもは学食か購買だもんね。
でも、今日は違うのだ。
新しいことに挑戦してみようと思ったから。
「うん、ちょっとね」
「ふーん…。じゃあ、二人だけで行ってくるわ」
「行ってらっしゃい」
私は、学食に向かう二人を見送り。
そして、学生カバンの中から、お弁当の巾着袋を取り出した。
…よし。
じゃ、私は。
「…結月君っ」
僅かな勇気を出して、私は結月君に声をかけた。
「は、はい?」
驚いたような顔で返事をする結月君。
それが、自分の彼女に声をかけられたときの反応か。
そんなにびっくりしなくても良いものを。
「お昼、一緒に食べよ」
「え…?」
「結月君、お弁当なんでしょ?」
「そうですが…。星野さんは、いつも学食では…?」
いつもは、そうなんだけどね。
でも今日はちょっと、趣向を変えてみたって言うか。
新しいことに挑戦してみたんだよ。
結月君を見習ってね。
「今日はお弁当にしてみたんだ。一緒に食べよう。…嫌?」
「あ、いえ…。嫌じゃないですよ。どうぞ…」
「じゃ、遠慮なく…。ここ、座るね」
私は、自分の椅子を持ってきて。
結月君の机の前に置いて、向かい合うようにして座った。
こうして学校で、昼休みに二人でお弁当を食べるなんて。
初めての体験だね。
…って言うか…。
結月君とやることなすこと、全部、お互いにとって初めてのような気がするよ。
まぁ、それも悪くないじゃない。
どんな経験でも。
君と一緒に積み重ねていけば、いつかきっと、この日を振り返ったとき。
「あぁ、こんなこともあったなぁ」って思い出して笑えるよ。
…と、まぁちょっと良い話みたいに言ってるけど。
実は、そんなにへらへらしていられないのよね。
結月君は慣れた手付きで、カバンの中からお弁当の入ったトートバックを取り出していた。
あ、あのトートバックも和柄だ。
さてはお主、それも縫ったな?お手製だな?
それどころか、お弁当箱を包んでいるハンカチも、結月君が縫ったものであるらしく。
端っこに、金魚の刺繍がしてあった。
冷静に考えたら、結月君って刺繍も得意なんだよね。
さすがの女子力。
「君は、生まれてくる性別を間違えたんじゃないかな…」
「え、な、何ですか?いきなり…」
「気にしなくて良いのよ」
羨ましくない。えぇ、羨ましくなんてありませんとも。
…。
…今ここにハンカチがあったら、血の涙を流しながら噛み千切ってるわね。
「それにしても、星野さんがお弁当って珍しいですね。どういう風の吹き回しなんですか?」
酷い言いようじゃないの。
「今日はちょっと、新しいことに挑戦してみたの。結月君を見習おうと思って」
「僕を…?」
私は、机の上に自分のお弁当箱を置いた。
…うぅ。勇気が出ない。
でも、折角持ってきたんだし…。
えぇい、ままよ。
「じゃん!今日は私、自分のお弁当を…自分で作ってきました!」
毎日、年中無休で自作のお弁当を持ってきている結月君にとっては、それが何だと思うかもしれないが。
普段は何処かで買うばかりで、そもそもお弁当を持ってくる習慣がなく。
ましてや、お弁当を自分で作ってくるなんて。
私にとっては大きな一歩だった。
お母さんにとっても、そうだったようで。
昨日私が「明日自分でお弁当作るわ」と言ったら、びっくり仰天された。
それこそ、「一体どういう風の吹き回し?」状態。
普段、どれだけ何もやっていないかがバレるわね。
でも、今日は頑張った。
「目覚ましをセットして、ちゃんと早起きして…お弁当作ってきたのよ」
「ほう…。凄いじゃないですか」
と、結月君も褒めてくれた。
ありがとう。
もうそれだけで充分だわ。
だって、このお弁当は…。
「見せてもらえませんか?どんなお弁当作ったのか…。僕、人のお弁当がどんな感じなのか、いつも気になってたんです」
「…」
「お弁当のおかずって、ついワンパターンになりがちじゃないですか。人のお弁当を見ることで、新しいアイデアが浮かぶかもしれない」
成程、それは一理あるわね。
結月君が見たがるのも理解出来る。
…でもね。
「…見せてあげないわ」
「えっ」
見せられる訳ないでしょ。私のお弁当なんて。
だって、このお弁当は…。
…日の丸弁当と良い勝負が出来るんじゃないかってくらい、超手抜き弁当なんだから。
実は、そんなにへらへらしていられないのよね。
結月君は慣れた手付きで、カバンの中からお弁当の入ったトートバックを取り出していた。
あ、あのトートバックも和柄だ。
さてはお主、それも縫ったな?お手製だな?
それどころか、お弁当箱を包んでいるハンカチも、結月君が縫ったものであるらしく。
端っこに、金魚の刺繍がしてあった。
冷静に考えたら、結月君って刺繍も得意なんだよね。
さすがの女子力。
「君は、生まれてくる性別を間違えたんじゃないかな…」
「え、な、何ですか?いきなり…」
「気にしなくて良いのよ」
羨ましくない。えぇ、羨ましくなんてありませんとも。
…。
…今ここにハンカチがあったら、血の涙を流しながら噛み千切ってるわね。
「それにしても、星野さんがお弁当って珍しいですね。どういう風の吹き回しなんですか?」
酷い言いようじゃないの。
「今日はちょっと、新しいことに挑戦してみたの。結月君を見習おうと思って」
「僕を…?」
私は、机の上に自分のお弁当箱を置いた。
…うぅ。勇気が出ない。
でも、折角持ってきたんだし…。
えぇい、ままよ。
「じゃん!今日は私、自分のお弁当を…自分で作ってきました!」
毎日、年中無休で自作のお弁当を持ってきている結月君にとっては、それが何だと思うかもしれないが。
普段は何処かで買うばかりで、そもそもお弁当を持ってくる習慣がなく。
ましてや、お弁当を自分で作ってくるなんて。
私にとっては大きな一歩だった。
お母さんにとっても、そうだったようで。
昨日私が「明日自分でお弁当作るわ」と言ったら、びっくり仰天された。
それこそ、「一体どういう風の吹き回し?」状態。
普段、どれだけ何もやっていないかがバレるわね。
でも、今日は頑張った。
「目覚ましをセットして、ちゃんと早起きして…お弁当作ってきたのよ」
「ほう…。凄いじゃないですか」
と、結月君も褒めてくれた。
ありがとう。
もうそれだけで充分だわ。
だって、このお弁当は…。
「見せてもらえませんか?どんなお弁当作ったのか…。僕、人のお弁当がどんな感じなのか、いつも気になってたんです」
「…」
「お弁当のおかずって、ついワンパターンになりがちじゃないですか。人のお弁当を見ることで、新しいアイデアが浮かぶかもしれない」
成程、それは一理あるわね。
結月君が見たがるのも理解出来る。
…でもね。
「…見せてあげないわ」
「えっ」
見せられる訳ないでしょ。私のお弁当なんて。
だって、このお弁当は…。
…日の丸弁当と良い勝負が出来るんじゃないかってくらい、超手抜き弁当なんだから。
「だ、駄目なんですか…?」
「そう、駄目よ。これはパンドラの箱よ」
「そ、そうですか…。そう言われると余計気になるんですけど…」
そう。
でも駄目よ。
とても、見せられる代物じゃないんだから。
「じゃあ、その…どうしたら良いですか?僕…後ろ向いて食べたら良いですか?」
「別に、前を向いて食べたら良いじゃない」
そんな後ろ向きにならなくても。
もっと前向きに生きて良いのよ。
「でも、正面を向いてたら、どうしても星野さんのお弁当が…目に入るんですが…」
「…」
「…あっ、えぇと…出来るだけ見ないように努力します…」
…出来るだけってことは、やっぱりちょっとは見るんじゃないの。
分かった、分かったわよ。
観念すれば良いんでしょ?
「分かった…見せるわよ…」
「い、良いんですか?」
「逃げ回ってもしょうがないもの…。言っておくけど、笑わないでね」
結月君に「ぷっ、クスクス」なんて笑われたら、私は心が折れるわ。
「もし笑ったら、おへそに箸突っ込んでやるから。絶対笑わないって約束して」
「…想像したら意外と痛かったので、絶対笑いません」
宜しい。
じゃ、見せてあげるわ。
私は巾着袋を開けて、お弁当箱を取り出した。
うぅ、この時点でもう恥ずかしい。
しかし、ここまで来たら引き返せない。
南無三とばかりに、私はお弁当箱の蓋を開けた。
何かの奇跡が起こって、お弁当の中身が美しく心機一転…!
なんてことは勿論なかった。
朝、お弁当箱に中身を詰めたときのまま。
それどころか、ちょっと寄り弁してて、朝より更に悲惨なことになっていた。
存分にご覧なさい。
これが私の人生で一番最初の、お弁当第一号よ。
「…さぁ、感想は?」
笑うんじゃないでしょうね。
笑ったら、へそに箸よ。
すると、結月君は。
「え、えぇと…」
何と言ったら分からない、みたいな顔をして。
視線をぐるぐると彷徨わせ、ついでに言うべき言葉を必死に探し。
結果、出てきたのは。
「…ど、努力が感じられて…い、良いんじゃないでしょうか?」
…物は言いようってことね。
でも、正直に言って良いのよ。
「下手くそにも程があるだろ」って言って良いのよ。
私でさえそう思ってるから。
私が今日、ドヤ顔で持ってきたお弁当は。
それはそれはもう、タダでもらっても食べたくないほどの酷い出来だった。
何度見ても、やっぱり酷い。
でも持ってきてしまった以上、今更どうしようもなかった。
受け止めなさい、星野唯華。
これが、このお弁当が、私に突きつけられた現実なのよ。
「そう、駄目よ。これはパンドラの箱よ」
「そ、そうですか…。そう言われると余計気になるんですけど…」
そう。
でも駄目よ。
とても、見せられる代物じゃないんだから。
「じゃあ、その…どうしたら良いですか?僕…後ろ向いて食べたら良いですか?」
「別に、前を向いて食べたら良いじゃない」
そんな後ろ向きにならなくても。
もっと前向きに生きて良いのよ。
「でも、正面を向いてたら、どうしても星野さんのお弁当が…目に入るんですが…」
「…」
「…あっ、えぇと…出来るだけ見ないように努力します…」
…出来るだけってことは、やっぱりちょっとは見るんじゃないの。
分かった、分かったわよ。
観念すれば良いんでしょ?
「分かった…見せるわよ…」
「い、良いんですか?」
「逃げ回ってもしょうがないもの…。言っておくけど、笑わないでね」
結月君に「ぷっ、クスクス」なんて笑われたら、私は心が折れるわ。
「もし笑ったら、おへそに箸突っ込んでやるから。絶対笑わないって約束して」
「…想像したら意外と痛かったので、絶対笑いません」
宜しい。
じゃ、見せてあげるわ。
私は巾着袋を開けて、お弁当箱を取り出した。
うぅ、この時点でもう恥ずかしい。
しかし、ここまで来たら引き返せない。
南無三とばかりに、私はお弁当箱の蓋を開けた。
何かの奇跡が起こって、お弁当の中身が美しく心機一転…!
なんてことは勿論なかった。
朝、お弁当箱に中身を詰めたときのまま。
それどころか、ちょっと寄り弁してて、朝より更に悲惨なことになっていた。
存分にご覧なさい。
これが私の人生で一番最初の、お弁当第一号よ。
「…さぁ、感想は?」
笑うんじゃないでしょうね。
笑ったら、へそに箸よ。
すると、結月君は。
「え、えぇと…」
何と言ったら分からない、みたいな顔をして。
視線をぐるぐると彷徨わせ、ついでに言うべき言葉を必死に探し。
結果、出てきたのは。
「…ど、努力が感じられて…い、良いんじゃないでしょうか?」
…物は言いようってことね。
でも、正直に言って良いのよ。
「下手くそにも程があるだろ」って言って良いのよ。
私でさえそう思ってるから。
私が今日、ドヤ顔で持ってきたお弁当は。
それはそれはもう、タダでもらっても食べたくないほどの酷い出来だった。
何度見ても、やっぱり酷い。
でも持ってきてしまった以上、今更どうしようもなかった。
受け止めなさい、星野唯華。
これが、このお弁当が、私に突きつけられた現実なのよ。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…