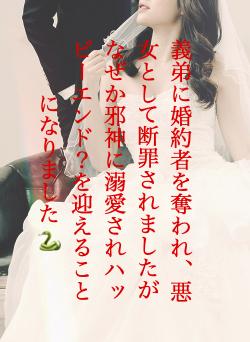「エルダの王太子が?」
「ああ。完全なる和平条約を結ぶことになったから、他国にも俺たちは仲良しですっていうアピール目的のためだろう。うちはかろうじて負けてないだけでこのまま続けば確実に負けてたし、あちらとの戦力差を見せられた以上、断る理由がないからな」
エルダの王太子が訪問する。
和平条約を結ぶとはいえ元敵国、その上こちらは宣戦布告もなしにいきなり戦争をふっかけた。
そんな国に次期国王が訪問とは無謀ではないか。
エルダには他にも王子がいるし、準王族だっているのに。
「エルダの魔鉱石を手に入れられなかった以上、エルダと和平条約を結ぶのは当然の流れね。我が国の領土を狙っているクレイルがいつ襲ってくるかも分からないし」
だからこそパイデスはエルダの持つ魔鉱石の鉱山を欲した。
結果は惨敗に近いけど。
エルダが良識と良心を兼ね備えた国で良かった。
でなければ、パイデスは終わっていただろう。
そこをパイデスの王族が分かっているといいけど。
いつだってパイデスはエルダを小国で歴史の浅い国だと馬鹿にしてきた。
「それだけじやないんだ」
さっきまで軽快に話していたエリックは急に言いよどむ。
「なに?」
いつまでも話そうとしないエリックに痺れを切らして先を促すと彼はようやく重たい口を開いた。
「ルーエンブルク領にも訪問したいそうだ」
思わず拳を握り締めてしまった。
何を緊張する必要がある?
戦争被害が一番大きい場所を相手国が訪問するのはよくあることじゃないか。他意はないし、彼が私の両親を殺したわけではない。いや、仮に殺したとしてもこちらに憎む資格はない。
戦争を仕掛けたのはパイデスだ。それに戦争だったんだ。殺し合うのは仕方がない。死人が出るのは仕方がない。
これは仕方のないことだった。
「分かったわ。領民には気を配っておく。中には愛する者を殺された憎みを抱いている者もいるでしょうし、トラブルになる可能性もあるからね」
それがキッカで漸く終わった戦争が再び勃発しかねない。今は特にとても重要な時期だ。何事も慎重に動かなければ。
「お前は?お前は大丈夫なのか?お前だって両親を亡くしてる。それに、俺と違って戦場に行ったお前は一番凄惨な光景を見てきたはずだ」
「何も問題はない。凄惨な現場を見て来たのはあちらも同じだ。戦争では受けた痛みだけが平等に与えられるのだから。一方的に責めるのは違うだろう。それに何を失おうと、どれだけの者を失おうと、戦争を仕掛けたのはパイデスだ。ならばパイデスがエルダを憎んだり、責めるのはお門違いだろう」
「戦争なんか誰も望んでなかったっ!」
堰き止めていた感情を吐き出すようにエリックは声を荒げた。
「パイデスの国民も俺たちも、アイリスだって」
「もしパイデスが戦争に勝てていたら、私たちも国民もパイデス出身というだけでその恩恵を受ける。それでも自分たちは関係ない、望んでいなかったと言える?」
「言える。安全を享受し、何も失わずに欲しいものだけを得た奴らから恩着せがましく与えられたものを手放しで喜べるほど、俺は無神経じゃない。アイリスは、戦争やパイデスの立場を利用して憎しみを押し殺そうとしているように見える」
エリックの目が真っ直ぐと私を見る。私の心を見透かそうとするその目は私が大好きだった家族と同じ目だった。あんなに大好きだった目も今では苦手となっていた。
「ならば憎むことは正しいの?憎んでどうするの?失ったものはもう二度と戻って来ないのに」
どうして私だけ生き残った。
どうして私も一緒に殺してくれなかった。
醜い感情を抱きながら死ぬまで生きなければならないのなら殺してくれれば良かったのに。
「ああ。完全なる和平条約を結ぶことになったから、他国にも俺たちは仲良しですっていうアピール目的のためだろう。うちはかろうじて負けてないだけでこのまま続けば確実に負けてたし、あちらとの戦力差を見せられた以上、断る理由がないからな」
エルダの王太子が訪問する。
和平条約を結ぶとはいえ元敵国、その上こちらは宣戦布告もなしにいきなり戦争をふっかけた。
そんな国に次期国王が訪問とは無謀ではないか。
エルダには他にも王子がいるし、準王族だっているのに。
「エルダの魔鉱石を手に入れられなかった以上、エルダと和平条約を結ぶのは当然の流れね。我が国の領土を狙っているクレイルがいつ襲ってくるかも分からないし」
だからこそパイデスはエルダの持つ魔鉱石の鉱山を欲した。
結果は惨敗に近いけど。
エルダが良識と良心を兼ね備えた国で良かった。
でなければ、パイデスは終わっていただろう。
そこをパイデスの王族が分かっているといいけど。
いつだってパイデスはエルダを小国で歴史の浅い国だと馬鹿にしてきた。
「それだけじやないんだ」
さっきまで軽快に話していたエリックは急に言いよどむ。
「なに?」
いつまでも話そうとしないエリックに痺れを切らして先を促すと彼はようやく重たい口を開いた。
「ルーエンブルク領にも訪問したいそうだ」
思わず拳を握り締めてしまった。
何を緊張する必要がある?
戦争被害が一番大きい場所を相手国が訪問するのはよくあることじゃないか。他意はないし、彼が私の両親を殺したわけではない。いや、仮に殺したとしてもこちらに憎む資格はない。
戦争を仕掛けたのはパイデスだ。それに戦争だったんだ。殺し合うのは仕方がない。死人が出るのは仕方がない。
これは仕方のないことだった。
「分かったわ。領民には気を配っておく。中には愛する者を殺された憎みを抱いている者もいるでしょうし、トラブルになる可能性もあるからね」
それがキッカで漸く終わった戦争が再び勃発しかねない。今は特にとても重要な時期だ。何事も慎重に動かなければ。
「お前は?お前は大丈夫なのか?お前だって両親を亡くしてる。それに、俺と違って戦場に行ったお前は一番凄惨な光景を見てきたはずだ」
「何も問題はない。凄惨な現場を見て来たのはあちらも同じだ。戦争では受けた痛みだけが平等に与えられるのだから。一方的に責めるのは違うだろう。それに何を失おうと、どれだけの者を失おうと、戦争を仕掛けたのはパイデスだ。ならばパイデスがエルダを憎んだり、責めるのはお門違いだろう」
「戦争なんか誰も望んでなかったっ!」
堰き止めていた感情を吐き出すようにエリックは声を荒げた。
「パイデスの国民も俺たちも、アイリスだって」
「もしパイデスが戦争に勝てていたら、私たちも国民もパイデス出身というだけでその恩恵を受ける。それでも自分たちは関係ない、望んでいなかったと言える?」
「言える。安全を享受し、何も失わずに欲しいものだけを得た奴らから恩着せがましく与えられたものを手放しで喜べるほど、俺は無神経じゃない。アイリスは、戦争やパイデスの立場を利用して憎しみを押し殺そうとしているように見える」
エリックの目が真っ直ぐと私を見る。私の心を見透かそうとするその目は私が大好きだった家族と同じ目だった。あんなに大好きだった目も今では苦手となっていた。
「ならば憎むことは正しいの?憎んでどうするの?失ったものはもう二度と戻って来ないのに」
どうして私だけ生き残った。
どうして私も一緒に殺してくれなかった。
醜い感情を抱きながら死ぬまで生きなければならないのなら殺してくれれば良かったのに。