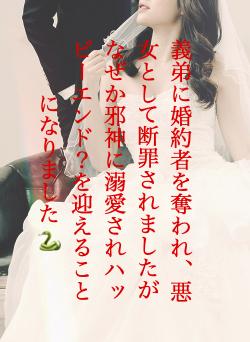side .シーラ
アイリスに言われて王宮から連れて来た使用人は全員帰した。
「そんな、私たちはちゃんとやっていました」
「長年、仕えてきた私たちよりも出自の不確かな孤児の言うことを信じるんですか」
連れてきた使用人はみんな、自分の行いに間違いがないと主張した。
暴力も全面否定。
私も彼女たちが可哀想な孤児たちにそんなことをしたとは思いたくはなかった。
「子供たちの話だけを聞いて判断したわけじゃないわ」
むしろ、それだけなら信じなかった。
卑しい生まれの人間は嘘つきだって王宮の家庭教師に教わったことがある。
私はそれ自体を悪と断じるつもりはない。身分が卑しいということはそれだけ心が貧しい証拠。それは彼のせいではない。生まれてきた環境の問題であり、そういう環境を作り上げている国に問題があると思うから。
「でも、医者の診断書まであるの」
「孤児院が雇っている医者など信用できません」
「私もそう思うわ」
「でしたら」
医者といえどアイリスの息のかかった人間のいうことなど信用できない。アイリスも私がそう思うのを見越したのだろう。
孤児院の医者の診断書とは別に私が子供たちのために連れてきた王宮の医者に書かせた診断書まである。
二人の医者が書いた診断書は内容が酷似している。
孤児院の医者だけなら証拠能力はないと言えたのに。
「でもそれは暴行を受けたという証拠にはなっても、私たちが暴行したという証拠にはならないはず」
この使用人たちは外部の人間が子供たちに暴行したと言いたいのだろう。でも・・・・・。
「今、孤児院にいる子供たちは私の指示で殆ど外出させていないわ。それに私の護衛にとお父様が連れてきた護衛たちの目撃証言もあるの」
アイリスは子供たちに一番必要な道徳面の教育を怠っている。
孤児院の子供たちの犯罪率が高いのはそのせいだ。これはアイリスだけではない他の貴族が運営する孤児院もそうだろう。
道徳教育を幼いうちからしっかりと教えれば盗みが悪いことだと理解し、犯罪率だって確実に下がる。寧ろなくなると私は踏んでいる。
だから道徳教育がしっかりとできるまで外出はさせないし、外部の人間との接触だってさせるつもりはない。
つまり、外部の人間が子供たちに暴行することは現状不可能なんだ。
まさか自分が立てた対策で自分の首を絞めることになるなんて思いもしなかった。
「あなたたちが可哀想な子供たちに暴力を振るったのは明白。これ以上の言い逃れは見苦しいだけよ」
「王女殿下」
尚も縋りつこうとする使用人の手を私は初めて振り払った。
「あなたたちは私の顔に泥を塗ったの。私の信頼を裏切るような真似までして、慈悲に縋ろうとなんて虫が良すぎるんじゃないの」
まさか孤児院の子供たちを不当に働かせているアイリスに人員のミスを指摘されるなんて思わなかった。これほどの屈辱はないわ。しかも王女である私を呼びつけるなんて。
ちょっと私の友人だからって図に乗りすぎよ。
貴族は甘い顔をするとすぐにつけ上がるから気をつけるようにとお父様に口酸っぱく言われてたわね。その時は私の友人に限ってそんなことあるわけがないと思ったけどまさかアイリスがあそこまで横暴に出るなんて思いもしなかった。
本来なら一貴族である彼女は私の行いに否を唱えることなんてできないのに。
「私に仕える者に役立たずはいらないの。ましてや主人の顔に泥を塗る使用人なんてね」
「殿下」
「王宮に帰りなさい。私があなたたちを強制送還する前に。代わりの人員は手配済みよ」
そこまで言うとようやく理解したのか全員、項垂れながらも素直に従った。どうして下々の人間ってこうも理解力が乏しいのかしら。
公爵になったアイリスでも私の行いを理解できないからこれが当たり前なのよね。ああ、でもアイリスは生まれながらの公爵ではないから比べる対象にはならないわね。
「孤児院のスタッフを呼び戻すんですか?」
「ルー」
ルーが掃除道具を持ったまま私のところに来た。ルーは私の弟だから雑用は使用人に任せればいいと言っているのに進んで色々としてくれる。ルーだけは私を裏切らない。
当然よね。ルーはスラム出身で死にかけているところを私が助けてあげたんだから。
「まさか。孤児たちを虐待していた人たちを使うわけがないでしょう」
「じゃあ、どうするんですか?孤児院には俺と殿下と院長先生しかいませんよ」
「新しい人材をお父様にお願いして送ってもらう手配を既に済んでいるわ」
「・・・・・王宮に仕える人間は貴族出身者です。今回のような問題がまた起きるのではないですか?」
「そうならない人材をお願いしたから大丈夫よ」
「・・・・・」
「私だって日々成長しているのよ。今回の件で学んだわ。下の者を信用しすぎない方がいいって」
「・・・・・」
アイリスに言われて王宮から連れて来た使用人は全員帰した。
「そんな、私たちはちゃんとやっていました」
「長年、仕えてきた私たちよりも出自の不確かな孤児の言うことを信じるんですか」
連れてきた使用人はみんな、自分の行いに間違いがないと主張した。
暴力も全面否定。
私も彼女たちが可哀想な孤児たちにそんなことをしたとは思いたくはなかった。
「子供たちの話だけを聞いて判断したわけじゃないわ」
むしろ、それだけなら信じなかった。
卑しい生まれの人間は嘘つきだって王宮の家庭教師に教わったことがある。
私はそれ自体を悪と断じるつもりはない。身分が卑しいということはそれだけ心が貧しい証拠。それは彼のせいではない。生まれてきた環境の問題であり、そういう環境を作り上げている国に問題があると思うから。
「でも、医者の診断書まであるの」
「孤児院が雇っている医者など信用できません」
「私もそう思うわ」
「でしたら」
医者といえどアイリスの息のかかった人間のいうことなど信用できない。アイリスも私がそう思うのを見越したのだろう。
孤児院の医者の診断書とは別に私が子供たちのために連れてきた王宮の医者に書かせた診断書まである。
二人の医者が書いた診断書は内容が酷似している。
孤児院の医者だけなら証拠能力はないと言えたのに。
「でもそれは暴行を受けたという証拠にはなっても、私たちが暴行したという証拠にはならないはず」
この使用人たちは外部の人間が子供たちに暴行したと言いたいのだろう。でも・・・・・。
「今、孤児院にいる子供たちは私の指示で殆ど外出させていないわ。それに私の護衛にとお父様が連れてきた護衛たちの目撃証言もあるの」
アイリスは子供たちに一番必要な道徳面の教育を怠っている。
孤児院の子供たちの犯罪率が高いのはそのせいだ。これはアイリスだけではない他の貴族が運営する孤児院もそうだろう。
道徳教育を幼いうちからしっかりと教えれば盗みが悪いことだと理解し、犯罪率だって確実に下がる。寧ろなくなると私は踏んでいる。
だから道徳教育がしっかりとできるまで外出はさせないし、外部の人間との接触だってさせるつもりはない。
つまり、外部の人間が子供たちに暴行することは現状不可能なんだ。
まさか自分が立てた対策で自分の首を絞めることになるなんて思いもしなかった。
「あなたたちが可哀想な子供たちに暴力を振るったのは明白。これ以上の言い逃れは見苦しいだけよ」
「王女殿下」
尚も縋りつこうとする使用人の手を私は初めて振り払った。
「あなたたちは私の顔に泥を塗ったの。私の信頼を裏切るような真似までして、慈悲に縋ろうとなんて虫が良すぎるんじゃないの」
まさか孤児院の子供たちを不当に働かせているアイリスに人員のミスを指摘されるなんて思わなかった。これほどの屈辱はないわ。しかも王女である私を呼びつけるなんて。
ちょっと私の友人だからって図に乗りすぎよ。
貴族は甘い顔をするとすぐにつけ上がるから気をつけるようにとお父様に口酸っぱく言われてたわね。その時は私の友人に限ってそんなことあるわけがないと思ったけどまさかアイリスがあそこまで横暴に出るなんて思いもしなかった。
本来なら一貴族である彼女は私の行いに否を唱えることなんてできないのに。
「私に仕える者に役立たずはいらないの。ましてや主人の顔に泥を塗る使用人なんてね」
「殿下」
「王宮に帰りなさい。私があなたたちを強制送還する前に。代わりの人員は手配済みよ」
そこまで言うとようやく理解したのか全員、項垂れながらも素直に従った。どうして下々の人間ってこうも理解力が乏しいのかしら。
公爵になったアイリスでも私の行いを理解できないからこれが当たり前なのよね。ああ、でもアイリスは生まれながらの公爵ではないから比べる対象にはならないわね。
「孤児院のスタッフを呼び戻すんですか?」
「ルー」
ルーが掃除道具を持ったまま私のところに来た。ルーは私の弟だから雑用は使用人に任せればいいと言っているのに進んで色々としてくれる。ルーだけは私を裏切らない。
当然よね。ルーはスラム出身で死にかけているところを私が助けてあげたんだから。
「まさか。孤児たちを虐待していた人たちを使うわけがないでしょう」
「じゃあ、どうするんですか?孤児院には俺と殿下と院長先生しかいませんよ」
「新しい人材をお父様にお願いして送ってもらう手配を既に済んでいるわ」
「・・・・・王宮に仕える人間は貴族出身者です。今回のような問題がまた起きるのではないですか?」
「そうならない人材をお願いしたから大丈夫よ」
「・・・・・」
「私だって日々成長しているのよ。今回の件で学んだわ。下の者を信用しすぎない方がいいって」
「・・・・・」