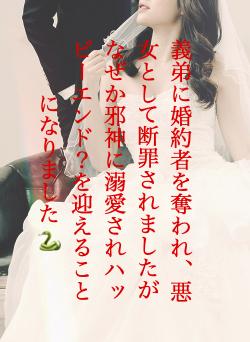side .レン
『レン、言葉だけが情報を得る手段ではない。人はね、ただそこにいるだけで存在そのものが情報源となる。仕草、表情、呼吸の仕方や立ち方、目の動き。よく観察しなさい。そこから得られる情報があるから』
これはアイリス様の言葉だ。
アイリス様は俺たちに情報収集を頼むことがある。孤児院の中にはいろんな奴がいる。赤ん坊の頃に孤児院に捨てられ、孤児院での暮らししか知らない奴、幼い時に親に孤児院に預けられた奴、スラム出身者もいる。
いろんな悪いことをして来て、騎士団に捕まってそのまま孤児院に預けられたりもする。
だから大人よりも世情を知っているし、暗い世界に精通していたりもする。アイリス様はそこを買って俺たちに情報収集させるのだ。
そのために必要なことは色々と教えてくれるし、必要な道具も与えてくれる。
「ルー先生、手伝うよ」
だから俺はアイリス様の役に立ちたい。そのために邪魔な王女を排除する。
だから俺は王女が連れて来た他とは違う、誰よりも俺たちに近いこのルーという人に近づく。彼を観察して考える。味方にすべきか、敵として排除すべき存在なのか。
「・・・・・」
ルー先生は廊下を掃除していた手を止めて俺を見つめる。時間にして数秒程度だ。
あの王女の従者とは思えないぐらい警戒心が強い。いや、あの王女だからこそ、ここまで警戒心が強いのかもしれない。
攻略は難航しそうだな。
「俺は先生じゃない」
そう言ってルー先生は再び廊下のモップ掛けに専念した。
「じゃあ、なんて呼べばいいの?」
「好きに呼んだらいい」
人に興味なしか。
「孤児院で働く大人を先生って呼ぶんだ。だからやっぱりルー先生って呼ぶね。好きに呼んでいいんでしょ」
「子供に何かを教えられるような真っ当な生き方はしてない」
「ここに自分の生き方に胸を張れる人間なんて一人もいないよ。アイリス様でさえそうなのに、どうして他の奴らが自分の生き方を誇れるって言うんだ」
全部背負わせた。
何もできない無力な子供である自分が許せなかった。
アイリス様に守れらただけの自分も、そう思わせた事実も全てが腹立たしかった。
「あの人はどういうお人なんだ?」
「アイリス様のこと?」
「ああ」
ふぅん、アイリス様に興味があるんだ。そう言えばあの人、王女様の前でルー先生のことを「ペット」呼ばわりしたって話を聞いたな。
ルー先生は怒らなかったらしいけど。
「真面目で、責任感の強い人。言葉だけではなく行動で指針を示してくれる人。だからこそ、その恩に報いたいと思う」
「・・・・・そうか」
「王女様はどんな人なの?」
「わざわざ聞く必要もないでしょう」
僅かだけで眉間に皺が寄った。表情があまり変わらないから何を考えているか分からない人だと思ったけどよく見たら違う。顔や仕草のどこかに何かしらの動きがある。
ああ、この人は王女様のことが嫌いなんだ。
「ルー先生の口から聞きたい。ルー先生の主観での王女様像を知りたいんだ」
これならルー先生をこちらに引き込めなくても王女様から奪うのは簡単だ。
ねぇ、王女様。
あんたは夢にも思わないだろうね。
あんたがアイリス様の名前を親しげに呼ぶ度に、意味不明な糾弾で貶めようとする度に俺があんたを殺してしまいたいなんて思っていることに。
だって、あんたにとって俺は庇護すべき可哀想な子供。何の力も持たない孤児なんだから。
だから俺みたいなガキに足元を掬われるんだ。
だからあんたが所有物のように扱っている弟を奪われるんだ。
あんたはたくさん持っているんだろ。なら一つぐらい奪ってもいいよな。
施しを与えるためにここへ来たのなら、施してくれ。俺があんたに望む施しはあんたの汚名だ。
ここへ来たことを後悔させてやるぐらいあんたの名前に泥を塗りたくってやる。
「王女様は何も知らない人なんだ。たくさんの物を持っているから、持っていない人間がいることを知らない。それが許される世界で生きてこれる人。俺たちとは住む世界が違う人。関われば、惨めになるだけだ」
そう言ったルー先生の声にも瞳にも何の感情も宿ってはいなかった。
『レン、言葉だけが情報を得る手段ではない。人はね、ただそこにいるだけで存在そのものが情報源となる。仕草、表情、呼吸の仕方や立ち方、目の動き。よく観察しなさい。そこから得られる情報があるから』
これはアイリス様の言葉だ。
アイリス様は俺たちに情報収集を頼むことがある。孤児院の中にはいろんな奴がいる。赤ん坊の頃に孤児院に捨てられ、孤児院での暮らししか知らない奴、幼い時に親に孤児院に預けられた奴、スラム出身者もいる。
いろんな悪いことをして来て、騎士団に捕まってそのまま孤児院に預けられたりもする。
だから大人よりも世情を知っているし、暗い世界に精通していたりもする。アイリス様はそこを買って俺たちに情報収集させるのだ。
そのために必要なことは色々と教えてくれるし、必要な道具も与えてくれる。
「ルー先生、手伝うよ」
だから俺はアイリス様の役に立ちたい。そのために邪魔な王女を排除する。
だから俺は王女が連れて来た他とは違う、誰よりも俺たちに近いこのルーという人に近づく。彼を観察して考える。味方にすべきか、敵として排除すべき存在なのか。
「・・・・・」
ルー先生は廊下を掃除していた手を止めて俺を見つめる。時間にして数秒程度だ。
あの王女の従者とは思えないぐらい警戒心が強い。いや、あの王女だからこそ、ここまで警戒心が強いのかもしれない。
攻略は難航しそうだな。
「俺は先生じゃない」
そう言ってルー先生は再び廊下のモップ掛けに専念した。
「じゃあ、なんて呼べばいいの?」
「好きに呼んだらいい」
人に興味なしか。
「孤児院で働く大人を先生って呼ぶんだ。だからやっぱりルー先生って呼ぶね。好きに呼んでいいんでしょ」
「子供に何かを教えられるような真っ当な生き方はしてない」
「ここに自分の生き方に胸を張れる人間なんて一人もいないよ。アイリス様でさえそうなのに、どうして他の奴らが自分の生き方を誇れるって言うんだ」
全部背負わせた。
何もできない無力な子供である自分が許せなかった。
アイリス様に守れらただけの自分も、そう思わせた事実も全てが腹立たしかった。
「あの人はどういうお人なんだ?」
「アイリス様のこと?」
「ああ」
ふぅん、アイリス様に興味があるんだ。そう言えばあの人、王女様の前でルー先生のことを「ペット」呼ばわりしたって話を聞いたな。
ルー先生は怒らなかったらしいけど。
「真面目で、責任感の強い人。言葉だけではなく行動で指針を示してくれる人。だからこそ、その恩に報いたいと思う」
「・・・・・そうか」
「王女様はどんな人なの?」
「わざわざ聞く必要もないでしょう」
僅かだけで眉間に皺が寄った。表情があまり変わらないから何を考えているか分からない人だと思ったけどよく見たら違う。顔や仕草のどこかに何かしらの動きがある。
ああ、この人は王女様のことが嫌いなんだ。
「ルー先生の口から聞きたい。ルー先生の主観での王女様像を知りたいんだ」
これならルー先生をこちらに引き込めなくても王女様から奪うのは簡単だ。
ねぇ、王女様。
あんたは夢にも思わないだろうね。
あんたがアイリス様の名前を親しげに呼ぶ度に、意味不明な糾弾で貶めようとする度に俺があんたを殺してしまいたいなんて思っていることに。
だって、あんたにとって俺は庇護すべき可哀想な子供。何の力も持たない孤児なんだから。
だから俺みたいなガキに足元を掬われるんだ。
だからあんたが所有物のように扱っている弟を奪われるんだ。
あんたはたくさん持っているんだろ。なら一つぐらい奪ってもいいよな。
施しを与えるためにここへ来たのなら、施してくれ。俺があんたに望む施しはあんたの汚名だ。
ここへ来たことを後悔させてやるぐらいあんたの名前に泥を塗りたくってやる。
「王女様は何も知らない人なんだ。たくさんの物を持っているから、持っていない人間がいることを知らない。それが許される世界で生きてこれる人。俺たちとは住む世界が違う人。関われば、惨めになるだけだ」
そう言ったルー先生の声にも瞳にも何の感情も宿ってはいなかった。