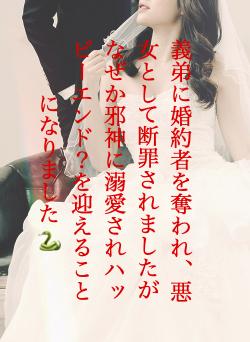side .レン
アイリス様はすぐに動いてくださった。王女様が連れてきた使用人は全て王宮に返された。けれど、先生たちが戻されることはなかった。
代わりに来たのはまたもや王宮で王女に仕えていた奴ら。
俺たちの敵だ。
王女は王族だろ?俺たちよりも水準の高い教育を受けているとアイリス様に聞いたことがある。それなのに理解力と学習力が乏しいのはなぜだろう。
自分に仕えている人間に孤児の世話が無理だと今回のことが分かったはずだ。それならば、普通はもう二度と王宮の使用人を使わないようにするものじゃないのか。
人さえ変えれば何も問題ないと思っているのか?
人格に問題があっただけだって?
違うだろ。
これは違う。そんな単純な話じゃない。根本にあるのは身分差であり差別意識だ。それが理解できていない。俺たち孤児でさえ分かっていることが王女には分からないんだ。
「どうして食べてくれないの?」
王女は俺たち孤児と同じ食卓についている。今夜の食事は王女が王宮の料理長を連れてきて作らせたものだ。食材も俺たちがどんなに働いても一生食べることができない高級な食材を用いている。
王女は当然の顔をしてそれを優雅に食べていたが、困惑してばかりで一切食事に手をつけない俺たちに王女は苛立っている。初めて会った時のような余裕は今の王女にはあまり感じられない。
せっかく連れて来た使用人をアイリス様に追い返されたことが思った以上にこたえているようだ。
「逆に聞きたい。どうして俺たちが食べられると思った?」
「?」
俺の質問の意図が分からなかったようだ。それもそうだろう。
金がないのなら親や大人から金を貰えばいい。パンがないのならケーキを食べればいい。そんな乏しい発想力しかないのだから。
「あんたは俺たちを何だと思っている?お貴族様の子息令嬢と勘違いしていないか?」
さっさとこんな奴、追い出せばいいのに。
こいつのせいでアイリス様も院長も先生たちもみんな困ってる。こいつがいなければ俺たちの日常は壊れなかったのに。それ以上に俺たちのことを何も理解していないこいつに腹が立つ。
俺たちを同情するばかりで、理解する気さえないのに。こういう奴のことを大人がなんて呼ぶのか知ってる。
”偽善者”って呼ぶんだ。
「俺たちの普段の食事がどういうものか、知っているか?王女様」
「ええ、知っているわ」
眉尻を下げて、王女は悲しげな表情を作る。俺たちを見るあの憐れみの目を抉り取ってしまいたい。
「可哀想に。アイリスはあなたたちにロクな食事を与えなかったのでしょう。そのように痩せ細って」
確かに腹一杯に食った記憶は数える程度しかない。それぐらい困窮してるからだ。でも、食事にありつけないような日はなかった。水で腹を満たすこともなかった。
「仮にあんたの言い分が正しかったとしよう。で?胃の弱った俺たちに消化に悪い肉類を食べさせて問題ないとでも思ったのか?ここに医者がいたらすぐに止めただろうよ。与えればいいと思っているのか?施せばいいって?」
「そういうわけではないわ」
王女は疲れたようにため息をこぼす。王女の言うことを聞かない、心を開こうとしない俺たちを責めているかのようだ。
「どうしてそう言う穿った見方しかできないの?私はアイリスからあなたたちを救おうとしているのよ。私はあなたたちの味方よ」
だから誰もお前に心を開かないんだ。
「最初の質問に戻る。王女様、あんたは俺たちを何だと思っている?お貴族の子息令嬢か?」
「質問の意味が分からないけど・・・・あなたたちは施しを受けるべき可哀想な子供たちだと理解しているつもりよ。アイリスと違ったね」
「確かに、俺たちは親にも世間様にも見捨てられた行き場のない可哀想なガキたちだ。そしてあんたはアイリス様と違う。アイリス様ならこんな食事は出さなかった」
褒められていると思っているのか?
アイリス様と比べられて、自分は優っていると俺が評価したとでも思っているのか?
俺は王女がどういう環境でどんなふうに育ったのか知らない。でも、王女の言動を観察して分かったことがある。王女はアイリス様に劣等感を抱いているんだ。だから何かにつけて優位に立とうとする。
「アイリス様なら正しく理解しただろう。俺たちがお貴族様に求められる食事のマナーを何も知らないただの孤児だと。だからアイリス様ならこんな食事は出さないのさ。こんな。ナイフとフォークを使わないと食べられないような食事なんて。俺たちはカトラリーの使い方すら知らないのだから」
「・・・・・知らないのなら学べばいいわ」
「何のために?俺たちはそんなものが必要な環境にはまず行かない。そんな俺たちに食事のマナーなんて必要ない。俺たちに必要なのは生きることに直結する知識と技術だ。王国貴族は俺たちが汗水たらして稼いだ金で暮らす。アイリス様のようにまともな方もいるだろうけど、そうでない奴はロクな仕事をしない」
貴族の中には仕事を部下に押し付けて豪遊三昧をしている奴もいる。というか、そういう奴の方が大半だ。
働いて稼ぐのは卑しいことという考え方があるようだ。
「いいよな、あんたらは寝てたって毎月金が貰えるんだから。俺たちが仕事中に寝て、貰えるのは金じゃねぇ、解雇通知だ。王女様、俺たちに懐いて欲しいのならもう少し俺たちのことを学ぶべきだ。行こうぜ、お前ら」
俺たちは唯一食べられるパンだけを貰って食堂を出た。
アイリス様はすぐに動いてくださった。王女様が連れてきた使用人は全て王宮に返された。けれど、先生たちが戻されることはなかった。
代わりに来たのはまたもや王宮で王女に仕えていた奴ら。
俺たちの敵だ。
王女は王族だろ?俺たちよりも水準の高い教育を受けているとアイリス様に聞いたことがある。それなのに理解力と学習力が乏しいのはなぜだろう。
自分に仕えている人間に孤児の世話が無理だと今回のことが分かったはずだ。それならば、普通はもう二度と王宮の使用人を使わないようにするものじゃないのか。
人さえ変えれば何も問題ないと思っているのか?
人格に問題があっただけだって?
違うだろ。
これは違う。そんな単純な話じゃない。根本にあるのは身分差であり差別意識だ。それが理解できていない。俺たち孤児でさえ分かっていることが王女には分からないんだ。
「どうして食べてくれないの?」
王女は俺たち孤児と同じ食卓についている。今夜の食事は王女が王宮の料理長を連れてきて作らせたものだ。食材も俺たちがどんなに働いても一生食べることができない高級な食材を用いている。
王女は当然の顔をしてそれを優雅に食べていたが、困惑してばかりで一切食事に手をつけない俺たちに王女は苛立っている。初めて会った時のような余裕は今の王女にはあまり感じられない。
せっかく連れて来た使用人をアイリス様に追い返されたことが思った以上にこたえているようだ。
「逆に聞きたい。どうして俺たちが食べられると思った?」
「?」
俺の質問の意図が分からなかったようだ。それもそうだろう。
金がないのなら親や大人から金を貰えばいい。パンがないのならケーキを食べればいい。そんな乏しい発想力しかないのだから。
「あんたは俺たちを何だと思っている?お貴族様の子息令嬢と勘違いしていないか?」
さっさとこんな奴、追い出せばいいのに。
こいつのせいでアイリス様も院長も先生たちもみんな困ってる。こいつがいなければ俺たちの日常は壊れなかったのに。それ以上に俺たちのことを何も理解していないこいつに腹が立つ。
俺たちを同情するばかりで、理解する気さえないのに。こういう奴のことを大人がなんて呼ぶのか知ってる。
”偽善者”って呼ぶんだ。
「俺たちの普段の食事がどういうものか、知っているか?王女様」
「ええ、知っているわ」
眉尻を下げて、王女は悲しげな表情を作る。俺たちを見るあの憐れみの目を抉り取ってしまいたい。
「可哀想に。アイリスはあなたたちにロクな食事を与えなかったのでしょう。そのように痩せ細って」
確かに腹一杯に食った記憶は数える程度しかない。それぐらい困窮してるからだ。でも、食事にありつけないような日はなかった。水で腹を満たすこともなかった。
「仮にあんたの言い分が正しかったとしよう。で?胃の弱った俺たちに消化に悪い肉類を食べさせて問題ないとでも思ったのか?ここに医者がいたらすぐに止めただろうよ。与えればいいと思っているのか?施せばいいって?」
「そういうわけではないわ」
王女は疲れたようにため息をこぼす。王女の言うことを聞かない、心を開こうとしない俺たちを責めているかのようだ。
「どうしてそう言う穿った見方しかできないの?私はアイリスからあなたたちを救おうとしているのよ。私はあなたたちの味方よ」
だから誰もお前に心を開かないんだ。
「最初の質問に戻る。王女様、あんたは俺たちを何だと思っている?お貴族の子息令嬢か?」
「質問の意味が分からないけど・・・・あなたたちは施しを受けるべき可哀想な子供たちだと理解しているつもりよ。アイリスと違ったね」
「確かに、俺たちは親にも世間様にも見捨てられた行き場のない可哀想なガキたちだ。そしてあんたはアイリス様と違う。アイリス様ならこんな食事は出さなかった」
褒められていると思っているのか?
アイリス様と比べられて、自分は優っていると俺が評価したとでも思っているのか?
俺は王女がどういう環境でどんなふうに育ったのか知らない。でも、王女の言動を観察して分かったことがある。王女はアイリス様に劣等感を抱いているんだ。だから何かにつけて優位に立とうとする。
「アイリス様なら正しく理解しただろう。俺たちがお貴族様に求められる食事のマナーを何も知らないただの孤児だと。だからアイリス様ならこんな食事は出さないのさ。こんな。ナイフとフォークを使わないと食べられないような食事なんて。俺たちはカトラリーの使い方すら知らないのだから」
「・・・・・知らないのなら学べばいいわ」
「何のために?俺たちはそんなものが必要な環境にはまず行かない。そんな俺たちに食事のマナーなんて必要ない。俺たちに必要なのは生きることに直結する知識と技術だ。王国貴族は俺たちが汗水たらして稼いだ金で暮らす。アイリス様のようにまともな方もいるだろうけど、そうでない奴はロクな仕事をしない」
貴族の中には仕事を部下に押し付けて豪遊三昧をしている奴もいる。というか、そういう奴の方が大半だ。
働いて稼ぐのは卑しいことという考え方があるようだ。
「いいよな、あんたらは寝てたって毎月金が貰えるんだから。俺たちが仕事中に寝て、貰えるのは金じゃねぇ、解雇通知だ。王女様、俺たちに懐いて欲しいのならもう少し俺たちのことを学ぶべきだ。行こうぜ、お前ら」
俺たちは唯一食べられるパンだけを貰って食堂を出た。