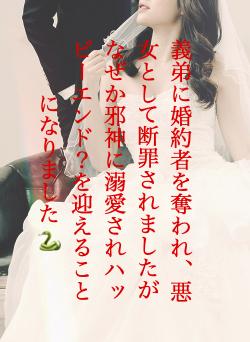「・・・・・・」
王女が孤児院の運営をする初日に起こした問題に頭が痛くなる。
「あなたが解雇を命じた者たちは人形でも玩具でもありません。生活のある人間です。不当な解雇は法律に反しますし、解雇されたスタッフの今後の生活はどうなさるつもりですか?」
現在、執務室に王女と孤児院の院長に解雇を言い渡されたスタッフが集まっている。
「不当ではないわ。彼女たちは子供たちを虐待しているんだもの。この解雇は妥当よ」
それを聞いたスタッフたちは反論したそうだったが平民である彼女たちが王女と貴族である私の会話に割って入ることはできない。そのため、奥歯を噛み締めて耐えていた。
運営側とスタッフの間に軋轢を生じさせれればまともな運営をする上で支障をきたす恐れがある。
それに子供たちはスタッフに懐いている。それを全員、解雇させて見ず知らずの人間に世話をさせるとなると子供たちにも不信を抱かせることになる。
真っ当な運営を望む割にはその道を自らの行いで遮断させるとは愚かとしか言いようがない。
「虐待だと言い張る証拠があるんですか?子供たちからそのような証言でも取れましたか?」
今度は王女が悔しそうに顔を歪めさせた。証拠は見つかっていない。当然だろう。その事実はないのだから。
「まだないわ。子供たちは洗脳されているためにそのような証言すらできない状態よ」
「洗脳されていると断言する根拠はなんですか?」
「自分達が受けるべき当然の恩恵を拒むから」
「それは根拠ではありません」
本当に頭が痛い。
「殿下と彼らの住む世界は違います。それ故に価値観も違うのです。ご自身の価値を一方的に押し付けることは慈悲でも優しさでもありません。傲慢というんですよ、そういうのを」
「なっ。私は傲慢さから言っているのではないわ。子供を働かせていなんて可哀想だと思わないの。ただでさえ、親を亡くして可哀想なのに、少しの慈悲も与えないなんて最低な行為よ」
王女でなければその頬を何度も引っ叩いていただろう。
ああ、思わず殺気が漏れてしまった。びくりと体を震わせ、青ざめる王女を見て私は自分を落ち着かせるために詰まりそうになっていた息を吐く。
「同情で腹が膨れますか?親がいないというだけで誰もが無条件に食事や衣服、さらには寝るところまで与え続けてくれると?その余裕がある裕福な暮らしの人間なら可能でしょう。その者が死ぬまでそうすればいい。与えられることに慣れた人間は生き甲斐を失くし、あなたの思う通りに動くペットとなってくれるでしょう。その者のように」
私は王女が連れている顔の整った青年に目を向ける。自然と王女の目もその青年に向いた。
「自分好みの服と装飾で飾り立て、自らの慈悲を他人に見せつけるように連れ歩けばいい」
「ルーは違うわっ!そんな目で見るなんて最低よ」
「お父様に言い付けるのならどうぞ、ご勝手に。あなたの父君がそのスラム出身者を弟だと言っていることにどのような感情を抱いているかは知りませんが、本当にご自分たちの関係が姉弟だと思っているのならそれ相応の扱いをすべきですね。少なくとも私には深き絆で結ばれた姉弟には見えません。ただの飼い主とペットです。陛下との取り決めがあります故、半年間はあなたの横暴を我慢しましょう。それにより被る被害は全て王家で補填してくれると最初に言質をとっておりますし、その契約書もあります」
怒りで震える王女に私はその契約書を見せつけた。
「スタッフの解雇は許可しましょう。その代わり、解雇されたスタッフの生活を半年間補償してもらいます。解雇された者は半年間の休暇を与えられたと思って過ごしてください。半年後には孤児院のスタッフとして戻ってもらいます。院長、皆様もよろしいですね」
スタッフは「それなら」と渋々だが承諾してくれた。
「虐待をしたスタッフを戻すなんて」と王女は一人不満を露わにしている。
「虐待の事実はありません。それと勘違いをなされないように。あなたはあくまで半年間、孤児院で運営の勉強をする身であって、領主代行でも院長代行でもありません。雇用権は院長もしくは私にあります。院長、面倒をかけますが半年間よろしくお願いします」
「はい」
「それと、必ずその日の報告を上げるように」
「かしこまりました」
初日からこれなら先が思いやられるわね。
エリックに仕事の一部を任せておいて良かった。でないと、本当に過労死していたかも。
『エルダに負担させればいい』
なんてことを平気で言う馬鹿のせいで。
・・・・・・戦争に備えておこうかしら。
王女が孤児院の運営をする初日に起こした問題に頭が痛くなる。
「あなたが解雇を命じた者たちは人形でも玩具でもありません。生活のある人間です。不当な解雇は法律に反しますし、解雇されたスタッフの今後の生活はどうなさるつもりですか?」
現在、執務室に王女と孤児院の院長に解雇を言い渡されたスタッフが集まっている。
「不当ではないわ。彼女たちは子供たちを虐待しているんだもの。この解雇は妥当よ」
それを聞いたスタッフたちは反論したそうだったが平民である彼女たちが王女と貴族である私の会話に割って入ることはできない。そのため、奥歯を噛み締めて耐えていた。
運営側とスタッフの間に軋轢を生じさせれればまともな運営をする上で支障をきたす恐れがある。
それに子供たちはスタッフに懐いている。それを全員、解雇させて見ず知らずの人間に世話をさせるとなると子供たちにも不信を抱かせることになる。
真っ当な運営を望む割にはその道を自らの行いで遮断させるとは愚かとしか言いようがない。
「虐待だと言い張る証拠があるんですか?子供たちからそのような証言でも取れましたか?」
今度は王女が悔しそうに顔を歪めさせた。証拠は見つかっていない。当然だろう。その事実はないのだから。
「まだないわ。子供たちは洗脳されているためにそのような証言すらできない状態よ」
「洗脳されていると断言する根拠はなんですか?」
「自分達が受けるべき当然の恩恵を拒むから」
「それは根拠ではありません」
本当に頭が痛い。
「殿下と彼らの住む世界は違います。それ故に価値観も違うのです。ご自身の価値を一方的に押し付けることは慈悲でも優しさでもありません。傲慢というんですよ、そういうのを」
「なっ。私は傲慢さから言っているのではないわ。子供を働かせていなんて可哀想だと思わないの。ただでさえ、親を亡くして可哀想なのに、少しの慈悲も与えないなんて最低な行為よ」
王女でなければその頬を何度も引っ叩いていただろう。
ああ、思わず殺気が漏れてしまった。びくりと体を震わせ、青ざめる王女を見て私は自分を落ち着かせるために詰まりそうになっていた息を吐く。
「同情で腹が膨れますか?親がいないというだけで誰もが無条件に食事や衣服、さらには寝るところまで与え続けてくれると?その余裕がある裕福な暮らしの人間なら可能でしょう。その者が死ぬまでそうすればいい。与えられることに慣れた人間は生き甲斐を失くし、あなたの思う通りに動くペットとなってくれるでしょう。その者のように」
私は王女が連れている顔の整った青年に目を向ける。自然と王女の目もその青年に向いた。
「自分好みの服と装飾で飾り立て、自らの慈悲を他人に見せつけるように連れ歩けばいい」
「ルーは違うわっ!そんな目で見るなんて最低よ」
「お父様に言い付けるのならどうぞ、ご勝手に。あなたの父君がそのスラム出身者を弟だと言っていることにどのような感情を抱いているかは知りませんが、本当にご自分たちの関係が姉弟だと思っているのならそれ相応の扱いをすべきですね。少なくとも私には深き絆で結ばれた姉弟には見えません。ただの飼い主とペットです。陛下との取り決めがあります故、半年間はあなたの横暴を我慢しましょう。それにより被る被害は全て王家で補填してくれると最初に言質をとっておりますし、その契約書もあります」
怒りで震える王女に私はその契約書を見せつけた。
「スタッフの解雇は許可しましょう。その代わり、解雇されたスタッフの生活を半年間補償してもらいます。解雇された者は半年間の休暇を与えられたと思って過ごしてください。半年後には孤児院のスタッフとして戻ってもらいます。院長、皆様もよろしいですね」
スタッフは「それなら」と渋々だが承諾してくれた。
「虐待をしたスタッフを戻すなんて」と王女は一人不満を露わにしている。
「虐待の事実はありません。それと勘違いをなされないように。あなたはあくまで半年間、孤児院で運営の勉強をする身であって、領主代行でも院長代行でもありません。雇用権は院長もしくは私にあります。院長、面倒をかけますが半年間よろしくお願いします」
「はい」
「それと、必ずその日の報告を上げるように」
「かしこまりました」
初日からこれなら先が思いやられるわね。
エリックに仕事の一部を任せておいて良かった。でないと、本当に過労死していたかも。
『エルダに負担させればいい』
なんてことを平気で言う馬鹿のせいで。
・・・・・・戦争に備えておこうかしら。