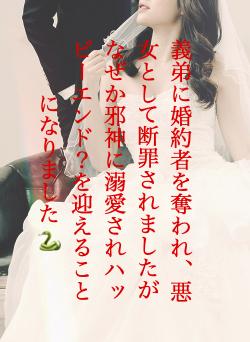どうして信じられたのだろう。
どうして疑わなかったのだろう。
当たり前だった日常は陛下の一言であんなにも簡単に崩れ去ったのに。
毎日たくさんの死を見てきた。
数えきれないほどの命を奪っていった。
血が固まって服も肌もカピカピになった。
想像もできなかった日々が日常と化していった。
そんな日々を送っていたにも関わらず私は何一つ疑わなかった。信じていた。帰るべき故郷が今も変わらずに存続していると。
◇◇◇
補給物資を届けるために使う橋に敵が爆弾を仕掛けていた。私は木の陰に隠れてライフルを構える。
引き金を引くとスコープ越しに見えていた人間がまるでネジが切れたブリキのおもちゃのように川に落ちて行った。
まずは一人、二人、三人。引き金を引くごとに敵は倒れていく。逃げていく敵も倒れる味方の姿に戸惑い、立ちすくむ敵も関係なく。
「さすだな、嬢ちゃん」
木の下から同じ隊の隊員が声をかけてきた。
「嬢ちゃん」とは私のことだ。隊の中で唯一の子供だからだ。本当のことだから呼ばれても何とも思わない。
「最初の頃は銃火器を持ったこともない場違いなお嬢様だったのに、今やぁ、隊一番の名手とはな」
どんな過酷な状況下でも人間は慣れる生き物だ。生存本能ゆえか、人の強さゆえか分からないが、直ぐに死にぬと思った命は今のところをまだ残っている。
人を殺すことに忌避感もない。
ただ引き金を引く度に心が冷たく凍っているように感じる。
「これで橋は大丈夫だな。戻ろう、嬢ちゃん。戻って昼飯だ」
「ああ」
アジトに戻ると既に食事が始まっていた。
「お前ら、俺と嬢ちゃんだけ働かせおいて。ちったぁ待ってろよな」
「悪い悪い」
「ほら」と言って私にご飯を持ってきたのは唯一の大人の女性であり我らが隊長だ。燃えるような赤い髪に黄緑色の目をしている。
顔は整っているが二の腕は男の太もも二つ分の太さで、胸はほぼ筋肉で柔らかさはゼロ。だからか、あまり女性扱いはされていない。
「どうだった」
私は近くの石に腰かけて食事を始める。
伯爵令嬢だった時は考えられなかった。地面に直に座って食事なんて。しかも、具が殆ど入っていない上に味がかなり薄い。食料が足りていないのだ。
「橋に仕掛けられた爆弾は全部で十個。タイマー式だったけど、リモコンで操作も可能なものだった。全て解除して持ち帰った」
「そうか。奴さんはまだまだ武器に余力がありそうだな」
「向こうは魔鉱石の鉱山があるから、困らないだろう」
こんな話し方をしているのを知ったらお父様もお母様も卒倒するだろうな。
「だんだん、国から送られてくる魔鉱石の数が少なくなっている。食料も足りてない。隊長、このままではいずれ尽きてしまう」
みんな口には出さないが、不安はどことなく漂っている。
恐らくこの戦線は負ける。
「嬢ちゃん、私は傭兵だからたくさんの戦場を見てきた。そこには多くの子供がいた。嬢ちゃんと同じように兵士として戦い、そして死んでいった。私らよりもずっと若い子たちが。武器の使い方も知らない子供だったろうに。私が知っている中でも嬢ちゃんはもっている方だ。こんなクソみたいな場所でそれを幸福だと言うことはできないが、それでも私は嬢ちゃんが生き残ることを願っているよ。戦争が終わって、平和になった国で、生きて幸せになることを」
そう言って隊長は私の頭を撫でた。分厚くて、ごつごつした大きな手だった。私の知っている女性の手とは程遠い。それは武器を持ち戦い続けた戦士の手だった。
どうして疑わなかったのだろう。
当たり前だった日常は陛下の一言であんなにも簡単に崩れ去ったのに。
毎日たくさんの死を見てきた。
数えきれないほどの命を奪っていった。
血が固まって服も肌もカピカピになった。
想像もできなかった日々が日常と化していった。
そんな日々を送っていたにも関わらず私は何一つ疑わなかった。信じていた。帰るべき故郷が今も変わらずに存続していると。
◇◇◇
補給物資を届けるために使う橋に敵が爆弾を仕掛けていた。私は木の陰に隠れてライフルを構える。
引き金を引くとスコープ越しに見えていた人間がまるでネジが切れたブリキのおもちゃのように川に落ちて行った。
まずは一人、二人、三人。引き金を引くごとに敵は倒れていく。逃げていく敵も倒れる味方の姿に戸惑い、立ちすくむ敵も関係なく。
「さすだな、嬢ちゃん」
木の下から同じ隊の隊員が声をかけてきた。
「嬢ちゃん」とは私のことだ。隊の中で唯一の子供だからだ。本当のことだから呼ばれても何とも思わない。
「最初の頃は銃火器を持ったこともない場違いなお嬢様だったのに、今やぁ、隊一番の名手とはな」
どんな過酷な状況下でも人間は慣れる生き物だ。生存本能ゆえか、人の強さゆえか分からないが、直ぐに死にぬと思った命は今のところをまだ残っている。
人を殺すことに忌避感もない。
ただ引き金を引く度に心が冷たく凍っているように感じる。
「これで橋は大丈夫だな。戻ろう、嬢ちゃん。戻って昼飯だ」
「ああ」
アジトに戻ると既に食事が始まっていた。
「お前ら、俺と嬢ちゃんだけ働かせおいて。ちったぁ待ってろよな」
「悪い悪い」
「ほら」と言って私にご飯を持ってきたのは唯一の大人の女性であり我らが隊長だ。燃えるような赤い髪に黄緑色の目をしている。
顔は整っているが二の腕は男の太もも二つ分の太さで、胸はほぼ筋肉で柔らかさはゼロ。だからか、あまり女性扱いはされていない。
「どうだった」
私は近くの石に腰かけて食事を始める。
伯爵令嬢だった時は考えられなかった。地面に直に座って食事なんて。しかも、具が殆ど入っていない上に味がかなり薄い。食料が足りていないのだ。
「橋に仕掛けられた爆弾は全部で十個。タイマー式だったけど、リモコンで操作も可能なものだった。全て解除して持ち帰った」
「そうか。奴さんはまだまだ武器に余力がありそうだな」
「向こうは魔鉱石の鉱山があるから、困らないだろう」
こんな話し方をしているのを知ったらお父様もお母様も卒倒するだろうな。
「だんだん、国から送られてくる魔鉱石の数が少なくなっている。食料も足りてない。隊長、このままではいずれ尽きてしまう」
みんな口には出さないが、不安はどことなく漂っている。
恐らくこの戦線は負ける。
「嬢ちゃん、私は傭兵だからたくさんの戦場を見てきた。そこには多くの子供がいた。嬢ちゃんと同じように兵士として戦い、そして死んでいった。私らよりもずっと若い子たちが。武器の使い方も知らない子供だったろうに。私が知っている中でも嬢ちゃんはもっている方だ。こんなクソみたいな場所でそれを幸福だと言うことはできないが、それでも私は嬢ちゃんが生き残ることを願っているよ。戦争が終わって、平和になった国で、生きて幸せになることを」
そう言って隊長は私の頭を撫でた。分厚くて、ごつごつした大きな手だった。私の知っている女性の手とは程遠い。それは武器を持ち戦い続けた戦士の手だった。