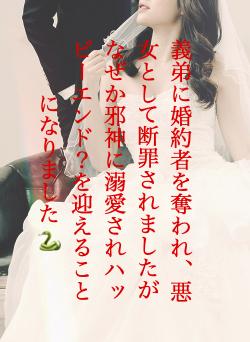戦場に行く前にまず王宮に行かなければならない。そこでルーエンブルクからお触れ通り一人、徴兵したことの証として宣誓書に署名することと死んだ時に身元が分かる為のタグを貰うのだ。
「まだほんの子供じゃない」
王の謁見の間にはたくさんの重鎮や貴族がいた。ここにいる人達は支援金や身代わりを立てて徴兵を免れた人たちなのだろう。
「ルーエンブルクは支援金を払う余裕もない程困窮しているのか。そんな貧乏人が貴族を名乗るとは世も末ですな」
「止しなさいよ。私たちと違って惨めな家なのだから」
そんな不愉快な言葉が飛び交う中で私は国の為に戦うことを宣誓した。
国の為に命をかける人間を送り出す場だとは思えないな。こんや奴らの為に今も多くの命が散らされているのか。無駄死にもいいところじゃないか。
彼らのように国を動かす人にとって私たちのようなものは同じ人ですらないのだろうな。
タグを受け取り、戦場に行く為の集合場所に向かう途中で私を呼び止める声がした。
薄桃色の髪に青い目をした人。この国でそんな容姿をしているのは一人しかいない。シーア・アダルトルート・パイデス。パイデス王国第一王女。たしか御年十六になられたとか父が言っていたな。
戦争は国民の生活にも多大な影響を及ぼしている。物価は上がり続け、物資が入らないせいで商店の棚が空になっているのも日常になっている。そんな中、宝石を多用したドレスを着ているとは。
ここだけは戦争の影が一つもないな。だから、簡単に戦争を仕掛けられるし、いつまでも続けられるのだろう。
困窮して、助けを求めにやって来る領民の姿が脳裏を横切った。目の前の無垢な少女に怒鳴りつけたい気持ちを拳を握ることで耐えた。
私は貴族令嬢として腰を曲げて頭を下げた。
「あなた、アイリス・ルーエンブルクよね」
「はい、王女殿下。王女殿下に知っていただけるとは光栄です」
「お父様に聞いたの。私とそう年齢が変わらないのに戦場に行く決意をしてくださった勇敢な令嬢がいるって」
勇敢?
そんなんじゃない。国の命令に逆らえなかっただけ。支援金を払う余裕がなかっただけ。
自分の父親が出した命令を知らないのか?或いは支援金を払うことができない貴族がいるとは思っていないのか。
「いくつ?」
「十二歳です」
「そう」
とても悲し気な顔をして王女は私の頬に触れる。
「まだ子供なのに、戦場に行くのね」
まるで他人事だ。彼女にとっては舞台越しの出来事なのかもしれない。ここまで戦火は届かない。砲撃も聞こえない。だから仕方がないのかもしれない。自分たちが決めて、始めたことでも。彼女には関係ない。彼女が決めたことではない。彼女の父親やその側近たちが決めたことだから。
「そうだ!今からね、お友達とティーパーティーをするのね。あなたも参加しない?戦場に行く前に。餞代わりに、どうかしら?」
「・・・・・有難い申し出ですが、時間がありませんのでご遠慮させていただきます」
「そう。残念だわ」
十六歳なら社交界デビューもしている年。それでも彼女がこうして無邪気でいられるのはそういう教育を受けているから。そういう環境にいられるから。それが不幸なのか幸福なのか私には分からない。ただ早くこの無邪気なお嬢様の前から消えたかった。
「嫌ね、あなたのような貴族の令嬢が戦場に行かなくてはならないなんて。こんな悲惨なこと早く終われば良いのに」
「・・・・・・戦場を知らない者がその悲惨さを語るのか」
「えっ」
「それでは時間がありませんので私はこれで失礼します」
「まだほんの子供じゃない」
王の謁見の間にはたくさんの重鎮や貴族がいた。ここにいる人達は支援金や身代わりを立てて徴兵を免れた人たちなのだろう。
「ルーエンブルクは支援金を払う余裕もない程困窮しているのか。そんな貧乏人が貴族を名乗るとは世も末ですな」
「止しなさいよ。私たちと違って惨めな家なのだから」
そんな不愉快な言葉が飛び交う中で私は国の為に戦うことを宣誓した。
国の為に命をかける人間を送り出す場だとは思えないな。こんや奴らの為に今も多くの命が散らされているのか。無駄死にもいいところじゃないか。
彼らのように国を動かす人にとって私たちのようなものは同じ人ですらないのだろうな。
タグを受け取り、戦場に行く為の集合場所に向かう途中で私を呼び止める声がした。
薄桃色の髪に青い目をした人。この国でそんな容姿をしているのは一人しかいない。シーア・アダルトルート・パイデス。パイデス王国第一王女。たしか御年十六になられたとか父が言っていたな。
戦争は国民の生活にも多大な影響を及ぼしている。物価は上がり続け、物資が入らないせいで商店の棚が空になっているのも日常になっている。そんな中、宝石を多用したドレスを着ているとは。
ここだけは戦争の影が一つもないな。だから、簡単に戦争を仕掛けられるし、いつまでも続けられるのだろう。
困窮して、助けを求めにやって来る領民の姿が脳裏を横切った。目の前の無垢な少女に怒鳴りつけたい気持ちを拳を握ることで耐えた。
私は貴族令嬢として腰を曲げて頭を下げた。
「あなた、アイリス・ルーエンブルクよね」
「はい、王女殿下。王女殿下に知っていただけるとは光栄です」
「お父様に聞いたの。私とそう年齢が変わらないのに戦場に行く決意をしてくださった勇敢な令嬢がいるって」
勇敢?
そんなんじゃない。国の命令に逆らえなかっただけ。支援金を払う余裕がなかっただけ。
自分の父親が出した命令を知らないのか?或いは支援金を払うことができない貴族がいるとは思っていないのか。
「いくつ?」
「十二歳です」
「そう」
とても悲し気な顔をして王女は私の頬に触れる。
「まだ子供なのに、戦場に行くのね」
まるで他人事だ。彼女にとっては舞台越しの出来事なのかもしれない。ここまで戦火は届かない。砲撃も聞こえない。だから仕方がないのかもしれない。自分たちが決めて、始めたことでも。彼女には関係ない。彼女が決めたことではない。彼女の父親やその側近たちが決めたことだから。
「そうだ!今からね、お友達とティーパーティーをするのね。あなたも参加しない?戦場に行く前に。餞代わりに、どうかしら?」
「・・・・・有難い申し出ですが、時間がありませんのでご遠慮させていただきます」
「そう。残念だわ」
十六歳なら社交界デビューもしている年。それでも彼女がこうして無邪気でいられるのはそういう教育を受けているから。そういう環境にいられるから。それが不幸なのか幸福なのか私には分からない。ただ早くこの無邪気なお嬢様の前から消えたかった。
「嫌ね、あなたのような貴族の令嬢が戦場に行かなくてはならないなんて。こんな悲惨なこと早く終われば良いのに」
「・・・・・・戦場を知らない者がその悲惨さを語るのか」
「えっ」
「それでは時間がありませんので私はこれで失礼します」