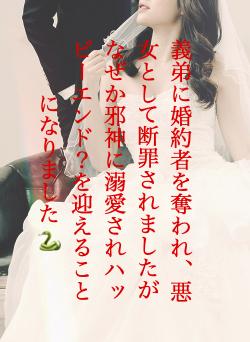「アイリス」
やっと解放されたと思ったら王女に見つかってしまった。夜会って本当に面倒だな。だからって姿を隠すわけにはいかない。一番、被害の大きかった領地の領主が夜会で姿を見せないのは様々な憶測を生んでしまうからだ。
「久しぶりね、アイリス。会いたかったわ」
大勢の取り巻きを連れてやって来た王女はとても友好的な笑みを浮かべる。
「お久しぶりです、王女殿下。たった数回お会いしただけの私のことを覚えてくださっているなんて光栄ですわ」
王女を通して私と親しくなろうとしていた人が取り巻きの中に数人ほどいたようだ。
普段から私のことを友達扱いしている王女に乗せられた彼女たちは私の言葉を正しく理解したようだ。当てが外れたという顔をしている。
「まぁ、当然ですわ。あなたは有名人ですもの。あなたのお店に私も興味があって侍女に頼んで購入してもらったのよ。とても美味しかったわ」
私の言葉をサラッと流した王女はとても楽しそうに会話を続ける。
「せっかくだし、御用達になってみない?」
王家御用達。誰もが喉から手が出るほど欲しがる称号。本来ならこんなふうに気軽に出せるものではない。王族の口に入れるものは厳選されたものだけなのだから。いくら公爵家が経営している店であっても、身元が確かだから出せるものでもない。だって、貴族が王族を絶対に暗殺しないという理由はないのだから。
「とても光栄な話ではありますが、私には身に余る称号です」
「あら、そんなことないわ。私とあなたの仲じゃない」
あくまでも自分たちは友人だと言いたいのか。友人だからって王家御用達になれるわけじゃないけど。
「私は自分の身の丈を知っています。それに公爵になったばかりの若輩者。いらぬ恨みを買いたくはありません。なので申し訳ありませんが、その栄誉を受け取ることはできません」
「あら、そうなの。残念だわ」
王女は私よりも四つ上のはず。だけど、頬に手を置いてため息をつく仕草や表情がまるで子供のようだ。
「楽しそうな話をしておりますね、私も混ぜていただくことは可能でしょうか」
片側に流した灰色の髪と瞳をした端正な顔立ちの男性に声をかけられ、王女の取り巻きたちは色めきたった。
ミラン・マグノイヤー・エルダ王太子殿下。
先ほど国王に挨拶をしている姿を多くの貴族が見ているので彼が誰か分からない人はいないだろう。
それとなく周囲に目を向けると、王太子に敵意を向ける者と王女の取り巻きたちのように色めきだっている令嬢と面白くなさそうな顔をしている男性貴族の三種類がいた。
敵意を向けているのは家族の誰かが戦場に行って亡くなったり領地が戦火に焼かれた人たちでそれ以外は戦争とは無縁の場所にいた人たちだろう。
一応、戦争とは無縁の場所で守られていたはずの王女が王太子に対して眉を顰めているのは彼女が王族だからだろうか。でも尚更、表情に出すべきではないと思うけど。
「お断りしますわ、私はあなたと親しくなるつもりありませんもの」
王女の言葉に取り巻きの令嬢は血の気がひいた顔をし、巻き込まれないようにさりげなく王女から距離をとる。王女の無礼な態度に対して王太子は声をかけて来た時と同じ友好的な笑みを浮かべている。
でもその笑顔の裏でどのような感情を隠しているか分からない怖さがある。それは彼の後ろに控えている側近にも言えることだった。
王女は分からないのだろうか。自分の言動一つで再び戦争が始まる可能性があるということが。次は持ち堪えられない。
「そうですか、それは残念です。けれどお気になさらないでください。私は女公爵に興味があったので声をかけただけですので」
私?まぁ、私の領地に訪問する予定もあるからおかしくはないか。
「女公爵、お話をしたいことがあるのですがよろしいですか?」
「は「ダメよっ!」」
私の返事を遮って王女は声を荒げ、私の腕を抱きしめながら王太子を睨みつける。流石に王太子から笑顔が消えた。
私は嫌な汗がずっと流れっぱなしだった。
王女は本当に戦争を再開させる気だろうか。あんな、失うばかりで何も得られない虚しい戦いを。それに今度は持ち堪えられない。間違いなくパイデスは滅びるのに。
「よくもアイリスの前に顔を出せたわね。自分たちが何をしたか自覚がないの」
何を言うつもり?止めて。
「あなたたちのせいでアイリスは両親を失ったのよ。あなたたちのせいで、どれだけアイリスが苦しんだか少しは考えたことがあるの」
「王女殿下っ!」
どうしてあなたがわけ知り顔で私のことを言うの。
何も知らないくせに。守られていたくせに。戦争中にティーパーティーなんか開いて、戦火に散っていく命を気にかけたことなんてなかったのに。
「もう、お止めください。皆が驚いています。王太子殿下、非礼をお詫びします。申し訳ありません。どうか、お許し頂けないでしょうか」
「アイリス、何をしているの。頭を上げて」
私がどうして王太子に頭を下げているか理解できない王女はとても慌てていた。でも、そんなことはどうでもいい。今は正に一寸先は闇という状態だ。踏み間違えれば奈落へ突き落とされる。
「頭を上げなさい、女公爵。私は夜会に無知な子供が紛れていたからといって腹を立てるほど狭量ではないよ。おいで、話をしよう」
「はい」
私は王女に掴まれていた腕をサッととって現状理解できずにフリーズしてしまった王女が回復する前に王太子とその場を離れた。
やっと解放されたと思ったら王女に見つかってしまった。夜会って本当に面倒だな。だからって姿を隠すわけにはいかない。一番、被害の大きかった領地の領主が夜会で姿を見せないのは様々な憶測を生んでしまうからだ。
「久しぶりね、アイリス。会いたかったわ」
大勢の取り巻きを連れてやって来た王女はとても友好的な笑みを浮かべる。
「お久しぶりです、王女殿下。たった数回お会いしただけの私のことを覚えてくださっているなんて光栄ですわ」
王女を通して私と親しくなろうとしていた人が取り巻きの中に数人ほどいたようだ。
普段から私のことを友達扱いしている王女に乗せられた彼女たちは私の言葉を正しく理解したようだ。当てが外れたという顔をしている。
「まぁ、当然ですわ。あなたは有名人ですもの。あなたのお店に私も興味があって侍女に頼んで購入してもらったのよ。とても美味しかったわ」
私の言葉をサラッと流した王女はとても楽しそうに会話を続ける。
「せっかくだし、御用達になってみない?」
王家御用達。誰もが喉から手が出るほど欲しがる称号。本来ならこんなふうに気軽に出せるものではない。王族の口に入れるものは厳選されたものだけなのだから。いくら公爵家が経営している店であっても、身元が確かだから出せるものでもない。だって、貴族が王族を絶対に暗殺しないという理由はないのだから。
「とても光栄な話ではありますが、私には身に余る称号です」
「あら、そんなことないわ。私とあなたの仲じゃない」
あくまでも自分たちは友人だと言いたいのか。友人だからって王家御用達になれるわけじゃないけど。
「私は自分の身の丈を知っています。それに公爵になったばかりの若輩者。いらぬ恨みを買いたくはありません。なので申し訳ありませんが、その栄誉を受け取ることはできません」
「あら、そうなの。残念だわ」
王女は私よりも四つ上のはず。だけど、頬に手を置いてため息をつく仕草や表情がまるで子供のようだ。
「楽しそうな話をしておりますね、私も混ぜていただくことは可能でしょうか」
片側に流した灰色の髪と瞳をした端正な顔立ちの男性に声をかけられ、王女の取り巻きたちは色めきたった。
ミラン・マグノイヤー・エルダ王太子殿下。
先ほど国王に挨拶をしている姿を多くの貴族が見ているので彼が誰か分からない人はいないだろう。
それとなく周囲に目を向けると、王太子に敵意を向ける者と王女の取り巻きたちのように色めきだっている令嬢と面白くなさそうな顔をしている男性貴族の三種類がいた。
敵意を向けているのは家族の誰かが戦場に行って亡くなったり領地が戦火に焼かれた人たちでそれ以外は戦争とは無縁の場所にいた人たちだろう。
一応、戦争とは無縁の場所で守られていたはずの王女が王太子に対して眉を顰めているのは彼女が王族だからだろうか。でも尚更、表情に出すべきではないと思うけど。
「お断りしますわ、私はあなたと親しくなるつもりありませんもの」
王女の言葉に取り巻きの令嬢は血の気がひいた顔をし、巻き込まれないようにさりげなく王女から距離をとる。王女の無礼な態度に対して王太子は声をかけて来た時と同じ友好的な笑みを浮かべている。
でもその笑顔の裏でどのような感情を隠しているか分からない怖さがある。それは彼の後ろに控えている側近にも言えることだった。
王女は分からないのだろうか。自分の言動一つで再び戦争が始まる可能性があるということが。次は持ち堪えられない。
「そうですか、それは残念です。けれどお気になさらないでください。私は女公爵に興味があったので声をかけただけですので」
私?まぁ、私の領地に訪問する予定もあるからおかしくはないか。
「女公爵、お話をしたいことがあるのですがよろしいですか?」
「は「ダメよっ!」」
私の返事を遮って王女は声を荒げ、私の腕を抱きしめながら王太子を睨みつける。流石に王太子から笑顔が消えた。
私は嫌な汗がずっと流れっぱなしだった。
王女は本当に戦争を再開させる気だろうか。あんな、失うばかりで何も得られない虚しい戦いを。それに今度は持ち堪えられない。間違いなくパイデスは滅びるのに。
「よくもアイリスの前に顔を出せたわね。自分たちが何をしたか自覚がないの」
何を言うつもり?止めて。
「あなたたちのせいでアイリスは両親を失ったのよ。あなたたちのせいで、どれだけアイリスが苦しんだか少しは考えたことがあるの」
「王女殿下っ!」
どうしてあなたがわけ知り顔で私のことを言うの。
何も知らないくせに。守られていたくせに。戦争中にティーパーティーなんか開いて、戦火に散っていく命を気にかけたことなんてなかったのに。
「もう、お止めください。皆が驚いています。王太子殿下、非礼をお詫びします。申し訳ありません。どうか、お許し頂けないでしょうか」
「アイリス、何をしているの。頭を上げて」
私がどうして王太子に頭を下げているか理解できない王女はとても慌てていた。でも、そんなことはどうでもいい。今は正に一寸先は闇という状態だ。踏み間違えれば奈落へ突き落とされる。
「頭を上げなさい、女公爵。私は夜会に無知な子供が紛れていたからといって腹を立てるほど狭量ではないよ。おいで、話をしよう」
「はい」
私は王女に掴まれていた腕をサッととって現状理解できずにフリーズしてしまった王女が回復する前に王太子とその場を離れた。