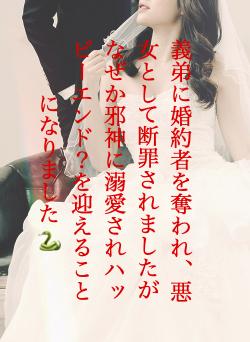王都に開いたお店は盛況で慌ただしい毎日を過ごしているとあっという間にエルダの王太子が来る日になった。
その間ずっと王女から手紙が送られ続けていた。私が開いた店が盛況になればなるほどかなり執拗になったが、領の再建で忙しいとずっと逃げ続けてきた。
でも今夜開催されるパーティーはエルダの王太子であるミラン・マグノイヤー・エルダ殿下を歓迎するためのものなので欠席するわけにはいかない。そこでシーラ王女殿下に嫌でも会うことになるだろう。そう思うと気が重い。
「お前が着飾る姿を見るのは久しぶりだな」
「そういうエリックもね」
女性が夜会に出席する時は男性にエスコートをしてもらうのがマナーだ。エスコートする男性は婚約者か身内。十二歳から戦場にいた私に婚約者はいない。だから今夜はエリックにエスコートをしてもらうことになった。
「軍服よりも、ずっと似合うよ」
震える声でそうエリックは囁いた。まるで「叔父さんも今のアイリスを見たかったと思うよ」と言っているみたいだった。
「私もお父様に見せたかった」という代わりに微笑んだ。
失われた未来。もう二度と来ることのない未来に私たちはいつだって思いを馳せる。まるでそうすることで戻ってくるのではないかと淡い期待を抱いているみたいに。けれどそんなことはあり得ない。それはお互いに分かっていることだからいつだって言葉を閉ざすのだ。
「行こう」
「ええ」
◇◇◇
「まぁ、ルーエンブルク女公爵ではありませんか。お久しぶりですわね」
少しふくよかな五十代の女性が話しかけてきた。かなりきつい香水を振り撒いているせいで鼻が曲がりそうだ。
先ほどからいろんな人が親しげに話しかけてくるけど久しぶりと思えるほど親しい人間は一人もいない。
「女公爵ももっと積極的に夜会にお顔を見せてくださればいいのに。みんな、寂しがっていましたわよ」
「申し訳ありません。何分、領地のことで忙しく」
「あら」と言って女性は扇子で口元を隠す。
「そういうのは男に任せればいいのですよ。女公爵がすることではないでしょ」
つまり、女の身で領地の仕事をするべきではないと?
「そうですわ、女公爵には私の息子を紹介したいと思っていたんです。女公爵も独り身では何かと淋しいでしょう」
領地経営は自分の息子に任せて、お前はお飾りの公爵でいろと言いたいのね。
さっきからそういう連中ばかり。まるで私が間違っているみたいに、私の存在そのものを否定してくる。ただ、私が始めた商売の利益が欲しいだけのくせに。
「それは伯爵夫人に気にしていただくことではございません。失礼します」
「無礼だ」と叫ぶ女性から足速に離れる。
婚約者という存在に興味がないわけではない。戦争が起きなければ私も普通の令嬢のように婚約者がいただろうし、領地のことは婚約者に任せていただろう。
婚約者と戯れる令嬢たちに目を向ける。
彼女たちが輝いて見えた。婚約者に恋をしているのだろう。
私もいつか、彼女たちのように輝けるだろうか。そう考えているとふと血まみれの自分の手が見えた。
今現在は地に染まっているわけではないから血は幻覚だ。でも時折見えるのだ。自分が殺した人間の顔や死んでいった仲間の顔、それに血まみれの自分の手が。まるで幸せになるのは許さないというように。私の罪を自覚させる。
「・・・・・分かってるよ」
私はパーティーを楽しんでいる令嬢たちに背を向ける。
私があちら側に行くことはない。それは失われた未来だ。いつまでもそんなものに縋っているわけにはいかない。
その間ずっと王女から手紙が送られ続けていた。私が開いた店が盛況になればなるほどかなり執拗になったが、領の再建で忙しいとずっと逃げ続けてきた。
でも今夜開催されるパーティーはエルダの王太子であるミラン・マグノイヤー・エルダ殿下を歓迎するためのものなので欠席するわけにはいかない。そこでシーラ王女殿下に嫌でも会うことになるだろう。そう思うと気が重い。
「お前が着飾る姿を見るのは久しぶりだな」
「そういうエリックもね」
女性が夜会に出席する時は男性にエスコートをしてもらうのがマナーだ。エスコートする男性は婚約者か身内。十二歳から戦場にいた私に婚約者はいない。だから今夜はエリックにエスコートをしてもらうことになった。
「軍服よりも、ずっと似合うよ」
震える声でそうエリックは囁いた。まるで「叔父さんも今のアイリスを見たかったと思うよ」と言っているみたいだった。
「私もお父様に見せたかった」という代わりに微笑んだ。
失われた未来。もう二度と来ることのない未来に私たちはいつだって思いを馳せる。まるでそうすることで戻ってくるのではないかと淡い期待を抱いているみたいに。けれどそんなことはあり得ない。それはお互いに分かっていることだからいつだって言葉を閉ざすのだ。
「行こう」
「ええ」
◇◇◇
「まぁ、ルーエンブルク女公爵ではありませんか。お久しぶりですわね」
少しふくよかな五十代の女性が話しかけてきた。かなりきつい香水を振り撒いているせいで鼻が曲がりそうだ。
先ほどからいろんな人が親しげに話しかけてくるけど久しぶりと思えるほど親しい人間は一人もいない。
「女公爵ももっと積極的に夜会にお顔を見せてくださればいいのに。みんな、寂しがっていましたわよ」
「申し訳ありません。何分、領地のことで忙しく」
「あら」と言って女性は扇子で口元を隠す。
「そういうのは男に任せればいいのですよ。女公爵がすることではないでしょ」
つまり、女の身で領地の仕事をするべきではないと?
「そうですわ、女公爵には私の息子を紹介したいと思っていたんです。女公爵も独り身では何かと淋しいでしょう」
領地経営は自分の息子に任せて、お前はお飾りの公爵でいろと言いたいのね。
さっきからそういう連中ばかり。まるで私が間違っているみたいに、私の存在そのものを否定してくる。ただ、私が始めた商売の利益が欲しいだけのくせに。
「それは伯爵夫人に気にしていただくことではございません。失礼します」
「無礼だ」と叫ぶ女性から足速に離れる。
婚約者という存在に興味がないわけではない。戦争が起きなければ私も普通の令嬢のように婚約者がいただろうし、領地のことは婚約者に任せていただろう。
婚約者と戯れる令嬢たちに目を向ける。
彼女たちが輝いて見えた。婚約者に恋をしているのだろう。
私もいつか、彼女たちのように輝けるだろうか。そう考えているとふと血まみれの自分の手が見えた。
今現在は地に染まっているわけではないから血は幻覚だ。でも時折見えるのだ。自分が殺した人間の顔や死んでいった仲間の顔、それに血まみれの自分の手が。まるで幸せになるのは許さないというように。私の罪を自覚させる。
「・・・・・分かってるよ」
私はパーティーを楽しんでいる令嬢たちに背を向ける。
私があちら側に行くことはない。それは失われた未来だ。いつまでもそんなものに縋っているわけにはいかない。