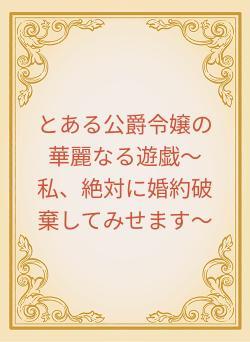み、見透かされている。
あまりにピタリと当てられてしまって、思わず笑顔が引きつった。
「そ、そんなこと……あるかもだけど…」
「でしょ?せっかくの日曜日なのにもったいないし。ほら、食べたら行くよ。食器直したら出てきて」
「う、うん。わかった…!」
最後のひとくちのパンを口に頬張り、コーヒーで流し込んだ私は急いで食器を片付ける。
「ごめん。おまたせしました」
すでにカフェの外に出ていた充希くんは私が出てくると、パーカーのポケットから鍵を取り出し、戸締まりをした。
天気は快晴。
気温も程よく出かけるにはちょうど良い気候だ。
私と充希くんは近くのバス停からバスを乗り継ぎ、ショッピングモールが立ち並ぶ繁華街までやってくる。
「日曜日だから人多いね…。そうだ、充希くん…いつもどこで服を…ってあれ?」
そう問いかけ、ちらりと横を見るとさっきまで近くにいたはずの充希くんの姿が消えていた。
あれ?充希くん?