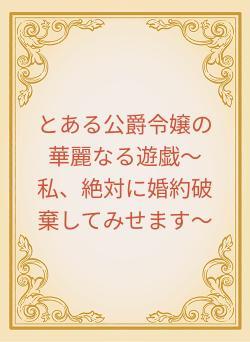「…え?み、充希くん!?」
「ッ〜、急に開けないでよ。頭打ったじゃん…!」
半分開いた扉の隙間からおそるおそる外を確認すると、そこにはドアによりかかって頭を押さえる充希くんの姿が。
若干涙目になりながら私をジトッとした目で見つめる彼に私は慌ててドアの隙間から声をかけた。
「ゴ、ゴメンね…!痛かったでしょ」
「ハァ…。いいよ、こんなところにいた僕も悪かったし…それより…」
サッと立ち上がり、充希くんは部屋のドアをゆっくり開く。
そして、私に向かって顔を近づけてきた。
…へ?な、なに??
突然、キレイな顔が近づいてくるものだから驚いて私は数歩後ずさる。
「動かないで」
ピタッ。
充希くんの言葉にカチンと体が固まってしまった。
ちょっと!ち、近いってば〜!
心のなかでそんな悲鳴をあげながら、不謹慎にもドキドキと高鳴る鼓動と格闘していると。
「あぁ〜、やっぱりかなり目腫れてるじゃん。季里、昨日泣いてかなり目擦ったでしょ?顔もむくんでるし…」
ヒヤッとした手の温度を頬に感じ私は目を丸くする。