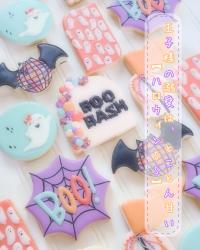それ、本当に私の事を言ってるのかな…。
もしそうだとしたら、私を過大評価しすぎてるよ。
自分がそんなふうに言われるような人間だとは到底思えなくて、思わず否定したくなってしまう。
その時、廿楽くんに両手をぎゅっと手を握られた。
「そうだよ。学校に来ることも授業を受けるのも…心優がいるって思うだけで頑張れた。なんなら、最近は家でも少し寝れるようになってきたし」
「っ…それ、ほんとう?」
私が廿楽くんを救えてるって…そう受け取っていいの…?
「うん。じゃないと僕、あんなに授業受けれてないよ?」
言葉では表現できない気持ちが、胸いっぱいに広がっていく。
知らないところで廿楽くんの助けになっていたことが、嬉しくて嬉しくてたまらないんだ。
「今日休んじゃったのは…昨日遊園地で、寝ぼけて心優に言ったことが原因」
『…どーせ僕は、なにも持ってないから…』