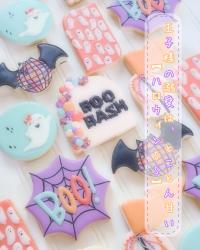そのうちの一人が廿楽くんのことを触って、頬を赤らめていた。
廿楽くんは無表情で何も考えていなさそうだけど、見ているこちら側としては良い気分になる光景ではない。
…彼女でもない私が入っていっていいの?
でも、ずっとこうしているわけにもいかないし…。
「あっ、心優ちゃ〜ん!こっちこっち…!」
立ち尽くしている私の名前を呼んだのは、明楽先輩だった。
「ってわけで、可愛い連れが来たんで行きますね。廿楽くんも行こ」
「言われなくても行くし」
ポカーンとする3人組を素通りして、2人は私の元に歩いてきた。
「ごめんね心優ちゃん。変な人たちに絡まれちゃってて」
「いや、私に謝る必要は…ないですから」
さっきの廿楽くんの姿がどうしても頭から離れてくれなくて、モヤモヤが晴れてくれない。
う…今の、ちょっと素っ気なかったかも。