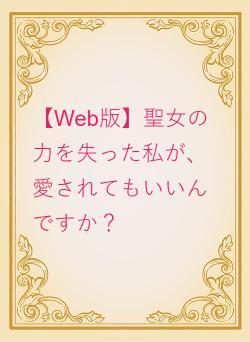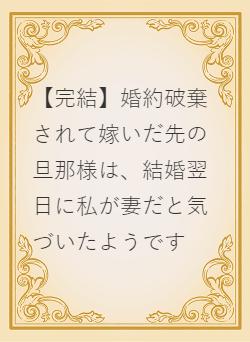エリーゼはラインハルトによる結婚宣言が終わった後、一足先に自室に戻っていた。
するりと手袋を外すと、そのままベッドに寝転がる。
(ああ……あんなに人がいたの生まれて初めてかもしれない……)
両手を大きく広げ、目を閉じて思い浮かぶのは先ほどの広場での様子。
割れんばかりの大きな拍手に胸がざわっとしてぎょっとした。
でもその中で会場の真下にいた老人たちの数人は、エリーゼをにらみつけるように見ながら、拍手の中を掻き分けて去っていった。
「私をにらみつけていた人は、この結婚を快く思っていないのかしら」
「その方々は元老院の皆様です」
ぽろっと口を突いて出た疑問に返答をしたのは、たった今入室したクルトだった。
「クルトっ!」
「申し訳ございません、ノックをしたのですが聞いていらっしゃらないようでしたので」
「ご、ごめんなさい!」
エリーゼはベッドから起き上がり、ワインレッドのドレスを急いで整える。
クルトは持ってきた水をテーブルに置くと、そっと話し始めた。
「エリーゼ様にぜひとも今夜のうちにご挨拶したいと皆様が待っていらっしゃいますが、いかがいたしますか?」
『皆様』という人物たちが、人間の貴族ではなくヴァンパイアであることをエリーゼはなんとなく察する。
【ヴァンパイアの王妃】となった彼女に気に入ってもらおうと、皆下心を持っての『挨拶』だ。
エリーゼは右手を左手に添えて擦ると、落ち着きのないように何度も息を吐く。
「ラインハルト様はどうなさっているの?」
「今は元老院の皆様との会議中です」
「その元老院?とういうのはどういう皆様なのでしょうか?」
「ヴァンパイア界で王に最も近い組織であり、何千年以上も王を支え続けた存在です」
「何千年も?」
(何千年も生き続けているということかしら? それとも世襲制とか? う~ん)
エリーゼはわからないというように小首をかしげると、クルトに質問を続ける。
「その元老院はラインハルト様をお支えする組織という感じですか?」
「……表面上はそうなります」
「表面上は?」
「基本的に元老院はなんでもできるラインハルト様に嫉妬してるしょーもないやつらよ」
そう言って扉を開いて登場したのは、短めの鮮やかな赤のドレスを着たアンナだった。
「アンナちゃん?」
「そのちゃん呼びやめてちょうだい、アンナにして」
「う、うん」
「で、あんたここで何やってるのよ」
「え?」
アンナは膝まで見えたドレスを揺らしながら、ベッドに腰かけるエリーゼに歩いていきぐっと近づく。
その目と顔は相手を吟味するような、それでいてすでに軽蔑するかのような冷たい視線も向けている。
「下で待ってるわよ、あいつら」
「はい、でもなんてお話していいかわからないし、ラインハルト様にお聞きしてから……」
「何甘っちょろいこと言ってんのよ!!」
「──っ!」
アンナはエリーゼの胸倉をつかむと、その綺麗で整った人形のように美しい顔を近づける。
「アンナっ!!」
「あんたは黙ってて!!」
クルトが制止するが、それを鋭い眼光でにらみつけて牽制する。
「あんた、ラインハルト様の妻なんでしょ?! ただの妻なんかじゃない、【ヴァンパイアの王妃】なのよ」
「……」
「世のヴァンパイアの女たちが喉から手が出るほど欲しい座にあんたは今いるの!!」
アンナの叫びが部屋中に響き渡り、その形相にエリーゼは一つも動けずに固まる。
「それに、なによりラインハルト様の……なんであんたなんか……」
「アンナ……?」
「【ヴァンパイアの王妃】になる覚悟がないなら、今すぐここから去りなさい!!」
「──っ!」
アンナはそれだけ言うとドアを荒々しく閉めて去っていく。
残されたエリーゼは、下を向いて俯き唇を噛みしめた。
「エリーゼ様、申し訳ございません。アンナが無礼なことを申しました」
「いいの、ドキっとした。ああ、そうだなって。私、なんにも自分の意思がなかったのよ。されるがまま、流されるままにラインハルト様に甘えて」
エリーゼは一息吐くと、クルトを見やって言った。
「少しの間一人にしてもらえる? 下にいる皆さんには代わりにお茶でもお願いできるかしら?」
「かしこまりました」
そう言って、ドアはゆっくりと閉じ、エリーゼはそのまま月の光を眺めた──
するりと手袋を外すと、そのままベッドに寝転がる。
(ああ……あんなに人がいたの生まれて初めてかもしれない……)
両手を大きく広げ、目を閉じて思い浮かぶのは先ほどの広場での様子。
割れんばかりの大きな拍手に胸がざわっとしてぎょっとした。
でもその中で会場の真下にいた老人たちの数人は、エリーゼをにらみつけるように見ながら、拍手の中を掻き分けて去っていった。
「私をにらみつけていた人は、この結婚を快く思っていないのかしら」
「その方々は元老院の皆様です」
ぽろっと口を突いて出た疑問に返答をしたのは、たった今入室したクルトだった。
「クルトっ!」
「申し訳ございません、ノックをしたのですが聞いていらっしゃらないようでしたので」
「ご、ごめんなさい!」
エリーゼはベッドから起き上がり、ワインレッドのドレスを急いで整える。
クルトは持ってきた水をテーブルに置くと、そっと話し始めた。
「エリーゼ様にぜひとも今夜のうちにご挨拶したいと皆様が待っていらっしゃいますが、いかがいたしますか?」
『皆様』という人物たちが、人間の貴族ではなくヴァンパイアであることをエリーゼはなんとなく察する。
【ヴァンパイアの王妃】となった彼女に気に入ってもらおうと、皆下心を持っての『挨拶』だ。
エリーゼは右手を左手に添えて擦ると、落ち着きのないように何度も息を吐く。
「ラインハルト様はどうなさっているの?」
「今は元老院の皆様との会議中です」
「その元老院?とういうのはどういう皆様なのでしょうか?」
「ヴァンパイア界で王に最も近い組織であり、何千年以上も王を支え続けた存在です」
「何千年も?」
(何千年も生き続けているということかしら? それとも世襲制とか? う~ん)
エリーゼはわからないというように小首をかしげると、クルトに質問を続ける。
「その元老院はラインハルト様をお支えする組織という感じですか?」
「……表面上はそうなります」
「表面上は?」
「基本的に元老院はなんでもできるラインハルト様に嫉妬してるしょーもないやつらよ」
そう言って扉を開いて登場したのは、短めの鮮やかな赤のドレスを着たアンナだった。
「アンナちゃん?」
「そのちゃん呼びやめてちょうだい、アンナにして」
「う、うん」
「で、あんたここで何やってるのよ」
「え?」
アンナは膝まで見えたドレスを揺らしながら、ベッドに腰かけるエリーゼに歩いていきぐっと近づく。
その目と顔は相手を吟味するような、それでいてすでに軽蔑するかのような冷たい視線も向けている。
「下で待ってるわよ、あいつら」
「はい、でもなんてお話していいかわからないし、ラインハルト様にお聞きしてから……」
「何甘っちょろいこと言ってんのよ!!」
「──っ!」
アンナはエリーゼの胸倉をつかむと、その綺麗で整った人形のように美しい顔を近づける。
「アンナっ!!」
「あんたは黙ってて!!」
クルトが制止するが、それを鋭い眼光でにらみつけて牽制する。
「あんた、ラインハルト様の妻なんでしょ?! ただの妻なんかじゃない、【ヴァンパイアの王妃】なのよ」
「……」
「世のヴァンパイアの女たちが喉から手が出るほど欲しい座にあんたは今いるの!!」
アンナの叫びが部屋中に響き渡り、その形相にエリーゼは一つも動けずに固まる。
「それに、なによりラインハルト様の……なんであんたなんか……」
「アンナ……?」
「【ヴァンパイアの王妃】になる覚悟がないなら、今すぐここから去りなさい!!」
「──っ!」
アンナはそれだけ言うとドアを荒々しく閉めて去っていく。
残されたエリーゼは、下を向いて俯き唇を噛みしめた。
「エリーゼ様、申し訳ございません。アンナが無礼なことを申しました」
「いいの、ドキっとした。ああ、そうだなって。私、なんにも自分の意思がなかったのよ。されるがまま、流されるままにラインハルト様に甘えて」
エリーゼは一息吐くと、クルトを見やって言った。
「少しの間一人にしてもらえる? 下にいる皆さんには代わりにお茶でもお願いできるかしら?」
「かしこまりました」
そう言って、ドアはゆっくりと閉じ、エリーゼはそのまま月の光を眺めた──