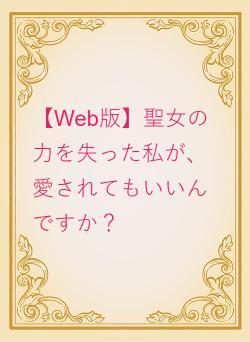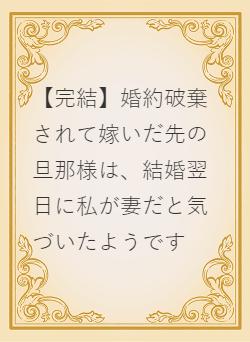ラインハルトはエリーゼの部屋のドアをゆっくり開けて姿を現す。
「気分はどうだい?」
「問題ございません、ありがとうございます」
そう言いながらラインハルトはベッドの近くにある椅子に座る。
「グラーツ公爵さ……」
「ラインハルト」
「え?」
「ラインハルトと呼んでほしい、ダメかい?」
「いえ、ぜひ呼ばせてください、ラインハルト様」
そうエリーゼが口にすると、椅子を立ち上がりベッドに腰かけるエリーゼの顔をぎゅっと自分の身体に押し当てて抱きしめる。
「ラインハルト様?」
「すまない、仕事で疲れたんだ。しばらくこうさせてくれないか?」
「私でよろしければ」
エリーゼは少しまだ戸惑いを感じながらもゆっくりと彼の背中に腕を回す。
ふんわりと優しく甘い香りが漂い、くらくらしてくる。
「そういえば、先ほどアンナちゃんとクルトくんに会いました。二人はラインハルト様にお仕えしている方なのですか?」
エリーゼの言葉を聞くと抱きしめていた腕を解放して、ゆったり優しい声で答え始める。
「アンナとクルトは僕の面倒を見てくれているんだ。けど、二人とも表向きは「伯爵令嬢」と「伯爵令息」だから自分の屋敷もあるよ」
「伯爵令嬢と伯爵令息……」
やはりここでも高い爵位を持つヴァンパイアの存在に貴族社会の理(ことわり)を感じたエリーゼは、ラインハルトに告げる。
「そんな方々が私のお世話をする方で良いのですか?」
「僕はあまり人を信用しなくてね、屋敷にも基本は僕と二人しかいなかったんだ」
「三人だけ……」
「でもエリーゼが来てくれたから、この屋敷もにぎやかになるかもね」
「そんな子供みたいにはしゃぎませんよ」
それを聞いてラインハルトはくすっと笑う。
笑われたことが不満なようにエリーゼは口をとがらせて聞く。
「何がおかしいんですか?」
「いや、君がはしゃぐ姿を想像したら面白くてね」
「だから、はしゃぎませんよ!!」
「わかったから、でもこれだけは覚えておいてほしい」
ラインハルトはエリーゼの頬をゆっくりなでると、そっと告げる。
「君は何があっても前を向いていてほしい」
「──? はい、かしこまりました」
そういってもう一度エリーゼを抱きしめると今度はそのままベッドに倒れ込んだ。
「ラインハルト様?!」
「こうするのは嫌かい?」
「いえ、そういうわけでは……でも初めてでちょっと恥ずかしいです」
「ふふ、可愛いね。初めてなんて男の前で軽々しく言うもんじゃないよ」
「え? きゃっ!」
そのままエリーゼは額にラインハルトの唇の熱を感じる。
照れて硬直してしまうエリーゼを彼は何度も髪をなでてあやすようにすると、そのまま抱きしめて眠る。
「ラインハルト様?」
静かな寝息が聞こえてくるが、エリーゼの胸は高鳴ったまま休むことはない。
(どうしよう、こんな状況で寝れないよ……)
自分の腕の中であたふたする彼女の様子を、本当は目を覚まして楽しんでいたラインハルトだった。
「気分はどうだい?」
「問題ございません、ありがとうございます」
そう言いながらラインハルトはベッドの近くにある椅子に座る。
「グラーツ公爵さ……」
「ラインハルト」
「え?」
「ラインハルトと呼んでほしい、ダメかい?」
「いえ、ぜひ呼ばせてください、ラインハルト様」
そうエリーゼが口にすると、椅子を立ち上がりベッドに腰かけるエリーゼの顔をぎゅっと自分の身体に押し当てて抱きしめる。
「ラインハルト様?」
「すまない、仕事で疲れたんだ。しばらくこうさせてくれないか?」
「私でよろしければ」
エリーゼは少しまだ戸惑いを感じながらもゆっくりと彼の背中に腕を回す。
ふんわりと優しく甘い香りが漂い、くらくらしてくる。
「そういえば、先ほどアンナちゃんとクルトくんに会いました。二人はラインハルト様にお仕えしている方なのですか?」
エリーゼの言葉を聞くと抱きしめていた腕を解放して、ゆったり優しい声で答え始める。
「アンナとクルトは僕の面倒を見てくれているんだ。けど、二人とも表向きは「伯爵令嬢」と「伯爵令息」だから自分の屋敷もあるよ」
「伯爵令嬢と伯爵令息……」
やはりここでも高い爵位を持つヴァンパイアの存在に貴族社会の理(ことわり)を感じたエリーゼは、ラインハルトに告げる。
「そんな方々が私のお世話をする方で良いのですか?」
「僕はあまり人を信用しなくてね、屋敷にも基本は僕と二人しかいなかったんだ」
「三人だけ……」
「でもエリーゼが来てくれたから、この屋敷もにぎやかになるかもね」
「そんな子供みたいにはしゃぎませんよ」
それを聞いてラインハルトはくすっと笑う。
笑われたことが不満なようにエリーゼは口をとがらせて聞く。
「何がおかしいんですか?」
「いや、君がはしゃぐ姿を想像したら面白くてね」
「だから、はしゃぎませんよ!!」
「わかったから、でもこれだけは覚えておいてほしい」
ラインハルトはエリーゼの頬をゆっくりなでると、そっと告げる。
「君は何があっても前を向いていてほしい」
「──? はい、かしこまりました」
そういってもう一度エリーゼを抱きしめると今度はそのままベッドに倒れ込んだ。
「ラインハルト様?!」
「こうするのは嫌かい?」
「いえ、そういうわけでは……でも初めてでちょっと恥ずかしいです」
「ふふ、可愛いね。初めてなんて男の前で軽々しく言うもんじゃないよ」
「え? きゃっ!」
そのままエリーゼは額にラインハルトの唇の熱を感じる。
照れて硬直してしまうエリーゼを彼は何度も髪をなでてあやすようにすると、そのまま抱きしめて眠る。
「ラインハルト様?」
静かな寝息が聞こえてくるが、エリーゼの胸は高鳴ったまま休むことはない。
(どうしよう、こんな状況で寝れないよ……)
自分の腕の中であたふたする彼女の様子を、本当は目を覚まして楽しんでいたラインハルトだった。