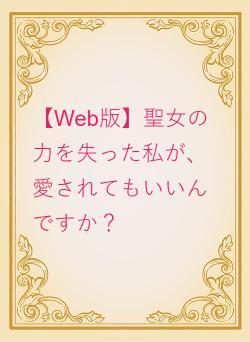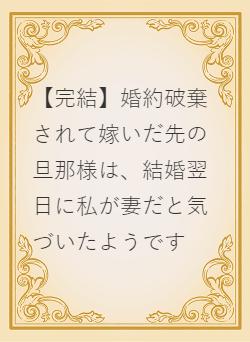エリーゼは夕方の日が沈む頃に目が覚めた。
ヴァンパイアの身体の体質により、普段から明け方前に眠って夕方に目を覚ます生活をしている。
「ん……」
ゆっくりとベッドで身体を起こすと、ぼうっとする頭を抑える。
(自分の家じゃない……きっと現実なのよね……?)
昨日の夜中にラインハルトに言われた事、そしてその光景をゆっくりと思い出していく。
(お父様もお母様も行方知れず……それに……婚約者……)
純血のヴァンパイアの王であるラインハルトの婚約者になるということは、ヴァンパイアを統べる一人になるということ。
それがエリーゼには全く実感が沸かなかった。
(どうして私なの……必ずグラーツ公爵の目的があるはず……それはなに?)
これまでの言動を振り返っても、自分に好意を寄せる理由に心当たりはなかった。
「こほっ……」
夜中から喉が渇き、グラスにあった飲み水も全て飲みほしてしまっていたエリーゼは、水をもらうために廊下に出る。
日も落ちてきたことで屋敷の中も薄暗く、右と左のどちらに向かってよいかわからなかった。
(人影もない……とりあえず右に行こうかしら……)
エリーゼは自分の直感を信じて廊下を進んでいく。
歩く途中にいくつもの部屋を見たが、キッチンのような部屋ではなかったためどんどん先に進んでいくことにした。
「何をなさっているのですか?」
「──っ!」
急に後ろから声をかけられたエリーゼは身体をびくんとさせて驚く。
声のした後ろを振り返ると、そこには金髪碧眼にすらりと細身の若い少年が立っていた。
(私と同じ年くらいの少年……お屋敷の方かしら?)
相も変わらず彼が「ヴァンパイア」であることはすぐにわかったのだが、そもそもラインハルトの屋敷にヴァンパイアがいることはなんら不思議ではない。
むしろ人間が堂々と混じって屋敷にいるほうが違和感を覚える。
エリーゼは勇気を出して少年に声をかけようとするが、その一呼吸前に少年が話し始めた。
「僕はラインハルト様にお仕えしております、クルトと申します。ラインハルト様がご不在の時はエリーゼ様のお世話を仰せつかっておりますので、なんなりとお申し付けください」
そういって軽くお辞儀をするクルトに、エリーゼもすぐさまお辞儀をして返す。
クルトはエリーゼの持っているコップを見ると、水をお持ちしますのでと告げる。
そんなやり取りをしていた最中、エリーゼが歩いてきたほうと反対側から可愛らしい女の子の声が響き渡ってきた。
「あっ! クルト! ラインハルト様からのご伝言なんだけど……」
かなり明るい声でエリーゼとクルトに近づいてきたダークブラウンの髪色に碧眼の少女は、エリーゼをみて「うげっ!」という声を出す。
「あんた……いたの……」
「え……」
(この子も私を知ってる……?)
「アンナ、ラインハルト様のご婚約者様だ。その口の利き方はよくない」
アンナと呼ばれた少女はクルトの言葉に「ふんっ!」と髪を振り乱して反論する。
「私はまだこいつがラインハルト様の妻になるだなんて認めてないからっ!!」
威勢よくそう告げると、エリーゼの前にずんと構えてエリーゼの身体を隅から隅まで観察するように見る。
「な、なにかございましたでしょうか……」
「ふんっ! なんでこんな陳腐で地味な女……どこがいいのかしら。まあいいわ、私に気安く話しかけないでよね!」
そう言ってエリーゼとクルトの間をすり抜けて、奥の廊下へと姿を消した。
「申し訳ございません。彼女はアンナ、僕の双子の姉です」
「おねえちゃん……」
「はい……少々性格に難がありまして、失礼な態度で申し訳ございません」
「いえ、大丈夫よ。私はこの家で異物みたいなものだから……」
「そんなことはございません。そういえば水でしたね。すぐにお持ちしますので、先程までいらっしゃったエリーゼ様のお部屋でお待ちいただけますでしょうか?」
「いいの? ご迷惑かけてごめんなさい」
「いえ、すぐにお持ちいたしますので」
そういってクルトはアンナが来たほうに向かっていき、エリーゼはもとの部屋に戻ることにした。
◇◆◇
あのあとすぐにクルトは水を運んでき、退室した。
(クルトくん、アンナちゃん……ラインハルト様にお仕えする方々……覚えておかないと)
そうして考えているうちにエリーゼの部屋のドアをノックする音が聞こえる。
「僕だよ、入ってもいいかい?」
「グラーツ公爵様。はい、どうぞ」
そういってドアを開けて入ってきたラインハルトは、エリーゼに優しい微笑みをかけた──
ヴァンパイアの身体の体質により、普段から明け方前に眠って夕方に目を覚ます生活をしている。
「ん……」
ゆっくりとベッドで身体を起こすと、ぼうっとする頭を抑える。
(自分の家じゃない……きっと現実なのよね……?)
昨日の夜中にラインハルトに言われた事、そしてその光景をゆっくりと思い出していく。
(お父様もお母様も行方知れず……それに……婚約者……)
純血のヴァンパイアの王であるラインハルトの婚約者になるということは、ヴァンパイアを統べる一人になるということ。
それがエリーゼには全く実感が沸かなかった。
(どうして私なの……必ずグラーツ公爵の目的があるはず……それはなに?)
これまでの言動を振り返っても、自分に好意を寄せる理由に心当たりはなかった。
「こほっ……」
夜中から喉が渇き、グラスにあった飲み水も全て飲みほしてしまっていたエリーゼは、水をもらうために廊下に出る。
日も落ちてきたことで屋敷の中も薄暗く、右と左のどちらに向かってよいかわからなかった。
(人影もない……とりあえず右に行こうかしら……)
エリーゼは自分の直感を信じて廊下を進んでいく。
歩く途中にいくつもの部屋を見たが、キッチンのような部屋ではなかったためどんどん先に進んでいくことにした。
「何をなさっているのですか?」
「──っ!」
急に後ろから声をかけられたエリーゼは身体をびくんとさせて驚く。
声のした後ろを振り返ると、そこには金髪碧眼にすらりと細身の若い少年が立っていた。
(私と同じ年くらいの少年……お屋敷の方かしら?)
相も変わらず彼が「ヴァンパイア」であることはすぐにわかったのだが、そもそもラインハルトの屋敷にヴァンパイアがいることはなんら不思議ではない。
むしろ人間が堂々と混じって屋敷にいるほうが違和感を覚える。
エリーゼは勇気を出して少年に声をかけようとするが、その一呼吸前に少年が話し始めた。
「僕はラインハルト様にお仕えしております、クルトと申します。ラインハルト様がご不在の時はエリーゼ様のお世話を仰せつかっておりますので、なんなりとお申し付けください」
そういって軽くお辞儀をするクルトに、エリーゼもすぐさまお辞儀をして返す。
クルトはエリーゼの持っているコップを見ると、水をお持ちしますのでと告げる。
そんなやり取りをしていた最中、エリーゼが歩いてきたほうと反対側から可愛らしい女の子の声が響き渡ってきた。
「あっ! クルト! ラインハルト様からのご伝言なんだけど……」
かなり明るい声でエリーゼとクルトに近づいてきたダークブラウンの髪色に碧眼の少女は、エリーゼをみて「うげっ!」という声を出す。
「あんた……いたの……」
「え……」
(この子も私を知ってる……?)
「アンナ、ラインハルト様のご婚約者様だ。その口の利き方はよくない」
アンナと呼ばれた少女はクルトの言葉に「ふんっ!」と髪を振り乱して反論する。
「私はまだこいつがラインハルト様の妻になるだなんて認めてないからっ!!」
威勢よくそう告げると、エリーゼの前にずんと構えてエリーゼの身体を隅から隅まで観察するように見る。
「な、なにかございましたでしょうか……」
「ふんっ! なんでこんな陳腐で地味な女……どこがいいのかしら。まあいいわ、私に気安く話しかけないでよね!」
そう言ってエリーゼとクルトの間をすり抜けて、奥の廊下へと姿を消した。
「申し訳ございません。彼女はアンナ、僕の双子の姉です」
「おねえちゃん……」
「はい……少々性格に難がありまして、失礼な態度で申し訳ございません」
「いえ、大丈夫よ。私はこの家で異物みたいなものだから……」
「そんなことはございません。そういえば水でしたね。すぐにお持ちしますので、先程までいらっしゃったエリーゼ様のお部屋でお待ちいただけますでしょうか?」
「いいの? ご迷惑かけてごめんなさい」
「いえ、すぐにお持ちいたしますので」
そういってクルトはアンナが来たほうに向かっていき、エリーゼはもとの部屋に戻ることにした。
◇◆◇
あのあとすぐにクルトは水を運んでき、退室した。
(クルトくん、アンナちゃん……ラインハルト様にお仕えする方々……覚えておかないと)
そうして考えているうちにエリーゼの部屋のドアをノックする音が聞こえる。
「僕だよ、入ってもいいかい?」
「グラーツ公爵様。はい、どうぞ」
そういってドアを開けて入ってきたラインハルトは、エリーゼに優しい微笑みをかけた──