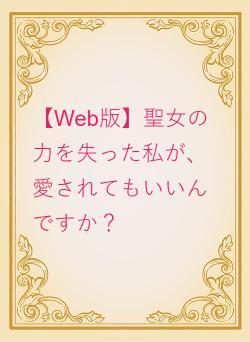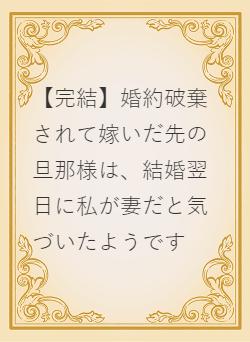「目が覚めたかい?」
エリーゼが目を覚ますと、目の前には一人の男性がいた。
ベッドに寝ていることに気づいたエリーゼは、何がどうなっているのか理解できなかった。
(私……なんでここに……それにこの方は……)
少しずつ覚醒していくエリーゼの頭は、自分の身に起こった恐ろしい出来事を思い出させる。
「──っ!」
(そうだ……私……ヴァンパイアに襲われて……)
そこまで思い出し、ようやく自分の記憶の中にある「助けてくれた人」と「目の前にいる人」が同じだということに気づく。
エリーゼはコップに水を注ぐ彼に目を遣ると、エリーゼの視線に気づいたようでコップの水を彼女に渡す。
「どうぞ」
そういってベッドの脇にある椅子に座ると静かな声で語り始める。
「僕はラインハルト・グラーツ。君はヴァンパイアに襲われた。覚えているかい?」
表情をあまり変えずに語るラインハルトに、エリーゼは緊張感を覚えた。
と同時に、その名前に聞き覚えがあり、ハッと顔をあげた。
「まさか……ラインハルト・グラーツ……公爵……」
その問いに彼は無言で小さく頷くと、同意の意を示す。
(グラーツ公爵って……ヴァンパイアの中でも特別な『純血種』を束ねる王のはず……)
エリーゼは自分の考えが信じられないというように首を何度も横に振るが、彼女自身の中にあるヴァンパイアの血が「彼は本物だ」と告げていた。
「グラーツ公爵がなぜ……」
「君をずっと見ていたからって言ったら信じるかい?」
「え……?」
「冗談だよ」
「そんなことより」とラインハルトは話を逸らして、ランセル子爵家の話をした。
「君の家は完全に燃え尽きてしまったよ」
「──っ!! お父様とお母様は……っ?!」
「残念ながら行方不明だよ」
「そんな……」
両親の行方知れずの報せを聞き、目の前が真っ暗になるエリーゼ。
その様子を可哀そうに思い、ラインハルトはエリーゼの頭を優しくなで、そっと自分の胸に引き寄せた。
「──っ!」
「心配ない、僕が君を守るから……ここにずっといるといい」
帰るところも失い、両親を失ったエリーゼに優しく寄り添うラインハルト。
そして、ゆっくりと自分の胸から離し、エリーゼの漆黒の瞳を見つめて告げる。
「僕の婚約者になってほしい」
そういってラインハルトはエリーゼの頬を優しくなでた──
エリーゼが目を覚ますと、目の前には一人の男性がいた。
ベッドに寝ていることに気づいたエリーゼは、何がどうなっているのか理解できなかった。
(私……なんでここに……それにこの方は……)
少しずつ覚醒していくエリーゼの頭は、自分の身に起こった恐ろしい出来事を思い出させる。
「──っ!」
(そうだ……私……ヴァンパイアに襲われて……)
そこまで思い出し、ようやく自分の記憶の中にある「助けてくれた人」と「目の前にいる人」が同じだということに気づく。
エリーゼはコップに水を注ぐ彼に目を遣ると、エリーゼの視線に気づいたようでコップの水を彼女に渡す。
「どうぞ」
そういってベッドの脇にある椅子に座ると静かな声で語り始める。
「僕はラインハルト・グラーツ。君はヴァンパイアに襲われた。覚えているかい?」
表情をあまり変えずに語るラインハルトに、エリーゼは緊張感を覚えた。
と同時に、その名前に聞き覚えがあり、ハッと顔をあげた。
「まさか……ラインハルト・グラーツ……公爵……」
その問いに彼は無言で小さく頷くと、同意の意を示す。
(グラーツ公爵って……ヴァンパイアの中でも特別な『純血種』を束ねる王のはず……)
エリーゼは自分の考えが信じられないというように首を何度も横に振るが、彼女自身の中にあるヴァンパイアの血が「彼は本物だ」と告げていた。
「グラーツ公爵がなぜ……」
「君をずっと見ていたからって言ったら信じるかい?」
「え……?」
「冗談だよ」
「そんなことより」とラインハルトは話を逸らして、ランセル子爵家の話をした。
「君の家は完全に燃え尽きてしまったよ」
「──っ!! お父様とお母様は……っ?!」
「残念ながら行方不明だよ」
「そんな……」
両親の行方知れずの報せを聞き、目の前が真っ暗になるエリーゼ。
その様子を可哀そうに思い、ラインハルトはエリーゼの頭を優しくなで、そっと自分の胸に引き寄せた。
「──っ!」
「心配ない、僕が君を守るから……ここにずっといるといい」
帰るところも失い、両親を失ったエリーゼに優しく寄り添うラインハルト。
そして、ゆっくりと自分の胸から離し、エリーゼの漆黒の瞳を見つめて告げる。
「僕の婚約者になってほしい」
そういってラインハルトはエリーゼの頬を優しくなでた──