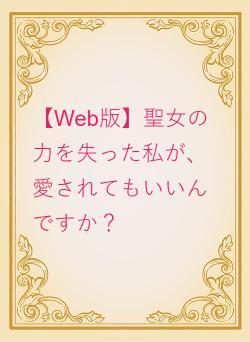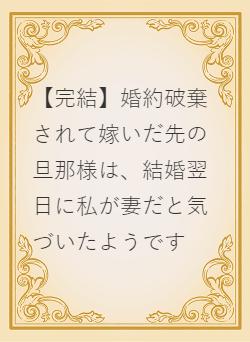ラインハルトはアンナをエリーゼのもとに向かわせたあと、来客を待った。
「さあ、もう出てきたらどうだい? ここに来て私を潰すつもりなんだろう?」
「おや、潰される覚悟がおありですか? ではお望み通りにして差し上げましょう」
元老院の老人三人がラインハルトの自室の扉を開けて入ってくる。
その目にはもう彼を敬う様子はなく、ラインハルトの息の根を止めにかかってきていた。
クルトはさっとラインハルトを守るように前に出てナイフを構える。
「クルト、私は大丈夫だから下がりなさい」
「ですが、──っ!」
クルトはラインハルトの瞳の奥底にあるどろどろとした怒りの感情を見て、思わず後ろに下がった。
「さて、王と王妃に刃を向けるということがどういうことか、理解はしているね?」
「はい、もちろんでございます。あなた様のお命を奪うときを今か今かと待ちわびましたよ」
「そうか、エリーゼに手を出したのは愚策だったね」
「ああ、そうでした。王妃様はもうこの世にはいないのではないでしょうか?」
そう言って老人の一人が目を蒼色に光らせると、透視をしてエリーゼともう一人の老人の様子を見た。
しかし、そこに映っていたのは紛れもない王妃──エリーゼの覚醒した姿であり、そして老人が倒された瞬間だった。
「なっ! まさか、なぜこんな力が……」
「君たちも知っていたんだろう? エリーゼの”稀血”のことを。そして彼女の両親を唆して亡き者にしようとした」
「そうだ、薄汚い人間どもの、あの先代の王を封印した人間の生まれ変わりだ」
「ああ、そうだね。でも、もう彼女はヴァンパイアだ。それも王の血を体内に含んだ」
「まさかっ! それが狙いで……」
ラインハルトは一歩老人のもとに近づくと、そっと告げる。
「さ、君たちの悪事もここまでだね」
「王があんな汚らわしい人間だった者と婚姻してその先も生き続けるなど、あってはならない!」
「君たちは何もわかっていないね」
「これはヴァンパイアと人間の新しい共存の形。全ては争いをなくすため」
ラインハルトは一気に老人たちに距離を詰めると、素早く身を翻して自らの鋭い爪で倒していく。
最後の一人にそっと何かを呟くと、そのままラインハルトはとどめを刺した。
「姉さん、全て終わったよ。これで、新しいヴァンパイアと人間の世界が始まる」
ラインハルトは窓の外に映る月を眺めながら言う。
「クルト」
「はい……」
「全部終わった、エリーゼのもとに向かおう」
「かしこまりました」
ラインハルトは返り血を浴びた爪をさっと振り払うと、老人たちだったものを素通りして部屋を出て行った。
「期待以上の成長をしてくれたね、エリーゼ」
ラインハルトの呟きは廊下に静かに響いて消えた。
「さあ、もう出てきたらどうだい? ここに来て私を潰すつもりなんだろう?」
「おや、潰される覚悟がおありですか? ではお望み通りにして差し上げましょう」
元老院の老人三人がラインハルトの自室の扉を開けて入ってくる。
その目にはもう彼を敬う様子はなく、ラインハルトの息の根を止めにかかってきていた。
クルトはさっとラインハルトを守るように前に出てナイフを構える。
「クルト、私は大丈夫だから下がりなさい」
「ですが、──っ!」
クルトはラインハルトの瞳の奥底にあるどろどろとした怒りの感情を見て、思わず後ろに下がった。
「さて、王と王妃に刃を向けるということがどういうことか、理解はしているね?」
「はい、もちろんでございます。あなた様のお命を奪うときを今か今かと待ちわびましたよ」
「そうか、エリーゼに手を出したのは愚策だったね」
「ああ、そうでした。王妃様はもうこの世にはいないのではないでしょうか?」
そう言って老人の一人が目を蒼色に光らせると、透視をしてエリーゼともう一人の老人の様子を見た。
しかし、そこに映っていたのは紛れもない王妃──エリーゼの覚醒した姿であり、そして老人が倒された瞬間だった。
「なっ! まさか、なぜこんな力が……」
「君たちも知っていたんだろう? エリーゼの”稀血”のことを。そして彼女の両親を唆して亡き者にしようとした」
「そうだ、薄汚い人間どもの、あの先代の王を封印した人間の生まれ変わりだ」
「ああ、そうだね。でも、もう彼女はヴァンパイアだ。それも王の血を体内に含んだ」
「まさかっ! それが狙いで……」
ラインハルトは一歩老人のもとに近づくと、そっと告げる。
「さ、君たちの悪事もここまでだね」
「王があんな汚らわしい人間だった者と婚姻してその先も生き続けるなど、あってはならない!」
「君たちは何もわかっていないね」
「これはヴァンパイアと人間の新しい共存の形。全ては争いをなくすため」
ラインハルトは一気に老人たちに距離を詰めると、素早く身を翻して自らの鋭い爪で倒していく。
最後の一人にそっと何かを呟くと、そのままラインハルトはとどめを刺した。
「姉さん、全て終わったよ。これで、新しいヴァンパイアと人間の世界が始まる」
ラインハルトは窓の外に映る月を眺めながら言う。
「クルト」
「はい……」
「全部終わった、エリーゼのもとに向かおう」
「かしこまりました」
ラインハルトは返り血を浴びた爪をさっと振り払うと、老人たちだったものを素通りして部屋を出て行った。
「期待以上の成長をしてくれたね、エリーゼ」
ラインハルトの呟きは廊下に静かに響いて消えた。