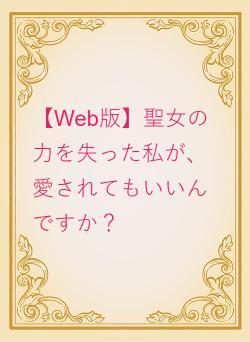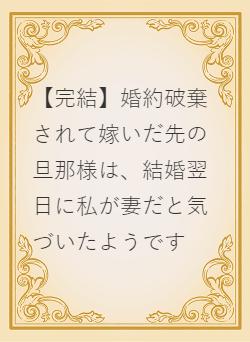エリーゼは目を次に目を覚ますと、そこは暗闇に包まれたどこかの貴族の屋敷だった。
(なに、ここは。あたたかいあの小屋は夢?)
そう思った時に、自分の足元に何かが転がっているのに気づいた。
何気なく目を移すと、そこにはなんと先程まであたたかいスープをご馳走して部屋を用意してくれていた男が息絶えていた。
「──っ!」
(夢じゃない、確かに全て現実。ではなぜ? どうして? どうなってるの?)
わけがわからずにいるエリーゼにゆっくりと一人の老人が近づいた。
「おや、目が覚めましたかな、【王妃様】」
老人のほうに目をやると、エリーゼはその顔に見覚えがあった。
かつてクルトによって、元老院の人間だと教えられていたうちの一人だった。
「あなた、元老院の人ね?」
「おや、よくおわかりですね? 王に教えてもらったのかな?」
嘲笑するように【王妃】、【王】と口にするその人物の様子から自分たちに敬意がないことは明白だった。
「何のつもりですか、こんなことをしてラインハルト様が黙っていないですよ」
「ええ、私たちは決めたのですよ。王を潰すことに」
「潰すですって?」
「あなたも利用されて可哀そうに。哀れな王妃様」
「え?」
「その様子だと何も知らないのですね、当然ですよね。王が話すわけないですものね。では、親切な私が教えてあげましょう。本当の”真実”というものを」
そう言って元老院の一人である老人は近くにあった椅子に座り、エリーゼの対面に座って話し始めた。
「あなたは幼き頃、下級ヴァンパイアに襲われて王に命を救われた。そうですね?」
「はい」
「なぜ襲われたか知っていますか?」
「稀血だからと聞きました」
「表向きはそうですね、ですがあなたを襲うように仕向けた人がいたのですよ」
「え?」
「あなたの両親ですよ」
「──っ!!!」
エリーゼは目を見開き、椅子から立ち上がって叫ぶ。
「嘘よっ! そんなはずないっ! お父様とお母様がそんなっ!」
「あなたの両親はあなたが”稀血”なのを知り、自分の娘の命を私たち元老院に差し出す代わりに爵位を得ようとした」
「そんな……」
「”稀血”はヴァンパイアにとって魅惑の血。ただし、あなたの血は他の”稀血”とは別物。ヴァンパイアを殺すことができる血でした」
「ヴァンパイアを殺す……」
「王はあなたを生かすために見守っていましたが、私たちがその隙をついて下級ヴァンパイアを送り込み殺そうとした」
「まさか……」
「それがあなたが幼い頃襲われた日の真実です」
エリーゼは言葉を失って力なく床にへたり込む。
しかし、エリーゼの中で一つの疑問が残ってそれを目の前の老人にぶつける。
「じゃあ、両親はなぜっ!」
老人は一つにやりと笑うと、そっとエリーゼの耳元で言った。
「あなたの両親を殺したのはラインハルトです」
「──っ!」
エリーゼの瞳の漆黒がより深くなり、その身体はもう立ち上がることができなかった──
(なに、ここは。あたたかいあの小屋は夢?)
そう思った時に、自分の足元に何かが転がっているのに気づいた。
何気なく目を移すと、そこにはなんと先程まであたたかいスープをご馳走して部屋を用意してくれていた男が息絶えていた。
「──っ!」
(夢じゃない、確かに全て現実。ではなぜ? どうして? どうなってるの?)
わけがわからずにいるエリーゼにゆっくりと一人の老人が近づいた。
「おや、目が覚めましたかな、【王妃様】」
老人のほうに目をやると、エリーゼはその顔に見覚えがあった。
かつてクルトによって、元老院の人間だと教えられていたうちの一人だった。
「あなた、元老院の人ね?」
「おや、よくおわかりですね? 王に教えてもらったのかな?」
嘲笑するように【王妃】、【王】と口にするその人物の様子から自分たちに敬意がないことは明白だった。
「何のつもりですか、こんなことをしてラインハルト様が黙っていないですよ」
「ええ、私たちは決めたのですよ。王を潰すことに」
「潰すですって?」
「あなたも利用されて可哀そうに。哀れな王妃様」
「え?」
「その様子だと何も知らないのですね、当然ですよね。王が話すわけないですものね。では、親切な私が教えてあげましょう。本当の”真実”というものを」
そう言って元老院の一人である老人は近くにあった椅子に座り、エリーゼの対面に座って話し始めた。
「あなたは幼き頃、下級ヴァンパイアに襲われて王に命を救われた。そうですね?」
「はい」
「なぜ襲われたか知っていますか?」
「稀血だからと聞きました」
「表向きはそうですね、ですがあなたを襲うように仕向けた人がいたのですよ」
「え?」
「あなたの両親ですよ」
「──っ!!!」
エリーゼは目を見開き、椅子から立ち上がって叫ぶ。
「嘘よっ! そんなはずないっ! お父様とお母様がそんなっ!」
「あなたの両親はあなたが”稀血”なのを知り、自分の娘の命を私たち元老院に差し出す代わりに爵位を得ようとした」
「そんな……」
「”稀血”はヴァンパイアにとって魅惑の血。ただし、あなたの血は他の”稀血”とは別物。ヴァンパイアを殺すことができる血でした」
「ヴァンパイアを殺す……」
「王はあなたを生かすために見守っていましたが、私たちがその隙をついて下級ヴァンパイアを送り込み殺そうとした」
「まさか……」
「それがあなたが幼い頃襲われた日の真実です」
エリーゼは言葉を失って力なく床にへたり込む。
しかし、エリーゼの中で一つの疑問が残ってそれを目の前の老人にぶつける。
「じゃあ、両親はなぜっ!」
老人は一つにやりと笑うと、そっとエリーゼの耳元で言った。
「あなたの両親を殺したのはラインハルトです」
「──っ!」
エリーゼの瞳の漆黒がより深くなり、その身体はもう立ち上がることができなかった──