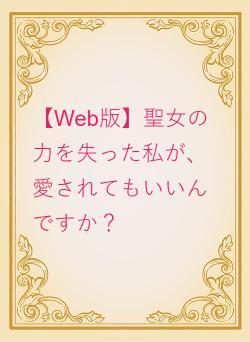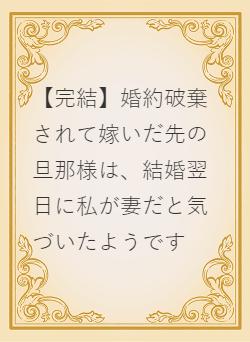ある日の夕方頃、エリーゼが自室で本を読んでいたところ、ドアをノックする音が聞こえる。
そのノックに応えると、ラインハルトが部屋へと入ってきてエリーゼに近づいた。
「ラインハルト様っ!」
「エリーゼ、よかったらこれから外に出かけないか?」
「いいのですか?!」
エリーゼは実家が襲われて、そして自身も襲われてからなるべくグラーツ邸にいるようにと言われてそのようにしていた。
外に出るという機会が出てむしろ彼女は驚いている。
「何か用事があるのですか?」
「いや、エリーゼと外に出たくてね。デートだよ」
「でーと?」
エリーゼはきょとんとした顔でラインハルトを眺める。
一方ラインハルトは、珍しくにこやかな顔でエリーゼを見つめていた。
◇◆◇
(こうしてみると、私たちも街にいるまわりの人も何も変わらないわね)
エリーゼはカフェラテを一口飲みながら、あたりを見回す。
彼女とラインハルトはデートのために近くのカフェに来ていた。
夕方にカフェ利用をする人は少なく、少々珍しそうに見られたが、夕方=朝である生活をしているエリーゼたちには普通のことだ。
「どうだい? 少しはうちの暮らしが慣れたかい?」
ブラックコーヒーを飲みながら、ラインハルトはエリーゼに問う。
「はい、とてもよくしていただいております。ランセル子爵家での暮らしより良いので少し戸惑うほどに……」
「そうか、少しずつ慣れてくれればいい」
コーヒーのカップを細い指が捕らえ、優雅に口元に運ばれる。
その様子をエリーゼはついうっとりと眺めてしまった。
「どうしたんだい?」
「あ、いえ、綺麗だなと思ってついみてしまい……」
(しまった、うっかり本音が……)
その言葉を聞いたラインハルトはそっと微笑むと机の下でこつんとエリーゼの膝に自分の膝をあてる。
「──っ!」
突然の触れ合いにエリーゼはドキっとすると、意地悪そうな顔したラインハルトは店員を呼ぶ。
人が来るという緊張感で赤くなった顔はさらに赤くなる。
やがて、店員が来ると、ラインハルトは注文をする。
「フレンチトーストを一つ彼女に頼む」
「かしこまりました」
店員はお辞儀をすると、そのまま何事もなかったかのように去っていく。
エリーゼは店員が気にしていないといえども、顔が赤い状態を見られたのではないかということに、余計に恥ずかしさを覚える。
「ふふ、ここのフレンチトーストは美味しいんだ」
「え、ええ。いただきます」
軽く俯きながら小声で言う様子を眺めて、ラインハルトは楽しむ。
エリーゼはこの時、ラインハルトが意地悪な人間だと思った──
デートを終えて邸宅に戻ると、すっかり夜になっていた。
(もう夜になっちゃったわね。本でも読もうかしら)
廊下を歩いて自室に戻っていると、通りがかった部屋から何やら声がした。
(誰?)
エリーゼは誘われるようにその部屋をそっと覗くと、中にはアンナとクルトがいた。
そしてアンナは少し服が乱れてソファにおり、クルトの表情はこちらからは見えない。
「──っ!」
思わず声が出そうになり、口元を慌てて抑える。
(吸血してる……!)
アンナの首元に唇を寄せてクルトが血をすすっていた。
その姿はおぞましいというものではなく、なんとなく美しいような艶めかしい様子だった。
エリーゼは慌てて自室へと駆けだした──
そのノックに応えると、ラインハルトが部屋へと入ってきてエリーゼに近づいた。
「ラインハルト様っ!」
「エリーゼ、よかったらこれから外に出かけないか?」
「いいのですか?!」
エリーゼは実家が襲われて、そして自身も襲われてからなるべくグラーツ邸にいるようにと言われてそのようにしていた。
外に出るという機会が出てむしろ彼女は驚いている。
「何か用事があるのですか?」
「いや、エリーゼと外に出たくてね。デートだよ」
「でーと?」
エリーゼはきょとんとした顔でラインハルトを眺める。
一方ラインハルトは、珍しくにこやかな顔でエリーゼを見つめていた。
◇◆◇
(こうしてみると、私たちも街にいるまわりの人も何も変わらないわね)
エリーゼはカフェラテを一口飲みながら、あたりを見回す。
彼女とラインハルトはデートのために近くのカフェに来ていた。
夕方にカフェ利用をする人は少なく、少々珍しそうに見られたが、夕方=朝である生活をしているエリーゼたちには普通のことだ。
「どうだい? 少しはうちの暮らしが慣れたかい?」
ブラックコーヒーを飲みながら、ラインハルトはエリーゼに問う。
「はい、とてもよくしていただいております。ランセル子爵家での暮らしより良いので少し戸惑うほどに……」
「そうか、少しずつ慣れてくれればいい」
コーヒーのカップを細い指が捕らえ、優雅に口元に運ばれる。
その様子をエリーゼはついうっとりと眺めてしまった。
「どうしたんだい?」
「あ、いえ、綺麗だなと思ってついみてしまい……」
(しまった、うっかり本音が……)
その言葉を聞いたラインハルトはそっと微笑むと机の下でこつんとエリーゼの膝に自分の膝をあてる。
「──っ!」
突然の触れ合いにエリーゼはドキっとすると、意地悪そうな顔したラインハルトは店員を呼ぶ。
人が来るという緊張感で赤くなった顔はさらに赤くなる。
やがて、店員が来ると、ラインハルトは注文をする。
「フレンチトーストを一つ彼女に頼む」
「かしこまりました」
店員はお辞儀をすると、そのまま何事もなかったかのように去っていく。
エリーゼは店員が気にしていないといえども、顔が赤い状態を見られたのではないかということに、余計に恥ずかしさを覚える。
「ふふ、ここのフレンチトーストは美味しいんだ」
「え、ええ。いただきます」
軽く俯きながら小声で言う様子を眺めて、ラインハルトは楽しむ。
エリーゼはこの時、ラインハルトが意地悪な人間だと思った──
デートを終えて邸宅に戻ると、すっかり夜になっていた。
(もう夜になっちゃったわね。本でも読もうかしら)
廊下を歩いて自室に戻っていると、通りがかった部屋から何やら声がした。
(誰?)
エリーゼは誘われるようにその部屋をそっと覗くと、中にはアンナとクルトがいた。
そしてアンナは少し服が乱れてソファにおり、クルトの表情はこちらからは見えない。
「──っ!」
思わず声が出そうになり、口元を慌てて抑える。
(吸血してる……!)
アンナの首元に唇を寄せてクルトが血をすすっていた。
その姿はおぞましいというものではなく、なんとなく美しいような艶めかしい様子だった。
エリーゼは慌てて自室へと駆けだした──