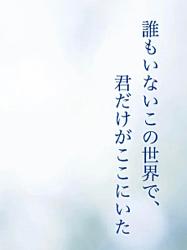*
——誰かが、私を呼ぶ声がする。
……芽依。
芽依……。
懐かしい、声。
……夢?
体が動かない。辺りは真っ暗で、私は腕を枕にして、もう長いこと眠りに落ちている。
懐かしい、匂いがする。
懐かしい、気配がする。
腕の隙間から、もうずっと長い間、私のことを呼んでいる声がする。
「……聞こえてるかぁー? 芽依」
聞こえてる。
そのいつも元気な、ちょっと高めの声。よく聞こえてるよ。
でも、返事ができない。
金縛りにあったみたいに、体が動かないの。
「芽依、全然俺のこと気づいてくれねぇのな。俺の念力が足りねぇのかなー」
気づいたよ。……今は、だけど。
いつも呼びかけてくれてたの?
……蓮くんを探して走っていた時も、私を呼んで、案内してくれたの?
そう聞きたいのに、声が出ない。
なんでだろう。体のどこもかしこも、岩に押し潰されているみたいに動けない。
「……あのさ。蓮は、いいやつなんだ。だからさ、……大丈夫だよ」
大丈夫って、なに?
どういう意味で?
今すぐ顔を上げて、あなたに抱きつきたいのに。
言いたいことは、たくさんあるのに。
もう、何もできない。謝罪も。懺悔も。感謝の言葉も、何も伝えられない。
……あぁ、そうか。
もう、いないから。
修ちゃんは、もうこの世にいないから。
だから、人は後悔をするんだ。取り戻せない時を、取り戻したくて。
でもそれは絶対に取り戻すことはできなくて。心を傷だらけにしながら生きていく。
それでも、生きるんだ。
それって、すごくつらいけど。
つらくて、またすべてを諦めたくなることもあるだろうけど。
……そうだね。
修ちゃんが言うなら、大丈夫。
きっと、大丈夫だよね……。
ようやく顔を上げると、そこは教室だった。
中学校舎。時刻は十七時を過ぎていて、辺りは暖かな夕日に染められていた。
私はあれから、修ちゃんが恋しくなった日には放課後の誰もいない時間を狙って、中学校舎に忍び込んでいた。
昔、私が座っていた席。三つ隣には修ちゃんが座っていて、いつも近くで私を見ていてくれた。
廊下寄りのその席は、いま窓の淵の影に入り込み、闇に消えようとしている。
……都合のいい、夢を見てたんだ。
この前みたいに、まぼろしにさえも会えない。寂しくて、何度も何度も頭の中にあの笑顔を思い返す。
「……あ」
指先に何かが当たった。眠り込む前は何も置かれていなかったはずの机の上に、いつのまにか何かが置かれていた。
タコのキーホルダー。
修ちゃんが蓮くんと井上さんにプレゼントした、横浜のお土産。
私には豚まんだけだと思ってた。
「……私の分も、あったんだね」
それを握りしめると、私の手のひらの温度よりも温かくて、心がほっと安らいだ。
夕日に当たっていたからだろうか。
それとも……。
落ちる涙をそのままにして、私はいつまでもその席で、修ちゃんの温もりを感じていた。
——誰かが、私を呼ぶ声がする。
……芽依。
芽依……。
懐かしい、声。
……夢?
体が動かない。辺りは真っ暗で、私は腕を枕にして、もう長いこと眠りに落ちている。
懐かしい、匂いがする。
懐かしい、気配がする。
腕の隙間から、もうずっと長い間、私のことを呼んでいる声がする。
「……聞こえてるかぁー? 芽依」
聞こえてる。
そのいつも元気な、ちょっと高めの声。よく聞こえてるよ。
でも、返事ができない。
金縛りにあったみたいに、体が動かないの。
「芽依、全然俺のこと気づいてくれねぇのな。俺の念力が足りねぇのかなー」
気づいたよ。……今は、だけど。
いつも呼びかけてくれてたの?
……蓮くんを探して走っていた時も、私を呼んで、案内してくれたの?
そう聞きたいのに、声が出ない。
なんでだろう。体のどこもかしこも、岩に押し潰されているみたいに動けない。
「……あのさ。蓮は、いいやつなんだ。だからさ、……大丈夫だよ」
大丈夫って、なに?
どういう意味で?
今すぐ顔を上げて、あなたに抱きつきたいのに。
言いたいことは、たくさんあるのに。
もう、何もできない。謝罪も。懺悔も。感謝の言葉も、何も伝えられない。
……あぁ、そうか。
もう、いないから。
修ちゃんは、もうこの世にいないから。
だから、人は後悔をするんだ。取り戻せない時を、取り戻したくて。
でもそれは絶対に取り戻すことはできなくて。心を傷だらけにしながら生きていく。
それでも、生きるんだ。
それって、すごくつらいけど。
つらくて、またすべてを諦めたくなることもあるだろうけど。
……そうだね。
修ちゃんが言うなら、大丈夫。
きっと、大丈夫だよね……。
ようやく顔を上げると、そこは教室だった。
中学校舎。時刻は十七時を過ぎていて、辺りは暖かな夕日に染められていた。
私はあれから、修ちゃんが恋しくなった日には放課後の誰もいない時間を狙って、中学校舎に忍び込んでいた。
昔、私が座っていた席。三つ隣には修ちゃんが座っていて、いつも近くで私を見ていてくれた。
廊下寄りのその席は、いま窓の淵の影に入り込み、闇に消えようとしている。
……都合のいい、夢を見てたんだ。
この前みたいに、まぼろしにさえも会えない。寂しくて、何度も何度も頭の中にあの笑顔を思い返す。
「……あ」
指先に何かが当たった。眠り込む前は何も置かれていなかったはずの机の上に、いつのまにか何かが置かれていた。
タコのキーホルダー。
修ちゃんが蓮くんと井上さんにプレゼントした、横浜のお土産。
私には豚まんだけだと思ってた。
「……私の分も、あったんだね」
それを握りしめると、私の手のひらの温度よりも温かくて、心がほっと安らいだ。
夕日に当たっていたからだろうか。
それとも……。
落ちる涙をそのままにして、私はいつまでもその席で、修ちゃんの温もりを感じていた。