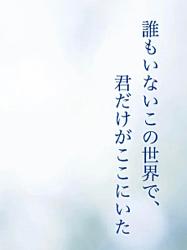でも、どこへ行っても蓮くんはいなかった。
授業中の廊下を走り抜ける。先生や生徒が教室の中から不思議そうに私の方を見るけれど、咎められる前に全力でその場を通り過ぎた。
階段の途中で足を止めて、もう一度チャットをする。
〝どこにいるの?〟
でも、返事はない。電話をかけても、出てくれない。
嫌な予感がして、胸が押し潰されそうになった。
きっとあの日、蓮くんも今の私と同じ気持ちだったのかな。
私が駅のホームから飛び降りようとした、あの日。
修ちゃんの、命日。
蓮くんはきっと、あの日が来るのを怖がっていた。何かが起こるんじゃないかと思って、ずっと私のことを見ていた。そして、朝から〝君の秘密、知ってる〟なんて気になるメールを送って、気を引いて。放課後待ってる、と送ったあとも、本当に来るかなんてわからないから、気が気じゃなくて、ずっと不安で。
私も蓮くんが屋上で〝ここから飛び降りようかな〟なんて言った時、本当に怖かったのに。
ごめんね。
蓮くん、ごめん。
どこにいるの?
今更会いたいなんて、虫がよすぎる。
昨日もたくさん連絡をくれたのに、無視した私が今度は連絡を欲しがるなんて、自分勝手だ。
それでも、諦めることなんてできなかった。
ひたすらに校内を走り続けた。でも、どこへ行っても蓮くんの姿はない。
もう何度目かわからない、涙がぼろぼろと溢れていく。
「……芽依!」
その時、どこからか声がした。
はっとして振り返る。でも、廊下の先には誰もいなかった。
だけど……。
感じる。気配を。
誰かが、私を……見ている。
階段の向こう。たしかに、誰かが、そこにいる。
声がした方へ、私はふらふらと走り出した。
階段を覗くと、誰かが駆け降りていく服の裾が見えた。
さわやかな青い生地——この学校の、中学生の制服。
無我夢中で、その姿を追う。涙で前が見えなくても、かまわずに。
まるで導かれるように、私はその影を追い続けた。
学校を出ると、私はそのまま走り続けた。
前方を誰かが走っている。曲がり角を曲がると、その誰かがまた道を曲がっていく。その人物が行くままに、私は道を走り続けた。
十分ほどそうしていて、たどり着いたのは最寄りの駅だった。
遠くに見える、いつもの景色。通勤通学の時間帯が終わったところなのか、今、ホームには誰もいない。
ただ、一人。
ホームの端、静かに佇む蓮くんを除いて……。
警報機がカンカンと鳴って、レバーが世界を分断しようとしている。
私はそれが下がり切る前に、前のめりに向こう岸へと渡った。
涙が、落ちていく。
それでも、その涙すらもその場に置いていくくらいのスピードで、私は駆け抜けた。
『列車が通過します。危ないですから黄色い線までお下がりください……』
蓮くん。
ごめんね。
ごめんなさい。
今まで、きっと私は、蓮くんにいろんなことをさせてきた。
ずっと気にさせて、ずっと不安にさせてきた。
蓮くんだって、修ちゃんが亡くなってつらかったはずなのに。
二人がどれくらい親密だったのかはわからないけれど、私と同じくらい、ショックだったはずなのに。
蓮くんは、修ちゃんと交わされた何かの〝お願い〟を守ろうとしていたんだよね。
でも、もう私のことなんて忘れていいから。
修ちゃんのお願いなんて、破っていいから。
……お願いだから、間に合って。
定期券を手にしていない私は、当然改札機に阻まれた。それでも、ごめんなさいっ、と叫びながらそのドアを跨ぐようにして通り抜けた。
背後に駅員さんの声がしたけれど、足を止めなかった。
ホームへ出る。左手を見ると、ずっと先、先頭車両が止まる辺りに立っている蓮くんの姿が見えた。
もう、通過車両は目の前まで迫っていた。
ごうごうと、世界が振動する。
蓮くんの右足が、一歩、前に出る。
待って。
お願い。
お願い——行かないで!
「——蓮くん!」
飛びつくように、蓮くんの体にしがみついた。
驚いたような表情の蓮くんを視界に捉えたあと、次の瞬間にはもう、私たちはホームに倒れていた。
ごうっ、と耳元で風を切る音がして、一瞬、跳ねられたかと思った。いつから鳴っていたのか、危険を知らせる警笛の音がしていた。
でも、私は生きていた。
蓮くんも。ホームぎりぎりのところで、私たちは倒れていた。
遠くから、駅員さんが走ってくる足音が聞こえる。それにもかまわず、私は蓮くんのことを強く抱きしめていた。
「……芽依ちゃん」
「死んじゃだめだって言ったの、蓮くんじゃん……!」
最初に出てきた言葉は、心配でも謝罪でもなくて。文句みたいな言葉になってしまった。
でも涙は止まらなくて、しがみつくようにして泣いた。
「……ごめ、ん」
蓮くんに抱きしめ返されて、私はようやく、生きている実感が湧いていた。
授業中の廊下を走り抜ける。先生や生徒が教室の中から不思議そうに私の方を見るけれど、咎められる前に全力でその場を通り過ぎた。
階段の途中で足を止めて、もう一度チャットをする。
〝どこにいるの?〟
でも、返事はない。電話をかけても、出てくれない。
嫌な予感がして、胸が押し潰されそうになった。
きっとあの日、蓮くんも今の私と同じ気持ちだったのかな。
私が駅のホームから飛び降りようとした、あの日。
修ちゃんの、命日。
蓮くんはきっと、あの日が来るのを怖がっていた。何かが起こるんじゃないかと思って、ずっと私のことを見ていた。そして、朝から〝君の秘密、知ってる〟なんて気になるメールを送って、気を引いて。放課後待ってる、と送ったあとも、本当に来るかなんてわからないから、気が気じゃなくて、ずっと不安で。
私も蓮くんが屋上で〝ここから飛び降りようかな〟なんて言った時、本当に怖かったのに。
ごめんね。
蓮くん、ごめん。
どこにいるの?
今更会いたいなんて、虫がよすぎる。
昨日もたくさん連絡をくれたのに、無視した私が今度は連絡を欲しがるなんて、自分勝手だ。
それでも、諦めることなんてできなかった。
ひたすらに校内を走り続けた。でも、どこへ行っても蓮くんの姿はない。
もう何度目かわからない、涙がぼろぼろと溢れていく。
「……芽依!」
その時、どこからか声がした。
はっとして振り返る。でも、廊下の先には誰もいなかった。
だけど……。
感じる。気配を。
誰かが、私を……見ている。
階段の向こう。たしかに、誰かが、そこにいる。
声がした方へ、私はふらふらと走り出した。
階段を覗くと、誰かが駆け降りていく服の裾が見えた。
さわやかな青い生地——この学校の、中学生の制服。
無我夢中で、その姿を追う。涙で前が見えなくても、かまわずに。
まるで導かれるように、私はその影を追い続けた。
学校を出ると、私はそのまま走り続けた。
前方を誰かが走っている。曲がり角を曲がると、その誰かがまた道を曲がっていく。その人物が行くままに、私は道を走り続けた。
十分ほどそうしていて、たどり着いたのは最寄りの駅だった。
遠くに見える、いつもの景色。通勤通学の時間帯が終わったところなのか、今、ホームには誰もいない。
ただ、一人。
ホームの端、静かに佇む蓮くんを除いて……。
警報機がカンカンと鳴って、レバーが世界を分断しようとしている。
私はそれが下がり切る前に、前のめりに向こう岸へと渡った。
涙が、落ちていく。
それでも、その涙すらもその場に置いていくくらいのスピードで、私は駆け抜けた。
『列車が通過します。危ないですから黄色い線までお下がりください……』
蓮くん。
ごめんね。
ごめんなさい。
今まで、きっと私は、蓮くんにいろんなことをさせてきた。
ずっと気にさせて、ずっと不安にさせてきた。
蓮くんだって、修ちゃんが亡くなってつらかったはずなのに。
二人がどれくらい親密だったのかはわからないけれど、私と同じくらい、ショックだったはずなのに。
蓮くんは、修ちゃんと交わされた何かの〝お願い〟を守ろうとしていたんだよね。
でも、もう私のことなんて忘れていいから。
修ちゃんのお願いなんて、破っていいから。
……お願いだから、間に合って。
定期券を手にしていない私は、当然改札機に阻まれた。それでも、ごめんなさいっ、と叫びながらそのドアを跨ぐようにして通り抜けた。
背後に駅員さんの声がしたけれど、足を止めなかった。
ホームへ出る。左手を見ると、ずっと先、先頭車両が止まる辺りに立っている蓮くんの姿が見えた。
もう、通過車両は目の前まで迫っていた。
ごうごうと、世界が振動する。
蓮くんの右足が、一歩、前に出る。
待って。
お願い。
お願い——行かないで!
「——蓮くん!」
飛びつくように、蓮くんの体にしがみついた。
驚いたような表情の蓮くんを視界に捉えたあと、次の瞬間にはもう、私たちはホームに倒れていた。
ごうっ、と耳元で風を切る音がして、一瞬、跳ねられたかと思った。いつから鳴っていたのか、危険を知らせる警笛の音がしていた。
でも、私は生きていた。
蓮くんも。ホームぎりぎりのところで、私たちは倒れていた。
遠くから、駅員さんが走ってくる足音が聞こえる。それにもかまわず、私は蓮くんのことを強く抱きしめていた。
「……芽依ちゃん」
「死んじゃだめだって言ったの、蓮くんじゃん……!」
最初に出てきた言葉は、心配でも謝罪でもなくて。文句みたいな言葉になってしまった。
でも涙は止まらなくて、しがみつくようにして泣いた。
「……ごめ、ん」
蓮くんに抱きしめ返されて、私はようやく、生きている実感が湧いていた。