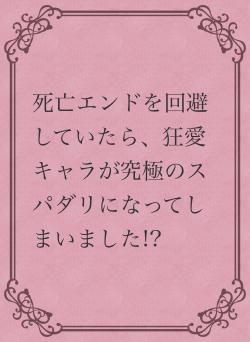「……つーかお前さ。心の底から本気で生きたいって、死にたくないって思ってるのかよ」
「どうしてそういう話になるの?」
思ってもみない質問だったからか、喉に力が入って想像よりもずっと硬い声が出る。
茶化してるわけでも、冗談で言っているわけでもない。それはサルヴァドールの本心での発言だった。
「ま、思ってはいるんだろうな。じゃなきゃあんな小っ恥ずかしいおべっかも媚びも売らないだろ」
「……ねえ、どうして怒ってるの?」
「はあ? なんでオレが怒る必要があるんだよ」
イラついているといったほうが正しいのだろうか。どちらにしてもサルヴァドールの様子は変である。
「サルヴァ……」
どうしてもすべてを理解することができなくて戸惑っていれば、サルヴァドールはため息をつきながら頭を乱暴に掻いた。
「あー……こんなことが言いたかったんじゃねぇ。ただオレは……お前のその、本心に反してたまに出る傍観したように場をやり過ごそうとしてる癖がなんか鼻についただけだ」
「……サルヴァ、それってつまり」