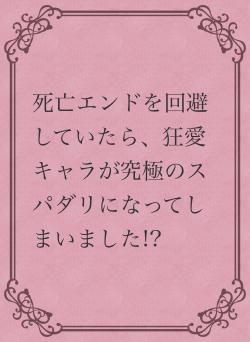目と鼻の先にある整った顔。一つ一つのパーツが完璧な位置に収まっており、文句のつけようがない容姿のドアップに心臓が跳ねる。
「顔、ちかいよ」
「……」
半分のしかかるような体勢でいるサルヴァドールの頬を、片手を使って押し返す。
素直に押し返されてくれたサルヴァドールは、それでも物言いたげな黄金の瞳をじっと向けていた。
私は上体を起こして毛布の端を整えたあとで、サルヴァドールに聞き返す。
「昼間のあれって、なに?」
「なにだって? 温室以外にあるか?」
「温室って……聞きたいのはわたしもだよ。どうしてあんな風を出したの?」
「それは――」
言いかけて、中途半端に口に手を当てたサルヴァドール。
まるで不貞腐れた子どものようにも見えた。
契約してからあまり見たことがない姿だったので、私はどうしたのかと不思議になりながら言葉を待った。