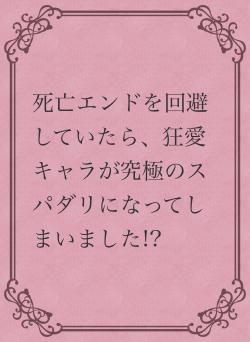(……どうしよう。このままあの二人に好き放題話されるのは気分がよくないし、ルザークに聞かせたままなのもまずいよね)
「何にしても、愛されていないってことでしょう。なんだか、可哀想ね」
お客様に聞かれていると知ったら、あの二人のメイドはどうするのだろう。ましてや私に聞かれているとは露ほども思っていないからか、今もペラペラと口が動いている。
(……ま、気に入られようと必死だっていうのも、血が繋がっていないのも、当たりだけど)
「それより、公爵様とお近づきになるには、やっぱり印象に残らないとダメよね」
「就寝前のお酒をお持ちするときに、なんとか話しかけるチャンスはないかしら。あわよくば……」
「ちょっとアンタ、何考えてんのよ。いやらしいわねぇ」
さすがにこれ以上は聞いていられないと、椅子から降りたときだった。
「耳障りだな。コイツら、飛ばすか」
「――あなた方は、ここをどこだと心得ているのですか」
私にだけ聞こえるように届いたサルヴァドールの声と、突然温室の裏口を開けて入ってきたゼノの声がぴたりと重なった。